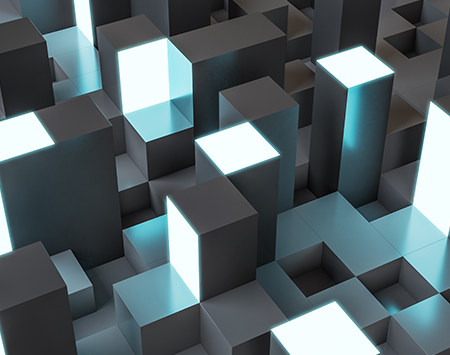人事コラム
パーパス経営と人事~パーパス浸透を促す人事制度の重要性
パーパスを軸とした人事プラットフォームを構築することで、戦略的・効果的にパーパスを体現する人材を育成する

パーパスとは
SDGsやサステナビリティなどの考えが広く普及しつつある昨今において、企業には社会的存在価値と貢献活動が強く求められる時代となってきた。パーパスとは、自社の存在意義や存在価値といった本質的な存続目的を指す上位概念であり、社会から見た我が社の立ち位置を示すものである。
パーパス浸透について解説する前にパーパスの定義をさらに深堀する。
似た概念・価値として「ミッション」がある。
企業によってミッションとパーパスの意味合いを明確に分けずに運用するケースもあるが、ミッションとは「自分たちは社会に何を働きかけていきたいのか(Do型)」、パーパスとは「自分たちは社会の中でどうありたいのか(Be型)」という違いで考えるのが分かりやすいであろう。
例えば、電気自動車で有名なテスラのミッションは「持続可能なエネルギーへのシフトを世界中で加速させる」と定義している一方で、世界最大の食品・飲料会社であるネスレ日本は「生活の質を高め、さらに健康な、未来づくりに貢献します。」とスタンスの違いが読み取れる。
いずれにせよ我が社が社会にとってどのような貢献を果たすべきなのか、果たしたいのかを明文化したのがパーパスであると認識されたい。

パーパス浸透の重要性
パーパスを掲げる以上は絵に描いた餅とするわけにはいかない。社員がパーパスに基づいた価値判断で行動・成果を挙げることを求めていきたいのは全企業の共通の想いであろう。
パーパスを浸透する理由は上記の通りであるが、代表的な3つの効果を挙げる。
①明確なパーパスの策定と浸透による優秀な人材や投資家目線での魅力度(エンゲージメント)向上
②変化の激しい時代でもパーパスに基づいて判断ができる人材の育成と意思決定のスピード向上
③パーパスを追求する組織風土の醸成
パーパスは組織風土を変え、社会(ステークホルダー)からの見られ方も変える。企業の持続性が求められる昨今の経営においては実装が不可欠な価値である。

パーパスを浸透するための具体的なステップ
パーパスを浸透させようと考えた時に重要となるのは、社員がパーパスに触れる機会をいかに作れるかである。ただし闇雲にその機会を作れば良いというわけではない。適切なステップで適切な取り組みを実装していくことが必要である。具体的には、「知る・触れる・落とし込む」の3ステップで考えるのが分かりやすい。
【STEPⅠ:知る】
当然のことながら、パーパスを浸透させようと考えた時には社員がパーパス自体を"知っている"必要がある。そのため会社が社員に対して意識的にパーパスを発信をしていかなければならない。発信の仕方はそれぞれの企業によって異なるが、トップからの発信は欠かせないだろう。パーパスの位置づけや意味合い、自社にとっての解釈などをトップから発信し、社員に語りかけることが、"知る"のステップでは最重要である。
【STEPⅡ:触れる】
次のステップは"触れる"である。パーパス浸透の一丁目一番地は"知る"ことであるが、知るというのは瞬間的である。パーパスを自分事として行動へと繋げるには多くの機会で触れる継続性が重要だ。
例えば、パーパスが記されたブックの作成や配布、朝礼での唱和、定期的なワークショップの開催などの取り組みが考えられる。社員がパーパスと常に触れ、考えるきっかけ作りに努めていきたい。
【STEPⅢ:落とし込む】
最後は"落とし込む"である。知って、触れているだけでは行動に結びつかない。パーパスは行動に起こし、成果を残すまでがゴールである。そこで昨今のトレンドとして注目されているのが人事制度との連動である。特に評価制度への落とし込みを検討する企業が増えている。パーパス評価や理念評価など名称は様々であるが、パーパスに沿った行動が出来たかを処遇に結びつけることで意識面だけでなく、持続的な仕組みとして浸透させていくのである。
以上のステップにてパーパスを戦略的かつ効果的に浸透させていくことが必要である。

パーパス浸透のための評価制度
落とし込むステップで人事制度との連動について述べたが、主に二つの取り組みが考えられる。
まず1点目は、表彰制度への落とし込みである。
自社のパーパスに沿った行動や成果を挙げた人材にスポットを当てて、それらの行動を全社として表彰する。この制度のメリットは表彰された本人のモチベーション向上はさることながら、行動のモデル化が出来る。どのような行動が自社のパーパスにマッチして表彰されるのかを全社員へ周知し、行動の方向づけが可能ということだ。表彰制度への落とし込みは比較的に容易であるため、多くの企業で取り入れやすい点もメリットであろう。
続いて2点目は、評価制度への組み込みである。
等級別にパーパスに沿った期待行動を明文化し、期待行動に対する実態を評価して処遇へと結びつける。評価制度と連動させることでパーパスと自らの行動のギャップを自然と振り返り、そのギャップを踏めるための思考と行動を促進することが可能だ。評価制度を構築するためのオペレーションコストは掛かるものの、全社員に対して仕組みとしてパーパスを浸透できる点は大きなメリットである。
さいごに
繰り返しになるが、パーパスは策定しただけではその効果を発揮できない。
社員へ浸透させ、行動へと結びつけ、伝承させていくことがパーパスの本質的価値である。
1社でも多くの企業が自社の掲げるパーパスを実現するため、「持続的な仕組みとはなにか、また人事制度との連動性は測れないか」を検討していただきたい。
本事例に関連するサービス
関連動画

TCG REVIEW ビジョン浸透
社員一人一人がビジョンを自分事とすることで主体性を高め、ビジョンを行動で体現することによって顧客の信頼性を高める「ビジョン実装メソッド」を提言します。
この資料をダウンロードする