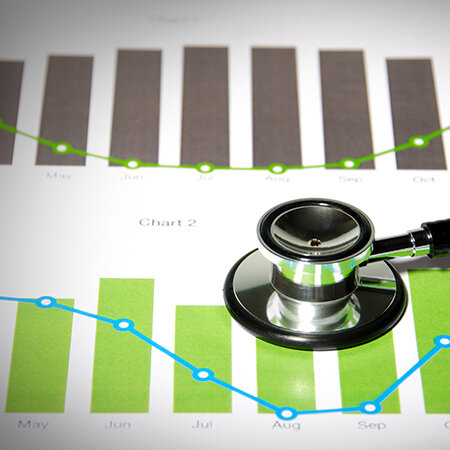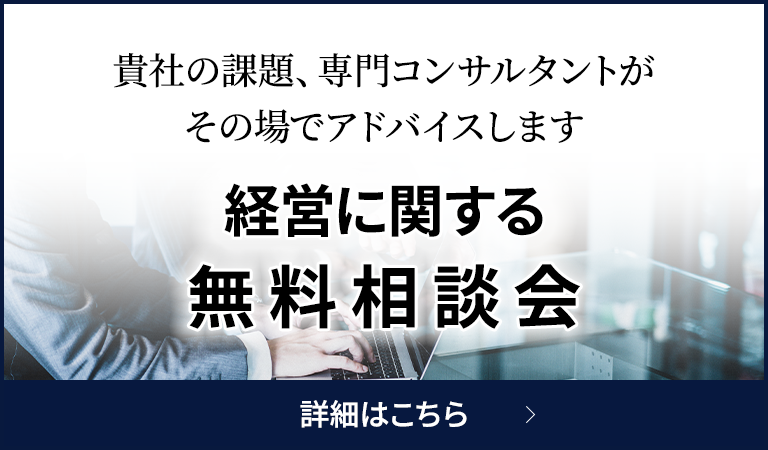物流業の資金調達はどうすべき?
補助金制度も紹介
- 企業価値向上

閉じる
国土交通省の調査によると、1990年から2010年の20年間でトラック運送事業者数は約4万社から約6万3千社に急増し、6割近く増加しました。一方で、輸送量の増加は約1割にとどまり、供給過多の状態から事業者間の競争が激化しました※。また、2019年4月から働き方改革の導入により、労働時間の上限が短縮されたことでドライバーが不足し、思い通りに貨物を運ぶことが難しくなるなど、物流業界を取り巻く環境は厳しい状況にあります。この環境を乗り切るためには物流倉庫や車両などへの多くの投資が必要になってきます。トラック輸送の多くの場合は原価の約半分を人件費が占めています。人手不足の影響から人件費は年々上昇しており、収益性を高めるには生産性向上が不可欠です。
そこで今回は、生産性向上や必要設備の導入に向けた、物流業界における資金調達方法をご紹介いたします。
※出典:ロジ・ソリューション株式会社著『物流業界のしくみとビジネスがしっかりわかる教科書改訂2版』(2024年1月24日発売)P32
主な資金調達方法について
主な資金調達方法として、1.銀行融資、2.リースの活用、3.補助金・助成金の3種類についてご紹介します。
1つ目は、金融機関の融資を活用した調達です。
最も馴染み深い資金調達方法であり、多くの企業が活用しています。金融機関からの借入については、会社の財務状況や収益状況を見て、融資の判断がなされます。また、金融機関から見て信用力が高いと判断された際や制度融資など公的機関の制度を活用することで優遇された金利で資金調達が可能です。
金融機関による融資(借入)を活用する際のポイントは、資金調達後に滞りなく返済ができるのかという視点です。借入時に資金繰り表を作成し、計画的な資金計画の立案が必要です。
2つ目の資金調達方法として、意外に見落としがちなのがリースを活用した資金調達です。具体的には、車両や事業で使用する備品(PCなど)をキャッシュで購入するのではなく、リース契約で購入することです。リース契約で購入することで、キャッシュの一時的な流出を防ぐことができ、月々リース料として支払う形になるので、実質的に資金調達と同じ効果を得られます。特に物流業において車両は高額な資産です。リース契約を活用して、資金繰りの改善を図ることができます。
3つ目は、補助金や助成金を活用した資金調達です。主な補助金として、事業再構築補助金や中堅企業向けに新設された中小企業省力化投資補助金があります。補助金の多くは設備投資後に入金されるケースが多いため、注意が必要ですが、設備投資額の多くの割合を補助されるなど大きなメリットがあります。また、補助金は返済の必要がないケースが多いため、企業としては積極的に活用したい資金調達方法と言えます。
また上記3つの資金調達方法以外にも様々な資金調達方法がありますが、中堅・中小企業が活用する主なものは上記3つです。また上記3つの資金調達方法を含めて、資金調達方法はデット調達(負債)とエクイティ調達(資本)の大きく2つに分けられます。昨今注目されているIPO(新規株式公開)は正にエクイティ調達の代表例です。IPOにあたっては定性・定量面の要件を満たす必要があり、ガバナンスの強化など簡単なものではありません。ただし、IPOの実行は信用力が高まり、デット(負債)での資金調達もしやすくなるといった効果が期待できます。
補助金を活用した資金調達方法について
昨今の働き方改革によって物流業を取り巻く環境が大きく変化しています。その対策として生産性向上や人材確保などの取り組みを検討している会社は多いですが、資金面ですぐには実施できないといったケースも散見されます。物流業の生産性向上や人材確保などを支援する補助金について一部をご紹介します。
中小企業省力化投資補助金は、中小企業などの人手不足解消につながる、IoTやロボットなど「省力化製品」の導入を支援する制度であり、補助対象となる省力化製品は、事務局ホームページの「製品カタログ」に登録されたものです。このカタログから、自社の課題・業種・業務プロセスにあった製品を選んで導入する流れであり、製品本体価格および導入経費の1/2の補助金が申請できます。(ただし従業員規模に応じて、補助上限額が異なります。)
積極的な投資で生産性向上を実現した事例として、材木をオート三輪で運ぶ運送会社としてスタートし、現在はトラック輸送から建設資材の搬入・組み立て、産業廃棄物の運搬、倉庫での一時管理まで、すべて自社で完結させるモデルを構築し、メーカーとの直接取引で事業を展開されている会社があります。事例企業のように、物流におけるサプライチェーンの1部分のみを担うのではなく、ワンストップで担うことでより多くの付加価値を生み出すことが可能です。今後の物流業界で生き残っていくためには積極的な投資は必要不可欠と言えます。
その他にも事業再構築補助金やIT導入補助金など様々な補助金があります。これらは全てホームページに要件などは公開されていますので、どのような補助金が世の中にはあるのか本コラムを見られた方はぜひご確認ください。設備投資にあたっては、資金が無いから何もできないではなく、さまざまな資金調達方法を検討することで生産性向上に寄与する設備や車両・倉庫等の物流業にとって必要不可欠な資産に投資が可能です。ぜひ自社にあった資金調達方法をご検討ください。
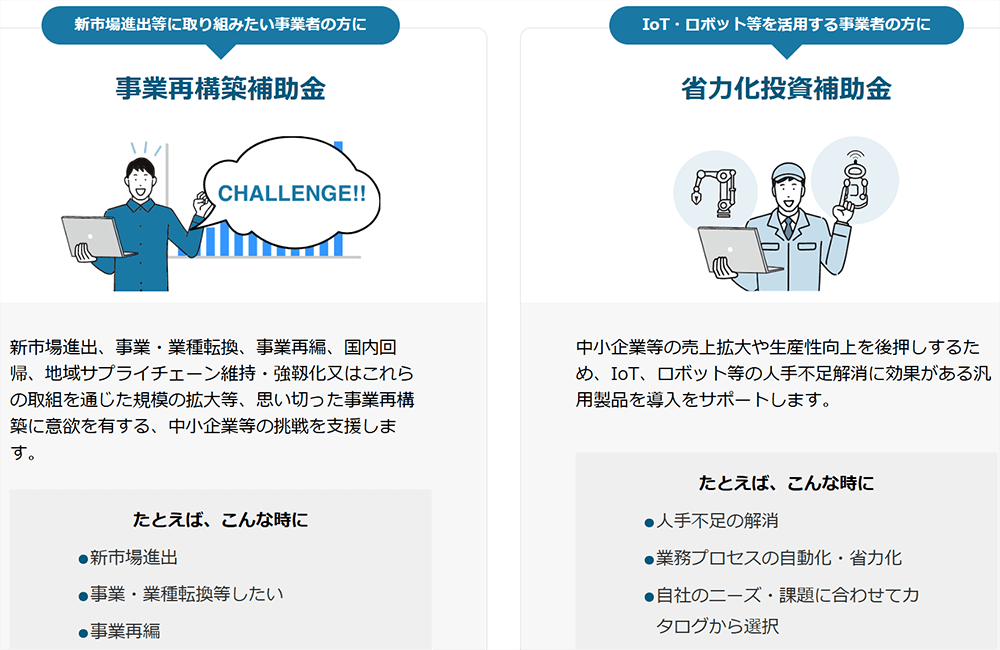
出所:ミラサポplus(経済産業省・中小企業庁)
最後に
物流業界は働き方改革の影響もあり、課題のある業界と思われがちです。ただ、この経営環境をチャンスと捉え、設備投資などを行う企業が生き残ることができると考えます。例えば、設備投資によって、物流機能のみならず倉庫機能・サプライチェーンの司令塔として活躍する可能性を広げることができます。物流機能の一部を担うのではなく、企業のロジスティクス戦略を一手に担うことで高付加価値の事業体へとアップデートすることが、持続的な企業発展のポイントとなります。
また、設備投資にあたっては、今回ご紹介した資金調達方法のメリット・デメリットを総合的に勘案した判断ができると良いと考えます。設備投資によるキャッシュフローを見積もり、車両や倉庫・燃料費の高騰によるコスト上昇を考慮するなど、保守的にシミュレーションした場合でも返済可能な資金繰り計画のもと資金調達の実行が必要です。特に受注のタイミングによっては、自社トラックや人材不足によって、協力運送会社などの庸車で仕事を回すなど突発的な資金需要が発生するため、ゆとりを持った資金繰りを回すことが重要です。投資(資金調達)においても、悲観的に準備し、楽観的に行動していきましょう。
関連記事
-

制度会計と管理会計の違いを徹底解説!企業成長に必要な「両輪」とは
- 資本政策・財務戦略
-

収益構造を見直して企業成長を実現!成功する5つの条件
- 資本政策・財務戦略
-

財務会計と管理会計の違いは?
- 資本政策・財務戦略
-

企業価値を高めるIR活動とは
- 企業価値向上
-

管理会計とは?導入のメリットとポイントを解説
- 資本政策・財務戦略
-

シェアードサービスとは?導入のメリットと成功事例
- グループ経営
- 資本政策・財務戦略
-

グループ経営におけるシェアードサービス
- グループ経営
-

 コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト
コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト