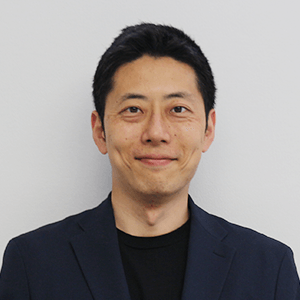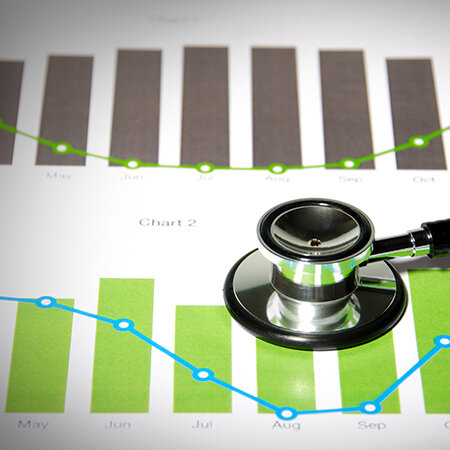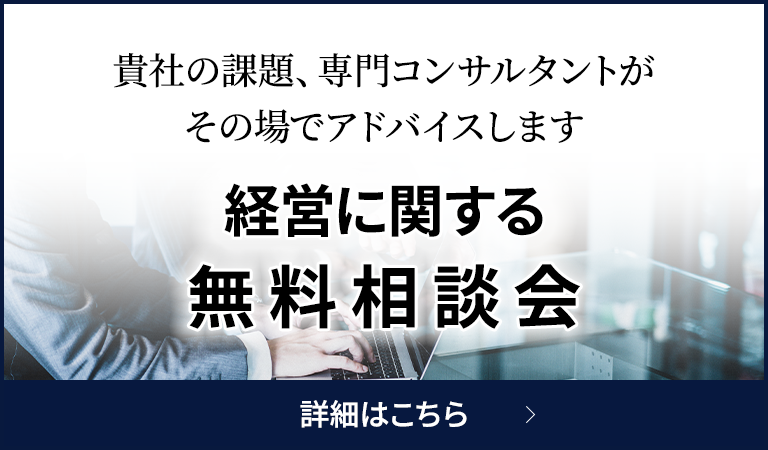高収益を実現するための
組織戦略のポイント
- 企業価値向上

閉じる
コロナ禍を経て、経済サイクルと社会や顧客の価値観が同期化し劇的な転換が行われるなかで、あらゆるシーンで新しい需要が湧き出ています。既存のマーケットや顧客だけをターゲットに自社の価値を提供するだけでは、更なる成長へのチャンスを逃すだけでなく、ライバルからも出遅れてしまう競争環境にあるといえます。
新たなマーケットで、新しい顧客を創造していくための価値提供を行うには、組織としても権限委譲・分散による意思決定スピードの加速化と、分散された意思決定を統制するガバナンス機能の再設計や、新たな収益源の開拓を行い、事業ポートフォリオの拡大をもって収益性を向上させることを推進しなければなりません。
本コラムでは、企業を取り巻く経営環境の変化にいち早く対応し、経営資源の最適化を図るための組織デザインについて解説いたします。
高収益モデルを支えるコーポレート戦略
コロナ禍を経て人々の働き方や価値観、生活スタイルなどが大きく変化したことで、新たな課題が多く見られるようになりました。テレワークによるコミュニケーションスタイルの変化や、その難しさ、IT需要の加速化による関連企業の急成長など、国内マーケットはシュリンクする一方で、新たな課題やマーケット、顧客需要はまだまだ開拓の余地があります。これまで目を向けていなかったマーケット、顧客、需要を取り込むことで成長することが求められており、そのためには迅速な意思決定のもと競合企業に対して優位性を確立していく必要があります。
日本における組織体制とは元来ヒエラルキー組織であり、変化が激しい社会に対し、意思決定が遅くなるというデメリットがあります。従来の職位や階層のみにこだわることなく、適切な価値判断基準のもと、意思決定権限を委譲・分散させることや、その意思決定構造を定期的に再定義することにより、組織体制を柔軟に変化させることが新たなマーケットを創出していくための戦略推進にとって必須となります。
権限の委譲・分散を行うことで、組織体制には迅速さ・柔軟性が生まれますが、ルールが整備されていない状況では、経営として一体感が失われ、権限委譲・分散を行って達成しようとした変化を生み出すことはできません。新たなマーケットに対して、組織として打つべき手を決定していくためには、コーポレートガバナンス体制を再構築し、成長を支える強固な基盤を整備することと、健全な意思決定を行う材料としてダッシュボードを活用したKPIマネジメントによる経営の見える化が求められます。
持続的成長を実現する組織デザインと組織機能
経営環境の変化と共に生まれる顧客を創造し、持続的成長を実現していくためには、事業ポートフォリオの多角化による機能強化や新事業の開発など、急速に変化するマーケットのトレンドを的確に捉え、ニーズにアプローチする体制を強化する必要があります。そのためには、マーケティングやブランディング、経営企画、財務などの戦略推進機能を確立し、各機能が付加価値を発揮する全社最適での機能・推進体制を整えることが重要となります。
持続的成長を実現する組織デザインの中で、「マーケット視点」で急速に変化するマーケットのニーズを的確に捉え、マーケット最適で経営資源を配分することが着眼点となります。全社で事業を成長させ、最終的には一事業としてインキュベートさせることを目指すのが望ましいといえます。そのためには、インキュベート組織の機能と責任・権限を明確化することが重要であり、それが新たな価値の創造につながるのです。
マーケット視点での組織デザイン
新たな成長機会として、マーケットに対して最適なアプローチを続けるためには、変化するマーケットニーズをリアルタイムに把握し、迅速な意思決定のもとで新事業開発やリブランディングを行う必要があります。このとき、既存事業のリーダーが兼任で新たな事業を担当すると推進力が高まらないことが多く、新事業開発を行うためには、最適な資源投下と組織デザインを両面から推進していくことが必要といえます。したがって、マーケット視点で組織をつくり、事業開発における役割と権限を与えることにより、推進力を担保していくことが必要ですが、はじめから独立した事業部として立ち上げるには高いハードルがあります。
そこで、組織化に向かうためのいくつかのステップをご紹介します。
【STEP1】横串でのプロジェクト組成
現状の組織の中で、全社横断的なプロジェクトとして製品・サービス開発を実施します。プロジェクトリーダーには、事業化に向けた製品化・サービス化にとどまらず、収益面からも十分な検討を行ったうえで事業計画やロードマップを検討させ、事業化を推進させます。
【STEP2】横串プロジェクトのプロフィット化
プロジェクトを立ち上げ、事業化を推進させた次のステップは、プロジェクトのプロフィット化となります。この段階ではプロジェクトを組織として独立させず、収益単位として捉えたうえで目標と実績を集計させ、事業を成長・拡大させることを推進します。人材を投入しつつ、経営資源も配分しながら組織化に向けた準備を進めていきます。事業内容にもよりますが、プロジェクトの成果となる売上高は3~5億円を目安とし、収益事業として成立させることを目指して推進させていきます。
【STEP3】事業部としての組織化
プロジェクトとして収益事業化する見通しが立ち、売上高が最低5~10億円規模まで成長した段階で、事業部として独立させることを検討します。事業をつくることはリーダーをつくることでもあり、リーダー育成など人的資本投資も組織化のテーマとなります。戦略推進のスピードはリーダー人材の質と数によっても決まることから、事業執行を任せられる人材を数多く育成するための、教育システムの構築も重要となります。
コーポレート戦略のあり方
本コラムでは、高収益モデルを推進していくためのコーポレート戦略について取り上げました。
製品・サービスや事業スキームそのものの魅力度はもちろん重要ですが、戦略としては組織としてやること、やらないことを意思決定できることが、高収益モデルを生み出していくためには不可欠となります。
経営環境の変化が急速に進むなかでも、他社よりもいち早く進むべき方向性を意思決定し、実行できる体制を組織面からも設計していくことが、結果として競争力を高めることにもつながります。
関連記事
-

物流業におけるROIC改善事例を解説!企業価値を高める方法とは?
- 資本政策・財務戦略
-

資本政策 事例|押さえるべき3つのポイントを事例を基に解説!
- 資本政策・財務戦略
-

組織における意思決定の種類とは?トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!
- コーポレートガバナンス
-

製造業における収益改善の2つの視点と5つのステップを徹底解説!
- 資本政策・財務戦略
-

-

収益改善の成功事例 | 効果的なポイントについて徹底解説!
- 資本政策・財務戦略
-

-

中堅企業が実装すべき財務戦略~ホールディング経営におけるトップのリーダーシップ~
- ホールディング経営
 コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト
コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト