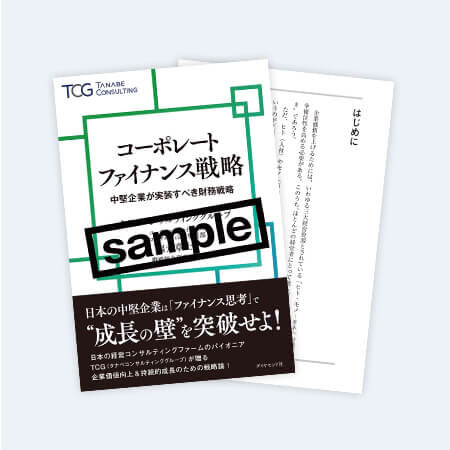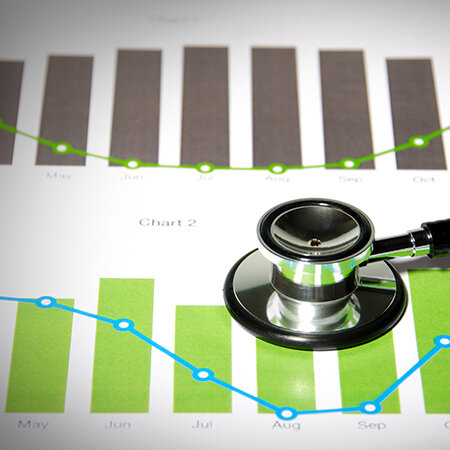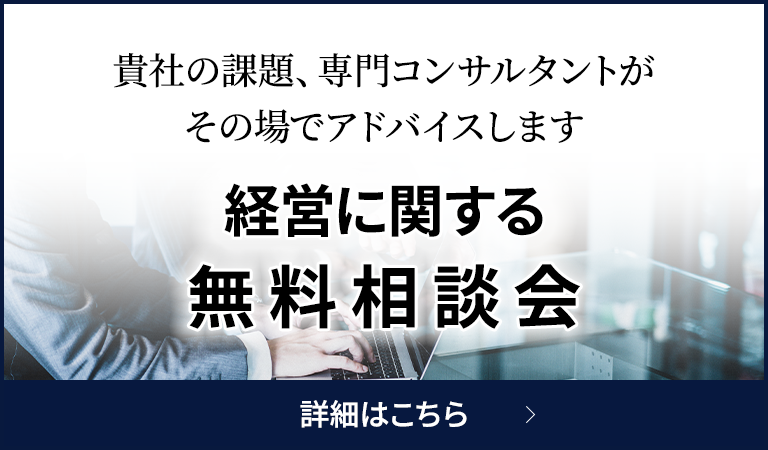製造業における業績マネジメントの
ポイントを解説!
製造現場のKPI設定も
- 企業価値向上

閉じる
製造業の現場における業績マネジメントには3つの視点があります。
1つ目は、製造現場の企業資源(ヒト、モノ、カネ)を部門単位や品目単位、工程単位で把握し、管理する「原価管理」です。
2つ目は、製造現場の目標達成度を評価するために主要業績評価指標(KPI:key performance indicator)を定めて管理する「製造現場KPI評価」です。
3つ目は、製造現場での作業をリアルタイムに捉える「現場作業監視」です。
本コラムでは、この3つの視点を具体的に解説します。
1.原価管理
製造現場の生産活動を、生産する製品と製造の流れ、さらに製造に関わるすべてのコストに関する項目を把握し、原価の視点で「見える化」します。予算立案時点での標準を決め、日々単位で把握した実績での製造指図ごと収率管理、能率管理、さらに月単位で製造委託料、社内労務費や経費の加工費を加味した実績原価(実績量×標準単価)、さらに実際原価(実績量×実績単価)を算出して、予算・標準と実績、実際との差異を分析し、生産業績を金額で評価します。1工場を1企業とみなして、管理用の製造原価報告書を作成することも行われています。
製造業の原価管理とは、製品の製造やサービスの提供に必要なコストを管理することです。コストマネジメントとも呼ばれます。目的としては、利益率の改善や経営判断、リスク管理を行うこと、さらにコスト削減や正確な原価予測を行い、利益を最大化して会社の成長につなげることが挙げられます。
手順は下記となります:標準原価(原価)の設定→原価計算→差異分析→改善/分析行動の実施
原価の管理方法としては、以下の2つがあります:①累加法:前工程の製造原価を次の工程に前工程費として集約する計算方法と原価管理システムの活用:納期や在庫などの製造現場工程の情報を一元的に管理する仕組み
また、原価管理の課題としては、品質重視で原価管理が細かく実施されていないことや、市場価格に対して割高な原材料の仕入れ、過剰在庫による不要な保管費が挙げられます。原価管理のポイントとして、導入目的の明確化、在庫管理との連動性、多言語・多通貨対応、使いやすさ、 サポート体制の確認が必要となります。
2.製造現場KPI
製造現場では業務の「見える化」を実現して生産効率などを高めていくために、KPIを利用します。新たな設備を導入したり、様々な技術を駆使し改善を図っています。
※KPIとはKey Performance Indicatorの略です。似たような言葉に「KGI」がありますが、KGIは企業の大きな目標を指し、KPIはその達成に欠かせない中間目標という違いがあります。
製造現場におけるKPI評価では、製造に関わる「ヒト・モノ・カネ(設備)」を指標としたKPIを作成して生産性を高めることを目的にします。その際には、QCD(品質、コスト、納期)の観点を含めることが重要です。ただし、品質を向上させると原価が高くなる、あるいは原価を下げると品質が低下するなど、相反する問題が頻繁に発生します。そこで、KPIツリーを作成して問題をツリー状に分解し、その原因や解決策を導き出すことができます。
まずは問題をKGI(重要目標達成指標)として設定し、その解決策をKPIで導き出して評価します。日々のアクションはKPIで設定し、進捗を管理していきます。導き出された課題に対しては、PDCAサイクルを回して改善に取り組みます。
製造業における国際基準のKPI『ISO22400』は、MES(製造実行システム)領域でのKPIを定めています。ISO22400は、次の6つの分類と合計34項目のKPIから構成されています。
(1)生産性:労働生産性、負荷度、生産量、負荷効率、利用効率、総合設備効率、正味設備効率、設備有効性、工程効率
(2)品質:品質率、段取率、設備保全利用率、直行率、廃棄度合、工程利用率、手直率、減衰率
(3)能力:機械能力指数、クリティカル機械能力指数、工程能力指数、クリティカル工程能力指数
(4)環境:総合エネルギー消費量
(5)在庫:在庫回転率、良品率、総合良品率、製品廃棄率、在庫輸送廃棄率、その他廃棄率
(6)保全:設備負荷率、平均故障間隔、平均故障時間、平均復旧時間、改良保全率
製造業のKPIは、自社の製造現場に合ったものを設定することが重要です。
以下の項目に該当するものを指標にしましょう。
(1)改善の余地がある
(2)改善目標を立てることができる
(3)継続して実績を把握できる
(4)目標と実績を比較することで改善策を検討できる
製造業でKPI管理を始めるにあたり、以下のようなことに注意しましょう。
(1)目的を見失わない
システムや仕組みにとらわれず、KPIで管理する目的を常に振り返り、改善し続けることが重要です。KPIの形が整ってからITシステムを導入しても遅くはありません。
(2)時系列を重視する
時系列で把握できないものは、「見える化」による評価や検証ができません。時系列で比較可能なものをKPIに設定することが大切です。
(3)現場の関係者が運用する
KPIの目標と実績にギャップがある場合、その原因は現場にあります。権限を持つ現場の関係者が、継続的に原因分析を行い、改善策を見出すことが重要です。
3.製造作業監視
ネットワークカメラを活用して、作業の状況をリアルタイムで監視します。具体的には、異常発生の瞬間を「見える化」し、原因分析や現場の情報共有を行います。また、録画映像を活用して「ムリ、ムダ、ムラ」の原因を分析します。さらに、動画マニュアルや現場へのタイムリーな情報配信により、「標準化」の支援も行います。このようにして、4M管理(人:Man、装置:Machine、方法:Method、原材料:Material)を実現し、QCD(品質、コスト、納期)の向上を目指します。
まとめ
製造現場におけるKPIは、利益などの資金管理と作業効率の大切な指標となります。継続的にQCDを向上し続けるには、より深く、高い精度で「ムリ・ムダ・ムラ」の原因を特定し、早期の課題解決が欠かせません。
また、QCD以外にも事故発生件数や健康経営の指標を含め、従業員の働きやすさや満足度の向上を目指している企業も多くあります。事業を拡大していくに伴い、管理すべき数値も対処すべき問題も膨れ上がりますので、自社の目的に応じたKPIを活用し業務を改善していきましょう。
関連記事
-

制度会計と管理会計の違いを徹底解説!企業成長に必要な「両輪」とは
- 資本政策・財務戦略
-

収益構造を見直して企業成長を実現!成功する5つの条件
- 資本政策・財務戦略
-

財務会計と管理会計の違いは?
- 資本政策・財務戦略
-

企業価値を高めるIR活動とは
- 企業価値向上
-

管理会計とは?導入のメリットとポイントを解説
- 資本政策・財務戦略
-

シェアードサービスとは?導入のメリットと成功事例
- グループ経営
- 資本政策・財務戦略
-

グループ経営におけるシェアードサービス
- グループ経営
-

 コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト
コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト