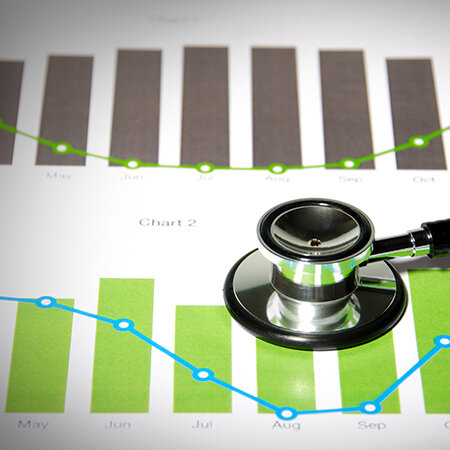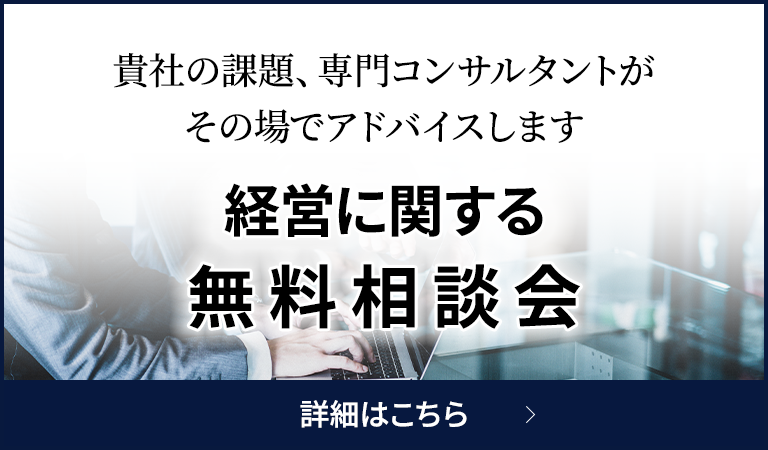株式移転、株式交換とは?
デメリットや留意点も解説
- 企業価値向上

閉じる
ホールディング経営とは、持株会社を中心に複数の事業会社でポートフォリオやバリューチェーンを形成し、グループの競争力を高めることで持続的成長を目指す経営体制のことを指します。近年、ホールディングス化を検討・実行する企業は増加しており、その規模感も大手企業に限らず、中堅企業・中小企業においてもひとつの経営技術としての普及が進んでいます。
本コラムでは、そのなかでもホールディングス化への移行手法として注目される「株式移転」と「株式交換」の違い、それぞれのメリット・デメリット、さらに上場企業の事例をご紹介します。
株式移転、株式交換とは?
株式移転:新設する会社に株式を取得させる
株式交換:既存の会社に株式を取得させる
「株式移転」とは、複数の会社が発行済み株式の全部を新たに設立する会社に取得させる手法です。一般的には、「新たに設立する会社」=「ホールディングス」として、持株会社を設立する手法が多く用いられます。また、異なる株主がそれぞれ経営する企業同士を経営統合することを目的に、共同出資のような形でホールディングスを設立する手法(この場合は共同株式移転と呼ぶ)として活用されるケースもあります。
「株式交換」とは、会社が発行済み株式の全部を他の会社へ取得させ、完全親子関係を構築する手法です。株式移転との最も大きな違いは、新たに会社を設立せず、既存の会社で親子関係が形成される点にあります。

株式移転、株式交換のメリット・デメリット
株式移転、株式交換のメリット
株式移転、株式交換の最大のメリットは、M&A(買収)との比較において、買収資金を必要としないことです。
親会社となる会社が子会社となる会社の株式を「買収」する場合は、当然ながら子会社となる会社の適切な企業価値評価に基づき、買収資金を用意する必要があります。また、買収資金は子会社の株主へ渡るため、経営統合後のグループにおけるキャッシュが放出される形となり、一定の財務基盤の棄損は避けられない状態となります。
株式移転、株式交換の買収対価は、資金ではなく自己株式を渡す取引であり、グループにおけるキャッシュの流出を防ぐことができます。
株式移転、株式交換のデメリットや留意点
1.株主構成が変動する可能性がある
単独株式移転や同一の株主における株式交換においては、両手法を実行した後にも株主構成が変動することはありません。一方、異なる株主が関係する共同株式移転等においては、経営統合後の株主構成が変動します。
株式移転、株式交換はともに、そもそも株主の同意が必要な組織再編行為になり、株主にとっては、経営統合後の自身の持株割合や議決権割合がどのように変動するかが意思決定に大きく関わってきます。
例えば、共同株式移転において異なる株主が保有するA社とB社が共同でホールディングカンパニー(持株会社)を新設する場合、ホールディングカンパニーの株式の保有割合は、A社とB社の企業価値に基づき算出された株式移転比率によって決定がなされます。当然ながらこの株式移転比率は、各事業会社の企業価値を公正に反映したものが要求されます。株式移転比率の計算によっては、仮にこれまでB社の100%オーナーであった株主であったとしても、経営統合後は新設したホールディングスにおいては過半数未満の議決権しか保有できないことになる、というケースもありえます。
このように、経営統合後の株主構成が変動する懸念があることを、念頭に検討することが重要なポイントとなります。
2.税務面、会計面、手続き面の複雑な検証が必要となる
同一の株主における単独での組織再編であっても、また、異なる株主が関係する組織再編であればなおさら、税務面・会計面・手続き面での複雑な検証が必要となります。
税務・財務上は、まず当該組織再編が税制適格に該当するかの判断が求められます。さらに、親会社となる会社における取得原価や、のれんの処理など、専門的な知識に基づく判断が必要です。
また、手続き面においても、株主総会での承認、債権者保護手続きの実施など、多くのステークホルダーが関与する手続きが求められるケースがほとんどであり、手続き上の不備が生じると重大な問題につながるため、慎重な対応が求められます。
その意味では、組織再編に精通する、税務・法務・会計等の専門家の助言を得ながら実行することが基本となります。社内に専門家がいない場合は、外部リソースを活用し、当該組織再編におけるプロジェクトチームを組成して実行することが一般的な流れとなります。
あるべき経営統合の姿
兄弟型か、親子型か、ホールディングス化か
ここまで株式移転、株式交換の手法について、その概念やメリット・デメリットに触れましたが、より重要となるのは自社が目指すあるべき経営統合の姿を明確にすることです。手法はあくまで手段であり、どのようなグループ体制を描きたいかという目的が先立って検討されているべきです。
経営統合の類型としては、以下の3つが考えられます。
1.兄弟型
あえて直接的な資本上の繋がりを作らない形態(グループとして考えるのであれば、株主は同一であることが前提)です。事業会社同士が対等かつ独立した関係を維持しやすいというメリットがある一方、両事業会社の株主が共通であったとしても資本が独立した状態となるため、グループとしての帰属意識や一体感を醸成することが極めて難しくなるデメリットがあります。
2.親子型
株式交換実施後、事業会社間において親子関係を構成する形態です。両事業の一体感を維持する形で経営統合を比較的簡便に実施することができます。一方、事業会社同士が主従の関係になり、一般的には親会社の業績や価値判断が優先されがちという懸念点があります。
3.ホールディングス化
兄弟型、親子型のデメリットを包括的に解消できる手法です。ただし、ホールディングス化にしたからといってグループ経営が思うように進むわけではなく、体制に応じた高次のマネジメントシステムが必要となります。

さいごに
企業経営における組織再編手法は多岐にわたり、かつ、複雑な検証が必要なケースが大半になります。当然ながら、これらの経営知識を習得しておくことは自社の選択肢を広げるうえで大変意義のあることだと考えます。
ただし、手法について専門知識が必要であるがゆえに、手法の検討が先行し、本質的な目的に対する議論がないがしろにされているケースをコンサルティングの現場でよく目にすることがあります。本コラムで触れた通り、経営統合であれば自社にとって最適な経営統合の姿がどのようなものか、ということをまず研究することから始めるのがよいでしょう。
関連記事
-

物流業におけるROIC改善事例を解説!企業価値を高める方法とは?
- 資本政策・財務戦略
-

資本政策 事例|押さえるべき3つのポイントを事例を基に解説!
- 資本政策・財務戦略
-

組織における意思決定の種類とは?トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!
- コーポレートガバナンス
-

製造業における収益改善の2つの視点と5つのステップを徹底解説!
- 資本政策・財務戦略
-

-

収益改善の成功事例 | 効果的なポイントについて徹底解説!
- 資本政策・財務戦略
-

-

中堅企業が実装すべき財務戦略~ホールディング経営におけるトップのリーダーシップ~
- ホールディング経営
 コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト
コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト