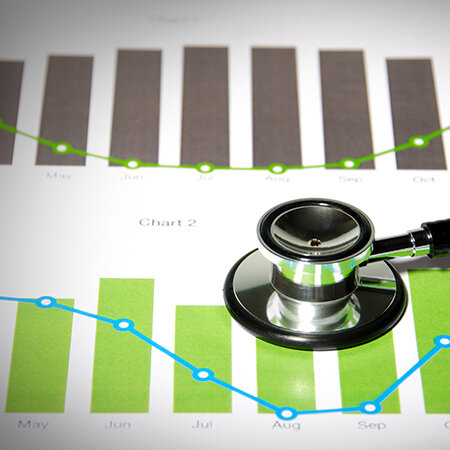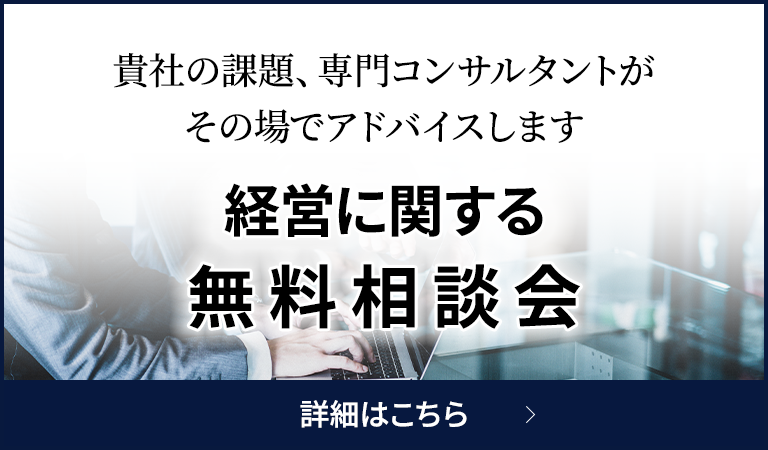業績マネジメントとは?
概略と実行ステップを解説
- 企業価値向上

閉じる
企業経営において、持続的成長を実現するためには、業績を計画的に創り出すことが重要です。そのためには、結果として得られる業績を追い求めるのではなく、計画的に業績を出すために未来視点で考えることが求められます。今回は、未来視点で考えていくための業績マネジメントについて概略とポイントについて解説します。
業績マネジメントの概略
企業経営における業績マネジメントは大きく以下の3つのレベルに分けられます。
1.遅行管理型マネジメント
マネジメントレベルが低く、月次決算の完成には1カ月前後かかる場合があります。特徴としては「結果はわかっていても手遅れになるケースが多い」、「良ければ褒める、悪ければ叱るの繰り返しに終わる」、「目先の短期業績主義の弊害が随所に派生する」ことが挙げられます。
2.同時管理型マネジメント
月次決算がタイムリーに把握できる程度のマネジメントレベルです。特徴としては「現状から見える課題を業績対策案に即反映できるという意味では効果は期待できるものの、プロセス管理にとどまってしまうケースが多いため、対策の範囲は限定的になることがある」といった点が挙げられます。
3.先行管理型マネジメント
業績結果につながるプロセスや原因を先行でマネジメントするレベルです。特徴として3~6カ月先・1年先を見通して、顧客または案件情報を管理できることが挙げられます。
上記の3つのレベルと比べた時に、自社の業績マネジメントはどの分類に当てはまるでしょうか。
タナベコンサルティングでは、業績マネジメントのあるべき姿として、多くのクライアントに「業績先行型マネジメント」の導入を提唱しています。目標数値から、着地見込み数値を差し引いた差額をつかみ、その差額を埋める対策を、先手・先行で立案し実行していく未来志向型のマネジメントスタイルです。今回の内容では業績先行型マネジメントに絞ってポイントをご紹介します。
業績先行型マネジメントの導入・展開ステップ
業績先行型マネジメントのポイントについては、導入・展開ステップに基づいて簡単にご紹介いたします。
大きく5つのステップがあり、それぞれのステップにおける重要な考慮事項も記載しています。
【導入ステップ】
ステップ1:自社の業績特性を把握する。
自社の業績特性を掴み、特性に即した手を打つということです。
代表的な業績特性タイプと対策の着眼は、以下のように分類されます。
(1)見込体質型【自社ブランドを持つ量産型メーカー等(需要予測をもとに見込み生産(仕入)をし、業績をつくる業種】
対策の着眼として、①需要予測、景気予測の精度アップ、②需要創造の先行仕掛け、③商品の独自性追求、などが挙げられる。
(2)ベース体質型【自動車・家電メーカー等への部品供給会社、設備・メンテナンス業、人材派遣業等(一度取引が始まると、継続収入が見込める業種)】
対策の着眼として、①ベースとなる売上の付加価値部分で固定費をまかなう「固定費カバー率」の向上、②リピートオーダーを作るための仕組み・体制・サービスづくり 、などが挙げられる。
(3)スポット体質型【建設業、住宅ビルダー、設備機械メーカー等(単発取引を主体に業績をつくる企業)】
対策の着眼として、①受注見込み情報のストック、②受注確率に基づくプロセス管理 、などが挙げられる。
上記のように、自社の業績特性を把握し、それに即した対策を立てることが重要です。
ステップ2:業績を区分して捉える
こちらは、現状の業績の構成は、ベース先に支えられているのか、スポット対応で成り立っているのかを分析し、対策を講じるということです。
業績の区分としては大きく3つに分けます。
(1)ベース(安定既存取引先の客先・既存納入商品)
(2)ニューベース(新規顧客で今後安定継続受注できる取引先)
(3)スポット(新規顧客・既存顧客で継続性のないもの)
上記の区分から考えた時に売り上げ構成の比率を見て、今後の対策を考えていきます。
例えば、ベース売上比率が低い場合、固定の継続購入客数が少ないことや定番商品が少ないなどの原因が考えられますが、そちらに対してどのように改善していくかを検討します。
ステップ3:管理フォーマットの作成
フォームを活用して差額を明確にする工程です。
まずは、現段階での差額を把握し、差額を埋めるための情報がどのくらいあるのかを確認します。
この時に、その差額を埋めるための情報については、ランク付けを行うと予測が立てやすくなります。
例えば、Aランク、Bランク、Cランクなどの項目を設定し、その基準に従ってランク付けを行うと効果的です。
【展開ステップ】
ステップ4:差額対策の協議と実行管理
実績と見込差額から考え、差額を埋める情報はどれだけあるのか、ない場合はどのように手を打つかについて検討します。
また、見込を確定させていくためにどのようなプロセスを踏むのかも協議する必要性があります。
情報管理については、訪問すべき優先順位、キーマンへのアプローチ、次のアプローチは決まっているかなど案件ごとに細かく協議します。
ステップ5:着地見込みの精度を上げる
着地見込みがぶれないよう、案件決定までのプロセスを定め、期日管理を行い進めていきます。
以上の5つのステップが業績先行型マネジメントの進め方です。自社の特性を押さえたうえ、これらの手法を活用することで、業績を先行でマネジメントし、持続的な成長を実現するためのヒントとなれば幸いです。
まとめ
今回は業績マネジメントにおける「業績先行型マネジメント」についてフォーカスしてご紹介しました。企業経営においてよく言われることは、「増えては困るモノが勝手に増えて、減っては困るモノが勝手に減る。」ということです。勝手に「増えるモノ」については「予算統制」して増えないようにし、勝手に「減ってしまうモノ」は「目標管理」して、増える努力をしていくことが大切です。今回のテーマに関して言うと、業績は何もしなければ自然に減少してしまうため、積極的な業績マネジメントが求められます。本コラムの内容が持続的に成長するための業績マネジメントについて考えるヒントとなれば幸いです。
関連記事
-

物流業におけるROIC改善事例を解説!企業価値を高める方法とは?
- 資本政策・財務戦略
-

資本政策 事例|押さえるべき3つのポイントを事例を基に解説!
- 資本政策・財務戦略
-

組織における意思決定の種類とは?トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!
- コーポレートガバナンス
-

製造業における収益改善の2つの視点と5つのステップを徹底解説!
- 資本政策・財務戦略
-

-

収益改善の成功事例 | 効果的なポイントについて徹底解説!
- 資本政策・財務戦略
-

-

中堅企業が実装すべき財務戦略~ホールディング経営におけるトップのリーダーシップ~
- ホールディング経営
 コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト
コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト