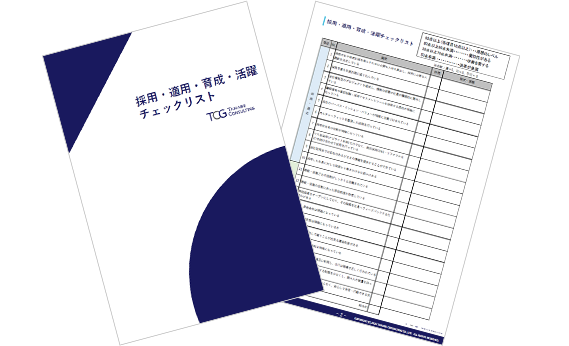人事コラム
採用迷子の中堅・中小企業必見!
今の時代に合った新卒採用ストーリーの描き方
【第4回】採用活動現場でちょっとした工夫をしよう(実践編)
採用迷子の中堅・中小企業必見!今の時代に合った新卒採用ストーリーの描き方と題して
イマドキの学生を採用する戦略について考えていくこととした当コラム。今回は第4回。

第1回では、イマドキ学生が共感する新卒採用ストーリーを描こうというテーマで、新卒採用ストーリーの定義や描き方について触れ、
第2回では、学生が知っている会社になろう(認知度UP編)というテーマで、どうやって学生に出会うのか?ということについて解説した。
第3回では、学生が入りたい会社になろう(志望度UP編)というテーマで、どうやって学生の志望度を上げるのか?ということについて説明している。
まだ読んでいない方は、まずはそちらを確認していただきたい。
第1回 https://www.tanabeconsulting.co.jp/hr/eye/detail192.html
第2回 https://www.tanabeconsulting.co.jp/hr/eye/detail212.html
第3回 https://www.tanabeconsulting.co.jp/hr/eye/detail222.html
当コラムは全5回で構成されており、それぞれ
第1回 イマドキの学生が共感する新卒採用ストーリーを描こう
第2回 学生が知っている会社になろう(認知度UP編)
第3回 学生が入りたい会社になろう(志望度UP編)
第4回 採用活動現場でちょっとした工夫をしよう(実践編)
第5回 2030年の新卒採用を考えて他社に差をつけよう
となっている。
今回は第4回 「採用活動現場でちょっとした工夫をしよう(実践編)」をお送りしたいと思う。
実際の採用活動現場において、成果を出すための"実践"に重きをおいた内容とさせていただく。

戦略を実践できる体制をつくる
様々な企業で採用コンサルティングをさせていただいた筆者の感想として、成果(採用)が出るかどうかの一番の分かれ道は、『人事専任人材を置くかどうか』である。
以前と比べて採用の業務は多岐に渡る。
また、採用後の新入社員の受け入れ(オンボーディング)や、人事として社員教育の段取りもするとなると、1年中忙しいというのが中小企業の人事業務の現状である。
しかし、中堅・中小企業はまだその実態を理解しておらず、人事の重要性を低く見ているところが多い。
そのため、総務メンバーが片手間で実施しようとしたり、採用プロジェクト等で推進しようとする。
しかし、この2つはそれぞれ下記の理由でうまくいかない。
(1)総務メンバーによる兼務
採用よりも、給料計算や支払い等の経理の業務を優先(実際、支払いが滞れば大問題)し、その結果、採用活動が推進されず採用がうまくいかない。
(2)プロジェクト形式
責任感を持って取り組む人がおらず推進速度が遅い。また、毎年メンバーが変わるため、知見やノウハウが積みあがらない。
上記のような課題を解決し、かつ採用の成果を出そうと考えた際のおすすめのスタイルは
専任者+プロジェクト形式
という形である。最優先業務が人事という専任者が、責任感とスピード感をもって実施するという点と、専任者には毎年知見やノウハウが積みあがっていくということが、採用活動を年々強化していくことに繋がる。
また、一人だけではできることが限られているため、プロジェクトという形を取り、人事を中心に各部署メンバーが協力することで、採用活動の推進力が出てくる。
まだ人事専任者を設けていない中堅・中小企業は、ぜひこの機会に専門人材を設けることを検討していただきたい。

認知を上げる実践の中での工夫
第2回では認知度UPに向けて5つの項目を記載したが、その深堀と、それ以外の実施内容についても記載していこう。
(1)合同企業説明会での呼び込みは必須へ
コロナ禍以降、合同企業説明会は大きく変わった。大きな変化のひとつに、参加者数の制限がある。参加企業1社につき、2人までしか参加できない等、つい最近までは参加者数の制限がつきものだったが、ここ最近はその制限がなくなりつつある。また、接触を極力減らすという意味で、呼び込みも禁止となっていたが、これも少しずつ解禁されているように思う。そのため、最近の合同企業説明会では、ブースで説明するメンバーと、説明会中を自由に動き回って、チラシを配ってブースへの呼び込みを実施するメンバーという風に役割分担をしている企業は着席数を伸ばすことができている。合同企業説明会へと参加する企業は、できる限り多くのメンバーを参加させ、ブースへの呼び込みを強化するようにしよう。
※ただし、いまだに呼び込みを禁止事項としている説明会も多くあるため、問題ないかどうかは主催者に確認しよう。
(2)大学訪問をしよう
大学を訪問しても成果に繋がらないという話をよく聞く。果たしてそうだろうか?筆者のクライアントの建設会社は、大学から毎年3名程紹介を受けることができている。また別の、製造業のクライアントは毎年同じゼミから1名採用することができている。では、成果に繋がっている会社とそうでない会社の違いは何だろうか?
筆者は、『キーマンに会えているか?』ということだと考えている。様々な大学の傾向を見てきた中で、ひとつの傾向を見つけた。それは、下記の通りである。
| 学生の傾向 | キーマン | |
|---|---|---|
| 国公立や各地域の 有名大学 |
就職活動への意識が高い 志望職種や業種が早期に決まっている 上記内容から、インターンシップへの参加が多かったり、自発的に就職活動に取り組む |
ゼミの教授 |
| その他の大学 | 就職活動への意識が低い 志望職種や業種が決まっている学生は少ない インターンシップへの取り組みも少なく、自発的に就職活動に取り組む学生が少ない |
キャリアセンターの担当者 |
国公立や各地域の有名大学のキャリアセンターに訪問すると、キャリアセンターに来てもらっても、学生は自らナビ等に登録し、インターンシップへ参加する企業を見つけているので、あまり意味がない。というようなことを言われることがほとんどだった。そのため、このような大学から学生を定期的に採用することができている企業は、自社の事業と関連性の高いゼミを見つけ、共同開発等を実施しながら、包括的連携等を結び、定期的に学生が来るような流れを創り出している。逆に、その他の大学のキャリアセンターに訪問すると、驚くことに多くの学生が担当者に相談に来ているのである。そのため、キャリアセンターの中でもベテランの方と仲良くなると、何人かの学生を紹介してくれる。ということがある。このように、大学によってキーマンが変わるのである。皆さんは今までターゲットや目的を明確にして大学へ訪問していただろうか?
今一度、上記のことを意識して訪問していただきたい。
(3)サークルや部活等のコミュニティと接点を持つ
先ほどは、ゼミやキャリアセンターの接し方について記載したが、その他にも学生と接点を持つ上で重要な切り口がある。それが、サークルや部活、もしくはアルバイトなどの学生のコミュニティとの接点である。例えばある会社では、社員が柔道部の卒業生であり、その柔道部の遠征費用や畳の張り替え等を支援している。その関係から、部員と社長との食事会等が定期的に開催されており、そのまま柔道部から数名採用することができている。また、ある会社では、グループ内の事業で飲食店を運営しており、そこでアルバイトをしていた学生を正社員で採用する等の工夫をしている。どのようなコミュニティと接触するかは、自社の社員が有している人脈等によるが、なんにせよ、直接学生と話すことができるよう、学生のコミュニティとの接点を意識して作るようにしてほしい。

志望度を上げる
経営戦略と人事戦略の連動がもたらす効果として、大きく2つある。
次に、第3回でも言及した志望度を上げる方法についてである。志望度を上げるための3つのステップを
STEP1 ペルソナを設定する
STEP2 ペルソナに響く尖ったキャッチコピーを考える
STEP3 ペルソナの期待や疑問へのANSWERを発信する
と説明した。上記内容に沿ってHPや各ナビの説明文を作成することが重要である。
今回はSTEP3について、HPやナビではなく、リアルの場でどのようにすればいいのかを深堀したい。
(1)合同企業説明会で志望度を上げるための工夫
合同企業説明会での説明の際についついやりがちなのが、一方的にパワポを説明して、最後に今後の選考の進め方を説明して終わりというやり方である。このやり方では、学生の志望度は上昇しにくい。重要なのは、学生の期待や疑問への答えを発信することであるから、着席してくれた学生が何を期待しているのか?何に疑問や不安を抱いているのかを聞くことが重要である。例えば、20分1ターンの説明会であれば、企業の説明は10分ほどで終わらせ、後は質疑応答や個々への説明の時間にして深堀していくことの方が重要である。そのための方法として
①大人数に着席してもらえる企業であれば、ブースに参加するメンバーを多めに準備し、ブース内で個々に対応
②着席する学生が少人数(1対1、1対2等)であれば、そのまま質疑応答や悩んでいること、不安に思っていることのヒアリング
等を実施し、ひとつひとつに自社であればどう解決できるのか?学生にとってどんなメリットがあるかを発信することで、学生の不安を解消し、志望度UPに繋がるので、ぜひとも実施していただきたい。
(2)志望度が上がる面接
採用活動において、面接は非常に重要である。ただそれは、「学生を選ぶため」ではなく、『学生に選ばれるため』である。
どういうことか?ひと昔前の採用は、企業側が選ぶ立場だったため、企業側が確認したいことを学生にひたすら質問する。という形で面接が行われていた。面接中に学生にプレッシャーをかけ、反応や耐性を確認する、圧迫面接等も普通に行われていた。
しかし今は立場が逆転し、学生側が選ぶ立場となっている。そのため面接も、「企業が学生を選考する場」ではなく、『学生が企業を選考する場』としての意味合いを持つようになってきている。
①面接官は、学生が自分をどう見ているか?ということを意識する
自分の上司になるかもしれない人が面接官であれば、学生は当然そういう視点で相手を見る。そんな中で威圧的な態度で面接に取り組めば、当然そんな上司のもとで働きたくないと考え、志望度は下がる。逆に、親切・丁寧に質問に答え、学生を安心させることができれば、その企業への志望度は向上する。
②面接を最後のPRの場だと考える
合同企業説明会や単独企業説明会でも様々なことを学生に伝えてはいるが、1対1でゆっくり話すという機会は意外と少なく、面接が初めての場となる。
この場を、ただ選考の場として使ってしまうのはもったいない。学生の回答に合わせて、自社のPRをはさみ、志望度UPに尽力することは非常に重要である。
例えば、学生の志望動機に合わせて、実際に入社後の具体的なことを説明し、『あなたのやりたいことはちゃんとチャレンジできる』ということを発信するだけで、良いPRになる。
こういったことを、各面接官ができなければ意味がない。中堅企業で、面接官が何人もいる場合は、このようなこともしっかりと面接官に教育することが重要である。
(3)共感型採用
最後に、共感型採用というあまり聞き覚えがないであろう採用の種類を記載して終わりにしたいと思う。
これは何かというと、
企業のミッションやビジョンに対して共感する求職者を採用する
ことである。この共感型採用は志望度UPに繋がる。最近の学生はSDGsへの関心やパーパスの重要性をよく理解している。そのため、自社がどのような社会的意義や存在価値があるのかをしっかりと発信すれば、そこに対して共感し、応募に繋がる学生はいる。
その際、ぜひとも意識してほしいのは、『社長が熱量をもって伝える』ということである。やはり、企業の未来について語る場合は、社長自ら話をすることで熱量が伝わり、説得力が大きく変わる。ある企業では、合同企業説明会の際に社長自らビジョンについて熱く語る場を設けており、その際に着席が非常に増えている。ぜひとも皆さんも共感型採用に取り組んでいただきたい。
さいごに
第4回は、少し具体的にどんなことをすべきなのかを記載した。
その他にも様々な具体策が存在するが、重要なのはその知見やノウハウが自社の中で積みあがっていく仕組みになっているか?である。
採用担当者が変わるたびに、自社の採用活動が大きく変わるという企業は、採用活動の仕組みやルールを明確にし、ちゃんと知見やノウハウ、人脈が積みあがっていくようにしていただきたい。
本事例に関連するサービス
関連動画