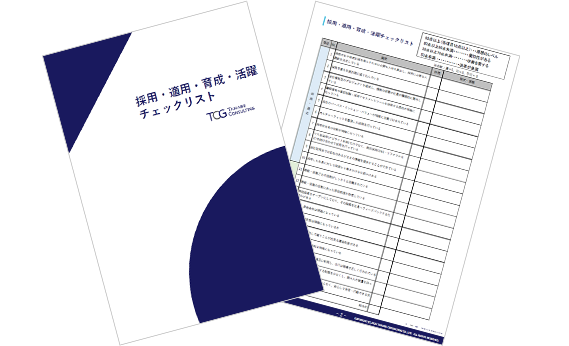人事コラム
採用迷子の中堅・中小企業必見!
今の時代に合った新卒採用ストーリーの描き方
【第2回】学生が知っている会社になろう(認知度UP編)
「採用迷子の中堅・中小企業必見!今の時代に合った新卒採用ストーリーの描き方」と題してイマドキの学生を採用する戦略について考えていくこととした当コラム。
今回は第2回。
第1回では、「イマドキ学生が共感する新卒採用ストーリーを描こう」というテーマで、新卒採用ストーリーの定義や描き方について説明させていただいた。
まだ読んでいない方は、まずはこちらを確認していただきたい。
当コラムは全5回で構成されており、それぞれ
- 第1回 イマドキの学生が共感する新卒採用ストーリーを描こう
- 第2回 学生が知っている会社になろう(認知度UP編)
- 第3回 学生が入りたい会社になろう(志望度UP編)
- 第4回 採用活動現場でちょっとした工夫をしよう(実践編)
- 第5回 2030年の新卒採用を考えて他社に差をつけよう
となっている。
今回は第2回 「学生が知っている会社になろう(認知度UP編)」をお送りしたいと思う。
中堅・中小企業が新卒を採用しようとすると4つの壁に当たる。
【中堅・中小企業が新卒採用をしていく上で当たる4つの壁】
- ・認知の壁:自社を知っているかどうか
- ・興味・関心の壁:自社に興味や関心があるかどうか
- ・応募の壁:自社に応募してくれるかどうか
- ・内定承諾の壁:自社が出した内定に応じてもらえるかどうか
その中でも特に、認知の壁は高く険しい。
中堅・中小企業が高く険しい認知の壁を乗り越えて、学生から認知されるにはどうすればいいのかについて考えていこう。
まず初めに現状認識として、学生がWeb上で自社を見つけられる状態にあるのかどうかを確認してみよう。
1.Web上で自社のHPにたどりつくことができるか
2.登録しているナビ上で自社のアカウントにたどりつくことができるか
どちらも、
1.社名
2.商品名
3.社長名
等、その会社のことを既に知っていないと出てこないワードを使うことなく、「〇〇県 〇〇業界 働きやすい」等、学生が企業を検索するであろう方法で検索していただきたい。
ナビであれば、検索オプション等も活用してもらったらよい。
どうだろう?自社のページやアカウントを発見することができただろうか?
多くの中堅・中小企業が、自社のページやアカウントにたどり着けなかった、もしくは辿りつけたもののかなり探したというのが現状なのではないだろうか?
ここで体験していただきたかったのは、HPやナビ、またSNS等の多くが、実は自社の認知に繋がっていないという事実である。
学生が、「どこの企業を受けよう」と考え探し始めた際に、既に社名を知られている、もしくは探している最中にすぐに社名が出てくる企業にならなければ、そもそも応募に繋がっていかないのである。
では、認知を拡大するためにはどのような方法があるか。筆者がクライアントをお手伝いさせていただく際に意識しているのは下記の5つの方法である。
【認知拡大に繋がる5つの方法】
- 1. ナビの活用
- 2. 合同企業説明会への参加
- 3. 宣伝広告の活用
- 4. SNSの活用
- 5. クチコミや紹介の強化
それでは、それぞれの方法について具体的に考えていく。

ナビの活用
第1回のコラムで説明したように、10年前と比較するとナビによる認知拡大の効果は大きく減少している。しかし、まだ新卒採用においてナビの担っている役割は大きい。
ナビを活用し、認知を広げる上で重要なのは、「ナビを活用しきっているか?」ということである。10年前であれば、ナビを登録していれば勝手にエントリーがきて、ある程度応募がくるものであった。"ナビに登録する"という行動自体が認知拡大に繋がっていたのである。しかし現在はナビに登録しても認知は拡大しない。
では、"ナビを活用しきる"とはどういうことか?大事なポイントは2つである。
(1)アクセス解析を活用して傾向を知る
ある有名ナビには、アクセス解析が備わっている。その機能を活用すると、自社アカウントのどのページにどれだけの人が来ているのかが日々確認できる。この機能の活用が重要だ。例えば、アクセス解析結果をよく見ると、学生がよく見ている曜日の傾向が見えてくる。筆者のクライアントの多くは月曜日のアクセスが増える傾向にあった。そのほかにも様々な傾向を掴むことが可能であり、アクセス解析機能を活用しきることが重要である。
(2)オプションの活用や文章の変更によるアクセス増加
オプションの成果の確定やページ内の文章のブラッシュアップにもアクセス解析機能が活用できる。オプションを活用した後や、文章を変更した後のアクセス数やクリック率の変化を都度確認し、成果の出るタイミングや内容に都度変更しながら、自社のページがブラッシュアップしていくことで、最終的にエントリーや応募に繋がっていく。
頻度の多い会社では毎週アクセス解析機能を活用して分析を実施し、ページ内の文章やオプション活用方法を変更している。ここまでやって初めて、「ナビを活用している」と言えるだろう。
合同企業説明会への参加
就職情報サービス会社の「学情」が1984年に日本初の合同企業セミナー「就職博」を開催してから40年がたったが、その間に採用のあり方が大きく変化してきており、合同説明会自体も大きく変化してきている。以前は大学3年生の3月から開催が当たり前であったが、現在は
・インターンシップ向けの合同説明会(3年生の4・5月~)
・業界研究セミナーと称した企業を探すための合同説明会(3年生の12月~)
等、早期に開催されるようになっていることに加え、理系向け・文系向け、業界・職種ごと等、様々な区分の合同説明会が存在し、多様化が進んでいる。
一方で現在ではWeb検索での情報収集が容易になっていることから、コロナ禍以降は学生の参加者数が大きく減少しており、ピーク時に比べると半分~1/3にまで落ち込んでいる。しかし、それでも中堅中小企業は合同説明会に積極的に参加すべきだと筆者は考えている。その理由は下記2点である。
(1)合同説明会は学生の目に留まる可能性が高い
(2)「認知」、「興味・関心」、「応募」という3つの壁を同時に超えることができる場
まず(1)について説明しよう。
先程記載したように、Web上で認知してもらうのは非常に難しいが、合同説明会では学生はひとつひとつのブースを一度は見て回る。その際に学生に響くメッセージをブースの装飾で目立たせながらうまく発信することができれば、学生の目に留まりブースへの着席を促すことができる。一度は目に入る時点で、圧倒的に認知してもらえる可能性が高い。
また、(2)に記載したように、その場で"認知"を獲得し、メッセージが"興味・関心"をひいてブース着席につながり、最終的に説明に共感してもらえれば、その場で"応募"までつなぐことができる。採用活動において、とても生産性の高い場、それが合同説明会である。以前と比較して参加者が減っており、確実に生産性は落ちているが、それでも中堅・中小企業にとっては母集団づくりのために積極的に参加すべき場であるといえる。
合同説明会成功に向けたポイントも少し記載すると下記のとおりである。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 自社に見合った合同説明会を選定する | 参加学生数が多ければ良い説明会というわけではない。 ・自社のターゲットとなる学生が参加するか? ・自社の規模感に合った説明会か?(大きすぎず、小さすぎないか) を考え、選定することがポイント |
| 学生が興味を持つブースづくり | 自社の伝えたいことや、自社の商品、サービスだけを装飾したブースでは学生は興味を持たない。学生は興味やメリットを感じなければブースに着席しない。その点を意識したブースづくりがポイント |
| 自社の理解に繋げる説明方法 | ブースに着席してもらった後は、自社を正しく理解してもらえるよう、一方通行ではなく双方向のやり取りを意識することがポイント。最近では、ブース内にブースをつくり、1対1で説明する企業もでてきている |
| 次のフェーズに繋げる取り組み | 「もしよろしかったら応募してください」という文言で締める企業は意外に多いが、それでは応募の確率は下がる。その場で次のフェーズまで申し込みをもらうことの徹底がポイント |
上記内容を意識して、合同説明会に取り組んでみてほしい。
広告宣伝の活用

認知を広げるという意味でいうと、広告宣伝の活用は王道だろう。しかし、よく考えて活用しなければ成果にはつながらない。重要なのは、ターゲットとした学生がどこにいるのか?である。闇雲にTVCMやWebCMを実施しても、ターゲットに届かなければ成果に繋がらない。
ある会社では、ターゲットとしている学生が多くいる大学への通学の多くがバス通学であることに目を付け、バスの中吊りや車外広告を実施した。その結果、その広告から数名の応募に繋がった。このように、ターゲットに届く広告宣伝を意識して実施することがポイントである。
また、費用がかかるものだけが広告宣伝ではない。"パブリシティ"という発想も採用において非常に重要になってきている。
※パブリシティ=企業がメディアを通して自社の製品やサービス、活動等の情報を報道してもらう広報活動
自社の新しい試みや、新商品・サービス、または社会貢献活動などを積極的にプレスリリースし、そこからパブリシティ活動に繋げていくことで
(1)費用がかからない
(2)メディアが取材等に基づき掲載・報道するので客観的な評価となるため、聞く側は受け入れやすい
(3)記事や報道を見てまた違う媒体からの取材依頼に繋がる等、拡散性が高い
等のメリットが享受できるため、積極的に取り組むべきである。
SNSの活用
採用活動においてもSNSを活用している企業は増えたが、実は成果に繋がっている企業は多くない。SNSにおいて重要なのは
(1)目的を明確にし、その目的に沿ったツールを選ぶ
(2)正しい頻度で継続をする
ということである。(1)のポイントは、そのSNSで達成したい目的が、何なのかで相性が大きく変わるということである。例えば、認知拡大に使いたいのであれば、拡散力の強いX(旧:Twitter)は相性がいいが、もしも目的が志望度UPなのであれば、拡散力は劣るが、画像で社風や職場を伝えやすいインスタグラムの方が相性がいい。
また、SNSは"1アカウント1テーマ"(仮に採用であれば採用に特化)という原理原則を意識することだ。1つのアカウントで様々な発信をしていると、そのアカウントが何を目的としたアカウントかが分かりづらくなり、フォロワーが増えない傾向になる。
最初にそのアカウントのターゲットとコンセプトを明確に決めた上で作りこむことで、成果に繋がりやすくなる。また、作ったものの更新頻度が少なすぎて成果に繋がらないアカウントも多く見かける。もしもSNSをするのであれば、インスタグラムであれば週に3~5回、Xであれば、毎日10投稿など、定期的な投稿ができる体制を整えた上で実施することをオススメする。でなければ、認知拡大という目的を果たすアカウントには育ちにくいためである。
クチコミや紹介の強化
認知度を高める上で、クチコミや紹介というのは非常に重要になってきている。例えば、以前は主流ではなかったクチコミサイトだが、企業が自分達でPRするナビやHP等と違い、クチコミは利害関係のない人からの客観的な意見となるため信憑性が高く、今では学生の6割が活用していると言われている。
ではどうやってクチコミや紹介を活用して認知を高めることができるのだろうか?
(1)社員にクチコミサイトへの記載をお願いする
(2)学生の集まる場所で紹介をお願いする
(3)内定者から後輩を紹介してもらう
(1)だが、クチコミサイトへ社員から記載してもらうようお願いするのが一番早いだろう。その際、いいことだけ書くように依頼するのではなく、ありのまま書いてもらうことが重要である。良いことだけが記載されているクチコミ程、信憑性が低いクチコミはないし、学生は悪い意見も知りたがっているものである。
(2)については、学生のたまり場や使う場所等、ターゲットとしている学生が普段から活用する場所に、自社の紹介やポスターを掲示することである。ある企業では、学生のよく活用する理容店にポスターの掲示と紹介をお願いしたところ、そこから2名紹介があった。
最後に(3)だが、内定者を抱えている企業はすぐにできるためぜひ実施していただきたいが、内定者の部活やゼミの後輩に、わが社を紹介してもらうというやり方である。内定者はまだ大学に通っているため、紹介のハードルは低く成果に繋がりやすい。ただし、内定者・後輩双方にメリットがあるようにしなければ、入社前から業務をやらされているように感じ、内定者の心が自社から離れ、内定辞退に繋がる可能性があることは留意していただきたい。
会社持ちの食事会などをセッティングし、内定者は社長や社員との関係性を強化でき、後輩はタダで食事ができた上に、社長や社会人に様々な話がきける有意義な場にする等が一般的である。
以上のように5つの切り口から認知の壁突破の方法について記載した。大事なことは、中堅・中小企業で認知の壁を突破できている知名度のない企業は、どこもこのようなことを地道に、かつ徹底して実施しているということである。
「自社は一生懸命採用活動をしている。なぜなら、SNSを開設している、ナビに登録している、広告を打っている、合説に出ている。なのに採用ができない」と言う経営者や採用担当者は多い。しかし、この採用難の時代、"開設している"、"登録している"程度では、「採用活動をしている」とは言えないのである。経営者や採用担当者の多くがここを勘違いしている。大事なことは、「活用レベルまで昇華しているか?」である。
ぜひこのことを意識して、ひとつひとつに向き合って認知拡大につなげていただきたい。
本事例に関連するサービス

採用ブランディング支援コンサルティング
お客様の採用ブランディングを成功に導くために、現状認識から、施策実行、効果測定まで一貫してサポートします。
採用ブランディング支援コンサルティングの詳細はこちら
関連動画