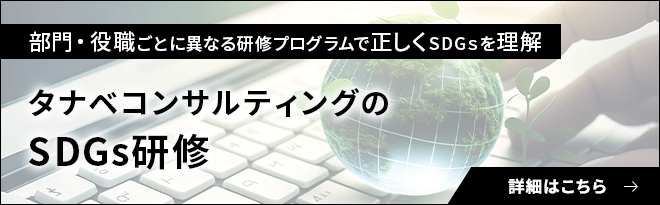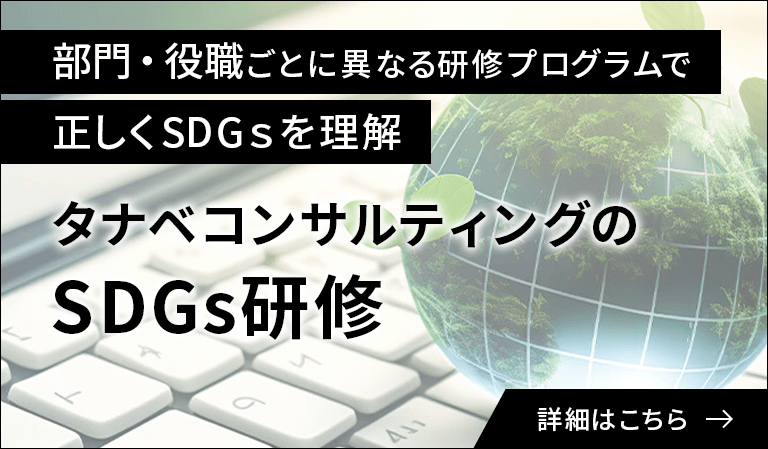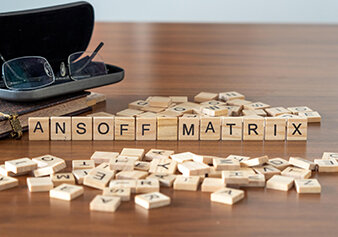COLUMN
コラム
閉じる
プラスチックが多大な影響を与えている海洋汚染は世界的に深刻な問題となっております。SDGsでは「目標14:海の豊かさを守ろう」という目標が掲げられており、2025年までにあらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減すると謳っています。今回は、プラスチックにおける社会課題と対策についてご紹介します。
SDGs 目標14「海の豊かさを守ろう」を妨げるプラスチック問題
世界に深刻な問題を与える海洋プラスチックとは?
私たちが生活を行う中で大量に出るごみや排水によって海洋汚染が進んでいます。
海洋汚染は深刻な問題となっており、SDGsにおいても「目標14:海の豊かさを守ろう」という目標が掲げられております。「海の豊かさを守ろう」の主旨は、持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用することです。
海洋に流出している廃棄物の中でもプラスチックは「海洋プラスチック」と呼ばれており、海洋汚染を急激に進めています。毎年約800万トンのプラスチックごみが海洋に流出しており、2050年には海洋中のプラスチックごみの重量が魚の重量を超えるという試算もあります。プラスチックは自然に分解されることが無いため、数百年にもわたって自然環境へ残ってしまう大きな問題へとつながっており、このままでは更に自然環境へ影響を与えてしまうのです。
【参考】
環境省 第3章 プラスチックを取り巻く状況と資源循環体制の構築に向けて>第1節 プラスチックを取り巻く国内外の状況と国際動向
https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r01/html/hj19010301.html
SDGsの達成を脅かすマイクロプラスチックとは?
マイクロプラスチックとは、微細なプラスチックごみの総称です。
マイクロプラスチックは発生源の違いで二種類に分けられます。
1.一次マイクロプラスチック
一次マイクロプラスチックとは、微細なサイズで製造されたプラスチックのことで、日常生活で使用している歯磨き粉や洗顔料などの製品に含まれています。一次マイクロプラスチックは排水溝から廃水として流れ海へたどり着きます。非常に細かいため、製品化された後の対策が難しく、回収は困難です。
2.二次マイクロプラスチック
二次マイクロプラスチックとは、プラスチック袋やペットボトルなどのプラスチック製品が自然環境の外的要因で細かくなったものです。海洋プラスチックを例にあげると、レジ袋などのプラスチックごみが海を漂い、砂浜へ打ち上げられると、照りつける紫外線や日光を受け劣化が進みます。そして、雨や風による外的要因で劣化が進み、二次マイクロプラスチックが大量発生するのです。
マイクロプラスチックは化学物質を吸着しやすい性質があるため、海に流れ出た排水に含まれる農薬などの有害な化学物質を吸収していると言われています。マイクロプラスチックを魚が誤飲し、その魚を人間が食べ続けると人間へも悪い影響が出る可能性があります。マイクロプラスチックは生態系を壊すだけでなく、人間への被害まで恐れられているのです。
【参考】
環境庁(2019年01月24日)
海洋における将来のマイクロプラスチック浮遊量の予測結果について
https://www.env.go.jp/press/106411.html

SDGsの達成に向けたプラスチック問題への取り組み
プラスチックに対する各国の施策
現在、世界中でプラスチックの削減が加速しています。その背景には前述した通り、プラスチックごみによる海洋汚染などのSDGsに関連するさまざまな環境問題が影響を与えています。このプラスチックごみに対して日本・アメリカ・中国の取り組み状況について紹介します。
■日本
2022年4月にサーキュラーエコノミーへの移行を推し進めるための法律「プラスチック資源循環促進法」が施行されました。プラスチックを扱う事業者が個々の役割を認識すると共に再資源化に取り組む働きかけにもなっています。「プラスチック資源循環促進法」はプラスチックの捨てる量を減らすだけでなく、捨てないことを前提とした経済活動への促進に貢献しています。
■アメリカ
1人当たりのプラスチック容器包装の廃棄量が、世界で最も多いアメリカ。
2021年11月に「国家リサイクル戦略」を発表し、国全体としてリサイクルと向き合っています。
リサイクル商品の増加や環境負荷の軽減を行い、2030年に向けたリサイクル率50%を目標としています。
プラスチックごみをクリーンエネルギーに変える技術開発など、プラスチック問題への解決に着手しています。
■中国
世界で最もプラスチックを消費している中国では、2021年9月に「プラスチック汚染改善行動計画」を発表。2025年までにプラスチックごみを削減するための目標や生産・流通・消費など各工程におけるプラスチック製品の管理を強化する取り組みが記されています。飲食店などでの使い捨てプラスチック製品の使用を減らすように求めており、ごみ回収のルール化についても発信しています。
世界各国でプラスチックの削減に向けた動きが取られていますが、現状は発展途上の段階です。
日本は世界3位のプラスチック生産国であり、先進的にプラスチックの再資源化と向き合う必要があります。
一人一人がプラスチックの削減に取り組み、環境保全に貢献しましょう。
【参考】
環境省 プラスチックを取り巻く国内外の状況
https://www.env.go.jp/council/03recycle/y0312-03/y031203-s1r.pdf
プラスチックごみを減らす取り組み事例3選
1.エコバッグの活用
日本では2020年からレジ袋の有料化がスタートしました。
レジ袋の有料化が大きな影響を与えたのは、「エコバッグを活用する」という消費者の意識変化です。
令和2年に環境省が行ったレジ袋の使用状況に関する意識調査では、マイバッグを持っている人は93.7%という結果が出ています。レジ袋の有料化によって、プラスチックの削減につながる行動を起こしている人が増加し、一人ひとりが環境のために日常生活を見直す良いきっかけとなりました。
2.バイオマス原料商品を選ぶ
近年、再生可能資源であるバイオマス原料のプラスチックが増加しています。
バイオマス原料は動植物由来のため、自然に捨てられても時間の経過とともに溶けていきます。
紙コップやストローも植物由来に切り替わっており、環境保全への取り組みが加速しています。
バイオマス原料の商品を選ぶことが、環境破壊を食い止める一歩目となります。
ぜひ、皆さんもバイオマス原料商品を選んでSDGsに貢献しましょう。
3.マイボトルを持ち運ぼう
コンビニや自動販売機のペットボトルはいつでも買うことができて便利ですが、毎回ごみが出てしまうというデメリットがあります。都度購入して捨てるペットボトルからマイボトルへ切り替えることでプラスチックごみの削減につながります。
環境保全のみでなく、節約にも大きな効果があるのでぜひ皆さんもマイボトルを持参しましょう。

SDGsの観点からプラスチックに対する意識変化が求められる
今回は、プラスチックにおける社会課題と対策について紹介しました。
プラスチックの削減がSDGsの達成に貢献することはご理解いただけたかと思います。
世界3位のプラスチック生産国である日本では、自治体や民間企業がSDGsに賛同して前向きに取り組むことが求められます。
「経済・社会・環境」の3つの側面からSDGsにどのように取り組むのかをそれぞれが考え行動に移すことが重要です。
民間企業は、自社の商品・サービスがSDGsの達成に向けてどう働きかけることができるのかを確認し、新たなSDGsへの取り組みを進めることで企業価値を高めていきましょう。
著者
最新コラム

- 事業ポートフォリオ再編のプロセスとリスク対策

- 選択と集中戦略とは?メリット・デメリットと成功事例を解説

- 新規事業開発プロセスの全貌!成功へ導く戦略とは

- 新規事業はどのように評価すればいい?成功に導くための10の評価軸
ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと
進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド
~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド
~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド
~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~
資料ダウンロード

- ストラテジー&ドメインコンサルティングメニュー紹介資料

- 統合報告書 ストーリー設計のコツ~企業価値は「説明」では動かない。「物語」が動かす。~

- 設備工事業界の未来を切り拓く:課題解決と成長戦略の最前線~人手不足からデジタル化まで、業界の変革を支える実践的アプローチ~

- TCG REVIEW 顧客創造モデル

- 収益構造を変える!ビジネスモデル・イノベーション~高収益を実現する事業ポートフォリオとPLのデザインはできていますか?~

- 食品業界の企業が中期経営計画策定で押さえるべきポイント~重要になるテーマと事例5選をご紹介~

- 経営者の成長投資アンケート調査レポート 2025年

- 海外展開における課題と新規の海外代理店開拓プロセス
 長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト
長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト