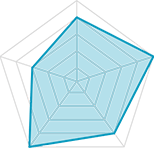人事コラム
人事評価制度における不満の原因とその対策
一貫性×透明性の両視点による人事評価制度が社員のモチベーションを高める
人事評価制度への不満を解決する設計と運用のポイント

人事評価制度とは
人事評価制度とは、予め定められた基準に基づいて社員を評価し、その結果を賃金や昇格・昇進などの処遇に結びつける仕組みである。最近ではノーレイティングという手法で人事評価を行わない企業も出てきているが、大多数の企業では、上記を目的として、なにかしらの評価の仕組みが採用されているだろう。
また具体的な評価の仕組みとして、「定量評価」と「定性評価」をハイブリッドで運用する企業が多い。定量評価は会社方針・戦略に沿って自らの取り組み事項を目標設定する「目標管理制度(MBO)」を採用し、その達成度や生み出された成果の価値を評価する仕組みである。一方で定性評価は行動面や仕事への向き合い方などを着眼にしており、いわゆる成果を生み出すためのプロセスを評価する仕組みである。成果とプロセスを総合的に評価することで適切な処遇に結びつけていく仕組みが人事評価制度である。
人事評価制度の重要性
前述の内容を平たく表現すると、人事評価制度は「査定」のために行うと表現できる。もちろん社員目線では自らの頑張りが正しく評価され、適切に報われる処遇を期待するため重要な機能と言える。ただしより本質的に考えていくと、以下重要な二つの機能が想起される。
〇本質的機能1:人事評価制度の運用によって人材育成や能力開発に繋がる
〇本質的機能2:上記の積み重ねによって理念・戦略の実現に繋がる
つまり人事評価制度とは、査定機能に加えて、本人の能力と会社が目指す姿の実現力を高めることがなによりも重要なのである。
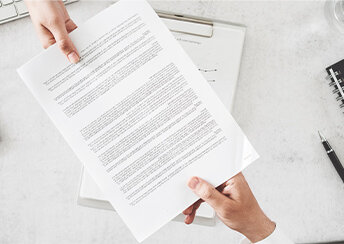
人事評価制度における不満の原因
人事評価制度は査定機能に加えて、育成や理念・戦略実現のためにあるということは述べた。おそらく多くの企業でこの重要性は認知されていることであろう。ただそれでも社員から不満が挙がり、悩みが尽きない企業が多いのも事実である。人事評価制度における不満は会社風土やビジネス環境によって様々な理由が考えられるものの、主要な要素は以下の三つに集約される。
まず不満原因の一つ目は、「会社が目指す姿・方向性が定められていない、または浸透していない」だ。人事評価制度は社員の活躍意欲を促すことが期待されるが、社員にとって「どこに向かって頑張れば良いかが分からない」というのは大きな不満に繋がる。ゴールなきマラソンは苦であるように、正しい方向付けがされるからこそ、その実現に向かって社員は自律的に行動ができるようになる。また仮に目指す姿・方向性が定められていたとしても、社員が腹落ちする形で浸透していないことは、定められていないのと同義である。
続いて不満原因の二つ目は、「人事評価項目や評価基準が曖昧である」だ。上記のように目指す姿・方向性を理解したとしても、「なにを頑張れば評価されるのかが分からない」という状態であると活躍意欲は削がれてしまう。また項目や基準が曖昧であると、評価者の好き嫌いなどの感情面によって評価されているのではないかという懐疑心を生み、会社への信頼感低下に繋がってしまう。
最後の不満原因の三つ目は、「評価に基づく適切なフィードバックがない」だ。フィードバックが行われないと会社の期待値と自らの現在地のギャップを把握することができず、結果として「次に何を頑張れば良いのかが分からない」ということに繋がる。人事評価制度は瞬間的なイベントであるが、会社での仕事は持続的である。つまり、フィードバックを通して自らの強みと弱みを適切に理解する機会がないと、未来へのモチベーション意欲の低下を招いてしまう。
以上三点が人事評価制度における不満の三大要素である。
不満を解消するための対策
前述のような不満を当然放置するわけにはいかない。不満を解消し、より社員がモチベーション高く、自律的に活躍することを全ての会社が願っている。そのためのキーワードは「一貫性」と「透明性」である。
一貫性とは、会社の将来ビジョンを実現するという価値観の下で、社員に期待する成果・プロセスを設計することだ。そしてビジネス環境が大きく変化する昨今においては、時代環境に合わせて柔軟にアップデートしていくことも重要となる。具体的には自社が掲げる中期経営計画と連動させると良いであろう。中期経営計画を実現するために必要な人事評価制度はどのような枠組みが適切かという思想で設計することを推奨する。したがって、おおそよ3~5年スパンで人事評価制度の見直しを図り、常に最新状態とすることで一貫性を担保されたい。
続いて透明性とは、会社が期待する成果・プロセスの基準を開示すること、および適切にフィードバックする仕組みを構築することだ。ポイントはどちらかではなく、双方がセットになっていることが重要である。人事評価制度に欠かせないマインドとして「会社に対する社員からの信頼感」がある。会社から頑張る軸が示され、かつその評価が適切なフィードバックによって次の活躍の方向付けが明確になることは、会社が社員の成長を願っているというメッセージになる。そのためには評価基準や評価結果をオープンにしていく覚悟と仕組みが必要であり、それらの導入によって透明性を担保されたい。
さいごに
これからは人口減少による人手不足が多くの企業の課題となる。人材確保は行いつつも、会社に入社してくれた人材がモチベーション高く、そして長く勤務できる仕組みを会社側が整備していく必要性がより一層高まっていくであろう。人事評価制度の不満原因と真に向き合い、一貫性と透明性の視点でより良い制度へとアップデートすることを期待したい。
本事例に関連するサービス
関連動画
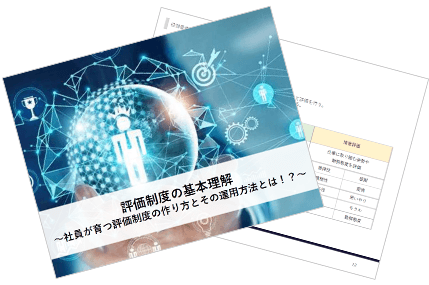
評価制度の基本理解
~社員が育つ評価制度の作り方とその運用方法とは!?~
単なるモノサシではなく、社員が育つ適切な評価制度の作り方、ならびにその運用方法を事例を交えて解説します。
この資料をダウンロードする