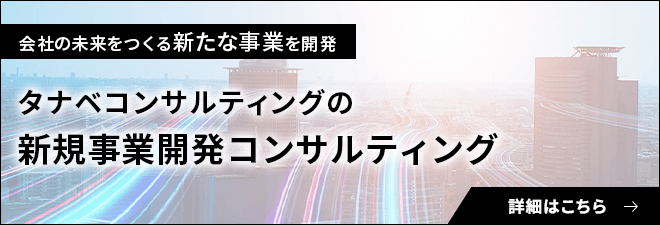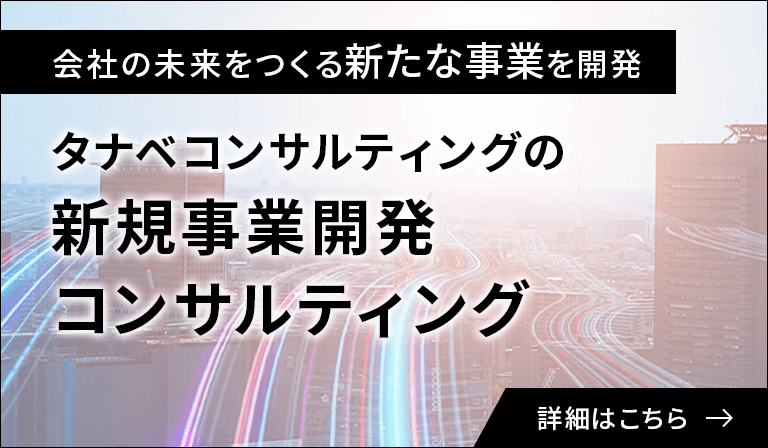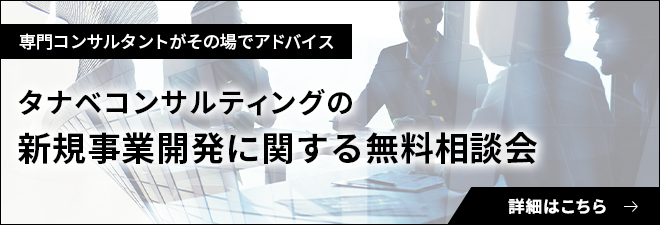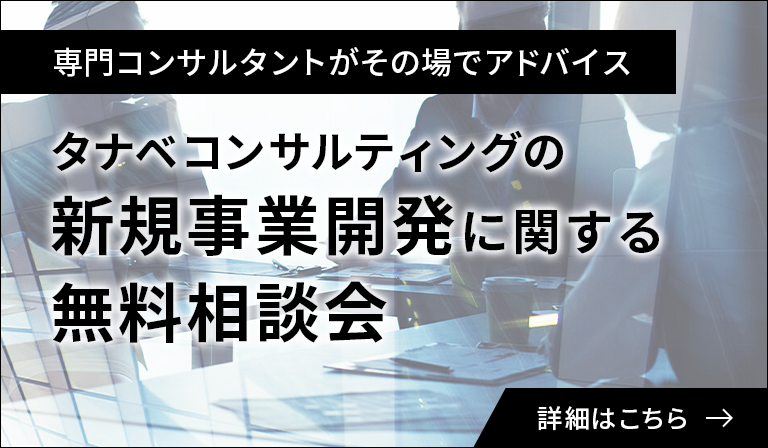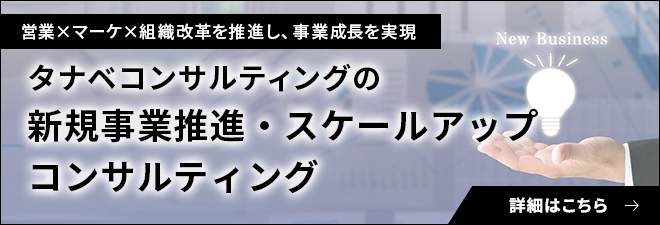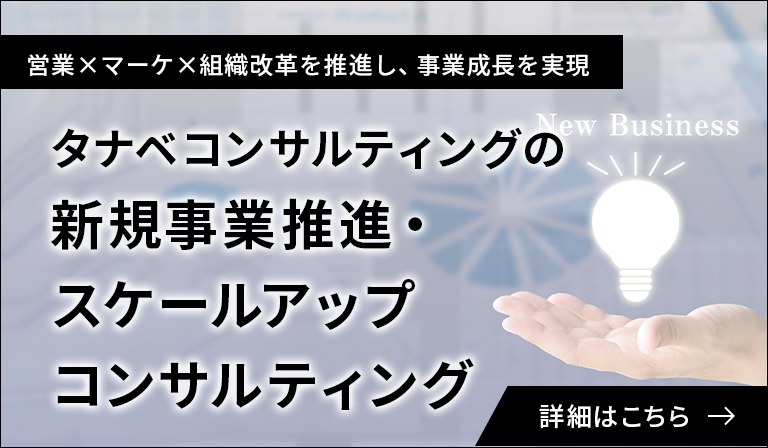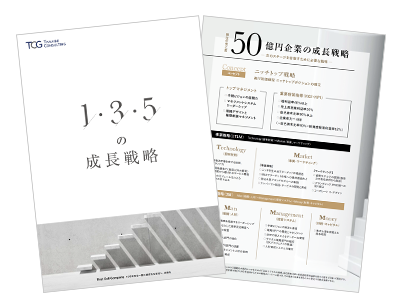COLUMN
コラム
閉じる

新規事業の立ち上げを検討しており、「新規事業を立ち上げる必要性について確認したい」「成功させるポイントを押さえたい」と考えている経営者の方は多いでしょう。
この記事では、新規事業の必要性と立ち上げのステップ、さらには成功させるポイントについて解説します。
新規事業を立ち上げる必要性と背景
新規事業とは経営の柱となる新しい事業を指し、従来と異なる商品・サービスの展開、技術開発、市場の開拓によって事業を発展・拡大させる試みです。 事業を立ち上げる必要性として、以下が挙げられます。
事業・収益拡大の必要性
企業は持続的に収益を上げ、存続しなければなりません。
商品・サービスには「プロダクトライフサイクル」があり、導入・成長・成熟・衰退の段階を経て最終的には陳腐化します。事業にも同様の大きなうねりがあるため、収益が上がらなくなる前に新しい事業を軌道に乗せなければなりません。
また、価値観やライフスタイルの変化とともに消費者のニーズも変わります。ニーズや動向を捉え、自社の価値やリソースを活かして新しい事業を展開する必要があります。
新しい経営環境に対応する必要性
VUCA時代と呼ばれる先の見通せない時代において、経営にはサステナビリティが求められます。社会の持続性を維持するための商品開発や技術開発、サービスの展開が必要です。
また、環境保全への取り組みを掲げたESG経営には投資家の関心が集まります。政府からのSDGsや、労働環境改善の要請に応えるための施策も必要です。
既存の事業では抜本的な対応ができないケースもあることから、新規事業の必要性があるといえるでしょう。
競争力確保の必要性
デジタル化やネットワーク化によって事業の参入障壁が低くなり異業種からも参入しやすくなったことが、市場競争の激化につながっています。スマートフォンの登場によって置き換えられる商品・サービスがある一方、新たに生み出される事業があります。
このような時代の流れに合わせて、他社にない自社ならではの価値に着目し、新しい方法でそれらを消費者に提案することで競争優位性を確保することが求められます。
そのためにはリソースを組み合わせて商品化、事業化できるクリエイティブな人材の育成が必要です。
技術革新の必要性
技術は日進月歩で、常に関わっていないとトレンドを逃します。ポイントになる技術については、常に動向を注視する必要があるでしょう。
新規事業に伴う技術展開には、以下のような2つの方向性があります。
・既存事業に新技術を取り入れる
・自社技術を異分野に展開する
現在の事業をより高いレベルに引き上げるために技術を導入すること、異分野に自社技術を投入して画期的な事業を生むこと、両方のアプローチが可能です。

新規事業立ち上げのステップ
ここでは、新規事業を立ち上げる流れを確認しましょう。
参入する市場を見誤らないためには、初期のリサーチが重要です。方向性がブレないようにするため、コンセプト立案は入念に行いましょう。
市場と自社の分析
市場や自社の分析には、以下のようなフレームワークが有効です。
・PEST:マクロな視点で外部環境を捉える
・SWOT:強み・弱み・機会・脅威の軸から自社と市場を捉える
・3C:顧客・競合・自社を把握する
・STP:市場・ニーズの細分化→ターゲティング→立ち位置を決める
これらの分析により、自社が対象とする事業領域を明確に定めます。
この段階における分析と、次の段階であるアイデア出しは順序が逆の場合があります。自社の価値をベースにアイデア出しをしたうえで、対応する市場を分析するアプローチもあるでしょう。
アイデアの創出
自社と市場の分析をもとに、新規事業のアイデア出しを行います。アイデア出しにはなるべく多くの人が関わるのがよいでしょう。社内で募集することもよい方法です。
アイデア出しに使えるフレームワークはいくつかありますが、新規事業では「スキャンパー(SCAMPER)法」が考えやすいでしょう。
・Substitute:代用する
・Combine:組み合わせる
・Adapt:適応させる
・Modify:修正する
・Put to other use:ほかの用途を見つける
・Eliminate:削減する
・Reverse・Rearrange:逆転・再配置
ニーズからの発想と自社価値からの発想の、2つの方向性があります。
コンセプト立案
事業のアイデアが固まれば、理念やコンセプトを設定します。社会的意義を背景に設定すると、多くの消費者に理解されやすいでしょう。また、経営理念を継承すると一貫性が保てます。
コンセプトはユーザーが得られるベネフィットを表現し、利用シーンが想像できるような分かりやすい言葉を選ぶとよいでしょう。
理念・コンセプトには自社価値を反映し、他社には作れない内容にすることで優位性を確保できます。
実施計画
この場合の「実施」とは、市場展開(ローンチ)を指します。
実施計画は、ローンチのための準備です。アイデアをコンセプトに沿って形にする作業で、概ね以下のようなさまざまな施策があります。
・事業計画立案
・提携など他社との協力関係の構築
・資金調達(補助金活用を含む)
・人材の採用・配置
・商品開発
・技術開発
・マーケティング戦略
・プロモーション戦略
これらの準備を整え、計画の実施に移行します。
実施と改善
新規事業立ち上げの初期段階では、市場やターゲットを小さく限定して商品・サービスをリリースすることが一般的です。これをテストマーケティングといいます。
計画どおりの反響が得られずに修正が必要になった場合でも、規模が小さければ経営への影響を最小限に抑えられます。
店舗での売れ行きや購買行動、WebサイトのコンバージョンやSNSのインプレッション、アンケート調査結果などから市場の反応を分析し、改善点を検討しましょう。
テストマーケティングによってPDCAを回し、市場・ターゲットを広げながら本格実施に移行します。

新規事業を成功させるポイント
新規事業を成功させるために押さえておくべき重要なポイントを解説します。
会社にとって初めての試みであることから、トップや経営層が責任を持って計画・実行をリードする必要があるでしょう。
トップのコミットメント
新しい事業を起こす際には、ステークホルダーに対して経営者は全責任を負います。
新分野・新技術はトップ自身には分からない要素は当然ありますが、詳しい人材を確保して実務を任せることは可能です。トップは詳細に関わる必要はなく、結果にコミットできれば役割を果たせます。
新規事業の必要性や意義を説き、社員が自分ごととして取り組むように仕向けることで、イノベーションの雰囲気を作ることが重要です。
優秀な人材
事業の成功にとって人材が重要であることはいうまでもありません。新規事業の実務を推進するリーダーには、起業家精神に近いマインドを持っている人材を選任する必要があるでしょう。
新規事業を担うスタッフは、事業領域や技術動向、市場のトレンドを把握・理解する力が求められます。既存のルーチン業務で優秀な人材を新規事業に異動させても、能力を発揮できないおそれがあります。
新規事業に適した人材を適切に配置し、社内にリソースがない場合はアウトソーシングを活用することも視野に入れましょう。
効率的な投資
新規事業立ち上げは、リスクが伴いますがまとまった投資が必要です。
成果の出ない無駄な投資を抑えるためには、以下のような段階的な投資や、他社とのコラボレーションを検討しましょう。
・リーンスタートアップ
・オープンイノベーション
・補助金・助成金の活用
オープンイノベーションとは、社外にある知識や技術を自社のプロジェクトに採用するほか、自社の技術やリソースを他社に提供するなどの幅広い活動を指します。もし自社が製造販売に強い場合、研究開発に強い企業と協力して、お互いのリソースを提供し合うことで相互に利益を得るという計画が可能です。
知的財産の管理
新規事業で忘れてはならないことに、知的財産のチェック(知財チェック)があります。
市場投入を予定する商品・サービスが、他社の特許を侵害しないか否かを事前に調べる必要性があるのです。商標権や著作権についても同様です。
また、市場にない技術(製法など)を使用した商品をリリースする前には、特許出願を済ませておきましょう。模倣によって自社の利益を他社に奪われないために、最低限必要な手続きです。

まとめ
新規事業の立ち上げは、既存事業のライフサイクルや市場の動向を見ながら、必要性が生じたタイミングを捉えることが重要です。
段階的なリリースや他社との協力によって投資やリスクを抑えながら、自社価値を反映した事業を展開することで、投資の効果を最大化できます。
新分野、新技術、トレンドを理解して、実務を遂行できる人材の育成にも力を入れましょう。
著者
最新コラム

- 海外販路開拓の具体的な方法4選!成功させるための戦略と手順を解説

- タイ進出を成功させるメリットと3つの注意点|進出前に知るべきリスクを解説

- バリューチェーンの重要性とは?最適な構築方法のポイントを解説

- 中期経営計画の期間は何年が最適?成功する策定のポイントを紹介
ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと
進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド
~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド
~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド
~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~
 長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト
長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト