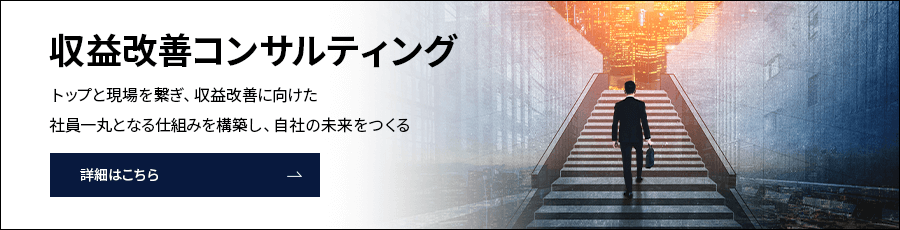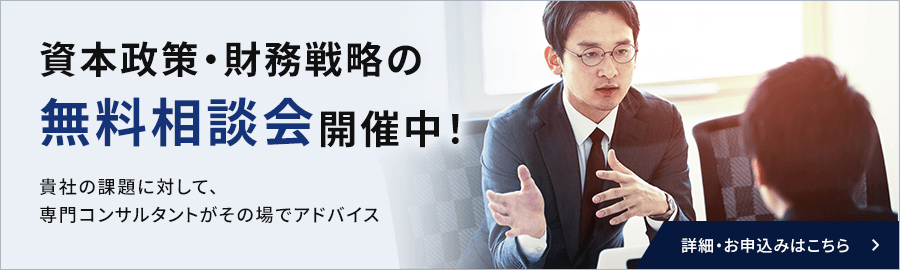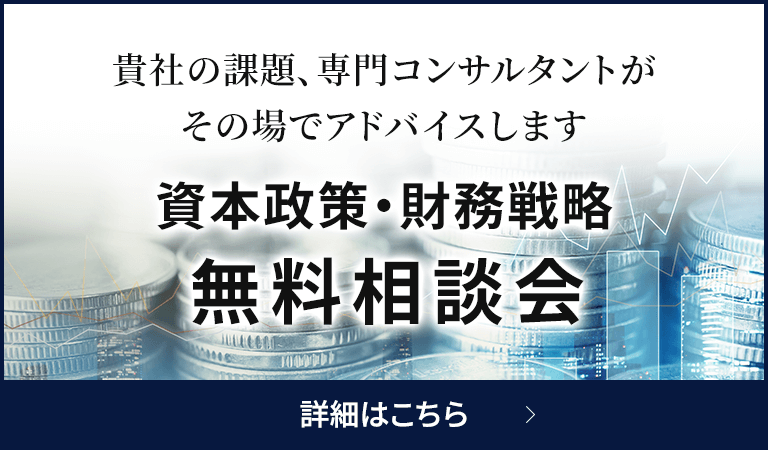収益構造とは?ビジネスモデルなどをわかりやすく解説
- 資本政策・財務戦略

閉じる
収益構造とは?
会社を取り巻く環境は日々変化しており、その都度に合わせて収益構造を見直す必要があります。時代遅れの商品やサービスになっている、売上が落ちてきて現状のコストを賄えない、などの問題がある場合、収益構造を把握し、定期的に確認し、改善していくことが大切です。収益構造とは、どの部分にどのくらいお金をかけて最終的にどのくらいの利益を出しているのか、たくさん売って利益を出しているのか、数は少ないが高い価格で売って利益を出しているのか等の仕組みのことです。
収益構造を把握するには、様々な角度から分析する必要があります。
以下の2点から見ていきます。
(1)数字を整理することで収益構造を把握し、改善ポイントを探す
(2)ビジネスモデルを整理することで収益構造を把握し、改善ポイントを探す
数字とビジネスモデル
まずは、決算書などで数字を整理し、収益構造を把握することが重要です。
例えば、同じコーヒーや軽食を売るコーヒーショップで、売上高が同じ1億円のA社とB社があるとします。A社は営業利益が1,000万円(営業利益率10%)、一方B社は200万円(営業利益率2%)です。売上高が同じなのに営業利益に違いがある2社には、どんな違いがあるでしょうか。この場合、A社の方が収益力が高いと言えます。
【数字から見る着眼点】
①A社商品の方が、売上単価がB社より高い
②A社の方が、営業時間がB社より短いがA社の顧客回転率がB社より高い
③材料費がA社の方が安い
④人件費がA社の方が安い
⑤A社は自社所有で家賃発生が無い等、固定費が抑えられている
など大きく整理すると、A社、B社を比較した場合、売上高が同じ1億円であれば原価、固定費のどこかの部分で、A社の方が、低い数値となっている勘定科目があるはずです。逆に高い数値が出る勘定科目のあるB社はその科目について原価や固定費を見直す対策を打つ必要があります。
仮に売上高が同じでない場合。業界平均で自社決算書と比較する場合などは、売上に対する原価の割合を示す原価率(材料費率、労務費率、外注比率、原価固定費率)や固定費率(水道光熱費、家賃など)など割合で見ていくとわかりやすいでしょう。
さらに、商品ごとの売上高に対する割合を算出したり、利益率を比較することで自社の強みや弱みとなる商品がわかるようになります。弱みとなっている事業の改善ポイントを見つけ、場合によっては、弱みとなっている商品を縮小し、販売中止などを検討することも可能です。
ビジネスモデルを理解する
次に、ビジネスモデルを整理することで、収益構造を把握し、改善ポイントを見つける方法を解説します。ビジネスモデルとは、端的に言うと、人、モノ、金の流れの仕組みを指します。自社のビジネスモデルを頭の中でなんとなく理解していても、図にして明らかにすることで、今まで見えていなかった改善ポイントを見つけることができます。
ビジネスは、ターゲットとしている顧客が求めているものと提供しているものの価値が一致していると、利益を出しやすいビジネスモデルが生まれます。
顧客が自社の商品やサービスを購入した後を考えてみます。何のために利用しているのか、利用することで得たいこと、ニーズが何なのか?この観点が重要となってきます。よくあるビジネスモデルの失敗例として、販売やサービスを提供する事業者側が顧客のニーズを無視して「美味しいから必ず売れる」「自分がやりたいサービスだから提供する」など、事業者側の都合でビジネスモデルを構築するケースがあります。当然、消費者はニーズもなく求めていない商品やサービスにお金を払いたいと思いません。
つまり、ビジネスモデルとは、「誰に(ニーズや困りごと)」「何を(ニーズや困りごとを解決する)」「どうやって(解決する手段⇒商品、サービス)」「儲かる仕組み」の4つが揃って成立するものです。そして、消費者のニーズや困りごとを超える商品やサービスが高付加価値となり、高い収益を生むことになります。かつては収益を生んでいた商品やサービスが今は収益を生んでいないのであれば、外部環境の変化に対応できていない可能性があります。そのような場合、改めて「誰に(ニーズや困りごと)」「何を(ニーズや困りごとを解決する)」「どうやって(解決する手段⇒商品、サービス)」「儲かる仕組み」の4つを現状分析し、改善していく必要があります。
ビジネスモデルには、業界や業種に応じて多くの種類が存在しています。代表的でよく目にするビジネスモデルとしては、以下のようなものがあります。
①販売モデル
「販売モデル」は最もシンプルでクラシカルなビジネスモデルです。商品を作ったり加工したりして販売することで利益を得る方法であり、「モノを売る」ことから、「物販モデル」とも呼ばれています。規模は関係なく、個人でも十分利用できるのが特徴です。しかしこのモデルで成功するためには、他社に追随されないように、できる限り商品の魅力を高め、市場で優位に立たなければなりません。飲食店やメーカー、農家などでは、このモデルが利用されています。
②小売モデル
モノを売るという意味では、「小売モデル」も存在します。小売モデルは「売る」ことに特化しているのが特徴で、商品の製造や加工のプロセスはありません。代わりに商品は他社から必要な分を調達し、仕入れによって確保します。そのため、提供する商品に自社ならではのオリジナリティを出すことは困難で、商品以外のところで付加価値を与え、差別化する必要があるのです。一般的にコンビニや百貨店、スーパーマーケットなどは、この小売モデルが採用されています。
③広告モデル
商品やサービスを売れやすくするためには、消費者に認知してもらうとともに、「欲しい」「使ってみたい」と魅力を感じてもらわなければなりません。そこで企業はコストをかけ、様々な手法で宣伝をしようとします。このような企業のニーズに着目し、生まれたのが広告モデルです。近年はSNSを活用してWeb広告を出す方法が増えてきています。認知される効果の高さから、動画配信サービス「YouTube」で広告を出し、広告料を得るYouTuberという職業も、広告モデルの一種として一般的になってきました。
④サブスクモデル
サブスクモデルは、近年、話題性のあるビジネスモデルです。毎月、もしくは毎週、毎年などの決められた期間で商品やサービスを提供する対価として、ユーザーに一定の定額料金を支払ってもらう仕組みが取られています。
以上、代表的なビジネスモデルを4つ挙げましたが、いずれも他社に追随されない固有の付加価値が必要です。
さいごに
収益構造は様々な視点から明らかにする必要があります。今回は、決算書から数字を整理して問題点を見つけるとともに、ビジネスモデルを整理して、顧客の求める価値を提供できているかを確認し改善していく方法を解説しました。収益構造は外部環境の変化に対応し、変えていく必要があります。たとえ利益が出ている企業であっても、定期的な見直しを図ることが必要となります。また、ビジネスモデルも一度作れば終わりではなく、市場や消費者のニーズに応じて変えていかなければなりません。もしうまくいかないことがあっても、ビジネスモデルを作っていれば、原点に立ち戻り何が原因だったのかを検討しやすくなります。企業のおかれる情勢が激しく変化する昨今では、スピーディな改善を繰り返すことが重要です。そのような観点からも、企業がビジネスモデルを取り決める必要性は高いのです。
タナベコンサルティングでは、貴社の収益性を最大化するための包括的なサポート「収益改善コンサルティング」を提供します。現状の収益構造を徹底的に分析し、潜在的な問題点や改善の機会を特定します。その結果を基に、具体的な改善策を提案し、実行支援まで一貫して行い、貴社の競争力を強化し、持続可能な成長を実現します。
収益改善コンサルティングサービスの詳細は下記よりご覧ください。
関連記事
-

中堅企業が実装すべき財務戦略~企業価値を高める収益改善のポイント~
- 資本政策・財務戦略
-

-
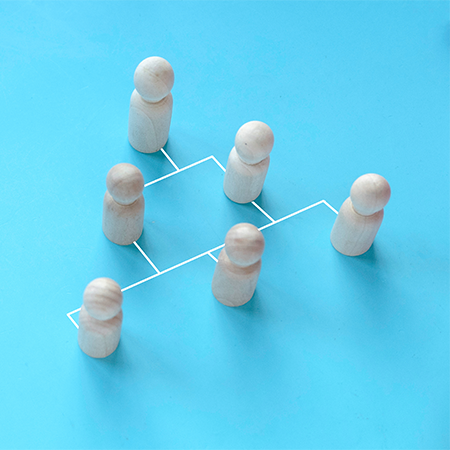
なぜ、組織的経営が企業に必要なのか?
- グループ経営
- ホールディング経営
-

中堅企業が実装すべき財務戦略~企業価値向上に必要な七つの重点テーマ~
- 資本政策・財務戦略
-

-

デシジョンマネジメントが企業成長を支える~管理会計の活用事例5選~
- コーポレートガバナンス
-

中堅企業が実装すべき財務戦略~企業の持続可能性を高める事業再生のポイント~
- 資本政策・財務戦略
-

オーナー企業の意思決定構造を解説:トップダウン経営の課題と成功させるポイント
- グループ経営
- ホールディング経営
 コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト
コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト