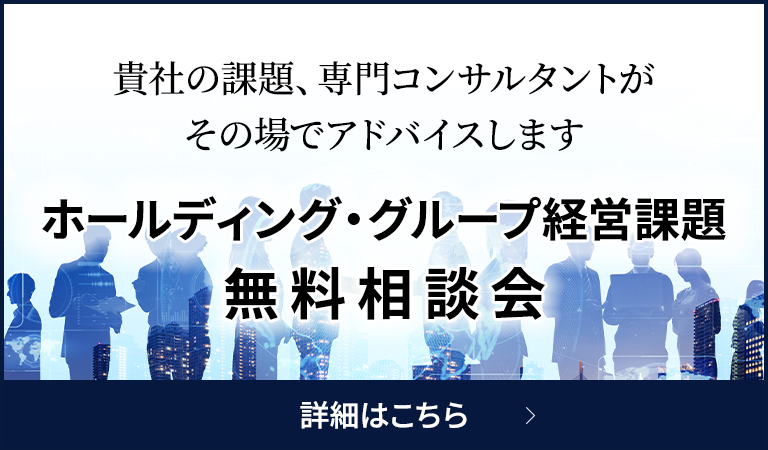子会社はどのように設立するのか?
メリットとデメリットを紹介
- グループ経営
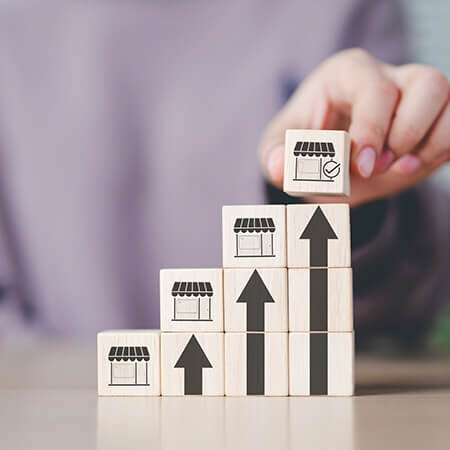
閉じる
昨今は事業拡大を目的に他社の株式を買い取ることで経営権を取得し、子会社化が進むケースが大半です。上場企業では、株式の移転によって子会社化を目指す場合も珍しくありません。
一方で企業が自社の事業の一部を切り出したり、新規事業を開始する目的で新たに子会社を設立する場合もあります。
本コラムでは、そうした子会社設立の際の手法や、注意すべき点について解説します。
子会社設立のスキーム
子会社設立のスキームは大きく分けて➀発起設立と➁会社分割(新設分割)の2種類があります。子会社設立のメリットは親会社とは異なる労働条件や報酬体系を採用でき、子会社の事業の性質や収益性に応じた柔軟な人事政策を策定することが可能となることや、法人税法や租税特別措置法などの税制メリットの享受、権限移譲によるインセンティブ向上、ブランディングなどが挙げられます。
どちらのスキームでも子会社設立によるメリットは享受できますが、子会社設立後のプロセスが変わってきますので自社に適したスキームを選択することが重要です。
発起設立のスキーム
発起設立とは、会社が発起人となり子会社を新規に設立する手法(会社法25条1項1号)です。新規事業を行う目的で子会社を設立する場合における比較的オーソドックスな手法となっており、発起人が設立時発行株式の全部を引き受けるため、100%株主となり新設会社を完全子会社とすることが特徴です。よく似た手法で募集設立というものがあり、発起人は設立時発行株式の一部を引き受け、残りの設立時発行株式を引き受ける者を募集する設立方法です(会社法25条1項2号)。募集設立は発起設立と比較して手続きが煩雑であり、現在の実務では発起設立により会社を設立することが多いため、本コラムでは発起設立を中心に解説していきます。
発起設立は短期間かつ簡易な手続きで子会社を設立することができる点がメリットですが(最短で数週間)、デメリットとしては設立した子会社は、あくまで会社のガワのみで、設立後に事業に必要な人材や資産などのすべてが移転してくる必要があることが挙げられます。
発起設立により、会社を設立する際には、一般的に以下のプロセスをとられることが多いです。
➀定款の作成
➁出資(金銭、現物出資)の履行
➂機関の設置
➃設立の登記申請
それぞれの手続きについて簡単に説明します。
➀定款の作成
定款とは、「会社の憲法」とも呼ばれるもので会社を経営していくための基本的なルールをまとめた書類です。定款の記載事項は、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つに分類されています。 絶対的記載事項とは、会社法上必ず記載しなければならない事項であり、会社の目的、商号、本店の所在地など全5項目となります。相対的記載事項とは、会社法の規定により定款に定めがなければその効力を生じない事項であり、株式会社の成立時の報酬や株式の譲渡制限などの項目があります。任意的記載事項とは、定款の記載事項のうち、絶対的記載事項および相対的記載事項以外の事項で会社法の規定に違反しないものをさします。具体的には株主総会の招集時期や事業年度等です。
定款は発起人が作成する必要があります。その後全員が署名又は記名押印を行い、会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局所属の公証人の認証を受ける必要があります。
➁出資(金銭、現物出資)の履行
出資の履行とは、出資者が会社に対して金銭などを拠出し、これと引換えに会社から株式の交付を受けることをいいます。発起設立は発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける手法であり、発起人(のみ)が出資を行うことが可能です。
定款に特に定めがない場合には、事前に以下の項目について発起人の全員の同意を得てこれを定める必要があります。
ア 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
イ アの設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
ウ 成立後の株式会社の資本金および資本準備金の額に関する事項
その上で、発起人は、設立時発行株式の引受後遅滞なく、出資金の全額を払込取扱機関において払い込むことで手続きが完了します。
➂機関の設置
発起人は、出資の履行が完了すると、遅滞なく、設立時役員等の選任をする必要があります。
設立時役員等は、定款で定めることもできますが、発起人の議決権の過半数をもって決定することも可能です。
設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合には、3人以上の設立時取締役を選任する必要があるほか、設立時代表取締役を選定する必要もあります。
➃設立の登記申請
発起設立は、以上の①~➂の手続きを履践した上、会社の本店所在地において設立の登記をすることによって成立します。設立の登記は、その本店の所在地において、設立時取締役等の調査が終了した日又は発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければなりません。
また発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となります。
会社分割(新設分割)のスキーム
会社分割(新設分割)とは、親会社の一部の事業を分割して新会社に承継させる手法(会社法762条1項)です。親会社が複数の事業を行っており、その一部を新会社に承継させるようなケースで事業承継を絡めて比較的よく用いられます。新設分割を実施する際には、原則として株主総会特別決議が必要となるため、親会社の株主の3分の2以上の承認が必要となります。
税務上「適格分割」(法人税法2条12の11)となる要件を満たせなかった場合、多額の課税を受けるリスクがあるほか、手続上の負担が大きいこともあり、発起設立と比べると難易度が高くなります。実務においては顧問税理士などの専門家に相談し、手続きを進めてもらうことが多いです。
会社分割(新設分割)の手法については、ホールディングス化の際の分社化スキームなどで使用されることも多く、別コラムで詳細説明していますのでそちらを参照してください。
分社化とは?分社化のメリット・デメリット
関連記事
-

中堅企業が実装すべき財務戦略~企業を取り巻く経営課題~
- 資本政策・財務戦略
-

中堅企業が実装すべき財務戦略~「財務価値分析」から見る経営実態~
- 資本政策・財務戦略
-

事例から学ぶROIC経営の落とし穴とは?
- 企業価値向上
-

-

-

-

企業価値とは?意味と評価方法をわかりやすく解説
- 企業価値向上
-

 コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト
コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト