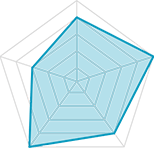人事コラム
古い評価制度がもたらすリスクから学ぶ、評価制度見直しのポイント
評価制度改定を検討されている社長・人事担当者必見!
古い評価制度の特徴と改善案についてお伝えします

古い評価制度の特徴とリスク
まずは、古い評価制度の特徴とリスクについて下記の通り共有する。
自社に当てはまる点が無いかを確認して欲しい。
1. 企業の理念やビジョンとの繋がりが無い・弱い
評価制度は、企業の理念・ビジョン・戦略を実現に向けた人材育成の一貫であるにもかかわらず、企業の理念やビジョンと結びついていないケースである。組織の方向性と無関係に評価が行われることで、方向性と相反する人材を育成してしまうリスクがある。
2. 賃金との連動不足
評価制度と賃金制度が紐づいていない。もしくは紐づきが不十分であり、経営陣の裁量によって賃金を調整するケースである。中小企業でよく見られるケースであるが、評価結果が賃金に反映されず、社員の不平不満につながるリスクがある。
3. 人材育成に活用できていない
社員の成長を支援する仕組みとして活用されておらず、評価が『査定』の枠を超えて社員の成長を支える役割を果たしていないケースである。具体的には、評価は行っているが、評価の内容が社員にフィードバックされておらず、本人は、自分が良い評価を受けている(この方向で良い)か、良い評価を受けていない(この方向では良くない)かが分からない。結果として、成長の方向性が分からず、モチベーションが低下するリスクがある。
4. 評価基準が曖昧
評価基準が具体的ではないことで、社員がどのような行動や成果を出せば評価が上がるか不明確なケースである。従業員規模が今よりも小さい時に策定した評価制度を使い続けている企業に発生しやすい。結果として、評価者の主観的な判断により評価されることで、社員の不平不満につながるリスクがある。
5. 制度運用ができておらず形骸化している
単なる定期的な事務作業として扱われており、形骸化しているケースである。評価者に対する十分な教育が行われておらず、評価制度の重要性・運用の仕方を理解していない企業で発生しやすい。目的が浸透していない中で、作業として扱われることで、社員のやらされ感が高まり、こちらも不平不満につながるリスクがある。

評価制度見直しの具体的ポイント
評価制度改定際してポイントは、簡単に言えば、上記の古い評価制度の特徴の裏返しで考えれば良いが、具体例も交えて下記の通り共有する。
1. 企業の理念やビジョンとの繋がりを強化する
評価基準を企業の理念やビジョンに基づいた内容に改訂し、組織の方向性と社員の行動を結びつけることで、会社・社員の成長の方向性を合わせる。企業理念・ビジョン実現をするための行動特性(コンピテンシー)を定め、コンピテンシー評価を実施する企業も増えている。
2. 賃金との連動を行う
評価結果を昇給や賞与に反映させ、公正で納得感のある賃金制度を確立する。評価制度の内容に個人評価・チーム評価を加え、チーム評価は賞与に反映させることで、チームワークの醸成を図ることも可能である。
3. 人材育成に活用する
評価後のフィードバックを行うことで、社員に求められることと現状のギャップを正しく理解をしてもらう。特に一次評価として、社員が自己評価を行う場合は、自己評価と二次評価(上司の評価)の差を基に本人への期待を伝えることが重要である。
4. 評価基準を具体的にする
評価基準を具体化し、社員が求められる行動や成果を明確化することで、納得感と公平性を高める。等級・職種により求めることは変わるので、内容を変えることや評価のウェイトを調整することがポイントである。
5. 制度運用支援を行う
評価者に向けた研修を行うことで、制度の目的や運用方法を理解を促進する。

評価制度改定の成功事例
ー実際の評価者が中心のプロジェクト型で評価制度改定を行うことで、会社への帰属意識を高めるー
ある会社で、社長が過去に作成した評価制度を改定することとなった。
改定理由は下記2点である。
1. 評価制度が人材育成に繋がっていない
2. 評価制度が形骸化しており、社員は事務作業としてこなしているだけである
評価制度改定にあたっては、実際の評価者が中心となってプロジェクト形式で実施した。
プロジェクトの中で、各部署の代表者が集まり改定を推進したが、そこで得られた成果は下記2点である。
1. 評価制度を通して、社長の想い・どのような人材を育てる必要があるかを理解できる
➡評価制度の上位概念として、人事ビジョン(人づくりの方向性)を社長が設定し、その内容を基に策定をした。評価制度構築をしながらも、社長の想いを部門ごとの評価基準に落とし込むことで、社長の人事ビジョンと評価者の想いをすり合わせることができた。
2. 運用を見据えた制度設計
➡評価の目的や運用について教育を行いながら作成をした。目的を理解し、運用をイメージしながら作成することで、改定後は、形骸化させず正しい運用を行うことができた。
また、後日談ではあるが、プロジェクトメンバーが主体的に年に1回改定について検討し、経営陣に意見具申をするようになったとのことである。自分たちが策定した評価制度に愛着心を持ち、運用を通して会社への帰属意識が高まった事例である。
さいごに
評価制度改定にあたり、最後にお伝えしたいことは"複雑な制度設計"にしないことである。
どれだけピントの合った評価制度でも継続して運用が出来なければ、また、誰でも運用が出来なければ価値は損なわれる。
上記事例のように、数年ごとにブラッシュアップをしていくことを前提に、"分かりやすい制度設計"を行うことが重要である。
本事例に関連するサービス
関連動画
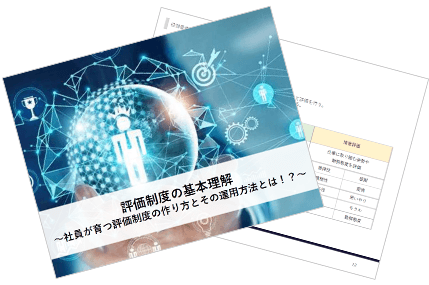
評価制度の基本理解
~社員が育つ評価制度の作り方とその運用方法とは!?~
単なるモノサシではなく、社員が育つ適切な評価制度の作り方、ならびにその運用方法を事例を交えて解説します。
この資料をダウンロードする