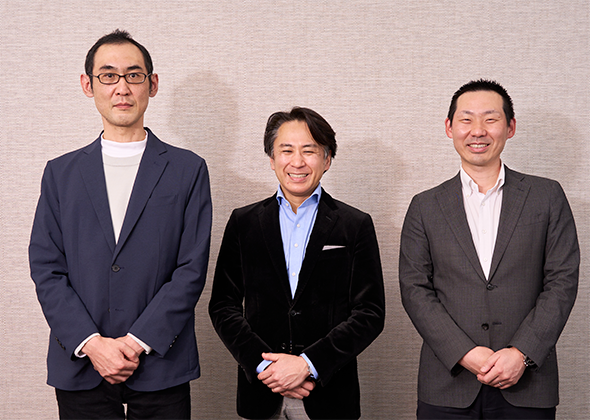デジタルトランスフォーメーションの潮流
- 武政:
-
本日はタナベコンサルティンググループ(TCG)の一員でもあるグローウィン・パートナーズ株式会社の佐野哲哉社長に、デジタルトランスフォーメーション(DX)の潮流や企業が抱えるDXの課題、そしてグローウィン・パートナーズが提供するデジタルソリューションについてお伺いいたします。まずは簡単にグローウィン・パートナーズの紹介をお願いします。
- 佐野:
-
当社は経営参謀のプロフェッショナルチームを標榜し、2005年に設立しました。TCGには2021年1月にジョインし、現在はその一員として活動しています。
当社は主に3つの領域のサービスを提供しています。1つ目がM&Aの支援。2つ目がバックオフィスのビジネス・プロセス・エンジニアリング、いわゆるDXです。3つ目がHR領域のコンサルティングです。本日は2つ目のバックオフィスのDXについてお話させていただきます。
当社はもともと会計に強く、「経営会計数値に強い」「ERPに詳しい」「会計士が在籍しており、内部統制に強く業務設計力がある」という3つの特徴を掛け算することで、企業のDX化を推進するサービスを展開しています。
具体的には、細かな業務に対するソリューションのパッケージやモジュールを作るのではなく、「なぜDX化しなければいけないのか?」「ERPを導入するとどのようなメリットがあるのか?」「お客さまはどのような価値を体現したいのか?」といった段階からコンサルティングをしています。
例えば、20年ぐらい使っている社内のレガシーシステムを新しいシステムに乗せてクラウド化する場合、「20年前にシステムを入れた担当者が社内にもういない」「進化が速すぎて何に投資したら良いのか分からない」といった課題に直面するお客さまに寄り添い、お客さまが実現したいDX化をきちんとコンサルティングしていきます。
まずは、「投資自体がどのような効果を生むのか」「どれくらいの費用対効果をもたらすのか」をシミュレーションするなど、経営者に判断材料を提供して決断していただきます。
投資が決まったら、お客さまがERPをどういった形で導入していくかを考え、ERPのベンダーやソフトウェアの開発会社に対してRFI(リクエスト・フォー・インフォメーション)やRFP(リクエスト・フォー・プロポーザル)などを作成し、どのような要求仕様でERPを導入していくかを説明します。
その後、ベンダーの提案の中からどれが最もフィットしているかをお客さまと一緒に選定する。選定後はスケジュールに合わせてどのようなモジュールを開発していくか、どのように業務フローに落とし込むか、完了するかまでの一貫したPMO(プロジェクト・マネジメント・オフィス)機能を提供しています。
- 武政:
-
上流から伴走し、実行支援までを提供できるところに強みが発揮されています。ここからは、グローウィン・パートナーズがサービスを提供する、主にバックオフィス領域におけるDXの潮流についてお聞きしていきます。最近特に取り組みが活発化してきたように思いますが、DXに対する国内企業の認識や取り組みにはどのような特徴があるのでしょうか。
- 佐野:
-
日本企業は独特のERPやソフトウェアの使い方をしている会社がかなり多くあります。具体的には、最初から会社の業務フローに合わせたオリジナルのシステムをシステムインテグレーター(SI)に依頼してつくってしまうケースがとても多く、"パンドラの箱"のような状態の会社がたくさんあります。それが日本の特徴だと思っています。
一方、海外はどちらかと言えばERPのベンダーが一番良いと考える業務フローでソフトウェアを開発し、それにお客さまが合わせていきます。もちろん、細部の開発は必要ですが、最初からフルスクラッチで開発するようなことはしません。
そもそも開発には、「IT化で何を実現したいか」という理念のような強い信念や経営の判断、理解が不可欠です。企業側にそれがないと頓挫してしまいますが、海外企業はかなり強い意思を持っています。
ある外資系企業に買収された日本企業をお手伝いしたことがありますが、パッケージなどは全て決まっており、「日本の会計ソフトを使っているかもしれませんが、うちの連結グループは○○を使っているので期限までに同じシステムで処理してください」と外資系企業の本部から指示されました。「日本には独特の商慣行がある」と進言しても、グループ内で活用しているシステムに合わせるよう指示を受けたため、過渡期は両方のシステムで処理していましたが、最終的にはグローバルの仕組みに移行しました。
これは本質的な話です。一方で、日本企業には各社に特徴的な業務フローが存在したり、非常に込み入ったシステムをつくっていたり、オプションがたくさんあったりします。独自の業務が発生することは当然ありますが、「システムが現場に合わせるべき」「業務は変えない」といった会社が多い。その考え方をいかに変えるかは課題だと思います。
- 武政:
-
システムを業務に合わせるのか、業務をシステムに合わせるのか。それは上流の発想によって大きく変わりますね。次に、DXに対する国内企業の取り組み状況についてお聞かせください。
- 佐野:
-
まず、DXという言葉が非常に難しいです。DXは概念のような言葉で、基本的にはデジタル化することによってビジネスモデル自体を変革していき、企業文化にまで取り込んでいくこと。経済産業省は、もう少し細かい定義を示していますが、DXは言わば「理想郷」であり、「DXが完了した」などと言えるような概念ではありません。
日本企業にはIT化とDXを同義に捉えているところが結構多いと思います。特にコロナ禍で在宅勤務が浸透したことで、会議がZOOMになったりグループウェアを使うようになったりしたことを「DXが進んだ」と言っていますが、これはデジタル化を通した業務効率化の1つであって、それ自体がビジネスモデルを変革したわけではありません。
バックオフィスのDXもその1つであり、さまざまな業務をデジタルに乗せることで幅広く利活用できるようになった結果、企業発展やビジネスモデルを変革していくことがDXの本質です。今はデジタライゼーションと言うよりも、多くの企業がデジタル化の推進に取り組んでいる段階だと思っています。
企業が抱えるDXの悩みと本質的な課題

- 武政:
-
企業が抱えるDXの悩みと本質的な課題についてお聞かせください。
- 佐野:
-
本質的な悩みで言えば、私どもがサービスを提供している建設業や物流業といった産業では、「そもそもDX化は必要か?」「何が便利になるのか分からない」といった声を聞きます。「DXがもたらす効果がまだまだ分からない」といった状況ですが、それ自体が大きな問題だと思っています。
ただし、建設業においても最近、SaaSベンダーがタブレットやスマートフォンを活用した現場管理や、工程管理の見える化を提案しています。いつでも、どこでもスマホで確認できるようなデジタルツールがすでに提供されているものの、日本のDXにおける根深い問題は、経営者がDXをシステム部門の仕事と捉えていること。これは本質的な課題だと思っています。
トランスフォームするには、経営者が率先してコミットすべきです。当然、トランスフォームには投資が伴いますし、上手くいかない可能性もあります。リスクを背負わないといけない以上、現場任せではなく、経営者が強い意思を持ってデジタル化を進め、社内改革していく必要があります。
なぜなら、導入して2、3カ月もすると業務が非常に楽になるにも関わらず、人は新しいことを取り入れるのが不得意ですから、必ず大きな抵抗に遭います。社内で文句が出たときに経営者が「システム部門に聞け」と逃げるようでは、システム部門もリスクを避けて小さい改革・改善にしか手を出しません。
DXとは改革そのもの。その意味では経営者がコミットしてリスクを取り、「進めばすばらしい未来とビジネスモデルができる」という強い意思を持つことが理想ですが、それをできる企業が少ないことが本質的な課題と言えます。
- 武政:
-
改革は経営者の覚悟からスタートするのだと思います。投資の話が出ましたが、もう少し深くお伺いできればと思います。手法やツールは多岐にわたるため、どこまでやるかによって投資額は変わってきます。企業が陥りやすいデジタル投資の落とし穴にはどのようなケースがあるのでしょうか。
- 佐野:
-
失敗したくないがゆえに、失敗しないところしかやらない会社は意外と多いです。まずは慣れるために小さな改善から始めるのも良いと思います。典型的なもので言えば、経費の精算があります。紙で経理に申請して現金で精算されていたところに、SaaSツールを入れるのも1つのやり方としてもちろん良いと思います。ただ、これに味を占めて周辺のデジタル化だけに手を付けて「終わり」という会社も少なくありません。
今のSaaSツールは、非常に安価で金額が張らず、失敗もしません。すぐに便利になったように感じるので、小さいツールをどんどん導入することに終始している会社が結構ありますが、それをもってDXが終了したと言うのは間違いです。
本丸、つまりメーカーであれば生産管理システム、物流で言えば運行管理のシステム、小売りならばPOSレジなどが該当しますが、そういったレガシー化している本丸にいかに投資していくかが重要です。
例えば、小売業の場合、デジタル化が進んでいるのは多店舗展開する会社ですが、10年、20年前に導入したPOSレジは時代遅れになっています。今から小売業をスタートする会社ならば、タブレット端末を使ったPOSレジが月額数百円程度で利用できますし、盗難防止用のカメラもスマホで確認できます。さらに、リアルタイムでお客さまが何を、いくらで購入したかが分かる仕組みも月額1000円程度で構築できてしまう。すでに初期投資がかからないシステムが普及していますが、大企業ほどかつての投資額に引っ張られて変更できないのが現状です。
メンテナンスをSIに依頼している会社では、社内にシステムが分かる人材がいないため、システムを変えると一から社員教育をしないといけません。そうなると、失敗するか成功するかが分からないシステムに変えるよりも、現状のまま保守費用を払っていた方が安くて安全だと思いがち。ですが、この感覚が悲惨な状況をもたらしていると思います。
最終的には「どういった世界を実現したいのか」という強い意思と戦略がないと、DXはなかなか進まないと思います。
- 武政:
-
人の話も出ましたが、DXを推進するときに必ず直面するのが人の問題です。先ほど経営者の問題を指摘されましたが、プロジェクトリーダーやシステム部門を担う人材について、「どんな人を育てれば良いか?」「採用すれば良いのか?」といった質問を受けることがあります。デジタル化を推進するに当たり想定される人の課題についてお聞かせください。
- 佐野:
-
これは非常に難しい課題だと思います。スイスの国際経営開発研究所(IMD)が公表した「世界デジタル競争力ランキング※」によれば、日本の総合順位は63カ国・地域の中で29位でした。上位の5カ国は、デンマーク、米国、スウェーデン、シンガポール、スイス。東アジアを見ると、韓国が8位、台湾が11位、中国が17位に入っています。
※国際経営開発研究所(IMD)「世界デジタル競争力ランキング2022」
https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness/
https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/10/1128218948d5f5df.html中でも「ビッグデータ活用・分析」「ビジネス上の俊敏性(Business Agility)」の項目では日本が最下位。デジタル人材に関する項目でも国際順位が低いのが現状ですが、なぜそういった状況が起きているのかと言えば、日本のシステム開発の歴史が関係しています。
繰り返しになりますが、スクラッチで業務フローを作っていくと、社内にノウハウが蓄積されません。SIに丸投げし、保守メンテナンスも任せっきり。そうした状況が10年、20年と続いているため、日本ではデジタル人材の大半がいわゆるIT企業に在籍しています。
本当は企業がシステムを使いこなさないといけませんが、社内に分かる人材がほとんどいない。しかも、経営者はそこに全く興味を持っていないことがマクロから見た日本の構造ですから、デジタル人材がいないのは当たり前だと思います。
それを前提として、ではどうすれば良いか。1つの解決策が、デジタルネイティブ世代、いわゆるZ世代と言われる1990年代以降に生まれた世代の人材をどんどん活用することだと思います。
彼(彼女)らはスマホネイティブ。SNSを使って日常的に情報発信することが当たり前の世代です。どのツールで情報を得るのが良いか、どんな仕組みが世の中にあるのかを感覚的に知っています。その上の世代になると勉強しないと使いこなせませんが、彼(彼女)らは違います。恐らくデジタルネイティブ世代からすれば、社内のある情報を別のシステムに入れるために、一度プリントアウトしてOCRに読み込んでデジタル化する業務などは全く意味が分からない世界。実際、そういった業務はたくさんありますが、デジタルネイティブ世代であれば「APIで連携すれば一瞬で完了する」と指摘する人がたくさんいるはずです。
もちろん、彼(彼女)ら全員がソースコードを理解しているかと言えば、そうではありませんが、感覚的に「これがおかしい」というセンスを持っている人を登用することは重要です。
- 武政:
-
登用した後、社内でどういった育成をしていったら良いのでしょうか。
- 佐野:
-
経営者や部門長クラスが社内のシステム部門を守ることです。例えば、システム部門がソフトウェア会社から提案されたシステムを「ぜひ導入したい」と考え、社内に「新しいシステムを入れるのでご協力ください」と伝えても、そのほとんどは潰されてしまいます。
「面倒くさい」「システムを理解できない」「今のままで良い」と言われてしまう。システム部門からすれば、良かれと思って提案したことや他社では当たり前となっているシステムすら反対されてしまうと、「この会社にいる意味はない」と感じて人が辞めてしまいます。
ですが経営陣は、そういった社員を守らないといけません。「彼(彼女)の提案は正しい」「変わるべきは会社だ」と経営陣が覚悟を持って後ろ盾になり、システム部門が社内でちゃんと意見を言える状況を作るべきです。DXには、企業文化にまで昇華するという意味も入っていますし、そこが経営者の仕事だと思います。
- 武政:
-
最後に人や投資の課題も含めて、佐野社長がお考えになるDXを推進するポイントやクリアしなければならない本質的課題について教えてください。
- 佐野:
-
一番本質的な課題としては、経営者が変わること。経営者は若くても40代以上であり、60代、70代も多く活躍されていますが、私も含めて経営者世代が経験してきた5年、10年と、今の世の中の5年、10年の変化のスピードは明らかに違います。
その一例が、この5年間のテスラの躍進です。5年前は「テスラという会社があるのか」くらいの印象しかなかったのに、今や同社の自動車は世界で100万台も売れており、トヨタ自動車ですら危機感を持つ存在です。私も含めて中小企業の経営者はデジタル化、DXにコミットしないといけません。
現代の潮流を知ることは当然のこと。さらに、それによって世の中がどう変わるか、そこに自社のビジネスモデルをどう合わせるかまで予測しながら、現在に巻き戻して投資を決めることが肝要です。そこが本質的な課題だろうと思いますが、今は経営者が予測できないからシステム部門に聞く状況。ですが先述した通り、情報化部門は各部門との軋轢を抱えているため、優秀な人材や先見性のある人材がいても忖度が働いて小さくまとまってしまいがちです。そうならないためにも、経営陣がいかにコミットするかが大事ですが、最も難しいところだと思います。
ただ、大事だと分かっていても、「詳しい人材が社内にいない」「経営陣も詳しくない」といったケースもあります。そういった場合は、当社のようなコンサルティング会社を活用するのも1つの手です。コンサルティング会社はさまざまな事例を見ていますから、すぐに案件を相談するだけでなく、経営陣が現在の潮流について直接ヒアリングするだけでも大きな意味があります。現場任せにしないことが一番の本質と思います。
ERP導入支援ソリューションのポイント

- 武政:
-
ここからはグローウィン・パートナーズ株式会社ストラテジー&オペレーション事業部の舟山真登事業部長にお伺いいたします。TGCとの連携によるERP導入支援ソリューションのポイントをお聞かせください。
- 舟山:
-
ERPと呼ばれる基幹システムは、会計を中心とする販売や購買、生産など基幹業務に関するシステムです。ERPパッケージを導入している会社も多いと思いますが、これがレガシー化してしまう。つまり、保守ができなかったり、導入した社員が退職しておりどう作り替えて良いのか分からなかったり。経済産業省の『DXレポート』にもそういった課題が記載されており、企業の競争力の妨げになると警鐘を鳴しています。
大事なことは、将来の企業目標や目的、経営理念を踏まえた上で10年、20年先の企業競争力を維持するには、どのようなシステム化やデジタル化を図っていくべきかしっかりと議論した上でベンダーやシステムを提供するSI、パッケージベンダーに伝えることです。
当社では、一般的にRFPと呼ばれる提案依頼書に落とし込み、ベンダーにしっかりと要求を伝えながら正しいシステムを作り上げていくサービスを提供しています。
- 武政:
-
これまでの支援で最も多い、あるいはニーズの高い業種はどこでしょうか。
- 舟山:
-
当社で扱っている事例としては、製造業や物流業、建設業といったデジタル化が遅れている業種や、過去に作り込んだシステムが今のビジネスと乖離しているような業種においてニーズが高まっていると感じています。
- 武政:
-
レガシーシステムはリプレイスのタイミングがあると聞きました。さらに上流の経営がどこを目指したいか。それがDXにおいて大事だと認識していますが、その辺りの設計やサポートもできると理解して良いのでしょうか。
- 舟山:
-
はい。そもそも経営がどんなシステムを求めているか。そこが定まっていないケースは非常に多いですね。システム部門にDX化するよう指示を出すものの、「経営の意思として何を重視して経営するのか(例えば、部門別の利益なのか、営業の数値目標なのか)」、あるいは、「どのタイミングでそれらの指標を見て経営判断するのか」が経営層から示されないまま、システムを作り込んでいるケースは非常に多くあります。
何を使って経営判断をしたいのか、あるいは社内をどのように効率化したいのかなど、経営の意思を示した上でシステムの仕様や要求に落とし込むことが重要です。
よく聞く事例としては、情報化部門発信で現場の要望をすべて盛り込んだ結果、企業のあるべき姿ではなく部分最適が達成されてしまうこと。経営の全体最適が達成されて正しい方向に進んでいくようなシステムにならない、という失敗事例が多々あると感じています。
- 武政:
-
そうなると、結果としてトータルコストも上がってしまいます。
- 舟山:
-
トータルコストで言えば、社外に払うコストだけでなく、導入期間の機会損失も発生します。ですから、しっかりと上流の思想から方針を決めて、個別の仕様などに落とし込んでいくアプローチが非常に重要になってきます。
- 武政:
-
一方、TGCとの連携によるERP導入支援のパッケージ型のモデルとして「DXクラウド」があります。DXクラウドについて、先述したソリューションとの違いも含めて教えてください。
- 舟山:
-
DXクラウドはパッケージ型のソリューションです。一般に広く利用されているシステムをベースにしており、システムに業務を合わせていただくという考え方。企業のデジタル化や標準化を実現していくソリューションになっています。
具体的には、業務の運用が紙やFAXで行われていたり、手書きのメモで連絡を取っていたりするアナログな業務プロセスが今も多く残っていると思います。そこをデジタル化することで企業活動に活用していく。あるいは、パッケージソフトの導入によって業務が標準化されると、人が変わってもスムーズに同じクオリティーの業務が維持できる効果が期待できます。
DXクラウドは、日本の商慣習やあらゆるノウハウが積み上げられたパッケージソフトであり、アナログで属人化されている業務やデータ化されていない業務があるならば、標準化や効率化、企業のデータ化の第一歩として活用してみるのも良いと思います。
- 武政:
-
現在、ラインナップを増やしている段階ですが、対象となる業種や規模についてお聞かせください。
- 舟山:
-
これからラインナップは増やしていく予定ですが、適応する業種として、まずは建設業と物流業を対象としたパッケージソフトウェアを提供しています。これらの業種はまだまだアナログな運用が多く残っています。当社としても、そこは早く着手すべきだと考えてパッケージ化を推進しており、ご活用いただくことで世の中のデジタル化や業務効率化、ひいては企業の競争力向上に寄与できればと注力しています。規模については、まずは20億円程度から100億円ぐらいの企業規模を対象としています。
- 武政:
-
本日は限られたお時間の中でご説明いただき、ありがとうございました。



 デジタル・DXの戦略・実装情報サイト
デジタル・DXの戦略・実装情報サイト