
1.物流業界におけるDX:変革の必要性と未来への道筋
近年、あらゆる産業領域でデジタル化の波が押し寄せている中、物流業界もまた、その変革の渦中にあります。かつては裏方とされてきた物流の現場ですが、EC市場の拡大や人手不足、環境負荷への対応といった多様な課題に直面し、いまや企業競争力の鍵を握る重要な領域へと進化しています。これらの問題に対応するため、物流業界ではDX(デジタルトランスフォーメーション)を通じて業務プロセスの見直しや構造改革が急がれています。本稿では、物流業界におけるDXの背景、導入技術、取り組み事例、課題と対策、そして今後の展望について整理します。
2.物流業界にDXが求められる背景
物流業界におけるDXの必要性は、いくつかの社会的・産業的背景から強く求められています。
第一に挙げられるのは、①少子高齢化に伴う人材不足です。特に配送業務を担うトラックドライバーの高齢化が深刻で、国土交通省が2022年にまとめた「我が国の物流を取り巻く状況」によると、道路貨物業で働く年齢層は40~54歳が45.2%で、若年層と言われる15~29歳が10.1%となっています。全産業平均が40~54歳は34.7%、15~29歳が16.6%であることを踏まえると、若年層の就業人口が少なく、高齢化が進んでいる業界の一つであると言えます。これにより、労働集約型のビジネスモデルから脱却し、省人化・自動化を伴う新たな運用体制が必要となっています。
参考:我が国の物流を取り巻く状況(国土交通省 P7)
次に、②EC需要増加に伴う小口配送需要の増加も見逃せません。消費者はスピードと柔軟性を求め、配送件数は年々増加する一方で、それを支える人手やインフラが追いついていません。特にラストワンマイル配送での効率化が求められています。
加えて、近年注目される③「2024年問題」では、働き方改革関連法の施行によりトラック運転手の時間外労働が制限され、業界全体の輸送能力の低下が懸念されています。具体的には、2024年の輸送能力はこれまでより14%低下し、重さにして約4.0億tの荷物が運べなくなるとされ、さらに、現状のまま推移すれば、2030年には輸送能力は34%低下し、重さにして約9.0億tの荷物が運べなくなる見通しです。
さらに、④環境への配慮も避けて通れない課題です。国や自治体はCO₂排出削減を強く求めており、物流分野でも車両のEV化や輸送の効率化を通じたカーボンフットプリントの削減が喫緊の課題となっています。
3.技術によって加速する物流DX
こうした複雑な課題を解決する手段として、多くの企業が注目しているのが、デジタル技術を活用した業務改革です。物流DXは単なるIT導入ではなく、業務プロセスそのものを再設計する包括的な取り組みとなっています。最新技術と組み合わせた活用方法を5点紹介します。
❶IoT技術を用いた位置情報や温度管理のリアルタイム可視化は、貨物管理の精度を飛躍的に向上させます。センシング技術を活用することで、荷物の現在地や保管環境を正確に把握でき、トラブル発生時にも迅速な対応が可能となります。
❷AIによる需要予測や配送ルートの最適化も注目されています。過去のデータや天候、地域ごとの傾向を基に、配送計画を最適化することで、無駄な輸送を減らし、燃料消費の抑制やドライバーの負荷軽減に寄与しています。
❸倉庫内作業のロボット化もDX化の柱の一つです。無人搬送車(AGV)やピッキングロボット、垂直自動倉庫などを導入することで、人的ミスを減らし、限られた人員でも大量の出荷業務に対応できるようになります。ロボットと人間が協働するスマート倉庫の構築は、今後のスタンダードになりつつあります。
❹クラウドプラットフォームとのAPI連携によって物流データをクラウド上で一元管理し、取引先企業や配送業者との情報共有が容易になり、サプライチェーン全体の可視化と連携強化を図ることが可能となります。
❺ブロックチェーン技術の活用により、輸送履歴や検品記録などのトレーサビリティを担保し、改ざんが困難であるため、品質管理や不正防止にも効果があるとして注目されています。
4.国内物流企業のDXへの具体的な取り組み
日本国内でも、物流DXに積極的に取り組む企業が増加しています。特に注目されているのが、共同輸配送のプラットフォーム構築やAIを活用した需要予測と発注業務の自動化、さらに倉庫内作業のロボット化と自動搬送技術の導入です。以下では、国内で実際に導入が進んでいる代表的な事例について紹介します。
①ヤマトホールディングスと富士通の「共同輸配送プラットフォーム」
・ヤマトHDが2024年に新会社「Sustainable Shared Transport(SST)」を設立。
・富士通と連携し、AI・ブロックチェーンを活用したオープンなシェアード型の輸配送プラットフォームを構築。
・荷主の出荷・荷姿情報と物流事業者のスケジュールを自動でマッチング。
・手作業の削減、配送効率の向上、空荷率の低下を実現。
・ブロックチェーンにより配送ログの改ざん防止・透明性確保。
・2025年初頭から宮城〜福岡で運行開始、2026年までに全国80便を目指す。
参考:日本経済新聞「ヤマトHD傘下のSSTと富士通、荷主企業・物流事業者向けの共同輸配送システムを稼働開始」
②日立製作所とヤマエ久野のAIによる需要予測・発注自動化
・ヤマエ久野が日立製作所のAIを活用した自動発注システムを2024年に本格導入。
・過去データや季節・販促要因を基に需要を精密に予測。
・発注作業時間を1日3時間から1.5時間に短縮。
・現場担当者による修正・調整が可能な柔軟なシステム。
参考:ヤマエ久野と日立が協創、AI需要予測自動発注で作業時間を大幅短縮(株式会社日立製作所HP)
③サミットにおける全店舗でのAI発注導入
・スーパー「サミット」が全店舗でAIによる発注提案システムを導入。
・販売傾向、天候、曜日などを基に高精度な予測を実施。
・提案の採用率は95%以上、欠品減少と在庫最適化に貢献。
参考:日立、サミット全店に需要予測型自動発注システムを導入 サプライチェーン全体最適化に向けたシステムの検討へ(株式会社日立製作所HP)
④自動倉庫とピッキングロボットによる作業効率化
・国土交通省支援のもと、自動搬送機器(AGV・RGV)とピッキングロボットを導入した次世代物流センターを開発。
・入出庫・仕分け作業を高速かつ正確に自動化。
・人手と作業時間の大幅削減を実現。
参考:物流・配送会社のための物流DX導入事例集(国土交通省 P10)
これらの取り組みに共通しているのは、「人間の判断を補助・代替するAI技術」「作業の機械化による省力化」「企業間連携による業界全体の効率化」という三つの柱が有機的に結びついている点です。物流業界のDXは、単なるIT化ではなく、業務の在り方や企業間の関係性そのものを再構築する動きとして進行しており、その変化は今後もさらに加速していくでしょう。
5.物流業界のDX推進における課題と対応
一方で、物流業界におけるDX推進には多くの障壁も存在します。
① 初期投資とコスト負担の重さ
多くの物流企業、特に中小規模の事業者にとって最大のハードルは、DX導入に伴う初期投資の大きさです。IoTセンサーやロボティクス、クラウド型物流システムといった高度なデジタル技術の導入には、多額の資金が必要であり、短期的な利益改善が見込めない場合には意思決定が停滞する傾向が強いです。
このような課題に対しては、公的支援制度の活用が有効です。日本政府や自治体では、DXを推進する中小企業向けに補助金や助成金制度を提供しており、具体的には「IT導入補助金」や「ものづくり補助金」、「スマート物流導入促進事業」などが該当します。また、大手企業が主導する共同配送ネットワークやクラウド型サービスに参加することで、プラットフォームの一部として機能しながら低コストで先端技術にアクセスすることも可能です。
さらに、近年ではサブスクリプション型のDXサービスも増えており、初期費用を抑えつつ段階的な導入が可能なモデルが登場しています。これにより、投資リスクを抑えながら業務改善を進められる環境が整いつつあります。
② デジタル人材の不足と現場のITリテラシーの低さ
物流現場では、ITやデジタルツールに不慣れな従業員が多く、最新システムを導入しても活用されずに形骸化するリスクがあります。特に、紙や電話、FAXに依存した業務が根強く残る中小企業では、デジタル化そのものが「現場とかけ離れたもの」として受け取られることがあります。
この問題に対する対策としては、段階的な教育と実践的なOJT(On-the-Job Training)を中心とした人材育成が不可欠です。まずは操作が簡便なシステムやツールから導入を始め、現場のスタッフが「成功体験」を得られるように設計することが重要です。そのうえで、管理職やリーダークラスには、外部講師による研修やeラーニングを通じてデジタルリーダーシップを育成していく必要があります。
また、人材の内部育成だけでなく、外部人材との連携強化も選択肢の一つです。IT企業やコンサルタントとの協業、あるいは地方自治体が運営する「デジタル人材バンク」などを活用して、社外の知見を取り入れることで、組織全体のデジタル対応力を底上げできるでしょう。
③ 既存業務やレガシーシステムとの整合性
DX推進の過程でしばしば直面するのが、長年使い続けてきた基幹システム(いわゆるレガシーシステム)との整合性の問題です。これらのシステムは独自にカスタマイズされているケースが多く、新しいクラウドシステムやAIエンジンと連携が取りにくいです。さらに、既存業務がアナログを前提に設計されている場合、単に新技術を導入しただけでは業務全体にかえって混乱をもたらす危険性があります。
このような課題に対しては、「業務の再設計(BPR:Business Process Re-engineering)」が不可欠です。単にツールを入れ替えるのではなく、業務の流れ自体を見直し、デジタル前提のプロセス構築を行うことが、真の意味でのDXに繋がります。また、API連携可能なシステムやオープンプラットフォームを選定することで、既存システムと新技術の「橋渡し」を実現することも可能となります。
加えて、導入フェーズを段階的に設定し、「試験導入 → 一部本稼働 → 全社展開」といったプロセスを丁寧に設計することで、現場の混乱を最小限に抑えながら移行を進めることができるでしょう。
④ 現場の意識ギャップと組織文化の障壁
DXの実現には、技術だけでなく組織全体のマインドセットの変革が必要です。しかしながら、物流業界では「現場は現場」「ITは本社任せ」というように、役割分担が固定化され、DXを「自分事」として捉えにくい土壌があるのも事実です。
このような組織文化の課題に対しては、トップマネジメントの強いリーダーシップと現場巻き込み型の推進体制が鍵となります。経営層がDXを戦略的課題として明確に位置付け、社内でその重要性を継続的に発信することが求められます。また、成功事例を社内で「見える化」し、取り組みの効果や恩恵を全社員と共有することで、徐々に現場の意識変革を促していくことができます。
さらに、KPI(重要業績評価指標)やインセンティブ制度にDX目標を組み込むといった方法も、社員の積極的な参加を引き出す有効な仕組みとなるでしょう。
6.今後の展望
物流業界のDX化は、単なる業務効率化にとどまらず、ビジネスモデルの根本的な転換を促す可能性を秘めています。たとえば、複数企業が輸送手段や倉庫スペースを共有する「シェアリング型物流」や、AIが完全にスケジューリングを担う「自律型ロジスティクス」など、新たな形態のサービスが今後ますます広がっていくでしょう。
さらには、環境負荷の低減や地域経済との連携を前提とした持続可能な物流のあり方も、DXを通じて再構築される段階に入っています。デジタル技術を活用しつつ、人と地域に優しい物流体制を築くことが、これからの物流業界に求められる姿と言えるでしょう。

バックオフィス業務の無駄を洗い出し、最新のデジタル技術によって改善を施すためのシステム再構築メソッドを提言します。
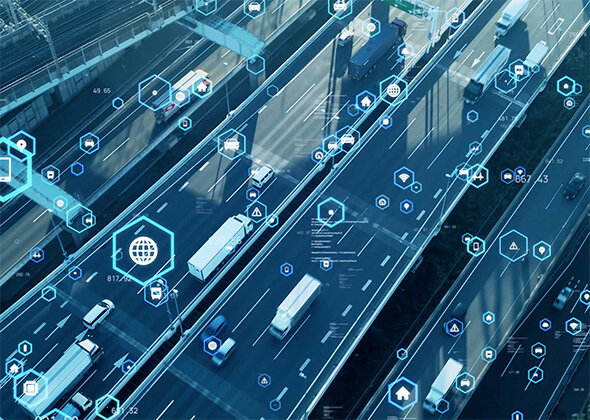
 デジタル・DXの戦略・実装情報サイト
デジタル・DXの戦略・実装情報サイト















