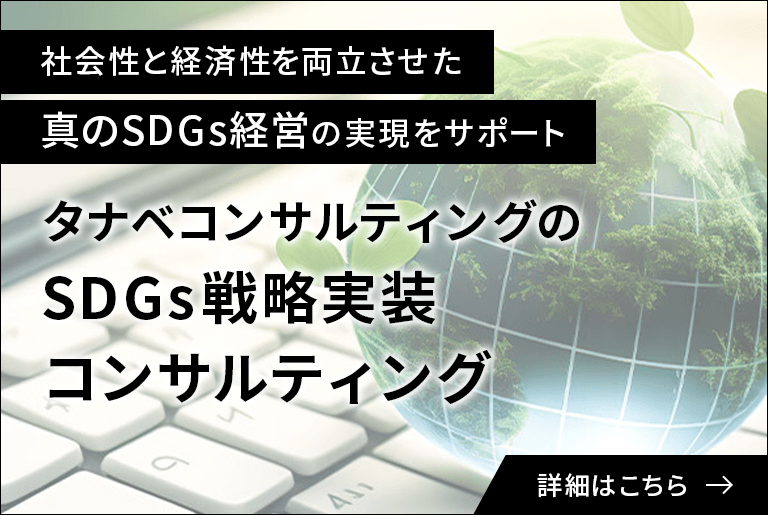COLUMN
コラム
閉じる
SDGs人材とは、現在の自身や自社の経済的な成功でだけではなく、持続可能な社会の実現も考慮し行動できる人のことを指し、世代を超えた時間軸で、自らや他者、社会の利益を考えられる人材のことをいいます。
企業経営でも重要視されるSDGs
なぜ企業経営にSDGsの取り組みが求められるのか
企業にとって、いかにして投資を呼び込んでいくかは重要な課題です。SDGsへの取り組みは企業イメージを向上させることから、多くの企業でSDGsへの取り組みを開始しています。
経済産業省は2019年に「SDGs経営ガイド」を策定し、民間企業に対してSDGsへの取り組みの方向性を示しました。このガイドの中では、各企業はSDGsに関して、17の目標、169のターゲット全てを求めているわけではないこと、自社と関連の深い目標を見定め資源を重点的に投入すること、などが示されています。自社の本業に即した投資を行うことで、効率的なSDGsへの貢献が可能となります。
日本企業の多くは、「社会貢献」の概念を経営理念に盛り込むなど、「SDGs経営」に通じる価値観がすでに存在します。SDGsへの取り組みと併せて、企業理念も積極的に外部に発信することで、企業を取り巻くステークホルダーからのイメージが向上します。
これらの活動は広く周知されることで、効果が上がります。そのためには、企業はこの取り組みを推進し、外部に効果的に発信することができる、「SDGs人材」の育成や確保が求められています。
参考
SDGs経営ガイド(2019年5月経済産業省)
SDGsの概念を経営に取り込んだ成功事例
婦人靴の企画製造から販売までを手掛ける株式会社クロスロードは、自社の製品に、革の鞣(なめ)し工程や染色工程で本来は廃棄される「米のもみ殻」や「ぶどうの搾りかす」を使用した新しい革素材を使用したことで、大きなPR効果を発揮することに成功しました。
この施策を立案し、実行に繋げていくのが、SDGs人材です。
婦人靴は紳士靴と比較し、ソールを交換して同じデザインの靴を長年履く習慣が少ないことや、季節ごとに流行が大きく変化することから、業界全体で大量生産・大量廃棄する状況が続いています。
このような業界の中にあって、クロスロード社は上記の新工程で製造された革素材を世界で初めて製品に使用し予約販売を始めたところ、それがインターネットニュースとして全国に発信されるなど大きなPR効果を生み出しました。
クロスロード社は約40年の歴史がありますが、中小企業で全国的な知名度はありませんでした。しかしながら、このSDGsへの取り組みによって自社の知名度を向上させ、環境に配慮した企業であるというブランドイメージの形成に成功しました。
掲載
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000069039.html

SDGs人材を育成する2大メリット
企業イメージの向上による集客効果
アメリカの経営学者であるフィリップ・コトラーが1980年代に提唱した概念で、ソーシャルマーケティングというものがあります。ソーシャルマーケティングとは、社会貢献や社会的な利益を重視した企業活動を指します。社会貢献というキーワードは、30年以上も前から必要性を認識され続けているのです。
SDGsの取り組みもこのソーシャルマーケティングと同様に、社会に貢献するものです。社会貢献への姿勢を打ち出すことで、消費者に好感されることに繋がり、特にB to Cビジネスを展開している企業にとっては大きなプラスになります。
また、SDGsの表彰制度としてSDGs推進本部が主催する「ジャパンSDGsアワード」があります。企業で実施しているSDGsへの取り組みをこの表彰制度にエントリーすることで、知名度やブランドイメージを高めることもできます。
表彰制度は注目度が高く、広く市場にPRすることが可能となるのです。
企業イメージ向上による求人効果
SDGsの17の目標の中には、「ジェンダー平等」や「働きがいも経済成長も」といった、人事関連の項目も含まれます。これらの目標に対して取り組む企業には、多様な個性と能力を持つ人材が集まるというメリットがあります。
またこの2項目に限らずとも、SDGsに取り組む企業はクリーンなイメージを持たれやすく、社会問題に対して積極的に対策を実行している姿勢から、求職者・地域住民からの評価も高まります。 労働環境の改善にも積極的だろうという客観的評価も高く、企業イメージの向上とともに、人材採用にも好影響をもたらします。
厚生労働省の発表によると、2022年4月の有効求人倍率(季節調整値)は1.23倍で、前月に比べて0.01ポイント上昇しました。労働力不足が深刻化する日本において、優秀な人材を確保する施策としてもSDGsへの取り組みは有効です。
この取り組みに対して先頭に立って推進していく担当者はSDGs人材です。担当者を任命し、SDGsへの理解を深め、施策を立案、推進していくスペシャリストを育成することは、企業の人材確保の面でもメリットをもたらすのです。
参照
厚生労働省の発表によると、2022年4月の有効求人倍率(季節調整値)
SDGsを推進するための人材育成施策とは?
SDGs人材育成のための3つのポイント
SDGsの取り組みを推進するSDGs人材育成のためのポイントは以下の3点です。
①SDGsへの理解の深化
SDGsの方針や他企業の成功事例は、外務省や経済産業省といった公的機関のホームページに広く掲載されています。SDGsの取り組みと利益追求が相反してしまうと、対応は続きません。将来のSDGs人材に対し、他社の事例をもとに自社で展開し、利益を上げていくためにはどうするかを考えさせることは、SDGs人材育成に有効です。
②積極的な外部研修の実施
2021年の帝国データバンクの調査によると、「SDGsに積極的」な企業の割合は39.7%(前年差+15.3ポイント)でした。SDGsに取り組む企業は年々増加しており、他社のSDGs人材と議論する場を提供することは、担当者の取り組み意識の醸成に寄与します。
③労務関連の整備
働き方改革や男女平等など、労働関連法はSDGsに繋がっています。まずは自社の環境を整えることで、会社としての取り組み姿勢を従業員に浸透させることも重要です。社員に対してSDGsの理解を求めるためには、その教育や環境を提供する必要があります。
参照
2021年の帝国データバンクの調査
SDGsはどうやって理解を深めればいいの?
SDGsを学ぶツールや研修は世の中に多く存在しますが、まずは何を学びたいかを定義しましょう。基礎知識を学ばせたい企業であれば通信講座も有効ですが、会社の取り組みを引っ張っていくようなSDGs人材として育成をするのであれば、やはり外部の研修に参加させることが効果的です。
ここでのポイントは、講演ではなく研修であることです。
研修では基礎講義だけでなく、他社のSDGs人材と議論をする時間や、実際にSDGsの取り組みに成功している企業を視察に行く機会もあります。実際の成功事例に触れることで、生きた知識を習得できるでしょう。
研修を通じてSDGsの重要さを理解したSDGs人材は、その熱意で周囲を巻き込み会社全体の取り組みの中心となります。
SDGsの取り組みは、業種や業態を問わず援用できる取り組みも多く存在します。これらの知識を深めることで、SDGsへの取り組みによるメリットを最大限に引き出すことができるのです。

最新コラム

- 海外進出を成功させるためのパートナーの選び方

- 海外進出に成功した企業事例と成功要因の解説

- 海外市場調査のアンケート調査・インタビュー調査の具体的な方法

- 事業ポートフォリオ再編のプロセスとリスク対策
ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと
進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド
~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド
~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド
~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~
資料ダウンロード

- 長期ビジョン・中期経営計画に関する企業アンケート調査レポート2025年

- ストラテジー&ドメインコンサルティングメニュー紹介資料

- 統合報告書 ストーリー設計のコツ~企業価値は「説明」では動かない。「物語」が動かす。~

- 設備工事業界の未来を切り拓く:課題解決と成長戦略の最前線~人手不足からデジタル化まで、業界の変革を支える実践的アプローチ~

- TCG REVIEW 顧客創造モデル

- 収益構造を変える!ビジネスモデル・イノベーション~高収益を実現する事業ポートフォリオとPLのデザインはできていますか?~

- 食品業界の企業が中期経営計画策定で押さえるべきポイント~重要になるテーマと事例5選をご紹介~

- 経営者の成長投資アンケート調査レポート 2025年
 長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト
長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト