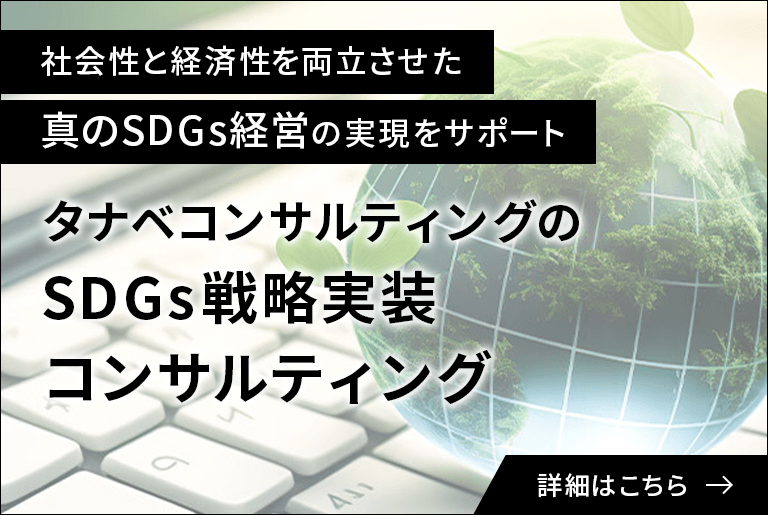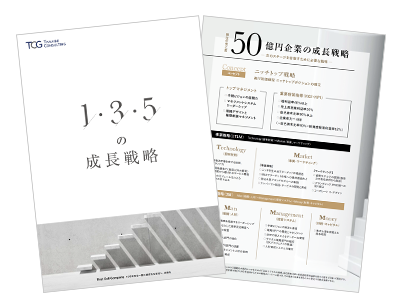COLUMN
コラム
閉じる
最近よく聞くSDGs。「単なるブームでは?」「中小企業には無関係」「余裕ができてから...」と考えていませんか?
SDGsは今後の中小企業にとっても「持続可能な組織」へと成長する上で必要不可欠な要素です。
1.中小企業のSDGsの取り組みの実態
⑴大企業と中小企業の取り組みの差
私たちの社会の持続可能性を脅かす社会問題や環境問題の深刻化を受けて、世界的にさらなる注目を受けているSDGs。
帝国データバンクの「SDGsに関する企業の見解」についての2021年6月の調査結果によると、「SDGsに積極的」な企業は前年と比較し15.3ポイント増の39.7%と大きく増加しており、実際にSDGsに対する企業の意識は高まっています。
しかしながら、「SDGsに取り組んでいない」企業は50.5%と半数を超えており、規模別にみると、「大企業」では37.3%に対し、「中小企業」では53.2%と、SDGsに対する意識は企業規模間で大きな差があるのが実状です。
SDGsは2015年に開催された国連サミットにおいて、国連加盟193カ国による全会一致で採択されたものです。
あらゆる個人・組織が当事者意識をもって取り組んでいくこと重要であり、中小企業としても自分事であると認識する必要があります。
それではなぜ大企業に比べて中小企業で取り組みの遅れが生まれているのでしょうか?
参照
①帝国データバンクの「SDGsに関する企業の見解」についての2021年6月の調査結果
⑵中小企業がSDGsを推進する為の課題感
一般財団法人 日本立地センターの「2020年度 中小企業のSDGs認知度・実態調査」によると、
「SDGsの重要性・必要製を認識していながら、SDGsに取り組んでいない理由」として、
①「取り組む余裕がない」 37.0%
②「自社の事業活動に比べると優先度は低い」15.9%
③「何から取り組めばよいかわからない」10.7%
の順に高くなっております。
中小企業のSDGs推進の課題としては「SDGsの優先度が低い」に集約されます。
またSDGs未取組企業において、「取り組む動機となりうる具体的なメリット」について調査を行ったところ、
①「売上高の増加」 38.8%
②「新規取引の増加」 30.5%
③「企業利益の増加」 30.1%
の順で多い結果でした。
中小企業がSDGsに取り組むことで、上記メリットは得ることは可能であるため、優先度高くSDGsに取り組んで行く必要があります。
それでは実際に中小企業が取り組むべき理由について考えていきましょう。
参照
②一般財団法人 日本立地センターの「2020年度 中小企業のSDGs認知度・実態調査」
【関連資料】:
【2022.4.14開催】SDGsフォーラムアンケート調査レポート

2.中小企業がSDGsに取り組むべき理由
⑴SDGsに向き合わない企業はこれからの市場競争で勝ち残れない
SDGsを軽視することで、社会的ニーズを掴み損ね、ビジネス上の機会損失のリスクが高まります。
SDGsは世界共通の価値観であり、今後の世界経済の方向性を指し示すものですので、企業にとってはビジネスチャンスそのものです。
実際にSDGsの取り組みに積極的な企業ほど「業績」や「ブランド力」の向上の効果が得られております。
日本経済新聞社と日経リサーチの「第3回日経SDGs経営調査(2021年)」において、
国内846社に対してSDGsの取り組みについて定量的に5段階の評価を行っております。
上位評価である4以上の企業において、
「企業イメージ・ブランド力の向上」を実感している企業が88.9%、
「業績の向上」については58.8%の回答率という結果でした。
SDGsに取り組む企業ほど、明確に社会課題を捉えたビジネス展開をしていると推察できます。
それでは取引関係・人材採用・資金調達の3つの観点から具体的なSDGsの必要性について考えていきます。
参照
③日本経済新聞社と日経リサーチの「第3回日経SDGs経営調査(2021年)」
【関連ページ】:
企業のSDGs取り組みポイント~お客様に選ばれ続ける持続可能なビジネスへ
中堅・中小製造業がSDGsに取り組むメリットについて
SDGs経営実装完全ガイド~メリット・事例・戦略のポイントまで一挙ご紹介
⑵取り組まなくてはいけない理由
①取引関係 「CSR調達」・「グリーン調達」といった概念が広がっています。
法令順守・労働環境への配慮のある企業であったり、環境負荷の低い製品・材料を扱う企業と取引をしようという流れが活発化しております。
今後の新規の取引先を拡大のためにはこの点を考慮しなくてはなりません。
②人材採用
現在小学生から大学生までSDGsの教育プログラムが組まれており、10代のSDGs認知率は7割を超えており、職先を選ぶ理由としても「社会貢献性の高さ」が急増しています。
2025年には「SDGsネイティブ世代」の「ミレニアル世代」が日本の労働人口の半数に達すると予測されてます。
労働人口が減りゆく中、優れた人材の確保のために、SDGsへの取り組みと発信は不可欠です。
③資金調達
「環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)要素を考慮した投資」=「ESG投資」に注目する必要があります。
機関投資家を中心に、サスティナビリティを評価する概念が普及し、SDGsがそのベンチマークとなっています。
ESG投資比率は年々拡大しており、資金調達面でもSDGsが重要になってきます。
それではどのようにSDGsの取り組みを始めれば良いでしょうか。
【関連ページ】:
SDGsとESGの違いとは~時代に求められる経営の在り方~
中小企業としてどのようにSDGsに取り組むか
ゴール17「パートナーシップで目標を達成しよう」の活用
SDGsの重要性を理解したところで、経営資源の限りのある中小企業にとって、SDGsは難しいと感じてしまうことは少なくありません。
そこで着目すべきがゴール17「パートナーシップで目標を達成しよう」の活用です。
第三回ジャパンSDGsアワード 内閣総理大臣賞を受賞した福岡県北九州市小倉北区の「魚町商店街振興組合」の事例をご紹介します。
商店街として「SDGs宣言」を行い、「誰一人取り残さない」形で、様々なステークホルダーと連携しながらイベントやサービスを実施しています。
ホームレス自立支援・障害者自立生活支援などの社会的包括に視点を置いた活動、飲食店等と協力したフードロスの削減、規格外野菜の販売等の地産地消の推進等、多くの社会課題にアプローチしています。
商店街の環境についても、若手起業家やワーキングマザーのためのビルのリノベーション、商店街への透過性太陽光パネル設置による電力活用などのリノベーションを実施しています。
地場の企業として地元を大切にし、地域が元気になる未来を描くことが中小企業には重要です。
ビジネスチャンスとしてのSDGs
SDGsは「世界共通の価値観をまとめた社会全体の経済の方向性を指し示すもの」です。
SDGsでは「誰一人取り残さない」の理念のもとに17のGoalsと169のターゲットと244の指標が設定されています。
これをもとに社会のニーズを"ビジネスチャンス"として捉えていく必要があります。
一般財団法人 日本立地センターの「2020年度 中小企業のSDGs認知度・実態調査」によると、「自社が主体的に貢献可能なSDGs の17 のゴール」について、
ゴール8「働きがいも経済成長も」 20.0%
ゴール3「全ての人に健康と福祉を」 10.9%
ゴール11「住み続けられるまちづくりを」9.8%
の順で多くなっています。
自社の事業活動や社会的活動に近いものは貢献しやすく、日頃なじみのないゴールほど低い傾向でした。
小さな貢献を足掛かりにして、自社の「あり方」と「強み」を活かしながら徐々に取り組みを広げていくことが求められています。
中小企業が「持続可能な組織」へ成長するために、今一度自社の事業活動や社会的活動を振り返り、SDGsの観点から長期的視野で経営を考えていくことが必要ではないでしょうか。

中小企業のSDGs事例
ここまで、中小企業のSDGs取組の実態、取り組まなければいけない理由、どのようにSDGsに取り組むべきか?をみてきました。続いて、具体的に中小企業が取り組んでいるSDGsの事例をご紹介します。
【関連事例】:
SDGs企業事例一覧
株式会社ハヤブサ様(製造業)
同社は1959年創業の、フィッシングブランドの【ハヤブサ】、アパレルブランドの【FREEKNOT】、ペット用品のブランド【Pets Republic】の3本柱で、各分野において、最高の品質・最高のシーンを提供している企業です。
2022年にSDGsブランディングプロジェクトを発足し、2030年SDGsビジョンの構築や顧客体験価値創造ストーリー設計に取り組んでいます。自社だけでなく、ハヤブサ商品を使用することで、ユーザーにもSDGsに貢献できているという「体験価値」を感じられる取組を設計したいと考えました。SDGsの活動を「点」ではなく「線」で捕らえ、環境負荷を低減した調達や雇用を生み出す海外製造、ユーザーに対する企画の実施や、海の清掃活動などの川上から川下までの一貫したストーリーを設計し、ユーザーもSDGsに貢献したという「体験価値」を見出すことができる仕組みを構築しています。
【関連事例】:
株式会社ハヤブサ 様|「体験価値」を重視した顧客体験価値創造ストーリー
近藤グループ様(建設業)
近藤グループはグループ傘下に近藤建設(株)、近藤不動産(株)、近藤リフレサービス(株)、(株)コミニスを持つ、埼玉県ふじみ野市に本社をおく総合建設・不動産業です。事業コンセプトを「快適生活応援企業として地域密着・親戚づきあい・迅速行動で幸せを建てる」とし、住まいづくりに関する事業をワンストップで展開しています。
同グループがSDGsの取組みを始めたきっかけとして、建設業界におけるSDGsへの取組みが加速していることがあげられます。例えば、スーパーゼネコンをはじめ、準大手、中堅地場ゼネコンにおいても、ホームページなどでSDGs宣言として掲げている企業が増えており、その取り組みの一部が、公共工事入札の評価点に加味され、発注先企業選定の基準にもなっているケースもあることから、同グループにおいても事業を継続していくためにはSDGs取組が必須であると認識し、新たな価値創造に挑んでいます。
【関連事例】:
近藤グループ 様|部門の垣根を超えたボトムアップ型のSDGsプロジェクト
著者
最新コラム

- 海外販路開拓の具体的な方法4選!成功させるための戦略と手順を解説

- タイ進出を成功させるメリットと3つの注意点|進出前に知るべきリスクを解説

- バリューチェーンの重要性とは?最適な構築方法のポイントを解説

- 中期経営計画の期間は何年が最適?成功する策定のポイントを紹介
ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと
進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド
~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド
~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド
~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~
 長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト
長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト