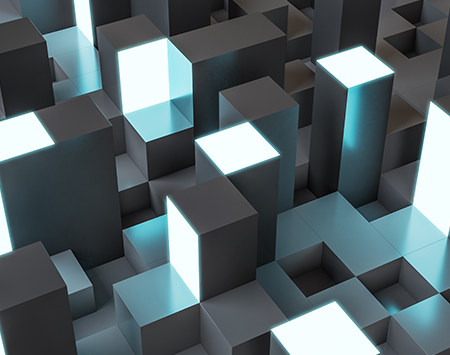人事コラム
エンゲージメントサーベイの活用最大化を通じた人事制度改定
パーパスやビジョンおよびエンゲージメントとの連動性を踏まえた人事制度リニューアル

人事制度改定にまつわる背景
昨今、働き方改革や労働時間の上限規制を中心とした2024問題が相まって、人事制度の改定と向き合う企業は増加の一途をたどっている。
しかし、大半の企業が人事制度の改定を労務面の法律を満たすことを前提とした、対処療法的な改定に留めており、根本的な各社の成長を促す制度改定にまで至っていないケースが散見される。
この背景には、
①自社のパーパス(自社の貢献価値)やビジョン(追求すべき姿)との連動性不足
②エンゲージメント(能動的な貢献意欲)との連動性不足 が挙げられる。
以下、それぞれポイントに切り分けて考察していきたい。

自社のパーパスやビジョンとの連動性不足
当然ながら、何のために人事制度改定をしていくのかと申し上げますと、第一義は「人材育成」であり、単なる「選別査定」ではないということを押さえていただきたい。
加えて、パーパスやビジョン・方針を軸とした人材育成に繋がる人事制度の改定(再構築)が極めて重要な制度思想となる。
我々タナベコンサルティングでは、「社員の成長=会社の成長」を実現できるアライメント(並列的)な制度になるよう、人事制度コンセプトの設計から評価制度(EX:等級要件、評価項目)や賃金制度(賃金分配思想)まで一つ一つ丁寧に繋がりを押さえながら、落とし込んでいくことを推奨している。
上記は、経営システム(パーパスやビジョン~人事制度までの繋がり)としての一体感の醸成や人事制度だけが別建ての制度として機能してしまう事を防ぐ狙いもある。

エンゲージメントとの連動性不足
パーパスやビジョンとの連動性を踏まえた人事制度を既に導入されている企業においては、次のステップとして、エンゲージメントとの連動性を踏まえた人事制度改革をオススメしたい。
具体的には、組織エンゲージメントや仕事エンゲージメントの構成要素となる各エンゲージメント項目の各社における課題要素を抽出し、評価制度へと繋げていく手法である。
組織エンゲージメントで言えば、心理的安全性やダイバーシティなど、対組織に対する貢献意欲を育んでいくための、エンゲージメント項目を評価制度へ落とし込むことができる。
仕事エンゲージメントで言えば、モチベーションやエンパワーメントやレジリエンスなど、対仕事に対する貢献意欲を育んでいくための、エンゲージメント項目を評価制度へ落とし込むことができる。
当然、無理に繋げることが目的ではないものの、エンゲージメント(能動的な貢献意欲)を育むことで、理想と現実を両輪で追求することができると言える。
さいごに
最後に、人事制度改定に向けた頻度について押さえておきたい。
これまで3年~5年に1回や、中には10年以上、現人事制度を放置している企業まで存在するが、取り巻く環境変化のスピードや自社のパーパス・ビジョンの実現およびエンゲージメントサーベイを中心としたパルスサーベイ(連続的・定点的な効果測定)を主流と考えた場合、比較的、短いスパン(半年に1回)を目安に、人事制度自体も改定をしていく事をオススメしたい。
それだけ、我々を取り巻く内外の環境は常に変化をし続けているのである。
本事例に関連するサービス

企業内大学(アカデミー)
設立コンサルティング
「学び方」を変えることで「働き方」が変わり、 更に魅力ある企業へと進化させます。企業内大学の設立により、人材成長の仕組みを構築します。
企業内大学(アカデミー)設立コンサルティングの詳細はこちら

Engagement KARTE
(エンゲージメントカルテ・エンゲージメントサーベイ)
人的資本投資において重要となる指標を明確化し、人的資本経営の推進と企業価値の向上をサポートします。
Engagement KARTE(エンゲージメントカルテ・エンゲージメントサーベイ)の詳細はこちら