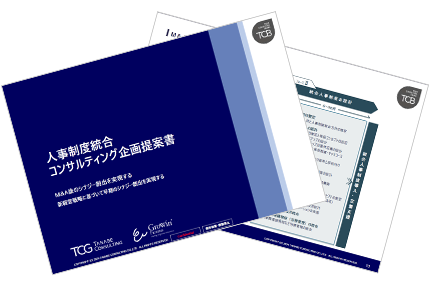人事コラム
M&A後の人事制度統合の進め方
―成功する「人事制度統合」ステップー
双方のシナジーを最大限に発揮させるための人事PMI
統合後のビジネスモデルをイメージし、
各社の役割に応じた制度を設計する

事業・組織モデルの変化に合わせ、統合制度の基本コンセプトを策定する
M&Aにおける人事PMI(人事制度統合)は、異なる企業文化や人事制度を有する企業同士の人的思想をまとめ、シナジー効果を創出することにある。これは単に会社の統合、人事制度を1つにまとめるということではない。
例えば、M&Aの目的が垂直的統合におけるバリューチェーンの拡大だとしたら、異なる職種・職群が1つの会社に内包されることになる。その場合、単に給与水準やインセンティブの支給方法を同じ思想で行うと、モチベーションを低下させる要因になる。一方で、M&Aの目的が営業エリアの拡大という水平的展開を目指したものとする。この場合、営業職のインセンティブの支給方法や給与水準が異なると、社員のモチベーションが大きく低下する要因となる。
つまり、人事PMIを行う上でのファーストステップは、統合会社の事業モデル・組織モデルを念頭に置いた上で、制度の差異をピックアップし、その差異はあってよいのか、あってはならないのかを検討することだ。大きくは、人事フレーム、評価制度、賃金・賞与制度、賃金水準、退職金制度、労務管理、人事関連諸規程だ。統合に対する不利益変更や課題点を抽出した上で、簡易的に統合制度の基本コンセプトを策定する。このコンセプトには人材マネジメント方針、つまり採用、配置・異動、評価、処遇、育成、退職に対する考え方を示すことが重要だ。いきなり統合することは現実的でないため、差異を明らかにした上で、方針を立てることを推奨する。

人事制度の根本となる求める人材像を定義する
統合制度の基本コンセプトが明確になったら、「求める人材像」のアップデートを行う。人事PMIのメリットの一つは、新会社の理念・ミッション・戦略の実現に向けたベクトルの統一にある。人事制度は「求める人材像」を出発点として各制度が形作られる。当然、それに近づけば近づくほど評価されるため、社員もそれを目指すことだろう。つまり、「求める人材像」の定義づけは、統合会社における組織風土や価値観を醸成することと同義であり、これなくしてはシナジーの発揮は見込めない。このステップにおいては現状や職種の差などは気にせず未来志向で検討いただきたい。具体的には、統合新会社の社員に求められる価値観・行動を明文化することである。

育成やステップアップを見据えた人事フレームの設計
「求める人材像」が定義された後に行うべきは、人事フレームの設計である。特にキャリアコース(マネジメント・スペシャリスト等)と等級(等級数や等級定義)の策定である。この場合、統合するにあたり新会社になるのか、もしくはホールディングカンパニーのもとグループインするのかで考え方が異なる。
新会社の場合は組織が1つになり、組織規模自体が変わるため、役職における職責や等級数などを統合しなければ、非常に運用に窮する可能性がある。当然昇格年数やキャリアの選択肢が異なることも弊害となるため、組織規模に合わせ調整することが求められる。
一方で、ホールディングカンパニーのもとに社名を残したままグループインする、させる場合には無理に統合する必要もないだろう。特に、垂直統合的なM&Aであり、グループ内取引を加速させるのであれば、多少賃金水準の統一化は必要であっても、単独で運営可能だ。しかし、グループ全体でサクセッションプランや育成を考える場合は多少の統合が必要となる。
人事フレームを統合にするにあたっても、念頭に置くべきは統合後、どのような事業運営をしていくのか、である。

評価制度と賃金制度の設計
人事フレームが確定したら、それに合わせ評価制度と賃金制度を策定することだ。ここで重要な点は、冒頭に述べた通り、その差は妥当なのか?である。同じサービスを販売する企業同士が統合した場合(水平的統合)、営業の評価指標が異なり、処遇も異なるというのは納得感はかなり低いだろう。反対に、明らかに市場価値が異なる職種同士を同じ賃金水準にすればそれも弊害である。これだけでなく、評価期間や福利厚生が異なる、みなし残業の時間が異なるなども同様である。
一方で、統一すべきものとして考えていただきたいことはバリュー評価である。バリュー評価とは、企業が掲げる価値観などに基づいて、従業員の行動や姿勢を評価するものである。企業理念や考え方を浸透させるため有効的な評価指標の一つである。人事制度は組織文化を形作る重要なものであることは前述したが、それを評価制度に落とし込む際にはバリュー評価を検討いただきたい。

社員の不安を取り除くことも重要なミッション
M&Aする・されるとなった場合、自身の処遇がどうなるか気にならない社員はいないだろう。そのため、社員とのコミュニケーションを充実させ、不安を解消することは欠かせない。人事制度であるため、後からかなりの制度変更が発生することは望ましくはない。だが、人材マネジメント方針については早期に発信することを推奨したい。わが社がどんな人事思想であるかを知ることは、安心感を持つことにつながる。また、新制度説明会は十分に行う必要がある。これまでと評価基準等も変わる可能性があるため、ルールは全社員に周知し、階層によって重点を置くべき箇所に分けて説明することが望ましい。いずれにしても、運用してこそ意味があるのが人事制度である。
事業・組織の変化を捉えた上で、人材マネジメント方針を策定し、具現化いただきたい。
本事例に関連するサービス
関連動画