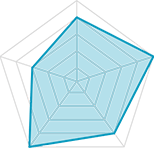人事コラム
賃金制度の見直しのポイントとは?
初任給引き上げに対応する注意点や見直すステップ
初任給を見直す際の注意点や見直すステップ、見直した賃金制度を浸透させていくポイントについて解説
賃金を見直す際は新卒だけでなく、既存社員にも配慮した見直しを意識しましょう

はじめに
近年大手企業を中心に「初任給の引き上げ」が注目されている。
労務行政研究所の「2024年度新入社員の初任給調査」(東証プライム上場企業152社の速報集計)によると、初任給を全学歴引き上げた企業は86.8%で、2022年度の41.8%から2年間で45ポイントも上昇している。
大手企業の引き上げの影響や労働力人口の減少、最低賃金の引き上げなど外部環境の変化に伴い、中小・地方企業でも初任給を見直さざるえない企業が増えている。
しかし、賃上げなどの賃金制度の見直しは進め方を間違えると既存社員のモチベーションを低下させる危険性や、業績や収益構造に伴わない賃上げが先行することで利益率の低下に陥る可能性がある。
本コラムでは初任給を見直す際の注意点や見直すステップ、見直した賃金制度を浸透させていくポイントを紹介したい。

初任給引き上げの背景
1. 採用力強化
初任給引き上げの一番の理由は採用競争力の強化である。
2024年卒の大卒有効求人倍率は1.71倍であり、前年より0.13%上昇している。
年々労働力人口が減少する中、今後も求人倍率は上昇する見込みであり、新卒採用に苦戦する企業は増えることが考えられる。
そのため優秀な若手社員の確保や離職防止のため引上げを実施していることがあげられる。
2. 働く価値観の多様化
新型コロナウイルスを機に働き方も多様化している。
終身雇用・年功序列という1つの会社でキャリアを積む従来のメンバーシップ型の雇用が限界を迎え、年齢・経験に関係なく職務に応じた報酬で採用するジョブ型雇用も増えつつある。
そして専門職や研究職など一部の職種においては新卒社員にもジョブ型採用を導入し、早い段階から優秀な若手人材を確保する動きが増えている。

賃金体系を見直す際のポイント
このような採用強化や働き方の変化に伴い、初任給を引き上げる企業が増える中、見直す際に注意していただきたいポイントを紹介する。
1. 既存社員のモチベーション
初任給の引き上げに合わせて既存社員の賃金を見直すケースが多いが、全ての社員に平等で、納得感のある対応は難しい。
特にこれまで昇給額が限られていた企業では、不公平感を感じるだけではなく、過去これまで還元してこなかったことに対して不信感さえ与えることもある。
その結果、既存社員のモチベーション低下や離職につながらないよう、管理職への事前説明や社員への落とし込みの方やコンセプト(目的)の明確化など丁寧な対応が必要となる。
2. 採用コストの増加
初任給を引き上げる際には、ライバル他社や地域特性に応じてどれだけ引き上げるか慎重に検討することが必要である。
無理に大手の引き上げ水準に合わせることや、競争力強化のため高く設定すれば、採用も慎重にならざるえない。
その結果、人件費だけではなく選考方法や時間など採用コストも増える傾向がある。
また新卒だけでなく、中途採用も賃金の見直しを検討する必要があり、採用コストの総額を考えて検討する必要がある。
3. 労務費全体の見直し
初任給の引き上げを考える際に労働分配率が適正かどうか基準を考える必要がある。
労働分配率とは付加価値に占める人件費の割合を表し、労働分配率=人件費÷付加価値(売上高-変動費)で求めることができる。
業界やビジネスモデルによって異なるが、タナベコンサルティングでは40%~50%を一つの目安として設定している。
会社と社員がともに成長するためにはバランスが大切である。
数年後のビジョン達成に向けて適切な労務費のバランスを考えて、賃金全体の見直しが大切である。

賃金制度見直しのステップ
具体的に賃金の見直しのステップについて紹介したい。
1. 賃金ポリシーを定める
まずは賃金を決める前に賃金ポリシー(理念)について検討したい。企業理念からあるべき姿を考え、どのような社員に賃金として報いていくのか方針を考えるのである。賃金や評価を人事ポリシーとして明文化することにより、社員に何を求め、どのように評価し、賃金として報いるのか、会社の考えを示すことができる。
2. 「グレード」ごとのモデル給与を決める
次に社員に求める役割や職務の範囲に応じてグレードを決め、あるべき役割や成果に基づきモデル年収を定める。次に社員をグレードに格付けし、シミュレーションしながら調整するのだが、社員の格付けはあくまで今の賃金水準から考えるのではないことに注意いただきたい。今の賃金から当てはめてしまうと、役割と乖離し不満や不公平感につながるおそれがある。まずはグレードを定め、グレードに求める役割を明確にし、社員を格付けした上でモデル賃金のレンジを検討していきたい。
3. 賃金体系・各種手当額を決める
最後に賃金体系や手当について検討する。近年では共働きやジェンダーの観点から家族手当など見直す企業も増えてきている。また賃金アップは社員のモチベーションアップにつながるが一時的なもので終わることも多い。そのためトータルリワードなどの非金銭的な報酬を整え、わが社らしさを表すことで社員の動機づけや採用活動にも活かす企業が増えている。
また、年収に占める賞与の比率が高い場合や生活給の要素が高い賞与制度である場合は、賞与原資の一部を月給へと充当し、年収は維持しつつ月給を引き上げる企業も多い。
さいごに
賃金制度を見直した後、正しく運用するポイントは評価者の育成である。筆者が過去支援させていただいたクライアントで、一律1万円賃上げをしたものの、その年の評価が同期よりも低かったため、納得できずに退職した若手社員がいた。評価による賞与の差は1,000円である。
大切なのは賃金を上げるだけではなく、社員と向き合い、コミュニケーションをとりながら「働きやすい」環境を整え、成長や貢献に報いることで「やりがい」を感じることであるにある。その結果「社員の働きがい」につながり、社員と企業がともに成長する組織に繋がるのである。
改めて世の中の潮流に合わせるだけではなく自社なりのポリシーを持ち、賃金引上げを行うのか検討いただきたい。
本事例に関連するサービス
関連動画