人事コラム
バックオフィス部門における目標設定のポイントとは?
その目標、正しい設定になっていますか?成果を上げる目標設定の方法について解説

目標管理制度の誤解
目標管理制度(MBO-S)とは、組織目標と個人目標のすり合わせを行い、社員一人ひとりの自主性を重視しながら、組織目標を達成する手法である。しかし、多くの企業では「上司が部下の目標を管理する」と誤認されており、"S"の観点が抜けているケースが多い。
あるべき目標管理制度の運用は目標に対して、セルフコントロール(自己管理)しながら目標に能動的に取り組み、上司と共に定期的に振り返りながら成果を上げることにある。にも関わらず、評価のための目標設定を行っているが故に、「高い目標は達成が難しく評価が低くなってしまう可能性があるので、実現可能な目標を設定する」ことも少なくない。
企業を取り巻く環境変化や価値観が多様化する現代においては、予め与えられた目標ではなく、組織目標を軸に個人で能動的に目標に向かう事ができる仕組みが必要である。
本コラムでは、目標管理制度を導入する企業のいくつかある課題の中で「バックオフィス部門の目標設定」に着目し解説を行う。

部門の役割と成果の明確化
前述する通り、組織目標と個人目標を繋げていくことが重要であるため、まずは前提となる組織に求められる責任と役割を明確にしていただきたい。例えば人事部に求められる役割は「採用、育成、労務管理を通じて人材管理を行う部門」として定義するのか、「経営目標を実現させるため、人材の能力を最大限に活用するための戦略を立てる部門」として役割を定義するかによって向かうべき方向性(目標)が異なる。フロントオフィス、バックオフィスに関わらず何を実現する部門であるのか、部門における役割責任を今一度再確認をしていただきたい。
その上で組織目標(年度目標、部門目標、部門のビジョンなど)を設定し、実現に向け、個人としては何に取り組むのかを設定することが重要となる。

バックオフィスにおける目標設定
バックオフィスの目標設定が難しく感じるポイントは"定性目標"であることではないだろうか。例えば営業であれば売上げや粗利など"定量目標"として設定することができるが、バックオフィスでは業績数値を持たない場合が多いため"定性目標"が主となる場合が多い。
ここからはバックオフィス部門が目標を設定する上でのポイントを3つ紹介する。
ポイント①:状態変化がわかる目標として設定する
定性目標だとしても、何がどのような状態になっていれば達成といえるのかを設定する。
例えば育成に関する目標を設定する場合、「○○さんが△△業務を一人で完結でできる状態になるまで指導教育する」と設定すればある程度場面が限定的で且つ、明確になり進捗状況や状態変化による評価がしやすくなる。
ポイント②:手順や手段などプロセス目標を設定する
最終的な結果だけを目標として設定するのではなく、最終的なゴールに向け「いつまでに何をやるべきなのか」を具体的な手順を設定し、その積み上げが最終目標の実現に繋がるように設定する。
タスクを時間単位で進捗管理することができることから、達成度や進捗度に応じた評価がしやすくなる。
ポイント③:数値化できないか検討する
①や②でも不安が残る場合はなんとか定量化できないか検討することも一つである。
例えば「業務内容の改善」の代用目標として「残業時間○○時間の削減」と設定するイメージである。
しかし、必ずしも業務改善=残業時間の削減に繋がっているとは限らないため、注意いただきたい。
その場合はポイント①で示す状態変化と数値目標を組み合わせることで、達成場面が限定されるので評価がしやすくなる。
具体的には「業務棚卸しを行い、不要な業務を整理することで(定性)、残業時間の○○時間削減する(定量)」のように組み合わせることも一つである。
まとめ
目標管理制度は、P(目標の設定)⇒D(目標を軸にした活動)⇒C(上司からのフォロー)⇒A(目標の達成度を踏まえた次の目標設定)のサイクルを循環させることが成功の鍵を握る。
つまり"どのような目標設定を行うのか"と"上司からの運用サポート"が非常に重要になる。
評価制度のため目標管理制度ではなく、標を達成するためのマネジメント手法の一つとして取り組んでいただきたい。
本事例に関連するサービス
関連動画
関連情報
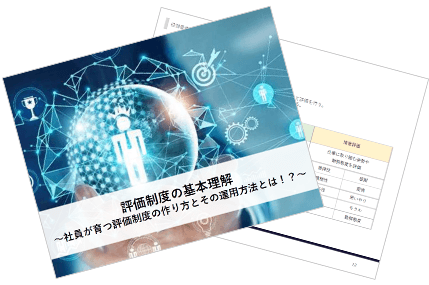
評価制度の基本理解
~社員が育つ評価制度の作り方とその運用方法とは!?~
単なるモノサシではなく、社員が育つ適切な評価制度の作り方、ならびにその運用方法を事例を交えて解説します。
この資料をダウンロードする



