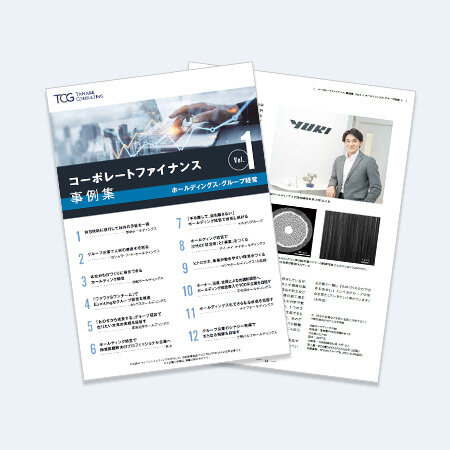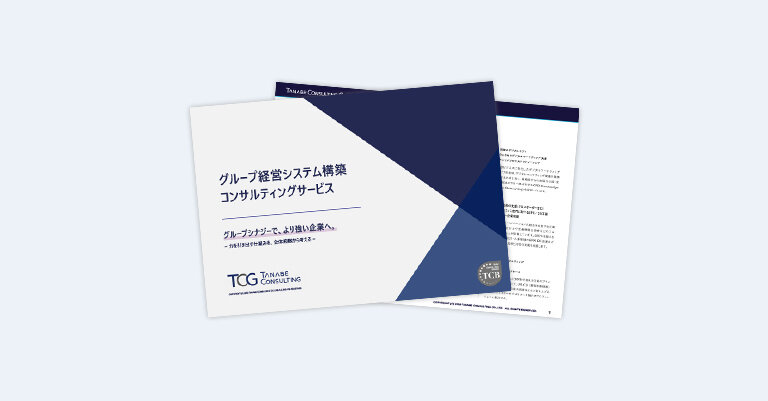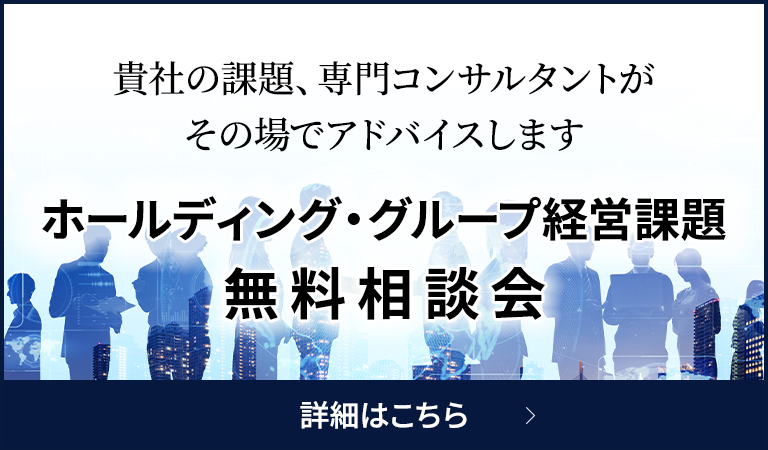グループガバナンスの重要性とは?
目的からグループガバナンスに必要なポイントまでを徹底解説
- グループ経営

閉じる
グループガバナンスとは?
グループガバナンスとは、直接的な意味合いは企業グループ全体の統治・管理を意味しますが、基本的な考え方としては企業価値の向上を目指せる体制や適正に業務を行える体制の構築を意味します。
近年は上場企業、非上場企業関係なく企業価値を向上させる経営戦略として事業の多角化やリスク分散、事業ポートフォリオ戦略の推進によりM&Aが加速し、企業グループ体制を構築している企業が多く存在します。そんな中で2019年6月に経済産業省より「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針(グループガイドライン)」が公表され、グループガバナンスの強化が求められています。
コーポレートガバナンスとグループガバナンスの違い
グループガバナンスを理解するうえで、まずは「コーポレートガバナンス」と「グループガバナンス」の違いを解説します。
「コーポレートガバナンス」は株主・ステークホルダーの視点で経営者や経営陣は株主の利益を最大化するための経営を実施しているかを管理するための仕組みです。特に「法令順守・不正防止」「管理と執行の在り方」の仕組み整備することがコーポレートガバナンスです。
一方でグループガバナンスは、経営者の視点で企業グループ全体の企業価値向上やリスクの最小化を実現する仕組みです。
グループガバナンスの重要性
グループガバナンスの重要性が高まるなかで、グループガバナンスの実態はどのようになっているのか?
企業規模や上場・非上場によって違いはあるが、多くの企業ではグループガバナンスの実効性が十分ではないのでしょうか。特にM&A等でグループインした企業に対してのグループガバナンスは不十分になっているケースが多く、企業価値向上を目的として企業グループを組織しているにも関わらず、グループガバナンスが不十分なため、企業価値向上の阻害要因になっている傾向になります。
グループガバナンスが機能していないと、企業グループ全体の効率的かつ効果的な資源配分ができなかったり、経営戦略(事業戦略)が浸透せず事業が思うように推進できなかったりして、結果として企業価値の最大化が困難につながります(攻めのガバナンス)。また、グループ企業全体の内部統制やリスク管理が不十分となり企業価値向上の阻害要因となります(守りのガバナンス)。
このようにグループガバナンスが機能していないと企業価値の向上が難しくなるため、グループガバナンスは非常に重要なものであると考えられます。
グループガバナンスの目的
先ほど説明したように、グループガバナンスは企業成長を促すうえでとても重要な役割だといえます。
では何のためにグループガバナンスを整えるのでしょうか?
ここではグループガバナンスの目的を2つ紹介します。
1.グループ全体の業務を適正に実施する
グループ全体の業務を適正に実施し、経営上のリスクを最小化することです。
グループ経営では、ルールが整備されていないことで、子会社が独自に経営判断を行ったり、グループ本社が子会社の業務支援に注力しない、といった問題が生じます。
こうした問題から、品質偽造や情報漏えい、贈賄などに発展する恐れがあります。
これらの事態を防ぐために、グループガバナンスの整備が求められます。
2.グループ全体の企業価値を高める
グループ全体の企業価値を高めることです。
リソースを最適に配分できていないなどの理由で、収益性や生産性に問題を抱えるグループ企業は少なくありません。経済産業省のガイドラインでも、日本は欧米と比べてROA(総資産利益率)が低水準であることが指摘されています。
特に近年は、国内市場の縮小や産業構造の急激な変化に伴い、国内外でのM&Aを含めた機動的なポートフォリオマネジメントの変革が重要になっています。
こうした課題を解決するためには、「攻めの姿勢」でのグループガバナンス強化が必要となります。
グループガバナンスに必要なポイント
グループガバナンスの重要性や目的についてお話ししましたが、実際にグループガバナンスを推進させていく上で必要なポイントについてここでは「ガバナンスを推進するための仕組みの整備」と「グループ全体の組織再構築」の2つを説明します。
ガバナンスを推進するための仕組みの整備
資源配分システムの再整備
ガバナンス強化において重要なポイントの一つは「攻め」のガバナンスです。そして、その中核をなすのは、資源配分に関わる意思決定システムの構築であり、前述の「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」においても「事業ポートフォリオマネジメント」という表現で言及されています。それゆえに、企業のグループ経営体制にマッチした資源配分システムに再構築することが重要であり、具体的な資源配分システムの再構築に関しては、資本コストをベースとするのが一般的です。
権限・責任の再定義
グループガバナンスにおいて、権限委譲の範囲をグループ全社全体として、それぞれのグループ特性により区分けし、区分けごとに権限委譲の方針を定めることにあわせて、権限移譲に伴う責任も再定義する必要があります。なお、ここでいう責任の代表的なものは業績責任であり、どのような指標を設定するかを議論する必要があります。具体的には、権限設定の際に行ったグループ会社区分に従って業績評価の指針を定めつつ、グループ会社それぞれに業績責任を図る指標と具体的な数値を設定することが一般的です。
人材マネジメントの再構築
企業において事業の多角化・グローバル化の進展と、その手段としての純粋持株会社制度への移行や、M&Aの活用などにより、近年ではグループ会社が量的にも質的にも増加しつつあります。そのため、グループ会社の経営陣をどのように配置するのかは重要な経営課題として、その認識が高まっており、実務指針においても指名・報酬についての言及がなされています。実務としてはグループ全体の経営幹部をコントロールできる一定の仕組みを構築する必要がありますが特に重要な仕組みとして、グループ会社間でスムーズに経営幹部が移動できるための候補人材のプールとその選抜のための基準作りや、グループ会社間での職位の読替え、そしてグループ内での報酬方針の整合性確保が挙げられます。一方で、仕組みを動かすには、全てのグループ会社に同一に運用することは現実的ではなく、グループ会社の性質や規模に応じた運用基準を合わせて検討することが重要です。
資金マネジメント
グループ本社は、グループ全体の企業価値向上に向けて経営陣の意思決定をサポートする重要な組織である一方で、適切なガバナンスを維持するための仕組みを構築する役割を担っています。その中でも近年、多くの企業において取組みが進められているのが資金マネジメントです。一般的に、グループ会社の増加とともにグループ全体での資金が増加し、再投資の原資へ回せるものと思われがちですが、資金自体は各社の事業活動の成果であるために、分散しているのが現状です。グループ本社としては、これらの資金を集約し、グループ全体最適の視点で再投資や調達した資金の返済原資に供することが望ましいため、グループ内での資金集約のルールを定め、CMS(Cash Management System)を活用した資金マネジメントを行う企業が増えています。
さらに今後は、単なる集約だけではなく、ガバナンスの観点からグループ会社の資本・配当政策に踏み込んだルールを定め、グループ会社の適正資本水準をにらみつつ、資金をグループ本社に集約していく動きが加速すると思われます。
モニタリング・監査体制の整備
グループガバナンスが重用される背景の一つに、ガバナンス強化の流れの中で企業の対応が進む一方で、発生した多くのガバナンスに関する問題はグループ会社が起点となるものが多く存在する、という点があげられます。それゆえ、実務指針においてもグループ内部統制に力点が置かれています。一方で、グループ会社全てに対してグループ本社が直接的に統制をかけることは、実務上困難です。そのためグループ会社の性質や規模に応じてグループ会社が直接統制を行うか、グループ会社の統制状況の有効性を確認する間接統制を行うか、その選択を検討する必要があります。この際には前提条件において整理した、グループ会社の区分にリンクしてモニタリングと監査体制を整備することが現実的です。
グループ全体の組織再構築
グループ経営を統括する組織設計
グループ本社は、グループガバナンスを円滑に進める存在として重要であり、ガバナンスに資する組織の設計要素、また最終的な組織形態の選択として、純粋持株会社制度に移行するか否かを決定する必要があります。また、グループ本社機能の補完として、グローバル体制における地域統括会社の要否や、さらに本社部門を中心とした間接部門効率化を図るためのシェアードサービスの活用なども検討する必要があります。
グループ再編の推進
グループ経営の形態を検討するに際して検討が必要なものとしては、グループ企業の再編があげられます。再編についてはポートフォリオマネジメントにおける集中と選択によるグループ外への退出はもちろんのこと、グループ内における類似の役割を担う会社の統合、さらには役割明確化のためのグループ会社の分割などが想定されます。特に、類似会社の統合についてはM&Aで買収した企業の子会社と、元来の子会社の間で頻繁に起こりうる事象でもあります。なお、再編の際に重要なガバナンス上の視点はグループ会社の数を絞り込むことにあります。グループ会社の数がガバナンス上のリスクがあるのは自明の理であり、過去のガバナンス問題が顕在化した企業を見てもグループ会社の絞り込みは重要なポイントといえます。
資本・出資比率の見直し
グループ再編と並行して実施すべき事項はグループ会社の資本と出資構成の見直しです。出資比率の見直しについては、戦略的な観点から完全子会社化や出資比率の引き上げ、もしくは引き下げなどが行われることが多いですが、今後はガバナンスという観点から特に上場子会社に対する出資比率の見直しも検討されることになると思われます。さらに今後重要となるのは、グループ企業の資本そのものをガバナンスの視点から見直すことです。なぜなら、多くの企業においてはグループ会社の資本金がどのような経緯で設定され、現在の水準に至っているのか、さらには剰余金についてはどのような方針で留保しているのかが明確でなく、また現在の水準が十分であるかの検証もなされていません。そして、この結果、グループ会社において過小資本や過大資本が発生している可能性があり、特に課題資本は、その過剰流動性を背景にした資金の流用や横領などガバナンス上の問題を惹起する可能性が高まるのです。なお、これらのグループ組織の再構築については、会計・税務上の影響を見極めるとともに、少数株主をはじめとしたステークホルダーへの対応など、現状に即した対応が必要となります。
グループ経営システム構築サービスの詳細は下記よりご覧ください。
グループガバナンスにおける課題
グループガバナンスを構築していく上での課題として以下が挙げられます。
1.企業グループ全体の方針(ビジョン)が浸透していない。グループ各社が自社の利益を最優先し、部分最適となっている。
2.グループ本社の機能が整備されておらず、各子会社の取りまとめ業務に留まり、グループ本社が子会社の経営に深く関与していない。
3.M&Aでグループインした企業に対してPMI(経営統合)が上手くできておらず、ガバナンスを効かせるルール整備が不十分。
4.グループ本社と子会社間でのルール整備が不十分で「責任と権限」が曖昧になっている。
企業グループの成り立ちや企業グループの規模等によって課題に違いはありますが、上記の課題は多くの企業グループで課題になっています。
この課題を以下のアプローチで解決します。
グループガバナンスの課題解決に向けたアプローチ
グループガバナンスの課題を解決するためには、グループガバナンス体制の構築と機能設計の最適化が必要です。グループ本社は企業グループにおける「司令塔」の役割を担います。そのため、グループ本社は企業グループ全体を全社最適で機能整備していくことが求められます。以下にそのアプローチ・ポイントを5つ挙げます。
1.グループ理念ーミッション・ビジョン・バリューー
企業グループ全体でのグループ理念を設定し、企業グループ全体が同じ価値判断基準で企業活動をすることで企業グループ全体の方向性を統一。
2.グループ経営企画機能ー戦略・企画ー
グループビジョンマネジメント、事業ポートフォリオ設計、グループ事業計画、グループブランディングなどの企業グループ全体の戦略設計や経営企画機能の整備。
3.グループガバナンス機能ー統治・管理ー
意思決定プロセス・権限と責任の整備、コンプライアンス・リスクマネジメント機能、グループ諸規程の整備、グループ会社の監査機能等、グループ会社の内部統制機能の整備。
4.グループマネジメント機能ー管理・評価ー
グループ管理会計システム、グループ業績マネジメント、グループ人材マネジメント、グループキャッシュマネジメントシステムなどの管理・評価機能の整備。
5.シェアードサービスセンター
財務・経理、人事・労務、情報システムなど、グループ共通業務を集約し企業グループ全体の業務の効率化を図る。
5つのアプローチ・ポイントをあげましたが、機能設計の注意点は、グループ本社がグループ子会社を「権力を振って抑えつけない、押し付けない」ことです。グループガバナンス体制が構築され、企業グループ全体の企業価値向上を実現するためには機能整備4割、運用6割です。グループ本社として良い機能設計ができたとしても、運用が上手くいかなければ元も子もありません。機能整備については運用を考えながら設計していくとともに、グループ子会社の理解を得ながら進めていくことが重要になります。
グループガバナンスシステムに関する実務指針
グループガバナンスを実効性のあるものにするためには、実務的な指針を基に具体的なシステムを構築することが求められます。2019年に経済産業省が公表した「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」は、設計と運用の方向性を示しています。この指針では、グループ全体の企業価値向上を目指し、ガバナンスの目的、体制、プロセスの明確化が重要とされています。
グループ理念を基盤とし、ガバナンスの基本方針を策定することが推奨されています。また、意思決定プロセスを整理し、権限と責任を明確化することで、親会社と子会社間の統制を強化します。さらに、リスク管理体制を構築し、内部統制を徹底することで、法令遵守やリスクの低減が可能となります。
これらの取り組みを進めるためには、定期的な見直しと改善が必要であり、企業環境や戦略の変化に応じて柔軟に対応することが求められます。
実務指針を基に、企業グループ全体が統一された方向性を持ち、戦略的かつ効率的に事業を運営できる体制を構築することが、グループガバナンスの成功につながります。
さいごに
改めて、グループガバナンス体制・機能の構築は企業グループ全体の企業価値を向上させることが目的です。
実効性のあるグループガバナンス体制・機能は一度整備したからといって終わりではありません。日々、経営環境は変化しており、企業グループの在り方や形も変化を続けていきます。その中で経営環境の変化や企業グループ全体の戦略の転換に合わせたかたちでグループガバナンス体制・機能も変化していくことが求められます。常に自社の企業グループ全体の企業価値を向上するために試行錯誤し、より実効性が高いグループガバナンスを整備していくことが重要です。
関連記事
-

中堅企業が実装すべき財務戦略~企業を取り巻く経営課題~
- 資本政策・財務戦略
-

中堅企業が実装すべき財務戦略~「財務価値分析」から見る経営実態~
- 資本政策・財務戦略
-

事例から学ぶROIC経営の落とし穴とは?
- 企業価値向上
-

-

-

-

企業価値とは?意味と評価方法をわかりやすく解説
- 企業価値向上
-

 コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト
コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト