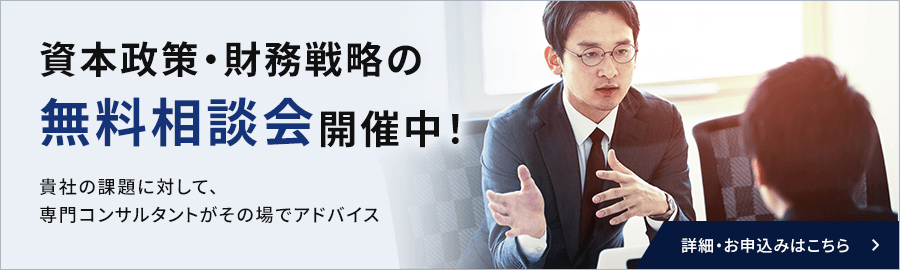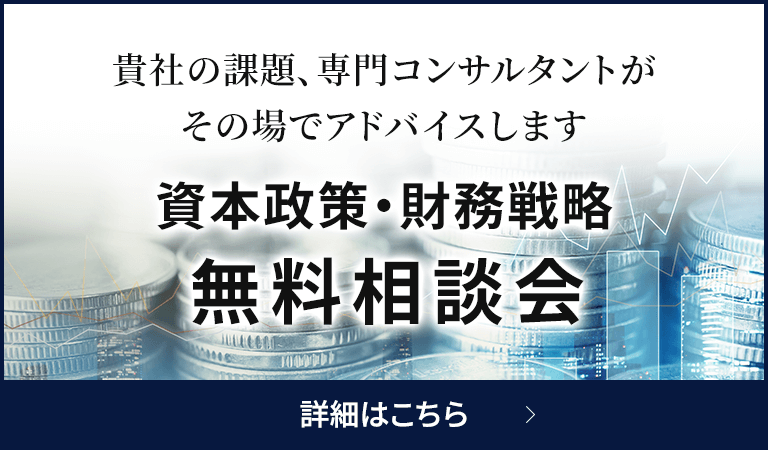キャッシュフロー改善とは?ポイントを解説
- 資本政策・財務戦略

閉じる
利益は出ているものの、手元資金が思っていた以上に少ない。または、新規事業の開発、人材投資・DX投資といった思い切った投資投資を行いたいが、どこまで資金を投資してよいかわからない ―
そのような悩みをお持ちではないでしょうか。
本コラムでは、キャッシュフローを改善するためのポイントを解説いたします。
キャッシュフロー経営の要諦
2023年世界の実質GDP成長率は3.2%とコロナ禍における後退局面から成長局面へと一転いたしました。けん引したのはアメリカの個人消費が中心となり、経済大国でありながら2023年のGDP成長率は2.5%と高水準を維持しております。日本経済に目を移しますと、2023年実質GDPは1.2%増と、世界・アメリカ経済と同様コロナ禍の経済状況からは回復が見られます。
一方で、国内倒産件数に着目すると、2023年の倒産件数は8,497件(前年6,376件、33.3%増)と、前年から2,000件以上上回っております。さらには2年連続で前年を上回り、2015年(8,517件)に迫る件数となっております。前年からの増加率に関しては、33.3%となり、バブル崩壊後で最も高い増加率となっております。(帝国データバンク全国企業倒産集計2023年報より引用)。
経済成長と裏腹に倒産件数が増加している背景・要因と致しましては、「販売不振」が6,672件(前年4,836件、38.0%増)で最も多く、全体の78.5%(対前年2.6ポイント増)を占めております。次いで「経営計画の失敗」「売掛金回収の困難」と続いている状況です。
どういった要因にしろ借入に対する返済不能が直接の倒産要因となっているのが大半となります。コロナ禍を経て借入が増加した背景がありますが、なぜ多くの企業が借入返済不能に陥るのでしょうか?
大きな要因の一つに、「キャッシュフロー経営」への理解が乏しいことが挙げられます。
「黒字倒産」や、「勘定合って銭足らず」など損益計算書とキャッシュフロー計算書の混同が散見されておりました。
私は金融機関に10年以上勤め、約500社以上のお客様と対峙して参りました。その中で、「キャッシュフロー」と「利益」を明確に区別出来ず返済に苦しむ社長を多く見て参りました。本コラムを通じて「キャッシュフローの改善方法」を体得し、ぜひ有効な資金調達・事業投資を通じ、企業の成長に繋げていただけますと幸いです。
特にキャッシュフローへの理解が深まることにより、どこまで新規投資が可能であり、どこまでの借入が返済可能か、また業績悪化時の資金繰り改善などに大きく役立てることができます。
つまりは、将来を見越した企業経営ができるようになり未来志向へと舵を切ることができます。反対にキャッシュフローへの理解が乏しいと、現預金が後からついてくる形となり、どこまで資金を使ってよいかわからない、や、過去の経験による感覚での新規投資など、無計画な経営となってしまいます。ぜひキャッシュフロー経営を皆様には体得いただければと存じます。
キャッシュフローとは何か?
「利益」とは財務会計上の概念であり、対外的にどれだけ儲けたのか、そして儲けに対してどれだけの税金支払義務が生じるのかを明確にする概念となります。一方で「キャッシュフロー」は、対外的な利益を示さず、つまりは税務とは一線を画した概念となり、手元にどれだけの現預金が増えたのか(減ったのか)といった指標となります。
当期純利益を基にキャッシュフロー計算が始まりますが、大きく「営業キャッシュフロー」「投資キャッシュフロー」「フリーキャッシュフロー」「財務キャッシュフロー」の4つに分類されます。
まず「営業キャッシュフロー」とは最終利益に減価償却費を加え、運転資本を増減して算出する、いわゆる事業上で生まれるキャッシュとなります。次に「投資キャッシュフロー」とは、設備や固定資産、投資有価証券の購入(売却)によるキャッシュの増減をいいます。この「営業キャッシュフロー」から「投資キャッシュフロー」を差し引くことで、手元に残るキャッシュとして「フリーキャッシュフロー」が算定されます。最後に、外部からの資金の調達(借入・増資)や返済などによるキャッシュの変動を「財務キャッシュフロー」と言います。「フリーキャッシュフロー」に対して、資金が足りない(余る)から外部から借入を行う(返済する)など「財務キャッシュフロー」によるキャッシュの増減を経て、当該決算期における手元現預金の増減が確定いたします。以上がキャッシュフローの大まかな流れとなります。
キャッシュフロー改善のポイント
上記よりキャッシュフロー改善の1丁目1番地は「営業キャッシュフロー」の改善から始まります。改善に向けては➀最終利益の計上➁減価償却額の把握③運転資金の増減となり、➀と➁のイメージは付きやすいと思いますが、特に業績悪化時における資金確保術の一手段として③の改善がキャッシュフロー改善のポイントとなります。
運転資金=売掛金+在庫-買掛金ですが、いわゆる運転資金額が大きければ大きいほど資金化されていない債権・在庫が大きい状態となります。取引額の増額か回転期間が伸長すると運転資金が大きくなりますので、経営改善時においては回転期間の短縮化がキャッシュフローの改善に直結いたします。
回転期間の短縮化に関しましては、売掛債権回転期間+在庫回転期間-買掛債務回転期間、いわゆるCCC(キャッシュコンバージョンサイクル)と呼ばれる指標の改善によりキャッシュを捻出いたします。売掛金の回収を早くする(場合によってはディスカウントして資金化を早くする。3か月入金を金利分入金額を減らし、2か月での入金交渉など)、製造から販売までの回転期間が早い物を中心に販売する(回転期間を重視したセールスミックス戦略の構築により、在庫として保有する機関を短くする。もしくは部品点数の少ない製品販売に重点化するなど)、もしくは金利を上乗せして支払いを遅らせる(買掛債務支払回転期間の伸長。信用力があれば支払手形により更なるサイトの伸長など)といった方法があります。
つまりは運転資金の期間を短くすることで、資金を捻出するということです。(売掛金が減少すれば資金回収が進む、在庫が減れば資金回収が進む、買掛金が増加すれば支払猶予により資金余裕ができるなど)あくまでもポイントは運転資金に関する「期間」の概念となります。
また、「投資キャッシュフロー」における段階では、不稼働資産の売却や、持ち合い株の売却などがあげられます。それでも資金的に足りない時には、「財務キャッシュフロー」での改善を図ります。金融機関との協調による計画的・戦略的な借入や、第3者割当による増資などとなります。
以上より、営業・投資・財務各フェーズにおけるキャッシュフロー改善が、全社的なキャッシュフローの改善に繋がります。
関連記事
-

組織活性化の手法や生産性を高める実践ステップ
- ホールディング経営
-

効果的なMBOスキームとは?EXIT戦略を成功に導く7つのステップ
- 資本政策・財務戦略
-

企業が行うIR活動の目的と効果を発揮する施策とは
- 企業価値向上
-

ROICを浸透させるためのポイントを探る
- 資本政策・財務戦略
-

PBR向上の意義とPERとの違いを解説
- 企業価値向上
-

ROE ~ 企業価値向上における枢軸
- 企業価値向上
-

-

組織再編の目的や手法、実施する際のポイント
- グループ経営
 コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト
コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト