
日本の製造業を概観すると、生産性が低い、つまり製品・サービスを提供するために人・お金・時間といったリソースを割く割には、それを提供することで得られる売上・収益が少ないということが言えます。日本の生産性は世界的に見ても低い水準であり、高齢化が進んでいることも考えれば、大変厳しい状況にあると考えられます。
こうした状況を打破するためにも、従来型の改善の取り組みの延長線ではなく、今までのやり方を大きく変える「破壊的イノベーション」が必要であり、それには最新の技術、特にデジタル技術を活用することが不可欠です。今の潮流を知り、その流れを静観せず、積極的に自社に取り込むことで、ピンチをチャンスに変えていきましょう。
1. ムーンショット型研究開発とは?
デジタル投資の特徴
我が国の政府主導で「ムーンショット型研究開発」というものが進められていることはご存じでしょうか。もともとこの言葉は、1960年代のアメリカにおける「アポロ計画」に由来しており、当時の大統領ジョン・F・ケネディが「月に人を送る」という大規模な目標を掲げたことから来ています。
では現代の日本における「月に人を送る」ほどの大規模・大胆な目標ですが、前述の状況を踏まえ、人々の幸福で豊かな暮らしの基盤となる3つの領域、つまり
① 社会:急進的イノベーションで少子高齢化時代を切り拓く。
② 環境:地球環境を回復させながら都市文明を発展させる。
③ 経済:サイエンスとテクノロジーでフロンティアを開拓する。
において、2024年7月現在では10個の目標を決定しています。
2. 製造業にどんな影響を与える?
10個の目標から、製造業に特に影響するものとして、以下の2つを考えています。
目標3「2050年までに、AIとロボットの共進化により、自ら学習・行動し人と共生するロボットを実現」
目標4「2050年までに、地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現」
これらが実現すると、あるいは実現に向けた取り組みが進んでいくと、日本の製造業はどのように進化していくかを考えてみましょう。
(1)技術開発における変革
たとえば新規事業を始めようとする場合、従来型のやり方においては、各種の調査や文献データなどを元にして、新規領域についてのリサーチを行い、その事業性・採算性などを判断するというのが一般的です。
これがAIやロボット技術が進展することにより、ビッグデータの中から過去の知見と知見を組み合わせて新たな仮説を生み出す、その仮説の検証をも自動で行うといったことも可能になるかもしれません。また人が行うのに比べて、こうした仮説設計から検証までのサイクル自体も速くなり、アイデアの数も増大することが考えられます。
(2)サプライチェーンにおける変革
技術革新により、従来の製造プロセスやサプライチェーンが見直される可能性があります。需要予測の精度が上がることで、人の勘と経験で差配していた「何をどこでいつ生産するか、いつ出荷するか」といったことも自動的にできるでしょう。
また3Dプリンターの技術がさらに発展・普及すれば、生産戦略(どこに工場・物流拠点を置くか)そのものも再構築され、それによってQCD(品質・コスト・納期)が劇的に改善し、他にはない価値提供が可能になると考えられます。
(3)環境技術における変革
モノを生み出す製造業において、エネルギー消費を減らし、環境負荷を低減することは、相反するようですが、ESG(環境・社会・ガバナンス)の取り組みが前提となっている今日においては避けては通れない問題です。
前述のように、技術開発やサプライチェーンにおける変革による環境負荷低減も考えられますし、「モノからコトへ」というように、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)の活用により、大量のエネルギーを消費せずとも新たな価値提供をすることも考えられます。
3. 2050年に向けて、私たちは何をするべきか?
2050年に向けて、産学連携での国家的な取り組みが進められているわけですが、では私たちは何をするべきなのでしょうか?デジタル技術が製造業に広く普及することを想定して、以下のようなことが必要と考えられます。
(1)デジタルスキルの習得
まずは、新しい技術やシステムを効果的に利用するためのスキルの習得です。リスキリングという言葉のとおり、今までに習得した知識だけを組み合わせるのではなく、AIの基本知識、プログラミングの知識、セキュリティの知識など、進化が著しい領域ですから、積極的に身につけることが必要です。
また学ぶことも膨大ですから、「広く薄く」つまり基本的なことは全社員に、「狭く深く」つまり専門的なことは特定の社員にと組み合わせ、学び方・学ばせ方について計画を立てて実践することも重要です。
(2)創造力の習得
ここが一番難しいかもしれません。筆者も過去には製造業に勤めていたのですが、工場で最も大事なことの一つに「決められた手順を守る」ことがあります。仕様書通りのものを正確に作ることが、品質の高さにもつながり、日本の製造業の強みでもあると言えます。
しかし、デジタル技術を活用し、新しい価値を生み出すためには「創造力」が必要と考えられます。今までになかったものを作り出すのですから、「わが社の今のリソースでできることは」という枠を超えて、データの活用による新しいビジネスモデルの創出など、創造的な思考が重要です。
(3)セキュリティの確保
デジタル技術でできることが増えている一方で、セキュリティを脅かすニュースも増えているのも事実です。その中にも内部・外部の2つがあり、内部においては重要な情報が漏えいすること、外部においては悪意を持ったものが侵入して重要な情報を盗み出すことがあります。
できることに目が行きがちですが、そのための安全確保との両輪でなければなりません。まず自社における弱点・リスクはどこにあるかという脆弱性を把握した上で、内部においてはマネジメントやセキュリティ教育を徹底すること、外部においては常に最新のセキュリティ対策を講じることが重要です。これらの取り組みに終わりはありません。
4. 破壊的イノベーションに向けて、一歩ずつ歩みを進めよう!
タナベコンサルティングのクライアントには、製造業も多くありますし、中堅・中小企業も多くあります。確かに「リソース(人・モノ・カネ)を割けない」「一品一様型の製造なので、なかなか機械化できない」といった声はよく聞かれます。
しかし日本は世界の中で後れを取っている面もあり、その劣勢を跳ね返そうと取り組みが進んでいることも事実です。
ですから、自社ならではの破壊的イノベーションに向けて、歩みを進めることが必要です。最後に、その歩みを進める上で筆者が重要と考えることを2点記載したいと思います。
(1)自社のコアコンピタンスを定義(再定義)し、磨き続ける
コアコンピタンスとは「他社にまねできない、企業の核となる能力」です。「不易と流行」の言葉通り、デジタル技術はものすごいスピードで進化していますが、その中において「不易」となる部分を定め、それを磨き続けることが、他社と同質化しないことにつながります。
(2)社内外のコミュニケーションを活性化し、協働・協創する
今までは「秘密主義」で、過去からの知見を社内外に見せないということが多かったですが、これだけのスピードで進化する中においては、いかに社内外のパートナーとのコミュニケーションを活性化するかが重要です。つまり、情報を取り入れ、変化を柔軟に受け入れ、お互い対等な立場で協働・協創することが求められています。
日本の製造業には本来世界をリードする技術力があります。データ活用のためのセキュリティや教育といった「守り」を万全にした上で、自社のコアコンピタンスを磨きながら、社内外と連携して協働する「攻め」を行う、これこそが自社ならではのFactoryDXに向けた指針となり、自社にしかできない価値提供ができるのです。
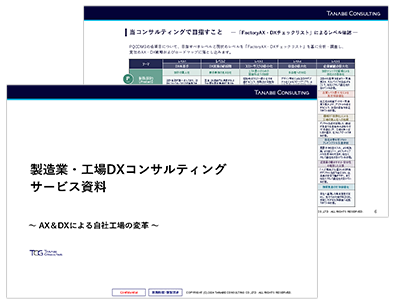

 デジタル・DXの戦略・実装情報サイト
デジタル・DXの戦略・実装情報サイト











