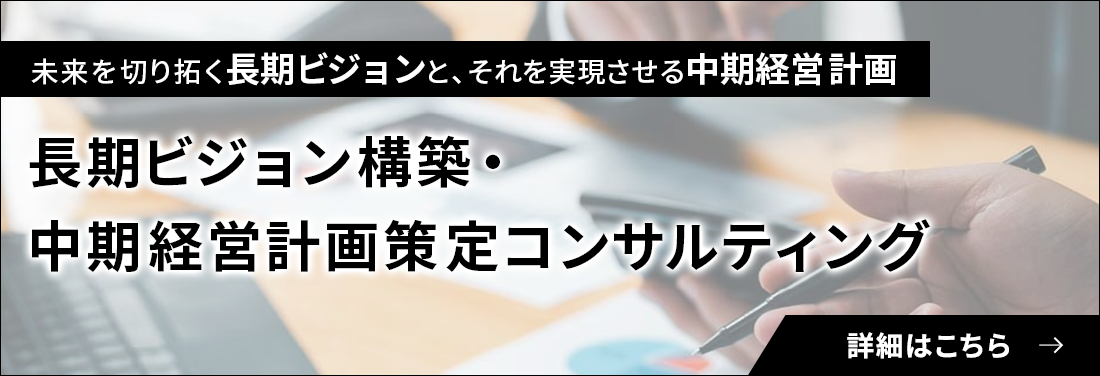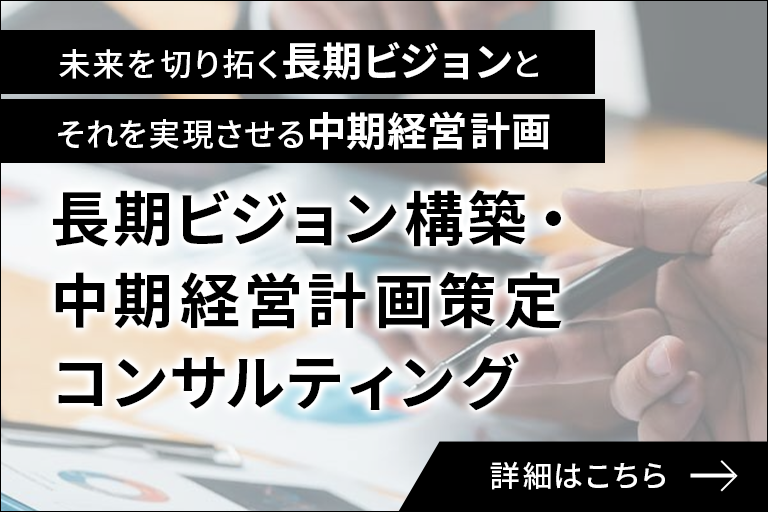COLUMN
コラム
閉じる

A社は、地方都市の地場エリアを主戦場とする生鮮食料品を主力とした地場のスーパーマーケットです。生鮮ディスカウンターという業態を早くから展開し、生鮮三品+惣菜の四品は新鮮で安いという地域・顧客・従業員からの信頼を得ています。上記に伴い、食品スーパーとしては県下第3位の地位を確立され、県下35店のドミナント展開を行っています。これまで創業者である社長の卓越したリーダーシップに基づく、スピード経営(過去に2度の業態転換を果たし、時代環境に合わせた成長)がなされているが、次世代への承継のタイミングで、中期経営計画づくりに着手されました。
市場の環境変化をチャンスにした成長戦略の考え方
■自社を取り巻く市場環境を読み解く
中期経営計画を策定する上で市場環境は以下のポイントで確認します。
1.市場規模とそのトレンドを知る
2.人口や生活に密着した商品・サービスの変化を価格、品ぞろえ、品質の視点からエリアごとに捉える
3.その業界企業における重点テーマを抑える
■社会構造変化の岐路にある食品スーパー
2022年スーパーマーケット年次統計調査によると、食品スーパーの国内市場規模はおよそ25兆円で横ばい。1都道府県のみでスーパーマーケットを展開している企業が70%を超え、また小規模店(売場面積が250~400坪タイプ)で展開している企業が41.3%というデータから見て分かるとおり、社会生活に密着した業界であります。2019年以降のコロナ禍において、国内スーパーの既存店売上高は、内食需要で大きく増加し、2021年以降も2019年比では概ねプラスを維持しています。(全国スーパーマーケット協会「スーパーマーケット販売統計調査」)。ただし一方で、商業動態統計の業種別販売額で見てみると食品スーパーに対しドラッグストアやCVSの方が高い増加率を示しています。特にドラッグストアは店舗数の増加により顕著な増加率となっています。少子高齢化による生産人口の減少は、人間の胃袋に入る量と移動による機動性に影響していくという意味で差別化要因に大きな影響を及ぼしています。
■外部環境から見たピンチ
・(市場規模/構造)CVSやドラッグストアが拡大で、小商圏エリアにおいてシェアの奪い合い
・(商品変化)少量目1次加工ニーズに対応したオンリーワン商品づくりが差別化のポイント
・(価格)商品値上げ傾向で大手はPB商品強化。ドラッグは食品の低価格化で競争激化
■ライバルと比較した自社の強み/弱み
・(強み)地域密着による店舗展開で業容拡大した歴史から鮮魚と精肉部門の支持率は高い
・(弱み)固定客のシェアは高いが、生鮮の鮮度アピール力が弱いため、若い新規顧客の獲得は弱い
・(弱み)管理が弱く品揃えやロスに対する意識が薄いため、チャンスロスや値下げロスが過大となり減収が続いている
■A社の将来に向けての最大テーマは「収益性の向上」
トップと後継者と共に外部と内部環境を共有する中で、明確にしたのは何を中期経営計画の重点ポイントにするのかであった。確かにこれまで大手チェーンをお手本にしてきた事で、全部を徹底できずに消化不良になっていた取り組みを止め、自社の優位性を明確化するものは何かを明確にしました。トレンドから、グロサリーなどの加工食品は、NBの仕入れやPB開発にはイオンなど大手チェーンに優位性有利になる。一方で生鮮食品は卸売市場経由の商品では鮮度重視であり規模の経済は生じにくい事から、よりくらしに密着した生鮮食品を強化する事を大きな方向性とすることにしました。
■市場環境から見たクロスSWOT
「生鮮強化で付加価値ある商品を提供しつづけ収益性を高める」事を方向性として進めましたが、ここまではどこの会社にもあるありきたりな発想です。自社の戦略に乗せるためには自社の強み弱みへと踏み込んでいく事が必要です。
・(強み強化)
①高齢者や新規客に提供する自社の勝てるカテゴリーを地域での圧倒的な差別化の一つとする
・(差別化)
①自社の勝てるカテゴリーをどう落とし込み、店舗のゾーニングに合わせるか考える
②イベント的な鮮度のアピールやSNSを活用維持した集客対策の実施
・(弱点克服)
①鮮度重視を軸とした店舗の管理力の強化
②店長や№2社員の管理技術の強化、動画による人材育成システムの強化
③計画的なMD力強化と仕入れルートの確保

コモディティ化を脱する自社の強みを活かした戦略の構築
中期経営計画の構築は、企業が中期(3〜5年後)の企業のあるべき姿を明確にし、計画実現に向けて数値目標を設定し具体的な施策を決めていきました。特に企業のあるべき姿を共有する場面においては、創業以来の経営理念の考え方を、昨今の経営環境において叫ばれてパーパスの考え方で振り返り、あらためて自社のミッション(指名)-ビジョン(目指す姿)-バリュー(提供価値)とは何かを検討しました。会社の歴史を知り、今の時流において再度翻訳してみる事で、自社の原点と未来に向けてその価値をアップデートしていくという意味では後継者にとっては有意義な場となりました。
■パーパス(企業の存在意義):「地域に溢れる高いレベルの商品でワクワクを伝え続ける」
■中期の戦略コンセプト
「お客様がワクワクする"超新鮮"な商品をニーズの対応でいち早く提供し地域№1を目指す」
一番重視する戦略のポイントは、品質=鮮度である。
■事業戦略
(1)超新鮮な食材を高回転で販売し、鮮度を強烈な打ち出しで提案する
(2)少人数・小口・高付加価値商品に特化し、限定ターゲットに対して狙いを集中させる
(3)低価格商品には管理体制強化で、価格で勝ち残る商品を顧客に提供する
■戦略コンセプト
(1)「アクティベート・フレッシュ・マーケット」(活動的にする)(超新鮮)
(2)ターゲット:高齢者・30歳~50歳の生産年齢世代
(3)モデル店舗フォーマット:店舗売場面積250~300坪の中型店舗
■財務戦略
(1)売上高210億円、経常利益率2.5%

経常利益率3%を目指すためのアクションプランづくり
■自社の強みを発揮できる店舗フォーマット(モデル損益)を設計する
~New300坪SMのモデルを目指す~
・生鮮売場の完全売り切り型対面販売(高齢化対応とスピード売り切りの実現)
・生鮮食材の加工ニーズへの完全対応(総菜版キットの販売で消費者の台所調理代行への挑戦等)
・地場産こだわり食材・メーカーによるコーナー化
アクションプランの中では、ターゲットのくらしや自社の提供する価値をより明確化していき、何を差別化していくのか、具体的にどのようにするのかを業界のこれまでの通例も一度ゼロリセットにして店舗モデルに落とし込みました。
■増やす商品サービス、減らす(無くす)商品サービスの明確化
~増やす~
・「超鮮度」売場の拡大(惣菜、加工需要など)+全国の青果物
・送迎(タクシー会社とのタイアップ)、移動式販売(水、米、焼酎、クリーニング持ち届け)
・参加型・体験型販促(朝採り農業体験等)
~減らす~
・競合店とのダブり商材
■実現に向けてのドミナント型のサービス体制(高齢者の足をカバーするサービス)
・母店を基幹店舗とし、周辺の小店舗をサテライト店舗としエリア内での高いサービスを実現する

中期経営計画の策定による、A社の未来地図を後継者と意思統一をする
■トップと後継者との意思統一とやるべきことの明確化
中期経営計画を策定されていない企業では、3~5年先の分からない未来を策定することの意味合いについて疑問符を持たれる事があります。ここで最もよくない事は、構想はあるがトップ以外は誰にも周知されていない状態です。経営理念や中期ビジョンで将来あるべき姿を明確にし、社員一人一人に会社の目指すべき姿を共有し、全社一丸となって同じ方角へ向かうための青写真となるものが中期経営計画です。
■策定する事の理解とやらされ感をなくす
また、後継者においてもトップ共に将来を戦略から社員のやるべき事まで具体化することで、次の中計策定の検証が可能になり、この繰り返しがより完成度を高めていく事につながります。後継者がより「やらされ感」をなく自発的に取り組むきっかけにつながります。
著者
最新コラム

- 海外進出を成功させるためのパートナーの選び方

- 海外進出に成功した企業事例と成功要因の解説

- 海外市場調査のアンケート調査・インタビュー調査の具体的な方法

- 事業ポートフォリオ再編のプロセスとリスク対策
ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと
進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド
~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド
~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド
~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~
資料ダウンロード

- 長期ビジョン・中期経営計画に関する企業アンケート調査レポート2025年

- ストラテジー&ドメインコンサルティングメニュー紹介資料

- 統合報告書 ストーリー設計のコツ~企業価値は「説明」では動かない。「物語」が動かす。~

- 設備工事業界の未来を切り拓く:課題解決と成長戦略の最前線~人手不足からデジタル化まで、業界の変革を支える実践的アプローチ~

- TCG REVIEW 顧客創造モデル

- 収益構造を変える!ビジネスモデル・イノベーション~高収益を実現する事業ポートフォリオとPLのデザインはできていますか?~

- 食品業界の企業が中期経営計画策定で押さえるべきポイント~重要になるテーマと事例5選をご紹介~

- 経営者の成長投資アンケート調査レポート 2025年
 長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト
長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト