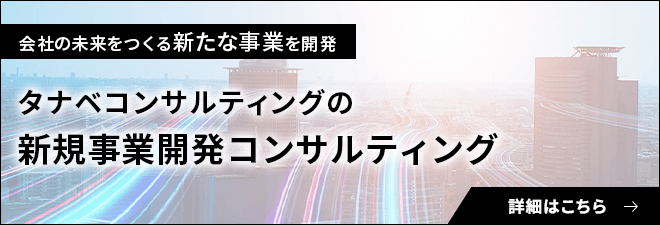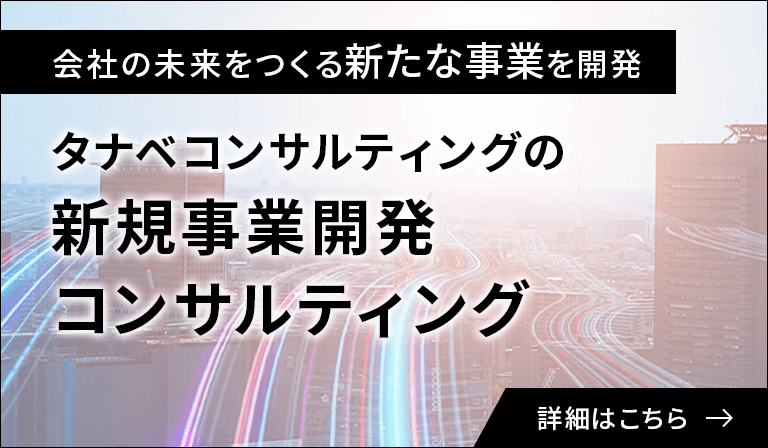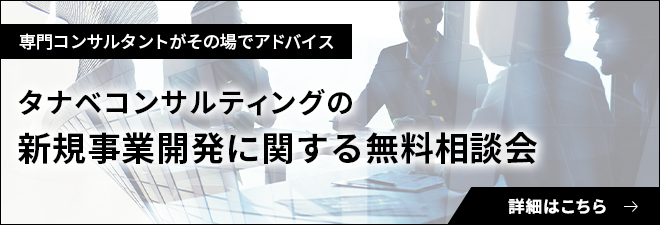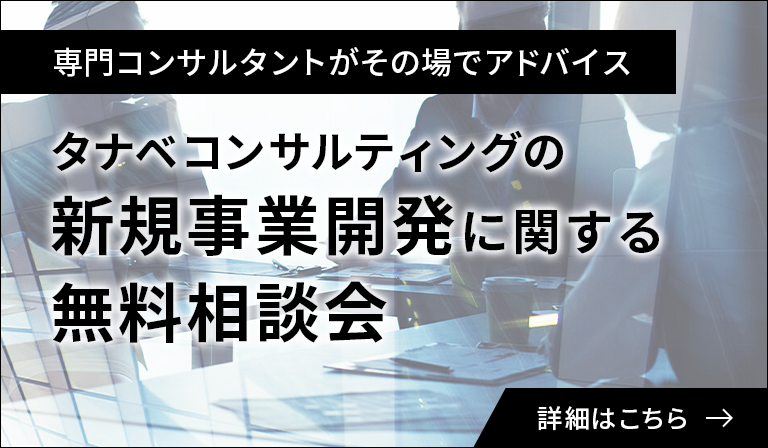COLUMN
コラム
閉じる
フォーマットを活用した戦略策定の全体像とメリット
企業の成長戦略について社内で検討しようとする際、「現場を離れて新たな視点で」と意気込んで議論を始めるも、「終わってみると真新しい意見が出ず例年と同じような戦略に落ち着く...」といった経験をされたことがある方も多いのではないでしょうか?
その際の要因として、「各人が日頃感じていることを結論ありきで論じてしまい、本来目を向けるべき社会ニーズや自社の本質的な強み・弱みについて十分に検討されていない」点が挙げられます。
本コラムでは、既存の思考・視点から脱却しイノベーションを創出する戦略的なフォーマット活用方法を紹介します。
戦略策定のステップは大きく「分析」「戦略骨子策定」「具体的戦略(戦術)策定」の3ステップに分けて行います。
各ステップにおいて、漏れなく・ダブりなく重要なポイントを押さえるうえで、戦略フォーマットが大きな役割を果たします。
また、フォーマットを活用することで、戦略策定に参画するメンバー間で各人が異なるテーマ、(一部)重複するテーマ、戦略・戦術などのレイヤーが異なるテーマを順不同に発言し議論の収拾がつかなくなるといった事態を避け、メンバー間で目線を揃えつつ議論を進めることができます。
次章からは、「分析」「戦略骨子策定」「具体的戦略(戦術)策定」の各ステップで活用すべき戦略フォーマットの具体例を紹介していきます。
戦略策定のスコープを定める第一ボタンとしての「現状分析」
現状分析は「既に知っていること」として流されてしまいがちですが、分析こそ戦略策定の第一ボタンであり、分析に誤りがあれば大きく的を外した戦略となってしまいます。
また、当然ながらこの段階でスコープから外れた項目はその後の戦略策定段階でも登場しません。
戦略策定段階で真新しい意見やアイディアが出ず悩む企業は、まず分析のスコープを広げてみると良いかもしれません。
現状認識の具体的な分析項目と活用フォーマットは以下の通りです。
各分析手法については、書籍やインターネット等で検索可能なため割愛し、ここでは各分析を行う際の視点について紹介します。
1.外部環境分析
(1)マクロ環境分析=PEST分析
(2)セミマクロ環境分析
①商流分析
②市場規模(推移)分析
(3)ミクロ環境分析=ファイブフォース分析
(4)ベンチマーク分析
PEST分析で政府方針や経済情勢、社会情勢、技術動向などの大きな業界潮流を押さえたうえで、現状の商流や市場構造、カテゴリー別の市場規模が今後どのように推移していくのかを5年~10年といった長期的な目線で予測します。
また、ファイブフォース分析を通じて足元の短期的な事業環境を分析します。
現在の業界環境と中長期の業界動向を抜け漏れダブりなく押さえることで、自社の現在のポジションと今後注力すべき事業ドメインを考えるうえでの参考とします。
またベンチマーク分析においては、同業他社の売上・粗利率・営業利益率などの主要財務指標や戦略方向を押さえ自社のポジションを把握することに加え、自社の戦略を描くうえで参考とすべき事例については同業種・異業種問わず収集することで視野拡大に繋がります。
外部環境分析から得られる結論の一例として、ガスエネルギー業界においては、自由化に伴う競争激化によって主要各社は軒並みシェアや利率を落としている中、政府が掲げる地域包括ケアや長期優良住宅の方針に則りガス以外の介護やリフォーム事業に参入する企業が多く、これらの取り組みに先行着手し成功している企業は利率が高い。といったことが挙げられます。
上記はあくまで一例ですが、重要なのは
・目的とストーリーを持って分析すること
・フォーマットを用いることで分析の視野を拡げること
となります。
2.内部環境分析
(1)財務分析(安定性・収益性・成長性・生産性の推移、他社比較)
(2)ABC分析(商品別・チャネル別・顧客別・エリア別などなるべく細かな単位での売上・粗利寄与度を分析)
(3)バリューチェーン分析(他社比較)
(4)組織・人員分析(年齢・性別・役職・等級別構成比や評価・賃金・教育制度の是非など)
(5)マネジメント分析(予算達成度や業績管理体制、会議体が最適か否かなど)
内部環境分析はビジネスモデル・組織構造・収益構造の視点で自社の伸ばすべき強み、解消すべき弱みを整理する。
自社について分析するため結論ありきにならないよう、可能な限り数値を用いて定量的・客観的に分析することが肝要となる。
また社内で分析する場合、分析から得られた結果が強みであるか弱みであるかの判断が難しいため、可能であればベンチマークとなる同業者と比較分析することが望ましい。
3.現状認識のまとめ
外部環境・内部環境を網羅的に整理するうえでは、SWOT分析を用いることが望ましい。
外部環境分析から得られる機会と脅威、内部環境分析から得られる強みと弱みの視点で整理することで、それぞれの分析結果を抜け漏れダブりなく整理することが出きる。
また可能であればSWOT分析の結果を一言(真因+状態)で要約することが望ましい。
これにより、現状の課題を全員が共通認識することができ、戦略策定段階での議論の齟齬を減らすことが出きる。
戦略を着実な実行推進、成功へと導く「具体的戦略(戦術)」策定
戦略骨子が定まったら、各戦略項目をどのように推進していくか?の具体的検討に移ります。
その際には、各戦略項目を達成するために必要な要素をロジックツリーを用いて整理し、その中の主要項目をマイルストーン、またはKPIとして設定します。
設定した各項目は具体的行動レベルまで分解して落とし込み、主担当と大まかな実施時期を定めて、アクションプランとしてまとめます。
これにより、現状認識→戦略骨子→具体的戦略→行動計画までを一連の流れとして整理することが可能になります。
また新規事業においては、具体的戦略検討段階の第一ステップとして、4P・4CやQCDSなどの観点で商品・サービスの提供方法(その中のどこに強みを置くか)を整理する手法も有効です。
著者
最新コラム

- 物流事業者が2030年に向けて打つべき手

- ビジネスモデルを構成する収益モデルとバリューチェーン

- バリューチェーンとサプライチェーンの違いとは?それぞれの役割と事業戦略の進め方

- パーパスと経営理念の違いとは?パーパス戦略の基本とその重要性を徹底解説
ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと
進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド
~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド
~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド
~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~
資料ダウンロード

- 製造業企業事例集_vol1

- 長期ビジョン・中期経営計画に関する企業アンケート調査レポート2025年

- ストラテジー&ドメインコンサルティングメニュー紹介資料

- 統合報告書 ストーリー設計のコツ~企業価値は「説明」では動かない。「物語」が動かす。~

- 設備工事業界の未来を切り拓く:課題解決と成長戦略の最前線~人手不足からデジタル化まで、業界の変革を支える実践的アプローチ~

- TCG REVIEW 顧客創造モデル

- 収益構造を変える!ビジネスモデル・イノベーション~高収益を実現する事業ポートフォリオとPLのデザインはできていますか?~

- 食品業界の企業が中期経営計画策定で押さえるべきポイント~重要になるテーマと事例5選をご紹介~
 長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト
長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト