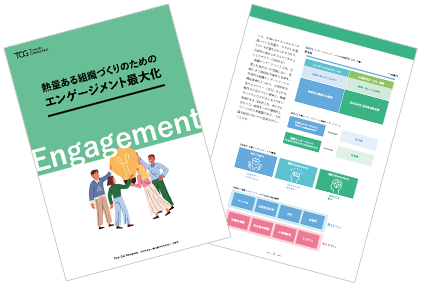人事コラム
エンゲージメントサーベイ活用のポイントと改善ステップ
エンゲージメント向上に向けて、各社が取り組むべきこととは
エンゲージメントサーベイを最大限活用し、
自社のエンゲージメント向上に繋げる

エンゲージメントサーベイとは
企業の成長と持続可能な発展には、エンゲージメントが不可欠である。エンゲージメントとは、社員が自らの仕事に対して持つ情熱やコミットメントを指し、企業の業績や文化に大きな影響を与える。エンゲージメントサーベイは、社員の仕事に対する満足度や意欲、企業文化への適応度などを測定するための調査のことを指す。このサーベイを通じて、企業は社員の声を直接聞くことができ、組織の強みや改善点を明らかにすることが可能となる。エンゲージメントサーベイは、社員の意見や感情を把握するための有効な手段であり、企業がエンゲージメントを向上させるための第一歩となることが多い。本コラムでは、エンゲージメントサーベイの活用方法と改善策の検討方法について詳しく解説する。

エンゲージメントサーベイ実施において求められること
エンゲージメントサーベイを実施する企業は増えている一方で、実施することに終始してしまう企業も増えている。社内への発信・開示が不足している状態である。その場合、社員からすると、せっかくサーベイに回答したにもかかわらず、会社は何も変わらないと判断し、よりエンゲージメントを下げることに繋がりかねない。そのため、エンゲージメントサーベイを実施するに当たり、まずは定期的な実施と結果の開示を行う必要がある。
1. 定期的な実施
前提として、エンゲージメントサーベイは一度きりの調査ではなく、定期的に実施することが重要である。パルスサーベイと言われる毎月など頻繁に実施する調査や、センサスサーベイと言われる1年や半年に1回など定期的に実施する調査があり、それを組み合わせる企業も存在する。実施目的に応じたサーベイを活用し、社員の意見の変化をリアルタイムに把握することで、迅速な対応が可能となる。各年の方針や取り組み事項に対する社員のエンゲージメント状態を把握することが重要である。
2. 結果の開示
定期的に実施するサーベイの結果をもとに、社員に対してフィードバックを行うことも求められる。まずはしっかりと結果を共有し、どこが自社の強みで、どこに課題感があるのかを明示する。サーベイ結果には定量的な数値で示されることが多いため、過去からの変化や、他社との比較などから見た自社の現状を社員に開示することが必要である。社員への開示範囲は階層や部署によって制限を行う場合が多い。少なくとも、会社視点で改善を行う必要がある経営幹部層にはすべてを開示することが求められる。
また、開示と共に求められるのは、改善策の検討・明示である。改善策を講じることで課題の改善が進むとともに、社員は自身の意見が尊重されていると感じ、更なるエンゲージメント向上に繋がる。
検討方法について、下記にて記載する。

全社レベルと部門レベルでの改善策検討
エンゲージメントサーベイの結果をもとに改善策を検討する際には、全社レベルで取り組むべき課題と、部門レベルで取り組むべき課題を明確に分けることが重要である。それぞれのレベルでの検討ポイントを整理し、適切なアプローチを取ることで、効果的かつ効率的な改善が可能になる。
・全社レベル:経営層や人事部が主体で取り組み、企業全体に共通する課題や、組織文化、経営方針に関わる広範なテーマに焦点を当てる
・部門レべル:部門長や管理職が主体で取り組み、各部門特有の課題や、部門内の業務プロセス、チームダイナミクスに焦点を当てる
※課題と改善策例は図表①の通り
【図表①】課題と改善策例
| 課題 | 具体策 | |
|---|---|---|
| 全社レベル | カルチャーの醸成不足 | ・企業の価値観や行動指針の再定義 ・社員に浸透させるための研修やワークショップの実施 |
| 全社コミュニケーションの 改善 |
・経営層が定期的に全社向けの発信の場をつくり、ビジョンや全社方針を共有 ・社内ポータルやニュースレターを活用して、全従業員に重要な情報をタイムリーに提供 |
|
| 人材育成の不足 | ・人材育成体系の構築 ・階層別研修・テーマ別研修の実施 ・全社統一でのOJTマニュアル作成 |
|
| 人事評価の納得性不足 | ・評価制度の見直し ・考課者研修・被考課者研修の実施 |
|
| 報酬・福利厚生の見直し | ・賃金制度やインセンティブ制度の見直し ・福利厚生の充実 (例:リモートワーク手当、健康支援プログラムの導入) |
|
| 多様性の推進不足 | ・リモートワークやハイブリッドワークの導入検討 ・新たな働き方の検討 |
|
| 部門レベル | 部門内コミュニケーション 改善 |
・部門内ミーティングの見直し (一方的な発信のみでなく、進捗状況や課題をメンバーから共有できる場へ) ・気軽に相談できるミーティングやポータルの設定 |
| 業務負荷の調整 | ・業務プロセスの見直し ・人員増加・外部リソース活用の検討 |
|
| キャリア開発の支援 | ・部門内スキルアップ研修や資格取得支援勉強会の導入 ・定期的にキャリア面談を行い、目標設定をサポート |
|
| 部門特有の課題への対応 | ・営業部門:目標管理プロセスを見直し、KPIを明確化 ・開発部門:アイデア共有の場の設定 |
|
| 部門内のリーダーシップ改善 | ・中堅リーダー層に対するリーダーシップ研修の実施 ・1on1ミーティングの実施 |
特に、部門レベルでの検討事項においては、各社工夫しながら取り組んでいる。全社では補いきれない部門特性に応じた課題に対しては、各部門で改善を図る必要がある。部門レベルでの検討においては、部門長だけで検討する場合と、リーダー層や一般社員などの層を巻き込んで検討する場合がある。
エンゲージメントサーベイからの改善策を検討する際、初めは部門長だけでの検討で十分であると考える。部門長が自部門における改善策を検討して、主導となって推進していく。しかし、その場合実態を踏まえられていない改善策になり、一般社員からの理解・納得が得られない場面が発生しうる。そこで、次の段階として、リーダー層や一般社員も巻き込んで、より実態に即した検討を行う会社が増えてきた。そうすることで、部門内のメンバー全員で検討した、という納得感が生まれ、よりエンゲージメントの向上に向けた施策の推進が図れるようになる。この際、一人ひとりが他人事ではなく自分事で考え、"自分たちに何ができるか"という視点で検討いただくように、部門長や外部人材がファシリテーションを行うことが求められる。
リーダー層や一般社員を含む検討においては、"社員の巻き込み方"が重要となる。課題に対していきなり対策を検討するとなっても、意見が出なかったり、方向性がバラバラになり結論がまとまらなかったりする。そこで、ステップを設けて社員を巻き込みながら実施することを推奨する。
第1ステップ:単一テーマを絞り、それに対して検討
第2ステップ:複数テーマ(3つ程度)に対して検討
第3ステップ:フリーテーマで検討
エンゲージメントサーベイから明確になった課題に対して、実態を分析し、それに対して部門内でできる改善策を検討する。ワークショップ形式で自由に意見を言えるようにしたり、部門内で複数チームに分かれて研修形式でしたり、実施方法は様々である。ワークショップ形式で実施し、経営層が混ざり、実態を把握する・全社の改善につなげる、ということを実践している企業も存在する。検討する階層や、実施方法など、自社に合った検討の進め方が求められる。

部門レベルでの検討を全社レベルへ
全社レベルと部門レベルでの改善策は、相互に補完し合う関係にある。全社レベルの取り組みが部門レベルでの課題解決を支援し、部門レベルでの改善が全社的なエンゲージメント向上に寄与するという循環を作ることが重要である。
全社的な方針の共有と部門ごとの進捗報告を通じて、より経営層と部門長層が相互にやり取りを行うことが求められる。具体的な連携方法としては、双方向に下記が考えられる。
①全社→部門:全社レベルでの改善方針を部門長に共有し、全社として取り組んでいくことを理解してもらい、自部門にもしっかりと発信できるようにする
②部門→全社:部門ごとの改善策の進捗状況を経営層や人事部に報告し、成功事例を共有する。また、部門内検討で出た意見のうち、全社にて改善すべき内容を意見具申する
改めて、エンゲージメントサーベイの結果を活用する際には、全社レベルと部門レベルでの課題を明確に分け、それぞれに適した改善策を講じることが重要である。全社レベルでは組織全体に影響を与える広範な課題に取り組み、部門レベルでは現場に即した具体的な課題解決を目指す。この両者を連携させることで、総合的に社員のエンゲージメントを効果的に向上させることが可能となる。
さいごに
エンゲージメントサーベイは、企業が社員の意見を把握し、エンゲージメントを向上させるための有効的なツールである。定期的な実施や結果の開示、自社に合った課題解決策の検討と推進を通じて、企業はエンゲージメントを高め、業績向上や離職率の低下、イノベーションの促進、組織文化の向上等に繋げることが可能となる。経営者や人事部長は、エンゲージメントサーベイを積極的に活用し、社員の声を大切にすることで、持続可能な成長を目指すことを推奨する。
本事例に関連するサービス

Engagement KARTE
(エンゲージメントカルテ・エンゲージメントサーベイ)
人的資本投資において重要となる指標を明確化し、人的資本経営の推進と企業価値の向上をサポートします。
Engagement KARTE(エンゲージメントカルテ・エンゲージメントサーベイ)の詳細はこちら
関連動画
関連情報