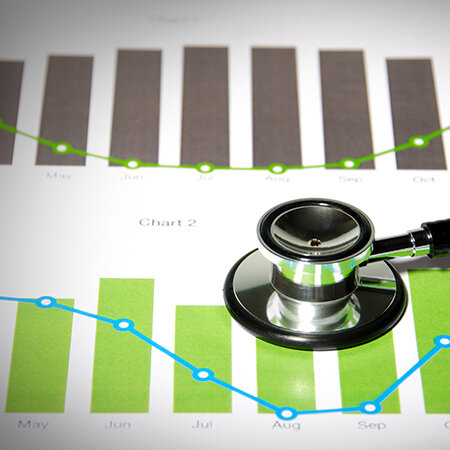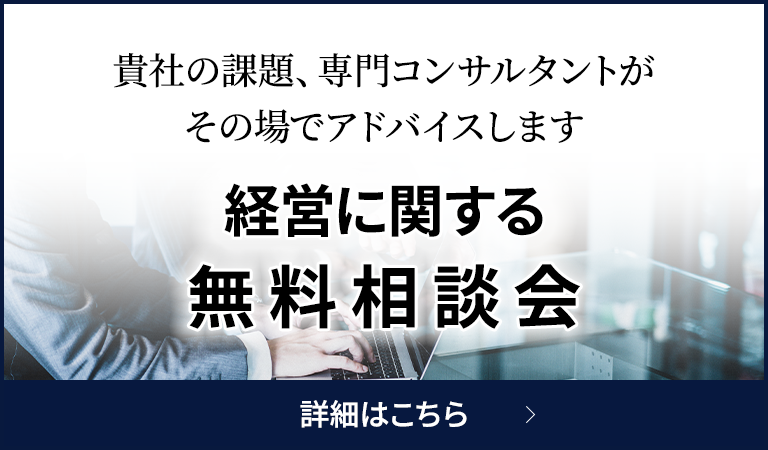企業経営における
ガバナンス・マネジメントの違いとは
- 企業価値向上

閉じる
昨今企業における不祥事は後を絶ちません。小林製薬の紅麹関連製品による健康被害や三菱UFJ銀行の個人情報の不正利用等、どの問題も社会に与えるインパクトは大きく、企業の信用度を失墜させる程であります。では、なぜこのような事象が起き続けるのでしょうか。
それは統治・統制する機能が十分に運用されていない事や、組織全体でのマネジメントが的確になされていない事であるケースが多いです。企業は成長すればするほど、業績規模・組織規模が拡大するため、成長レベルに則したガバナンス・マネジメント体制を強化していく必要があります。本コラムでは、企業活動におけるガバナンス・マネジメントの在り方や違いを中心にお伝えしたいと思います。
1.ガバナンス機能とは
ガバナンスとは統治・統制を指しています。ガバナンスが効いている企業は社内の風通しが良く、不祥事が発生もしくは発生する前段階で自浄作用が働きやすくなります。一方、ガバナンスが効いていない企業は、隠ぺい体質となりやすく、不祥事が起きやすい体質となります。
国内企業の組織体制の大半は、ヒエラルキー組織です。経営層の上位レイヤーから担当者レベルの下位レイヤーまでが各階層別で分かれ、ピラミッド型に展開される組織体制のことですが、上層部の意思決定から、下層部による実行までに時間がかかるため、意思決定スピードが遅くなりがちであったり、部門別やチーム別でのセクショナリズムが生まれやすく、組織の力が発揮されにくいというデメリットがあります。無論、明確な役割分担と意思決定構造が整備されているため、権限と責任が明確になりやすいというメリットがありますが、それが、かえって風通しの悪さに繋がる可能性が高くなるのです。
従って、ガバナンス体制を構築し、企業の成長を支えるためには下記のような仕組みを整えることを推奨します。
⑴社内規程の整備と浸透
情報漏洩や個人情報等の不正利用等の企業不祥事は、社内において適切に社内規程を整備する事で、一定程度防ぐことが可能となる。また、策定した規程が社内に浸透・理解されていない場合、策定されていない事と同義になります。
よって、社内へ周知する研修を定期的に実施する事が必須となります。その際には禁止事例や他社事例を基にした事例研究を従業員に展開するとより理解度が高まるので、実施すると良いでしょう。
⑵内部通報制度の導入
社内で組織内の不正行為に関する通報や相談を受け付けて、不正の調査や是正をする制度のことを指します。一定条件を超える企業は内部通報制度の導入が義務付けられており、既に導入している企業も多いかと思います。先述の通り、企業規模が大きくなると、現場で起きている不正が、経営陣が気づけないという事が少なくありません。という事は、不正が常態化し問題が大きくなることで収拾がつかなくなってしまっては、遅いという事です。
内部通報制度を導入する事で、社内で不正を発見した従業員から早期の情報提供を得やすくなり、不正について発見と是正がしやすくなります。
しかし、注意点として、内部通報をした従業員が不利益を被ることがないようにする事です。
⑶監査体制の確立
社内における規程・ルールの運用状況や適切な監督がなされているかを監査にて定期的にモニタリングする事です。
人間だれしも、楽をしたり、面倒なことから目を背ける生き物です。一事が万事このような惰性で不祥事が起きてしまっては元も子も無いので、監査体制を整える事で、的確にルールが運用されるようにしてください。
2.組織におけるマネジメント
組織におけるマネジメントには、経営資源である「ヒト・モノ・カネ」を差配する事をよく指します。しかし、企業統治を行う上ではリスクマネジメントという考え方が一番大事となります。本コラムにおけるマネジメントの定義はリスクマネジメントであるという前提で話を進めていきます。
リスクマネジメントには大きく、⑴信用・市場リスク ⑵ハザードリスク ⑶オペレーションリスクの3つがあります。
⑴信用・市場リスク
・取引先の倒産、調達先・提携先の変化、含み損の発生、債権回収遅延
・競合の戦略変更、新規参入、顧客ニーズ変化、顧客層の変化
・金融市場(為替・金利・株式・債権)の変動リスク
⑵ハザードリスク
・地震・噴火・洪水・台風・風水害、落雷、停電等の自然災害
・特許権・商標権・著作権・知的財産権の被侵害等の制度リスク
⑶オペレーションリスク
・ネットワーク断絶、盗難、システムへの攻撃、不正アクセス等の情報セキュリティリスク
・マスコミ報道、ネットでの誹謗等のレピュテーション(評判)リスク
・法令違反行為、道徳・倫理逸脱行為、権限逸脱行為、社員不祥事等の人的要因リスク
・契約書不備、知的財産権の侵害、インサイダー取引等のコンプライアンスリスク
このように企業を取り巻くリスクは様々あり、いつどこで何が起きるかわからない現代の中では、様々なリスクに対して想定されうる限りリスクヘッジできる体制を整備しておく必要があります。
例えば、信用・市場リスクに対応するためには、市場分析を常に行う事で、市場・顧客のニーズを適時的確に把握するマーケティング・ブランディング機能を持つことや、金融市場リスクに対しては為替予約やデリバティブを活用した上昇リスクに備える等であります。
また、日本国内では大規模災害に対するリスクヘッジは必須要件となります。BCP対策を実現する計画策定はまさしく進めるべきであり、災害発生時の対応マニュアルの策定や定期的な訓練の実施がそれにあたります。オペレーションリスクの最たるものは労務・コンプライアンスであり、昨今の働き方改革で従業員の働き方に対する取組や制度がない企業は魅力度が下がり、結果的に従業員の定着率低下や離職率が上がることに繋がります。ハラスメントや労災に対する対応を1つ間違えると、損害賠償請求を被ったり、企業のブランド低下に大きくインパクトを与えますので、このような事が起こらないように仕組みと体制を整える事を推奨します。
3.最後に
企業におけるガバナンス・マネジメントについてお伝えをしましたが、ガバナンスとは企業価値を毀損する事態が起こらないように統治・統制する機能のことであり、マネジメントとは企業を取り巻く様々なリスクに対して、管理又はヘッジするための仕組みのことを指します。企業の持続的成長を実現するためには、あらゆるリスクを想定した体制を構築していくべきであり、本コラムにおいてその気付きを得ていただければ幸いでございます。
関連記事
-

物流業におけるROIC改善事例を解説!企業価値を高める方法とは?
- 資本政策・財務戦略
-

資本政策 事例|押さえるべき3つのポイントを事例を基に解説!
- 資本政策・財務戦略
-

組織における意思決定の種類とは?トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!
- コーポレートガバナンス
-

製造業における収益改善の2つの視点と5つのステップを徹底解説!
- 資本政策・財務戦略
-

-

収益改善の成功事例 | 効果的なポイントについて徹底解説!
- 資本政策・財務戦略
-

-

中堅企業が実装すべき財務戦略~ホールディング経営におけるトップのリーダーシップ~
- ホールディング経営
 コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト
コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト