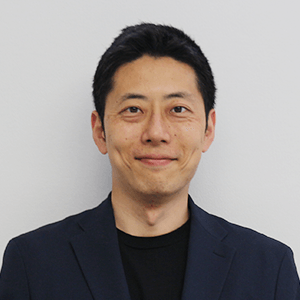事例から学ぶROIC経営の落とし穴とは?
- 企業価値向上

閉じる
ROIC(投下資本利益率)は、企業が投下した資本に対してどれだけの利益を生み出しているかを示す指標であり、資本効率を測る上で非常に有用です。近年、ROICを重視した経営が注目される理由は、資本効率を改善することで企業価値を向上させ、投資家からの評価を得られる点にあります。しかし、ROICを過度に重視するあまり、短期的な効率性に偏り、長期的な成長や競争力を損なうリスクも存在します。本コラムでは、具体的な事例をもとにROIC経営の落とし穴を掘り下げ、成功へと導くための視点や実践方法について考えていきます。ROICの本質を正しく理解し、持続可能な成長を実現するためのヒントをお届けします。
短期的な効率性の追求がもたらす経営の歪み
はじめに、ROICの計算式を確認いたします。
ROICは以下により算出され、有利子負債や自己資本の調達コストにあたる加重平均資本コスト(WACC)を上回るリターンが確保される投資であるかが採算性の判断基準となります。
<計算式>
投下資本利益率(ROIC) = 税引後営業利益(NOPAT) ÷ 投下資本
<投資判断>
ROIC > WACC ⇒ 調達コスト以上のリターンが生まれている
ROIC < WACC ⇒ 投資家から求められるリターンに満たない
以上からも、ROICは「投資効率」が判断基準となることがご理解いただけるものと思います。
企業の資本効率を測る上で非常に有用な指標ですが、短期的な改善に過度に注力すると、経営全体に歪みをもたらすリスクがあります。特に、長期的な成長や規模の視点が欠如することで、企業の競争力が低下し、持続可能な成長が阻害される可能性があります。
ROICを短期的に改善するために低収益事業の撤退やコスト削減が行われることがあります。これらの施策は短期的にはROICを向上させますが、売上高や利益額の成長を停滞させるリスクを伴います。低収益事業であっても撤退により売上規模が縮小し、規模の経済が失われる可能性や、他事業のシナジー効果がなくなることがあります。また、コスト削減を優先するあまり、製品やサービスの品質が低下し、顧客満足度が損なわれることで、売上減少に拍車がかかることもあります。
さらに、ROIC偏重の経営では、初期投資が大きく短期的にROICを低下させる可能性のある新規市場への進出や革新的な技術開発が抑制される傾向があります。このようなリスク回避志向が強まると、企業は安全な選択肢に固執し、成長のための挑戦を避けるようになります。その結果、競合他社が新市場でシェアを拡大する一方で、自社は市場の変化に取り残される可能性があります。
また、設備投資を抑制することで投下資本を削減し、短期的にROICを改善することも一般的ですが、これにより生産能力が限界に達し、需要増加に対応できなくなるリスクがあります。設備の老朽化や技術革新の遅れが競争力低下を招き、長期的な成長を阻害する要因となります。
投資効率を優先し成長を阻害した企業の失敗
仮の消費財製造メーカーA社の事例から、ROIC経営の落とし穴について解説します。
<A社概要>
売上高:1,000億円
営業利益:100億円
投下資本:800億円
A社の現状では、ROICは以下の通りです。
ROIC = 営業利益100億円 ÷ 投下資本800億円 × 100 = 12.5%
A社は、投資家から「ROICを15%以上に改善する」という目標を求められたため、次の施策を実行しました。
①売上高200億円、営業利益10億円、投下資本150億円のX事業からの撤退
X事業のROIC = 営業利益10億円 ÷ 投下資本150億円 × 100 = 6.7%
②設備投資の抑制
年間50億円の設備投資を削減 = 投下資本50億円の減少
③新規市場への製品投入見送り
初期投資100億円
(新規市場の業績見通し)
当初:売上高50億円、営業利益5億円 ⇒ ROIC 5.0%
5年後:売上高300億円、営業利益30億円 ⇒ ROIC 30.0%
A社が実行した施策により、ROICを15%に改善することができました。
<ROIC改善施策実行後のA社概要>
売上高:1,000億円 → 800億円(低収益事業撤退の影響)
営業利益:100億円 → 90億円(低収益事業撤退の影響)
投下資本:800億円 → 600億円(撤退と設備投資抑制の影響)
施策実行後のROIC = 営業利益90億円 ÷ 投下資本600億円 ×100 = 15.0%
しかし、数年後、A社は深刻な状況に置かれることになりました。
5年後には次の要因により、業績が大きく悪化したのです。
①売上の停滞とブランド力の低下
低収益事業からの撤退による減収、成長市場への進出を見送り成長機会を逃したことで、市場シェアが低下しブランド力も低下しました。これにより、売上高は5年後に800億円から700億円に低下しました。
②生産設備の老朽化
生産効率が低下し、売上高営業利益率が低下しました(10%⇒8%)。
<5年後のA社概要>
売上高:700億円(1,000億円 → 700億円)
営業利益:56億円(100億円 → 56億円)
投下資本:600億円(800億円 → 600億円)
5年後のROIC = 56億円 ÷ 600億円 × 100 = 9.3%
ROIC経営を成功させるための視点
ROIC(投下資本利益率)は、資本効率を測る上で有用な指標ですが、過度に偏重すると経営が硬直化し、長期的な成長を阻害するリスクがあります。事例から得られる教訓を踏まえ、ROIC経営を成功させるためには、複数の視点を組み合わせた柔軟なアプローチが必要です。
まず、ROICだけでなく、売上高、利益額、成長率、市場シェアなどの指標を総合的に評価することが重要です。ROICは資本効率を示す指標ですが、売上や利益の成長を軽視すると、企業の規模や競争力が低下する可能性があります。複数の指標を組み合わせることで、短期的な効率性と長期的な成長のバランスを取る判断が可能になります。
次に、短期的なROIC改善だけでなく、長期的な成長を見据えた投資を行う視点が求められます。例えば、新規市場への進出や革新的な技術開発は、初期投資が大きく短期的にはROICを低下させる可能性がありますが、長期的には企業の成長を支える重要な取り組みです。短期的な成果に固執せず、長期的な視点での意思決定を行うことが必要です。
また、柔軟な意思決定を行うことも重要です。ROICを唯一の基準として硬直的な経営を行うのではなく、状況に応じてリスクを取る姿勢を持つことで、成長機会を逃さず、競争力を維持することができます。市場環境や顧客ニーズの変化に迅速に対応するためには、柔軟性が欠かせません。
おわりに
ROIC経営は、投下資本をより効果的に活用していく観点からは有用な考えです。一方で、先行投資に消極的な判断をもたらす可能性がある点を十分に理解し、活用していくことが必要です。
過去のデフレ局面では、手元の現金を減らさない守りの姿勢が成功をもたらしたケースも多くあるでしょう。しかし、足元の日本ではインフレが進行し、現金の実質的な価値が低下している状況にあります。
今後、成長を実現していくためには「投資力」が求められます。将来に向けた投資判断の中で、ROICを経営の一助としながら、企業の競争力を高めていきましょう。
関連記事
-

物流業におけるROIC改善事例を解説!企業価値を高める方法とは?
- 資本政策・財務戦略
-

資本政策 事例|押さえるべき3つのポイントを事例を基に解説!
- 資本政策・財務戦略
-

組織における意思決定の種類とは?トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!
- コーポレートガバナンス
-

製造業における収益改善の2つの視点と5つのステップを徹底解説!
- 資本政策・財務戦略
-

-

収益改善の成功事例 | 効果的なポイントについて徹底解説!
- 資本政策・財務戦略
-

-

中堅企業が実装すべき財務戦略~ホールディング経営におけるトップのリーダーシップ~
- ホールディング経営
 コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト
コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト