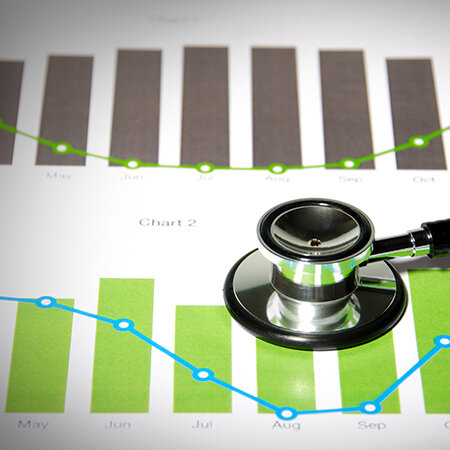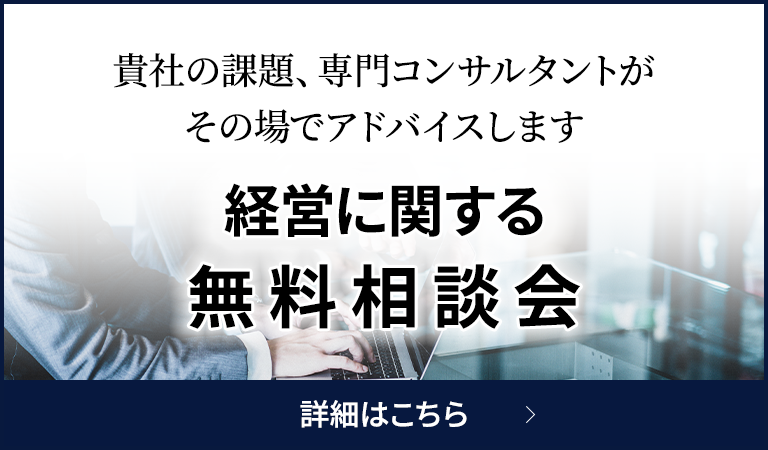建設業の資金調達方法と
事業計画の重要性
~A社の事例より~
- 企業価値向上

閉じる
近年、建設業界を取り巻く環境は急速に変化しております。
深刻化する労働力不足やデジタル化の遅れ、業界全体の高齢化といった構造的な課題に加え、社会全体における働き方改革の流れを受け、建設業界も変革を余儀なくされている状況です。また建設業界は資金調達がうまくできるかどうかによって事業の成否が大きく左右される業界でもあります。また企業の中には自社だけで資金調達を模索するだけでなく、事業計画を弊社のような外部機関とともに策定し、それを基に銀行へ説明することで、事業の継続に成功した企業もあります。今回は、建設業界特有の事情を踏まえ、弊社と連携して資金調達に取り組んだ企業の事例を交えながら、昨今の建設会社における資金調達について説明します。
建設業の資金調達方法~A社の事例より~
まず初めに建設会社の資金調達方法で主になるのはやはり銀行融資を活用した資金調達です。
銀行は、企業の信用力を踏まえて必要な資金を提供します。融資の条件や金利は、企業の財務状況や市場環境によって異なるため、事前にしっかりとした準備が必要です。信用力を図る指標として決算書上の数値も重要ですが、建設業者の施工能力や経営状況などを客観的指標で評価する経営事項審査も重要になってきます。しかし、設立間もない企業は、金融機関からの直接融資が難しいため、保証協会を活用して融資を受けるケースが一般的です。保証協会とは中小企業などが市中の金融機関から融資を受ける際に中小企業などの債務を保証する公的機関のことです。またその他にも弊社のような外部機関と一緒に作成した事業計画を基に銀行へ説明して融資資金を調達することもあります。
今回は弊社を活用したA社の事例を説明します。A社は建設事業を主力事業の1つとして様々な事業を営む会社でしたが、年々業績が悪化し、銀行からも今後の融資見通しについてネガティブな反応が聞かれるようになっていました。今後どのような形で業績を立て直していくのか、そのために必要な資金はいくらか、本業に使用していない無駄な資産はないのか、など今後の事業改善に様々な課題がありました。
そのような状況下で弊社が入り、まず行ったことは正確な現状把握でした。実態の収益力、会社の実際の資産価値(土地・建物含めて)など現状について正しく知り、経営者と共有するところからスタートです。その後は再建計画ということで時系列での本業の立て直し施策と共に改善後の数値計画を策定しました。建設事業ゆえに業績の将来予測は立てづらいのですが、3年後の数値目標を掲げたうえで直近1年間の想定される案件を全て洗い出しを行うことで、3年後の数値計画の妥当性を補完しました。また同社の場合は粗利改善も大きな命題でした。案件を受注しても結果的に赤字になっているというケースが過去実績から散見されたために、黒字を確保するための見積もり算定や原価改善の仕組み作りにも取り組むことを同事業計画では重要施策として打ち出しました。銀行の融資の中で重要になってくるのは売上高ではなく、利益です。したがって、赤字を回避するための具体的な施策や仕組みを事業計画に明記することが重要です。
事業計画を策定した後は取引銀行を集めてのバンクミーティングを開催して説明しましたが、事前にメインバンクに説明していたことで、バンクミーティングではスムーズに合意をとることができ、会社が事業存続することができました。
上記事例からも分かる通り、資金調達の基本は銀行融資となりますが、赤字会社が銀行から資金調達を受けるためには何よりも事業計画が重要になってきます。またその事業計画は当然黒字でなければいけませんし、黒字化するための施策は不可欠になってきます。
その他の資金調達方法
銀行融資が主の資金調達になるのは前述した通りですが、昨今は生産性向上や人材確保などの取組みを検討している会社を支援する補助金・助成金が政府から発信されていますので、一部をご紹介します。
まず、中小企業省力化投資補助金※と呼ばれる補助金を紹介します。中小企業等の人手不足解消につながる、IoTやロボットなど「省力化製品」の導入を支援する制度であり、補助対象となる省力化製品は、事務局ホームページの「製品カタログ」に登録されたものです。このカタログから、自社の課題・業種・業務プロセスにあった製品を選んで導入するといった流れになりますが、建設業でも省力化を実現する機能を持つ測量機などを導入することによって、製品本体価格および導入経費の1/2の補助金が申請できます。(ただし従業員規模に応じて、補助上限額が異なります。)
その他にも事業再構築補助金やIT導入補助金など様々な補助金があります。これらは全てホームページに要件などは公開されていますので、まずはどのような補助金が世の中にはあるのか本コラムをご覧いただいた方はぜひご確認いただければと思います。皆様にお伝えしたいのはお金が無いから何もできないではなく、企業規模が小さくてもできることは必ずあるということで、補助金も返済不要な資金を調達する手法の1つであるということを認識いただければと思います。
また昨今注目されている資金調達方法の1つにIPO(新規株式公開)による資金調達もあります。建設業界は一般的にIPOが難しい業界といわれていますが、IPOが不可能というわけではなく、むしろIPOによって信用力が高まり、デットでの資金調達もしやすくなるといった効果も期待できます。
※出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構
まとめ
今回は建設業を取り巻く環境を説明したうえで、事例も交えながら銀行融資、補助金、IPOによる資金調達手法を紹介いたしました。建設業は業績にバラつきが生じるため資金調達が難しい業種ではありますが、事業計画をきちんと説明できれば銀行融資を受けることも不可能ではありません。また資金調達方法やタイミングについてもその場その場で判断することも大事ですが、最低でも先行1年間の資金繰り計画を作成したうえで最適な資金調達手法を考えながら、計画的に資金調達をしていくことも建設業界では重要になってきますので、ぜひ今後の経営の参考にしていただければと思います。
関連記事
-

中堅企業が実装すべき財務戦略~企業を取り巻く経営課題~
- 資本政策・財務戦略
-

中堅企業が実装すべき財務戦略~「財務価値分析」から見る経営実態~
- 資本政策・財務戦略
-

事例から学ぶROIC経営の落とし穴とは?
- 企業価値向上
-

-

-

-

企業価値とは?意味と評価方法をわかりやすく解説
- 企業価値向上
-

 コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト
コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト