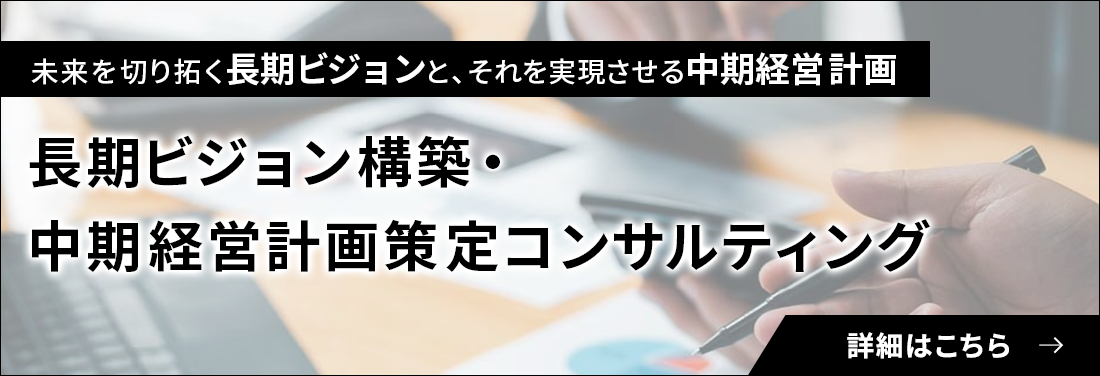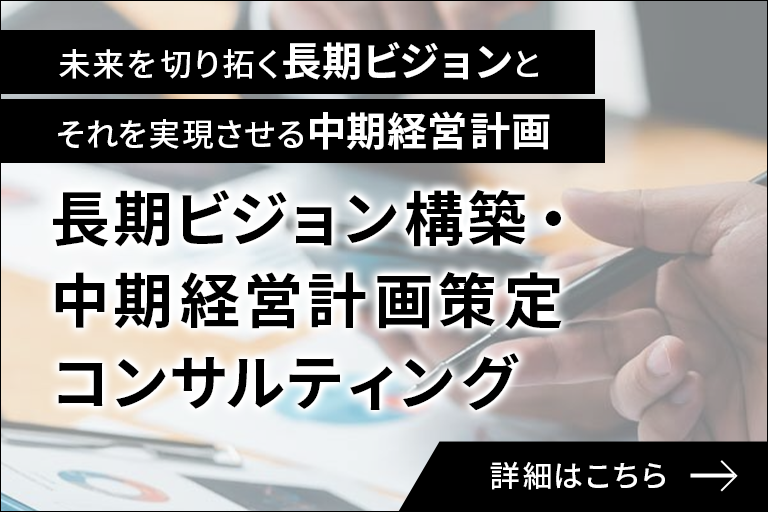COLUMN
コラム
閉じる

経営戦略を策定する目的
ここでは企業経営は、「経営戦略と事業戦略で成り立っている」と定義し説明していきます。企業経営の原理原則の1つに1T4Mがあります。Technology(ノウハウ)×Market(ターゲット市場)が事業戦略であり、その事業を推進するために経営戦略【Man(組織・人材)、Money(投資配分)、Management(仕組み・制度)の3M】があります。この経営戦略と事業戦略の整合性を取らない限り、事業戦略が正しくても事業は伸びません。
事業には必ず寿命があり、永遠に変わらない事業戦略は存在しません。したがって、戦略を構築しうまく推進していても事業の持続的成長を約束するものではなく、マーケットは成熟し必ず衰退へ向かうということになります。
このように事業にライフサイクルがあり、サイクルが長い事業もあれば、短い期間でマーケットが縮小する場合もあるということになります。技術革新が加速しVUCA時代の現代では、事業のライフサイクルも過去に比べて短くなっていると言えます。
経営戦略は事業戦略に沿って変化させる必要があります。成長企業の多くは、事業戦略の変更・進化と平行して経営戦略を変化させます。Man(組織・人材)、Money(投資配分)、Management(仕組み・制度)の3Mを事業戦略および企業規模に応じて変化させるということです。
例えば、単一事業であった今までは機能別組織で事業戦略を推進してきました。しかし複数事業になると、機能別組織のままでは事業責任者が曖昧になり、組織の原則である「役割・責任・評価/分配」の三面等価が崩れていきます。
また、企業規模が大きくなり、従業員数が増えてくると今まで問題のなかった評価制度や賃金制度がうまく回らなくなっていきます。このように事業戦略と平行しての経営戦略の策定も経営者の必須マターと言えます。

経営戦略の策定手順と経営戦略の策定ポイント
経営戦略とは、Man(組織・人材)、Money(投資配分)、Management(仕組み・制度)と説明しました。策定手順を紹介します。主に下記の5つを決めていきます。
1.組織:事業戦略を推進する組織デザイン・組織機能を設計する
2.人材:組織デザインに応じて、誰に任せるかを決める
3.投資配分:事業戦略を推進する投資額と基準値(撤退基準などを含む)を決める
4.仕組み:権限移譲やコミュニケーションパイプ、ガバナンス、KPIマネジメントサイクルを決める
5.制度:人事制度(評価制度や賃金・賞与などの分配制度)を改修する
まず、組織には3つの基本パターンがあります。機能別組織、事業別組織、マトリクス型組織でありますが、本コラムでの詳細説明は割愛します。
過去の組織図も含めて振り返った時に「事業戦略が〇〇であるので組織をこのようにした。この時の重点課題は〇〇なのでそれを解決するために組織・役割をこのようにした」と言えるかどうかが重要です。当然、過去だけではなく現在の組織図にも理由があるはずです。意志として先に箱(組織図上の部門)を作るべきであり、担当者や推進者が居なくても部門・組織図を先に作ることで会社としてどのように推進しようと考えているのか意思が伝わり、人材の不足も明確になります。幹部層の経験値や年齢も考慮して、次の「誰に任せるか」を決めます。これは経営者の意志を反映することが最重要であり、合議制で決めるべき内容ではないことが注意点です。
投資配分は年度経営方針発表会で事業戦略や組織デザインを発表すると同時に決まっていることが望ましいです。第1四半期が過ぎ、第2四半期が過ぎた後では、基準が変わり"判断と決断"ができなくなります。撤退基準やリスクプランを同時に策定しておくことで、投資ラインを整備できB/Sや利益率に影響を及ぼさない健全な経営活動ができます。
素晴らしい事業戦略と計画的な投資基準やスケジュールがあっても、仕組みがなければ組織はうまく機能しません。事業のPDCAサイクルが適切であるかどうかのKPI設定、業績や経営計画をタイムリーに効果測定できるコミュニケーションパイプ、戦略推進者への権限移譲(=稟議決裁権限の見直し)まで細やかに設計する必要があります。目標だけ増やしたり、与えても組織は機能しません。
最後に人事制度について、これは経営の最後の仕組みですが、従業員と最初に約束しなければいけない制度です。権限移譲と同時に何で評価するのか、事業戦略の重点方針は個人にまで目標設定されているかが肝要です。ここを見落とす経営者が多いので、部門の業務分掌目標と事業戦略の重点方針が個人目標まで行きわたっているか今一度確認してみてください。

策定を行い経営戦略が成功した事例
働き方改革に伴い、労務管理を含め個人の生産性を高めていく必要性が高まっています。A社はビジョンおよび中期経営計画の1つに「全社連携による従業員の生産性向上」を掲げました。従業員の労働生産性を分析した際に、直接人員(現場ライン)と間接人員(本社部門等)の一人当りの労働生産性が大きく異なることが分かりました。つまり現場ラインに負荷が多くかかっており、バックオフィス部門と差があり、処遇(給与や賞与など)はあまり差がなかったのです。
ここに目を付けた経営者は、組織にミドルオフィスを新設いたしました。ミドルオフィスとは、現場のサポート特化型の組織です。現場で負荷がかかっている業務をミドルオフィスが一手に引き受け、直接人員の業務負荷の低減につながり結果的に生産性は向上しました。
多くの企業が、残業時間を減らすために「上長が早く帰る」「勤怠管理を強化する」などできることから実践されていますが、本質的な課題解決には至りません。もしくは事業戦略が推進され、売上高が上昇、企業規模の拡大に至った場合は解決できない問題となります。戦略を推進するために組織・業務分掌・決裁権限を変更し成功した事例をご紹介しました。

著者
最新コラム

- 海外進出を成功させるためのパートナーの選び方

- 海外進出に成功した企業事例と成功要因の解説

- 海外市場調査のアンケート調査・インタビュー調査の具体的な方法

- 事業ポートフォリオ再編のプロセスとリスク対策
ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと
進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド
~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド
~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド
~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~
資料ダウンロード

- 長期ビジョン・中期経営計画に関する企業アンケート調査レポート2025年

- ストラテジー&ドメインコンサルティングメニュー紹介資料

- 統合報告書 ストーリー設計のコツ~企業価値は「説明」では動かない。「物語」が動かす。~

- 設備工事業界の未来を切り拓く:課題解決と成長戦略の最前線~人手不足からデジタル化まで、業界の変革を支える実践的アプローチ~

- TCG REVIEW 顧客創造モデル

- 収益構造を変える!ビジネスモデル・イノベーション~高収益を実現する事業ポートフォリオとPLのデザインはできていますか?~

- 食品業界の企業が中期経営計画策定で押さえるべきポイント~重要になるテーマと事例5選をご紹介~

- 経営者の成長投資アンケート調査レポート 2025年
 長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト
長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト