
DX内製化とは
DX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉が市民権を得てから数年が経ち、一旦落ち着きを見せているように感じます。現在、DXという言葉を聞いてその意味が分からないという方は少なくなっているのではないでしょうか。しかし、真にDXを推進している企業はまだ少なく、アナログから脱却できていない企業も多いのが現状です。自社だけでは難しい場合でも、Sierやコンサルタントなど外部の力を借りてスタートし、最終的には自走できる形を目指すことが理想です。デジタルの力を取り入れたとしても、外部リソースに依存している限り、まだ道半ばであると言えます。本コラムでは、DXにおける内製化というキーワードを中心にご紹介します。
DX内製化がもたらすメリット
内製化によって、企業の競争力は確実に向上します。目の前の課題に対する対応力や予見能力など、さまざまな力が身につきます。
1. 予算の削減
まず、予算の大幅削減が可能です。Sierやコンサルタントがプロジェクトに参画すると、それだけで大きなコストが発生します。システムの開発・導入、構築、運用開始までのフェーズでは専門家の支援が必要ですが、定着フェーズに入る頃には各部門が徐々に自走できる形を作ることが理想です。これにより、DXの恩恵が予算の削減という目に見える形で現れるでしょう。
2. システムや運用への理解
内製化することで、システムそのものへの理解が深まります。外部の専門家が課題を解決し続けると、自社の知識や経験、スキルは向上しません。これはシステム導入前からプロジェクト参加者全員が意識しておくべき重要なポイントです。
3. 次の一手に対するスピード感の向上
課題が発生した際に外部へ依頼していると、時間をロスしてしまいます。契約内容やシステム自体の特性によっては、想定以上の時間を要することもあります。内製化することで、迅速に修正を行うことが可能になります。また、新しく導入したシステムが現時点で最善であっても、より良いシステムは確実に出てきます。内製化により日々の課題を着実に見つけ、変化に対応し続けることで、システム入れ替えのタイミングを逃さず、全社でバージョンアップが可能となります。
4. 自社に合わせたシステムへのカスタマイズ
外部に依頼した場合、自社のことを理解しないままカスタマイズが行われることがあります。「この部署はこの機能を使わない」といった細かいカスタマイズは、内製化を行わないと難しい注文となるでしょう。
5. 最終的な目標に対する推進力
DXは手段であり、決して目標ではありません。例えば、「●●を導入することで原価を8%削減する」や「●●をチームメンバーで使用することで、▲▲にかかる時間を40%削減する」といった具体的な目標が重要です。システムを導入して満足し、成果が不明では本末転倒です。Sierやコンサルタントに任せっきりの企業でよく見られる事例であり、経営者が理解していないケースもあります。筆者が何度も提唱しているように、「DXの先頭に立つのは経営者であり、会社のビジョンに沿ったDXビジョンを描き、全てを連動させる」ことが競争力を向上させるために重要です。
DX内製化に伴うデメリット
DX内製化によるデメリットは主に人に関することです。ただし、システムの使い勝手やカスタマイズも年々進歩しており、人に頼らないシステムも増えてきています。競合が恐れるデメリットを克服できてこそ、競争力が身につくでしょう。
1. 専門人材の確保
専門人材が不足していることが最大のネックポイントとなることがほとんどです。人を育てるのか、採用するのか。新しくDX担当になった人の業務は今後誰が担当するのかなど、人材に関する課題は多くなります。
2. 予算の確保
新たに人材を採用したり配置したりする場合、人件費が必要となります。一からのスタートとなるため、時間が想定以上にかかることもあります。Sierやコンサルタントに依頼した方が安くなる場合もあるため、しっかりと調査・分析を行いながら自走する形をとることが重要です。
3. 担当者への負担増
自社での運営を行うと、さまざまな課題が出てきます。そのたびに利用者だけでなく周囲の人々にも影響が出るでしょう。例えば、生産管理のシステムがストップすれば、営業はもちろん、購買、生産、配送などあらゆる部門に影響を及ぼします。そうなると担当者への負担は大きくなり、時には心的負担も生じることがあります。また、システムは常にアップデートされるため、そのたびに担当者は関係者に説明を行い、理解と協力を得る必要があります。
DX内製化の成功事例
ここではDX内製化を成功させた企業の事例をご紹介します。
売上高50億円程度のあるメーカー企業では、営業スタッフの人手不足に悩まされていました。採用活動を行っても良い人材に巡り合えず、人手があればさらなる売上向上も見込める状況でした。そこで、筆者と社長を中心に営業DXプロジェクトを立ち上げ、システムの選定、導入、運用、定着まで伴走し、現在は筆者もベンダー企業も入らず、完全に内製化された状態で運用されています。特段システムに詳しい専門人材はおらず、全くのアナログ集団であったこの会社がDXによって生産性を飛躍的に向上させた要因はどこにあったのでしょうか。成功のポイントをお伝えします。
1. 様々な部署からのメンバー選出
どのシステムが自社に合っているのか、一部門だけの意見で決めてしまうと失敗に終わることが多くなります。例えば、顧客情報を蓄積したり営業日報を管理したりするSFAツールは営業部隊の声だけで決めてしまったり、MAツールはマーケティング部隊だけで選定されがちです。生産、生産管理、購買、経営企画、システムなど、あらゆる部署が営業と密接に関わっています。全ての部署の意見をしっかりと聞きながら導入することが重要です。
2. 運用フェーズでも他部署の意見を取り入れる
主に営業が使うツールではありましたが、生産管理、生産、総務、マーケティングのメンバーのアカウントも用意し、全員が使えるようにしました。何か課題があった際には、他部署のメンバーからの意見も参考にしながら改善を行い、全員で考え答えを出してきたことがその後の内製化につながったと考えています。
3. 社長、リーダーの揺るぎない決意
DX成功の鍵は、経営層やリーダーの決意です。どの企業にもベテラン社員やITに不慣れな社員はいます。彼らでも簡単に使えるように設定や説明を行い、使ってもらえるようにマネジメントすることで、全員が使いこなせるように成長し、生産性も格段に向上しました。ツールは使いこなせば必ず成果が出ます。揺るぎない決意をもって全社で取り組めたことが最大の成功要因と言えるでしょう。
DXは生産性の向上やスピード感のアップなど、企業力を強力に向上させる手段です。内製化にあたっては人材、時間、予算の確保など多くの課題が存在しますが、外部の力を上手く活用しながら全社視点を持って取り組むことで、より持続的な企業の競争力を築くことができるでしょう。
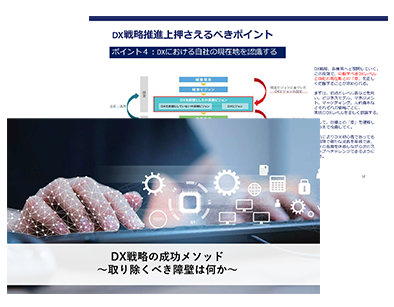

 デジタル・DXの戦略・実装情報サイト
デジタル・DXの戦略・実装情報サイト















