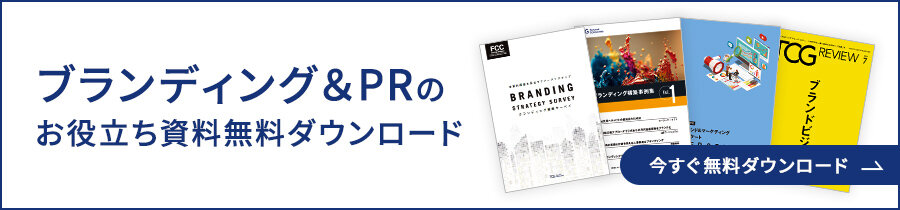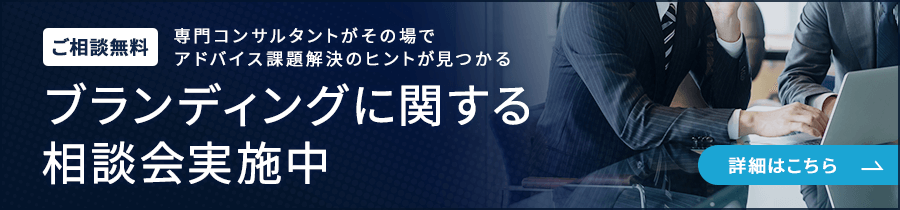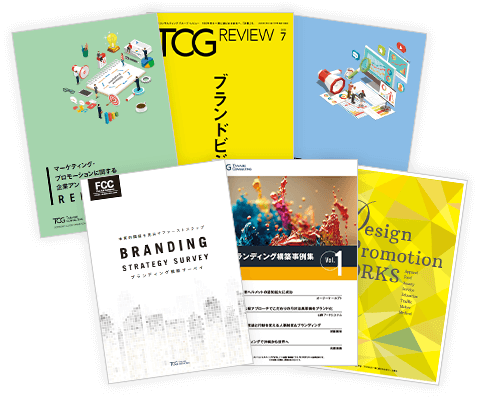閉じる
PRがPublic Relathions(パブリックリレーションズ)の略称であることは多くの方がご存知かと思います。
では、パブリックリレーションズとは何なのか、企業と社会が良い関係を築くためには何が必要なのかをこのコラムでは解説します。
PRの定義と歴史
なぜ日本ではPR=パブリックリレーションズではないのか
日本において、PRと聞くと「プレスリリースを出すこと」「パブリシティ獲得を目指すこと」と捉える方が多くいます。
しかし、パブリックリレーションズの定義は「企業とステークホルダーが良好な関係を共に創っていくための活動および考え方」であり、要約すると「社会と良い関係を築くためのコミュニケーション」ということになります。
そのため、プレスリリースやパブリシティに留まらず、広告やSNS、セールスプロモーション、企業HPなど、ステークホルダーに向けたすべてのコミュニケーションがPR活動と言えるのです。
日本でPRの意味が正しく理解されにくい理由は、歴史を振り返ると納得できます。
そもそものPRの起源は、18世紀後半の米国独立戦争と言われています。
その後、19世紀末~20世紀に鉄道会社が米国内で鉄道インフラを広げるうえで、様々な利害関係や地域社会との軋轢が生じる中、社会的な合意形成のために行った活動(雑誌刊行、ロビー活動、インフルエンサー活動etc.)が、事業におけるPRの始まりとされています。
日本では、第二次世界大戦後、GHQが日本の民主化政策実現のために米国のPRを紹介したことで始まりましたが、その際日本政府がPublic Relationsを「広報」と日本語訳したこと、そして、本来のPRが浸透する前にGHQが撤退したこと、さらに、高度成長期において日本全体が大量生産・大量消費の「露出すればするほど売れる」マスメディア・広告主体の社会であったことによって、「マスメディアにとりあげてもらう(パブリシティ)ための活動」という独自の考えが形成されたのです。
露出内容を重要視するコミュニケーション
情報のコントロール力の主体の変化
社会と良い関係を築くためのコミュニケーションとは言え、やはりパブリシティや広告が大事なのではないか、という声も多く聞かれます。
しかし、広告やマスメディアの力が圧倒的に強く、露出量が重要視される時代は既に終わりました。
現在は、TVCMの影響力が弱まり、消費者の広告に対する懐疑心も高まってきたことで、SNSをはじめとした第三者発信の情報の影響力が強くなっています。
このように企業が情報をコントロールしづらくなっている中で、情報を広くステークホルダーと共有していくためには、「いかに第三者に価値を感じてもらえるか、信頼してもらえるか」といった観点で、露出量だけでなく、露出内容を重要視する必要があるのです。
露出内容を重要視するということは、「誰に」「何を」届けるかを決めることであり、つまり、ブランディング発想とPR発想を掛け合わせた「戦略ブランディングPR」の考え方でPRストーリーを組み立てることです。
戦略ブランディングPR、およびPRストーリーの組み立て方については、『戦略ブランディングPR支援コンサルティング』ページもぜひご参照ください。
戦略ブランディングPR支援コンサルティング:
https://www.tanabeconsulting.co.jp/brand/service/branding-pr/
パブリックリレーションズにふさわしい効果測定とは
広告換算からの卒業
PR活動に関する質問として最も多いのが、効果測定についてです。
これまでは、獲得したメディア露出を広告として購入した場合の金額に置き換えて算出する「広告換算」をKPIとするのが主流でしたが、PRを社会との良好なコミュニケーションの構築という本来の意義で捉えた場合、この方法はふさわしくないとされています。
広告換算では露出量しかわからないこと、そして、広告換算をKPIとすることで、パブリシティ獲得がPRの目的になってしまうことが理由です。
国際的なコミュニケーション効果測定・評価協会であるAMECが提唱したPRの効果測定に関する7原則である「バルセロナ原則3.0」でも、「広告換算はコミュニケーションの価値を測定するものではない」と明言されています。
▼「バルセロナ原則3.0」の7項目
1.ゴールの設定は、コミュニケーションのプランニング、測定、評価に絶対的に必要なものである。
2.測定と評価はアウトプット(施策の成果)、アウトカム(目標に対する成果)に加え、潜在的なインパクトを明らかにすべきである。
3.ステークホルダー、社会、そして組織のために、アウトカムとインパクトを明らかにすべきである。
4.コミュニケーションの測定と評価は、質と量の両方を含む必要がある。
5.広告換算はコミュニケーションの価値を測定するものではない。
6.包括的なコミュニケーションの測定と評価には、オンラインとオフラインの両チャネルを含む。
7.コミュニケーションの測定と評価は、学びとインサイトを導くため、誠実さと透明性に基づくべきである。
引用:
公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会「バルセロナ原則3.0(Barcelona Principles)」
では、PRの効果測定とはどうあるべきか。おさえるべきポイントは2点あります。
1.目的に合わせたKPIを設定する
2.量だけではなく質も見る
先に述べたとおり、PRとは、ステークホルダーに向けたすべてのコミュニケーションを指します。
そのため、KPIは各コミュニケーションの目的に合わせたものであるべきであり、また、そのKPIを量だけでなく質でも測ることで立体的なものとなります。
例えば情報拡散・認知浸透を目的にX(旧Twitter)で発信するコミュニケーションを行った場合、KPIはリツイート数となりますが、その数だけでなく、リツイートとともに発信されているコメント内容も見ていく必要があります。
また、資料請求の問い合わせ獲得のためにWEB広告というコミュニケーションを行った場合、KPIはやはり資料請求数となりますが、ここでも数だけでなく、誰からの問い合わせであったかも重要です。
メディア露出を目的として記者発表会というコミュニケーションを行った場合でも、記事掲載・報道数だけでなく、どのメディアにどのような内容で報道されたかにも焦点を当てなければなりません。
まとめ
日本でのPRの始まりや、広まった背景から、PR=メディア露出や広告という捉え方がいまだに残っているのも事実です。
しかし、あくまでPRは企業と社会が良好な関係を築くことであり、結果的に企業のサステナビリティを向上させる活動でもあります。
そのため、時代とともに最適なコミュニケーション手法を見極め、自社の自己満足ではなく、社会に共感される情報発信を行っていくことが重要なのです。
 ブランディング・戦略PR情報サイト
ブランディング・戦略PR情報サイト