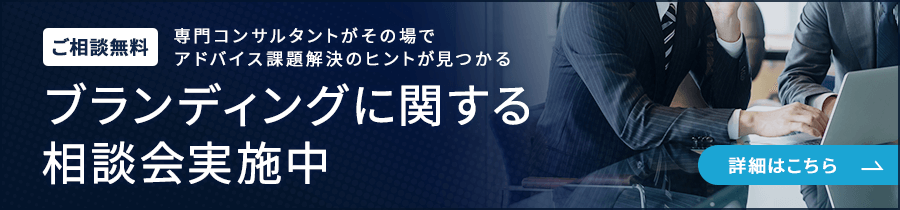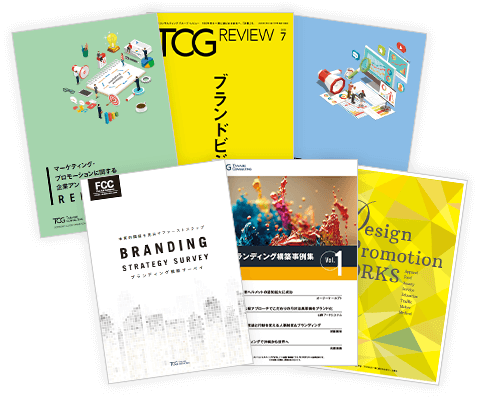閉じる
新型コロナウイルス感染症によるリモートワーク文化の促進や、生成AI技術の台頭により、IT市場はますます活性化の様相を呈しています。一方で、帝国データバンクの調査によると、2024年度の「ソフトウェア業」の倒産件数は220件で、2023年度比で約1.4倍に達したとのデータもあります(https://www.tdb.co.jp/report/industry/20250423-software-br24fy/)。
大きなチャンスがあるにも関わらず、競争の激化や人材不足によって潰れてしまう企業が多いIT業。この課題を解決するキーのひとつがブランディングであると言えます。自社の貢献価値を明確にし、それに共感するターゲットを見定めることで、目指すべき未来を明確にする「ブランディング」によって、企業の本質的価値を発信してみませんか。
そもそもブランディングとは?
IT業に限らず多くのお客様との対話の中で、ブランディングという言葉の解釈はバラバラです。企業の経営理念を作る/作り直すこと、企業・商品・サービスの新商品名とキャッチコピーを考えること、新商品のPRを行うことなど、そのどれも間違いではありません。しかし、ブランディングの本質とは何かを考えた時に「必要条件は満たしているが十分条件は満たしていない」というのが率直な感想です。
タナベコンサルティングでは、ブランドを「その企業や商品の提供価値や様々な構成要素、ブランドとのコンタクト体験とが複合的に結びついて、消費者・顧客の頭の中で作り上げられるイメージ」、ブランディングを「企業や製品・サービスによって提案したいアイデンティティやブランド独自の価値を魅力的に伝えることで、消費者・顧客にその価値を認知させ、そのイメージを向上させる活動」と定義しています。
ポイントは2点あります。
ひとつは「顧客視点の重要性」。
いくら自社がAという理念を立てていたとしても、それが顧客に伝わっていない、もしくは、Bというイメージを持たれているとすれば、それはブランディングとして失敗していると言えます。創業からの自社の理念と、顧客が自社にどういうイメージを持っているのか、何に共感し支持してくれているのかの両軸から、自社のブランドを正しく現状認識する必要があります。(具体的な手法については『ブランドイメージを数字で把握する!ブランディングイメージ調査のススメ』をご参照ください)
もうひとつは「発信=PRすること」です。
様々な手法を通して自社のあるべきブランドを明確化できたとします。それをプロジェクトメンバーだけで抱えていては意味がありません。前述の通り、ブランドは「消費者・顧客にその価値を認知させ」ることが重要なので、ターゲットに対してブランドを伝える仕掛けが必要となります。
この2点を踏まえると、独りよがりに企業の在り方を定義することは正しいブランディングとは言えませんし、単に見た目の良いプロモーションを展開するだけでもブランディングとは言えないということがご理解いただけるかと思います。
IT業になぜブランディングが必要か?
私がIT業界にこそブランディングが必要だと考える理由はシンプルです。それは、ITという無限の可能性を秘めた分野でありながら、多くの企業がいまだに日本の伝統的なものづくりメーカーと変わらない「プロダクトアウト」の発想で事業を展開している現状があるからです。
例えば、どのIT企業もAIを取り入れた技術開発に日々力を入れていることと思います。実際にWeb検索したところ、「AIを取り入れ○○をグレードアップ」「AIで○○を○%削減」など多様なサービスが展開されていることが分かります。
ただし、同じことはどの企業でも謳っています。逆に言えば、自社のサービスが優れていることを謳わない企業はありません。にも関わらず、AIの有無であったり、何かを改善するシステムであればその対象とパーセンテージが異なることを訴求するばかりで、素人目からすると結局何が違うのか判断がつかないのです。
導入側担当者はそのような状況の中であっても、見積やコンペ依頼を出さないといけないため、複数の企業に声をかけますが、結局価格だけで選んだり、デメリットがあることが前提で何となく一番課題解決に結び付きそうだという感触だけで選ぶため、最終的に納得感が得られないという事態に陥ります(ただし、ここには導入側のDX戦略の有無も影響があると言えますが...)。これは、ベンダー側・導入側双方にとって不幸なことです。
このように、競合との価格競争に晒される状況を防ぎ、システム導入の納得感を高めるのに有効なのが、ブランドを明確に発信しそれを顧客に理解・共感いただくことなのです。
コンペに勝った時のことを思い出してみてください。もちろん、価格優位性で勝ち取った案件もあるかと思います。しかし、「あなたの企業・サービスのここに共感した」「うちの企業のことを分かってくれていると思った」というような言葉を頂いたことはありませんか?
自社が社会に対して与えているインパクト=貢献価値を見定め、その貢献価値に基づくコミュニケーションを図っていくことで、その価値に共感をしてくれる顧客が現れます。その時の経験だけでなく想いを積み重ねていくことでブランドが自ずと大きくなり、これに伴って事業も拡大していく。このような善循環を生み出すためにも、戦略的にブランディングを行うことは大変重要な事業課題であると言えます。
企業としてのブランドが明確になっていることは、人事・採用にも良い影響を与えます。すなわち、給与や開発しているサービスではなく、理念に共感し企業へのロイヤリティが高い人材の採用ができますし、社内の共通言語として、ロイヤリティ・エンゲージメントを維持し、高めることにもつながります。
事業上は何でもできてしまう、それ故に、何を行うべきかの指針が必要である。これがIT業においてブランドが必要な理由なのです。
他社事例からIT業におけるブランディングを学ぶ
ブランドの在り方も様々ありますが、近年トレンドになっているのが、PMVVです。
企業の貢献価値とそれに共感を覚えるターゲット、そのターゲットにもたらす未来の姿を「Purpose=自社の存在意義」「Mission=果たすべき使命」「Vision=自社のあるべき姿」「Value=理念を実現するために持つべき価値観・取るべきふるまい」の4つの観点で整理したものとなります。企業によっては、順番が変わったり、全てが揃っていない、言葉の定義が変わっていることなどもありますが、基本体系は上記の通りです。
例えば、株式会社DeNAではMVVが設定されており、さらにValueを社会への約束であるPromiseと、自社が大切にすべき価値観であるQualityに分類しています(https://dena.com/jp/company/policy/)。
また、企業ではありませんが、デジタル庁でもMVVが設定されています(https://www.digital.go.jp/about/organization)。デジタル庁のバリューは4つ設定されているのですが、「一人ひとりのために」「常に目的を問い」「あらゆる立場を超えて」「成果への挑戦を続けます」とつなげると、ひとつの文章になっているのが特徴です。
PRの観点で外せないのはSky株式会社でしょう。「青空のごとく大きな考えでシステムを創る」という企業理念のもとに事業展開を行い、対外的には「まだ見ぬテクノロジーの空へ」というメッセージを中心に、コーポレートならびに各サービスブランドにイメージキャラクターを設定し、大々的なプロモーションを展開しています。SNS・Webに限らず、TVCMや交通広告にも積極的に広告展開を行っており、目にしない日はないと言っても過言ではありません。
一見派手なプロモーションに目を奪われがちですが、統一化されたブランドアイデンティティやブランドネーミング、イメージに合わせたキャスティング、ターゲット導線に合わせた広告展開など、練りに練られた戦略に基づくブランディングを展開しています。
大手企業の例を挙げましたが、なすべきことは事業規模に関わらず同じで、まずは自社の在り方を明確にすること。そして、そのPRの観点においては、まずはターゲットの絞り込みをしっかりと行ったうえで費用の最適化も行いつつ、狙った領域で唯一無二性を発揮しニッチナンバーワンポジションを獲得する。それを横展開・拡大展開していくことで事業を大きくしていく道筋が考えられます。
さいごに
本コラムでは、IT業界におけるブランディングについて、顧客目線で課題の本質を考察し、取り組むべきポイントや具体的な事例を交えながら解説してまいりました。最後までお読みいただき、自社においてもブランディングの必要性を感じられた方がいらっしゃいましたら、ぜひタナベコンサルティングまでお気軽にご相談ください。
 ブランディング・戦略PR情報サイト
ブランディング・戦略PR情報サイト