
1.サービス業界を取り巻く環境変化
(1)多様化するニーズとスピード感が必要な環境へ
「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉は、現代において広く知られるようになりました。DXの定義は幅広く、企業規模や取り組み内容によって異なる場合があります。本コラムでは、「業務や組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争優位性を確保するもの」と定義します。
近年、企業を取り巻く環境は大きく変化しています。新型コロナウイルスの流行、ロシアのウクライナ侵攻など、社会を揺るがす出来事が相次ぎました。国内でも、新型コロナウイルスの影響で接客を伴うサービス業が大きな打撃を受けました。さらに、人手不足や消費者の価格志向が強まり、経営環境は厳しさを増しています。
従来、訪問型が主流だった営業活動も、オンライン商談へ移行する企業が増加しました。こうした環境変化に適応するため、DXの取り組みが加速しています。
(2)DX化が進まない背景
その一方で、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「DX動向2024」によると全社的にDXに取り組んでいるサービス業の割合は26.8%と他業種よりも低く、DXの取り組みが遅れている実態があります。
(出所:DX動向2024)
DX化が進まない背景として、全社的なITリテラシーの不足、DXを推進する人材の確保・育成の2つが考えられます。
① 全社的なITリテラシーの不足
DXを進めていくうえでは、事業及び業務改革(BPR)の視点が必要であり、それぞれにおいて社内体制を整備していく必要があります。ITに関する知識量の差から、経営陣が部下に権限を委譲し、システム開発をITベンダーに任せている現状はないでしょうか。また、過去の成功体験(歴史)により、変える必要性は認識しているが、変えることで成果が出るのか疑問を感じ、一歩を踏み出せない企業も多いのではないでしょうか。結果的に事業変革を目的としないシステム投資となってしまうケースもあります。
② DX推進人材の確保・育成
DXに対応・推進できる人材(ITアーキテクト、ITスペシャリスト等)は、主に東京や大阪などの都市に集中しており、他エリアにおいては採用が難しい状況です。縁があって、システムエンジニア経験者を採用したとしても、現行システムの保守・運用にスキルは発揮するものの、全社的視野から攻めと守り、それぞれの視点を持ってDX化を推進できる人材は少ないのが実態です。採用もですが、育成においてもITに関するスキルを体系立てて、自社で育てて抱えていくことはノウハウがない限り難しいと言えます。これらのことから、DX推進人材を確保・育成する意味では、難しい状況であると言えます。
上記のようにDX化が進まない背景はありますが、サービス業において、人手不足は顕著であり、維持・成長をしていくために変化を止めることは望ましくありません。サービス業において変化に適応し生き残るためには「生産性向上」「顧客体験価値の向上」を実現していくことが必要です。
以下より、サービス業において「生産性向上」「顧客体験価値の向上」を図った事例を紹介します。
2.サービス業DX
(1)サービス業におけるDX推進事例
サービス業においても技術革新・DXは進んでいます。AIによる自動受付・発注、配膳ロボット、AR、VR等業務をアシスト・効率化していく技術が日々開発されて、ローンチされています。最新技術をサービス業として取り入れたDXの事例として、以下ご紹介します。
① 宿泊業(A社):旅館管理システム
課題:館内の情報伝達が紙や口頭確認が中心のアナログ運用となっており、既存の旅館管理システムもフロントのみであり、使用できる端末が限られていました。過去の履歴等も紙の台帳管理のみとなっており、すぐに確認できる場所になく、顧客情報を十分に記録・活用できていませんでした。
改善策:クラウド型旅館管理システムを導入し、効率化を図った。クラウド型を採用したことで館内の情報共有(例:フロント→調理場)が容易になり、転記等が不要になりました。また、予約・顧客情報の共有化ができ、従業員に配布しているiPhoneから、お客様ごとの予約詳細や過去履歴などの情報が直接確認できるようになりました。結果、紙の転記作業も減り、1日1時間の作業時間短縮を図ることができました。
サービスレベルも向上し、お客様からの依頼事項へのタイムリーな対応や、過去履歴やニーズ等をシステム管理することによるきめ細やかなサービス提供を実現し、サービス品質が向上した好事例です。
(出所:宿泊業の生産性向上事例集)
② 飲食業(B社):クラウドPOSシステム
課題:これまで手切りの食券で注文を受け、そろばんで計算をしており、紙の売上台帳で日々の売上を管理していました。そのため、紙の情報しかなく、データ活用に至らないため、「勘と経験」に頼った経営状況でした。
改善策:まずはオンプレミスのPOSシステムを導入し、データを収集・蓄積する仕組みを作ったうえで、紙の売上台帳からエクセル管理へと変えていきました。これまで記載していなかった転記や気温などの情報も付加し、傾向を把握できるようにしました。その後、クラウドのPOSシステムへ移行し、店舗の状況を共有・可視化できるようBIツールを導入しました。来客予測をするためにAIも取り入れ、通行量やPOSデータを分析し、売上増につながりました。これらは10年間で取り組んだことであり、いかに早く取り入れ、自社で活用していくことが必要かを考えさせられる事例です。
(2)実現に向けた3ステップ
環境変化に適応していくため、意思決定をスピードアップしていくいわゆる"スピード経営"を実現するためにはまずデータを統合管理していくためのシステム(ERPシステム)を活用することが必要です。事例の2社においても統合管理をしていくためのシステムを導入していました。一元管理されたデータをもとにリアルタイムで業績を把握し、事業変革へ対応していく。つまりDX化をしていくことが現代の企業経営には求められてきています。DX化を進めていくためにはデジタイゼーション、デジタライゼーション、デジタルトランスフォーメーション(DX)の3段階があります。
以下、DX化を進めていく3ステップを以下に示します。
① 現状認識
はじめにわが社の現状の問題点を把握します。各部門で活用しているシステムにデータが蓄積されているも、点在化しているため活用されず、保守・運用がブラックボックス化している状態。紙ベースで属人的な業務運用が見直されぬまま踏襲され、転記作業や時間の無駄が発生している状態。業績把握のために、経営会議や部門会議等の報告資料や各種集計資料を作成するため、各部門からデータを集め手作業で集計・加工が必要なため時間がかかります。または、これらがデータ連携されていないことから、お客様の利便性が損なわれていないか。こうした社内外の非効率なアナログ業務を定量・定性の両面で把握します。
② システムを活用したデータ統合
現状の課題を押さえた後はデジタイゼーションの領域から始めましょう。現状認識で棚卸をした課題を基にデジタル化を進めていきます。例えば、紙文化を改めデジタルのワークフローに置き換えて、単一業務をデジタル化し、効率化していくことです。また、基幹業務にパッケージシステムが活用され、データの蓄積とデータ連携ができている状態へと転換します。システム導入をする際は自社の業務に合わせてシステムをカスタマイズするのではなく、システムの標準機能に業務を合わせる「Fit to Standard」の考え方が有効です。この考え方を基にシステムを導入することで、短期間且つコストを抑えながら、二重入力や業務の重複が解消されて効率化されることとなります。システム内のデータを抽出・加工することで、業績把握を速やかかつ容易に行うことができる状態を目指します。
③ データ利活用による経営変革
ここまでのステップを踏んでいくことでDX(デジタルトランスフォーメーション)へと進めることができます。システムが明確な目的のもとに全社最適化されており、情報資産がデータベースとして一元管理される状態や、システム機能を活用した業務の標準化が徹底され、業務は適時見直され、効率化・省力化される状態を目指します。ここまでいくと、自社のデータを情報資産としてリアルタイムに確認・活用することができ、事業変革・顧客体験価値の向上に機動的に対応できます。
以上、3ステップをご紹介しました。一度に全て推進していくことはリソース上、難しいと思います。しかし、顧客体験価値の最大化に向け、描いたあるべき姿が絵に描いた餅にならないよう、着実に進めていくことが重要です。
3.さいごに
サービス業においてDX化が進めにくいという悩みの本質には、現状をなんとなく押さえており、「こうあるべき」が描けていないことだと感じます。DX化を進めていく上では、まずは自社の経営視点、現場視点で課題を洗い出し、全社最適となるあるべき姿を描くことが重要です。また、繰り返しになりますが、サービス業においては「顧客視点」も欠かせません。顧客体験価値を向上させるために、お客様のどのような情報が必要で、どう集めるか。集めたものをどう分析し、業務に活かしていくか。それぞれを検討したうえで、情報の収集・蓄積・分析・活用を前提としたあるべき姿を描きましょう。根底となるITリテラシーやDX推進人材の育成については、ITベンダーなど外部の力を借りることも有効です。本コラムがサービス業におけるDX推進の一助となれば幸いです。
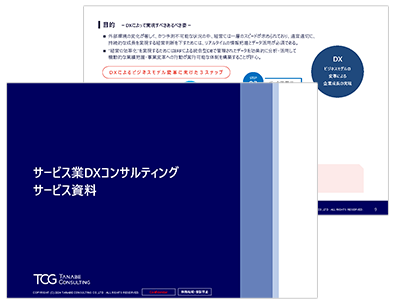

 デジタル・DXの戦略・実装情報サイト
デジタル・DXの戦略・実装情報サイト














