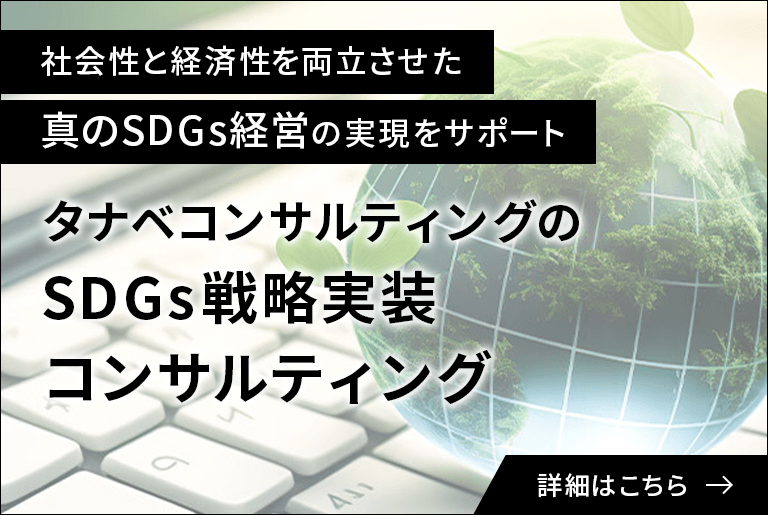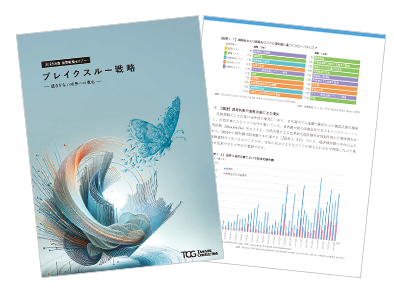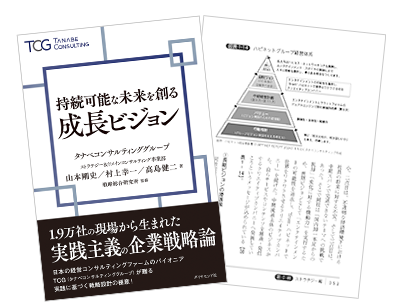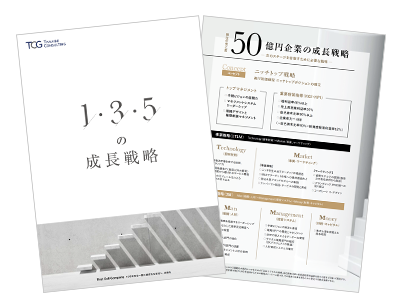COLUMN
コラム
閉じる
コロナ禍という先行き不透明な状況において、企業ビジョンや中期経営計画の見直しをかける企業が増加しました。その流れの中で多くの企業が自社の事業へSDGsを実装した経営戦略を打ち出しています。
SDGs構造分析フェーズ
外部環境・内部環境を分析する
事業戦略および経営戦略を策定する際と同様に、自社を取り巻く環境=外部環境の分析と社内の環境分析=内部環境の分析を実施します。外部環境においては、自社の業界構造やトレンドを把握すると共に社会的視点・環境的視点にて機会と脅威を洗い出したうえで把握しておくことがポイントです。
また、内部環境分析においては自社の経営資源(ヒト・モノ・カネ)の実態把握をすると共に、固有技術=コアコンピタンスがなにかを把握しておくことが重要です。その際に社内での取り組み事項についてを列挙しておくと後工程がスムーズになります。
外部環境と内部環境を分析し整理ができたら、バリューチェーンマッピングを行います。各機能ごとに自社が社会・環境に対して、影響を与えている事項を洗い出します。このステップでは正(良い)の影響と負(悪い)の影響のそれぞれを整理しマッピングを行います。正の影響であれば更なる強化、負の影響のであれば最小化の検討を行うことで、施策アイデアベースでのブレストやディスカッションにてロングリストを作成します。
これが、将来的な正の影響・負の影響を整理するためのSDGs構造分析となります。
優先課題の整理
将来的な正の影響の最大化、負の影響の最小化のための施策アイデアをロングリストとして作成した後に、各施策アイデアを抽象化することでテーマ出しを行います。例えば「事業活動で発生した廃棄物の再利用」「事業活動における再生エネルギーの活用促進」などのアイデアが生まれれば「エコ活動への取り組み」といったテーマでまとめるようなイメージです。ロングリストで列挙したアイデアに対して、テーマ分類を行うことでまとめていき、全てのアイデアを分類します。テーマとして分類したものを便宜上、重点テーマと呼びます。
重点テーマとして分類ができたら、次は重点テーマをマテリアリティマトリクスに落とし込みます。マテリアリティマトリクスとは、縦軸にステークホルダーへの影響度(または重要度)、横軸に自社への影響度(または重要度)というマトリクスを描き整理する手法です。自社にとっての重点テーマの内、優先されるものはなにかを社内でよく検討し、落とし込みをかけていくことが求められます。
重点テーマをマテリアリティマトリクスへ落とし込んだら、優先度の高い重点テーマをまとめ、マテリアリティとします。重点テーマを中項目とするならば、マテリアリティは大項目に対応しており、施策アイデアは小項目と認識していれば、整理しやすくなります。
【関連ページ】:
SDGsで企業経営を成功させる5つのステップを大紹介(連載コラム第1弾)

SDGs戦略策定フェーズ
SDGsビジョン策定
自社が目指すべき姿、向かうべき方向性を経営理念や企業トップとの考えと照らし合わせ、ミッションの再定義を行います。ミッションとは社会に対する自社の存在意義を示したものになります。企業経営をしていく中でとても重要度が高いものになりますので、企業トップのみならず経営幹部層や社員の皆様としっかりと議論をした上で時間をかけて決定していくことが推奨されます。
ミッションの再定義が完了した後、SDGsビジョンの策定に入ります。ミッションと照らし合わせ、自社が何のためにSDGsへ取り組むか、何を目的にSDGsへ取り組むかを明確にし、SDGsへ取り組みの中で自社が目指すべき姿をSDGsビジョンとして明文化します。SDGsビジョンとして明文化することで社内外へ浸透しやすくなる効果があるため、発信する企業も増えています。また、SDGsビジョンを目指すためのロードマップ=ストーリーをビジョンをゴールとした上で、5年や10年という中長期的な単位でのマイルストーンを置くことで描きます。
アクションプランの策定
SDGsビジョンとロードマップを策定した後に、再度マテリアリティを検討します。SDGsビジョンと照らし合わせた際に、優先度の設定が問題ないかを判断軸とし再度の確認を行います。問題なければ、マテリアリティを確定とします。その際、3~5個程度のマテリアリティに絞ることが一般的です。
次にマテリアリティを構成する重点テーマに対して、追加・削除することを検討します。その作業の際にも、SDGsビジョンを念頭に置いて進めることが、目指すべき方向性と施策のズレを無くすポイントになります。
各マテリアリティに対して、重点テーマが決まれば、重点テーマごとの施策アイデアを見直していきます。言い換えると、施策アイデアからSDGs施策として決定をしていくステップです。フェーズとしては初期の方で設定している施策アイデアとなりますので、過不足が多く見られるかもしれませんが、このフェーズに入ると具体的なイメージを持って進められるのではないでしょうか。
施策に対して時間軸を反映し、いつまでに何をしていくかを明確化していくことで、アクションプランが完成します。
SDGs実装フェーズ
社内外への発信
アクションプランは上記までのフェーズにて策定が完了しますが、社内外へ発信していく際にはKPIの設定は欠かせません。KPIは重点テーマ別に設定し、ロードマップのマイルストーンを明確にしておくことが一般的です。
SDGsビジョン、ロードマップ(ストーリー)、マテリアリティとアクションプランが出そろった段階で、社内へ発信をします。社内へ発信する前段階として、社内浸透策や方法を検討しておくことも必要になります。各コミュニケーションパイプ(会議体)の中で伝達をすることや、社内ネットワークでの発信、SDGsブックのようなインナーブランディングを行っていくことが一般的であり、社内へ発信する際の手段です。人事評価指標として組み込むことも検討の余地がありますが、ある程度の浸透の後に組み込んだ方が社員からのアレルギー反応は少ないのではないでしょうか。
また、外部への発信についてはHP上に掲載することやプレスリリースを発信することが多いですが、掲載する範囲については企業によって様々です。SDGsビジョン・マテリアリティのみ掲載しているところもあれば、マテリアリティ選定までのプロセスを載せている企業もありますので、自社のご事情やPRしていきたい思いにて判断すると良いでしょう。
推進体制の構築とKPIマネジメント
実装していくための最後のステップとしては、推進していくための体制整備とKPIマネジメントになります。
SDGs推進室のような形で独立させSDGsへの取り組みを推進していける企業もあれば、その機能を経営企画室が担っているパターン、各部門ごとの代表者がプロジェクト形式で推進しているパターンと多岐に渡ります。
社内環境によっての判断になるため、一概には言えませんが現場に一任し半期ごとに進捗の確認をするという運用ではSDGs浸透や施策推進が進みづらいのは事実です。代表者を集めたプロジェクトチームを組成した上で、TODOと責任を明確にしておくことが求められます。
また、誰がなにをどの程度やるのかをアクションプラン策定時に可能な限り明確にしておくことや、KPIを月次の確認とし、経営会議のアジェンダに組み込む等の運用をすることでSDGs実装・推進が円滑に進むのではないでしょうか。
【関連ページ】:
SDGsで企業経営を成功させる5つのステップを大紹介(連載コラム第1弾)
SDGs経営実装完全ガイド~メリット・事例・戦略のポイントまで一挙ご紹介

最新コラム

- 海外販路開拓の具体的な方法4選!成功させるための戦略と手順を解説

- タイ進出を成功させるメリットと3つの注意点|進出前に知るべきリスクを解説

- バリューチェーンの重要性とは?最適な構築方法のポイントを解説

- 中期経営計画の期間は何年が最適?成功する策定のポイントを紹介
ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと
進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド
~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド
~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド
~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~
 長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト
長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト