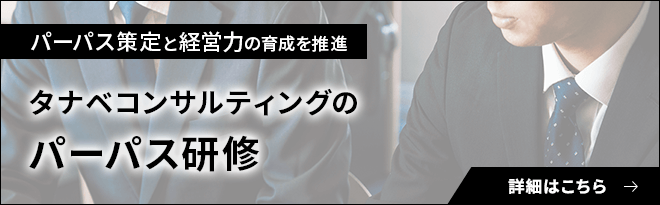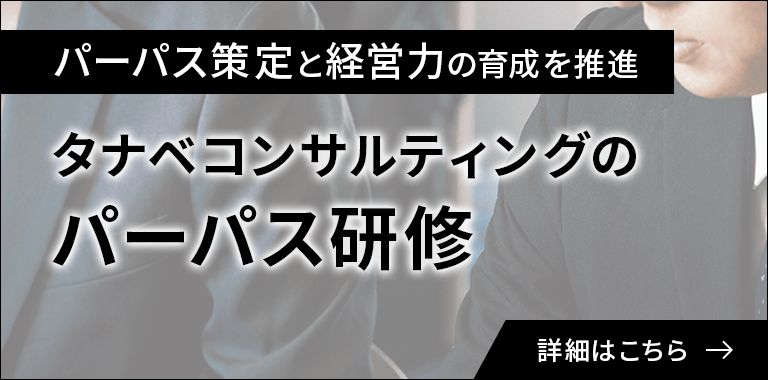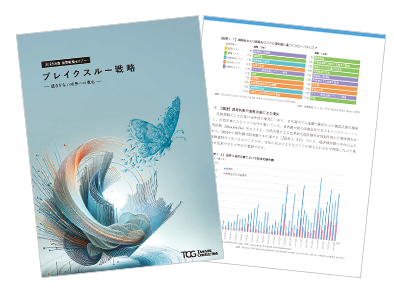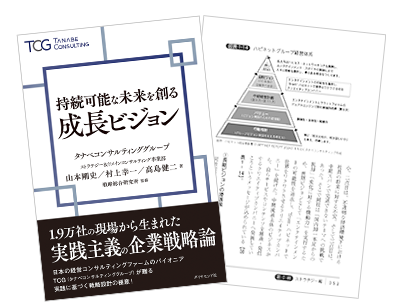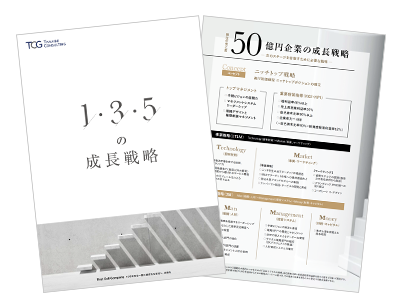COLUMN
コラム
閉じる

【結論】
パーパス・マネジメントとは、組織の存在意義によって、従業員のエンゲージメント向上や持続的成長を促す新しいマネジメント手法であり、働き方の多様化や社会課題の複雑化が進む中、従業員一人ひとりが自分の仕事に誇りと価値を感じ、生き生きと働ける組織を作る施策として注目が高まっています。全ての従業員が自分ごととして日々の行動に落とし込めていることが成功指標であり、社員参加型のプロセス設計や継続的な改善がパーパス浸透の成功の鍵となります。ここでは、これからの組織に求められる新しいマネジメント手法であるパーパス・マネジメントの効果と実践のための4ステップ、失敗事例から紐解く成功のヒントを解説します。
パーパス・マネジメントとは
パーパスとは
「会社って何のために存在するのか?」「この仕事にどんな意味があるのか?」
そんな問いが、今多くの経営者や従業員の心に浮かんでいるのではないでしょうか。特にZ世代を中心とした若い世代においては、単に給与が高い企業よりも社会的意義や自分自身の存在意義を感じられる企業で働きたいと考える傾向が強まっており、こうした社会的背景から、企業の「存在意義」を意味するパーパスが注目されるようになりました。
SDGsやサステナビリティへの注目も相まって、利益追求だけでなく社会的意義を重視する経営が、今求められるようになっています。
パーパス・マネジメントとは
パーパス・マネジメントとは、組織が「なぜ存在するのか」という根本的な問いに答え、その答えを組織全体で共有・実践するマネジメント手法です。重要なのは、パーパスが日々の業務や意思決定の根幹に据えられ、それを社員一人ひとりが自分ごととして捉え行動に移せていることです。
パーパス経営との違い
パーパス経営は、企業の存在意義を経営戦略の中核に据え、社会課題の解決を通じ企業価値を高めていく「経営モデル」です。一方、パーパス・マネジメントは、そのパーパスを組織内部に浸透させ、現場レベルでの実践を促進するマネジメントにフォーカスしています。つまり、パーパス経営が「経営の軸」を定めるのに対し、パーパス・マネジメントは「現場での実践」を重視するアプローチと言えるでしょう。

パーパス・マネジメントの5つの効果
従業員エンゲージメントの向上
パーパスが明確になることで従業員は自分の仕事の意義を実感しやすくなり、モチベーションが向上します。
世代間ギャップの緩和
価値観が異なる世代間でも、共通のパーパスを軸にしたコミュニケーションが生まれ、組織の一体感が向上します。
意思決定の迅速化
パーパスが明確な行動指針として機能し、「パーパスに沿っているか」という判断基準が複雑な意思決定のヒントになります。
ステークホルダーからの信頼獲得
社会的意義を明確にして、それを実践することで、顧客や取引先などからの共感を得やすくなり、信頼の獲得へ繋がります。
優秀な人材の確保と定着
明確なパーパスを掲げる企業は、同じ価値観を持つ優秀な人材を引き寄せ、これは離職率の低下へと繋がります。

実践のための4つのステップ
ステップ1:パーパスの明確化
経営陣だけでなく、様々な部門や階層の従業員を巻き込みながら、組織のパーパスを言語化します。表面的な美辞麗句ではなく、社員一人ひとりが「自分ごと」として捉えられる心から共感できる言葉を見つけ、言語化することが重要です。
ステップ2:共感の醸成
パーパスを社員一人ひとりが自分ごととして捉えられるよう、継続的にワークショップを実施します。ブックやムービーを活用することも有効ですが、このステップでは、トップダウンによる一方的な説明ではない双方向のコミュニケーションが鍵となります。
ステップ3:日常業務への落とし込み
パーパスを、日常業務や評価制度、目標設定などに組み込み、パーパスの実践が評価やキャリア形成につながる仕組みを整備します。ロールモデルとなる個人やチームを表彰するなど、具体的な行動に移せる形まで落とし込むことが成功の要件です。また、現場リーダーのマインドセットと実践が、全体への浸透において重要な役割を果たします。
ステップ4:継続的な改善
パーパスの効果を定期的に測定し、必要に応じて改善を図ります。エンゲージメント指数や離職率などの定量指標と、社内コミュニケーションの活性状況といった定性指標の両方で評価することが重要です。

失敗パターンから学ぶ
表面的な理念にとどまる
美しいパーパスを掲げても、実際の日常業務へ反映されず「絵にかいた餅」として受け取られてしまうケース。
トップダウンの押し付け
経営陣がトップダウンで一方的にパーパスを決定し、社員の共感を得られないケース。
継続性の欠如
パーパスは掲げたものの浸透策の設計・運用が十分でないケース、短期間で効果を求めすぎて取り組みが中断してしまうケース。
これらを避けるためには、社員参加型のプロセス設計、評価制度との連動を含めた具体的な日常行動への落とし込み、長期的な視点での継続的な取り組みが必要です。

これからの組織に求められるマネジメント
パーパス・マネジメントは、社員一人ひとりの多様な価値観を尊重しながら、組織全体の持続的成長を実現する新しいマネジメント手法です。パーパスが組織と社員一人ひとりの「バックボーン」となり、日々の意思決定や行動の価値判断基準として機能していることが重要です。働き方の多様化や社会課題の複雑化が進む中で、パーパス・マネジメントの重要性はさらに高まることが予想されます。従業員一人ひとりが自分の仕事に誇りと価値を感じ生き生きと働ける組織を作ることが、これからのマネジメントの最終的な目標です。
著者
最新コラム

- 海外販路開拓の具体的な方法4選!成功させるための戦略と手順を解説

- タイ進出を成功させるメリットと3つの注意点|進出前に知るべきリスクを解説

- バリューチェーンの重要性とは?最適な構築方法のポイントを解説

- 中期経営計画の期間は何年が最適?成功する策定のポイントを紹介
ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと
進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド
~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド
~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド
~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~
 長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト
長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト