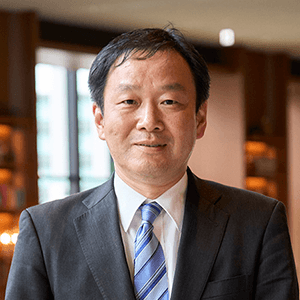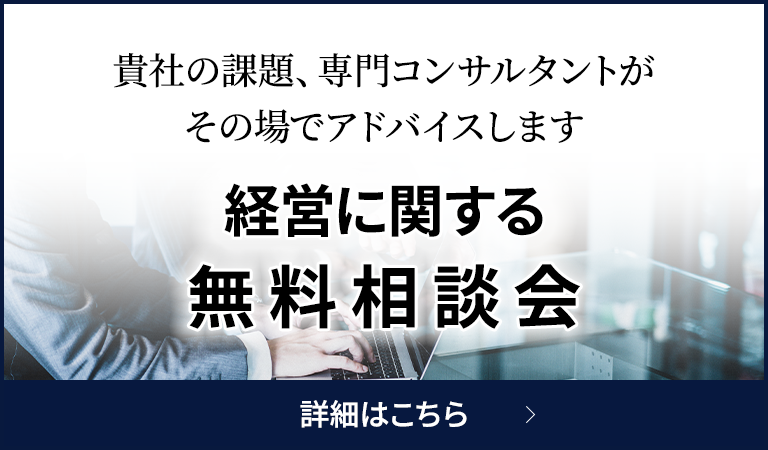企業存続のカギを握る「事業承継」のコツ
- 事業承継

閉じる
本コラムは『THE GOLD ONLINE』の寄稿原稿です。
東京商工リサーチによると、後継者不在が原因で倒産する企業が2024年に過去最多を記録。少子高齢化などを背景とした「後継者問題」が深刻化するなか、これまで以上に「事業承継」の重要性が高まっています。そこで、事業承継の成否を左右するポイントについて、詳しく解説します。
"継ぐなら長男に"は過去の話...刻々と変化する「経営環境」
事業承継は一品一様であり、コンサルティングの現場でもそのように感じることが多い。譲る側も譲られる側も、1度きりの経験である。名経営者であっても、事業承継がうまくいかないことが多いのが現実だ。
講演会で「兄弟経営は、40歳までは仲良く、50歳で自分の考えが定まり、60歳で喧嘩し、70歳で裁判になることが多い」と話すとあきれ笑いが起こるが、実際にこのようなケースは多い。
「娘婿」への承継が増えている
また、ここ10年ほどで、娘婿への承継も増えている。かつては、息子や娘が2人以上いる場合、長男に継がせたいケースがほとんどであったが、長女の配偶者に継いでもらうほうがいいと考える親が増えているのだ。
ただし、この場合は株式の問題が発生する。親としては、株を娘婿に渡したくないという気持ちがあることが多く、さらに万が一婚姻関係が破綻した場合、株の所有者が変わることで新たな問題が生じるからである。
一方、娘婿が株式を持たない同族の社長であれば、娘婿はいつでも首を切られる存在として不安を抱え続けることになる。
少子化は深刻...「採用」は「営業」よりも難しい
経営環境が変われば、会社経営の価値観も変えていかなければならない。
たとえば、とある市の今年の出生数が202人、小学校6年生の人数が798人であった。この数字が示すのは、干支ひと回り(12年)で出生数が4分の1になっており、将来的に若い人の採用が難しくなることが予想できるということだ。
実際、「採用が難しくなった」という声は多い。企業にとって、若い人材の採用は最重要課題だ。「採用活動は、営業活動より難しい」といっても過言ではない。
営業はお客様から選ばれるための活動であるが、採用もまた、学生や求職者から選ばれるために行うものだ。営業も採用も、ともに「会社が社会から選ばれるため」の活動とも言い換えることができる。
経営者は、会社が主体となって"採って、用いる"採用ではなく、入社希望者が"選ばれて、貢献したい"と思うような採用活動へ、価値観を転換させるべきだろう。
事業承継のファーストステップは「いつ承継するか」
あなたが現経営者であれば、まずなにを決めるべきか。会社には倒産、廃業、売却、存続と潰れるか、やめるか、売るか、続けるかの4つの選択肢しかない。
存続させる場合には、いつ、誰に承継するのかを決める必要がある。ここを決めなければ、具体的な対策を打つことはできない。つまり、経営者がゴールを決めることが最初のステップだ。
筆者も多くの顧客から事業承継の相談を受けてきたが、もっとも重要なのは「いつ承継するのか」であった。これを決めてはじめて、「後継者育成」「経営人材育成」「ホールディング経営などの組織・体制づくり」「M&Aでの売却」「IPOやMBO」など、取り組むべき項目が定まる。
方向性を定めることで、事業・人・組織のあり方が決まっていくのだ。
経営者が変われば企業の「意思決定ポイント」も変わる
経営者が変わることで、企業は良くも悪くもなりうる。なぜなら、企業は"環境適応業"であり、経営者の判断が変われば意思決定のあり方も変わるからである。
新しい経営者が前経営者とは異なる答えを出せば、その結果成功する場合もあれば、失敗する場合もあるだろう。
また、組織は現経営者に意思決定が近く、かつもっとも優秀な人物が経営トップを受け継ぐと思われがちだが、実際はそうとは限らない。特に同族企業の場合、親子の考え方が異なるケースも多い。
新たに経営者となった子どもは、親の判断基準を否定することからスタートしてしまい、それにより現在の経営幹部との信頼関係を失い、価値判断の揃わない組織が誕生してしまうことになる。
たとえば、70歳の社長と40歳の専務が交代する場合、同時に役員も変わるということはほとんどない。そのため、40歳の新社長は、会長や現在の役員を否定するか、気を遣うかで数年間を過ごし、リーダーシップを発揮できないケースが多い。
「会長派」と「社長派」の二頭政治になるケースも多くみられる。
こうなると、最終的に企業の意思決定は中途半端なものになってしまう。
創業は易く、守成は難し...「承継技術」が企業存続を左右する
"創業は易く、守成は難し"
この考え方は、中国の古典『貞観政要』に由来する。唐の太宗が臣下に創業と守成のどちらが難しいかを尋ねた際、魏徴という臣下が「守成のほうが難しい」と答えた。これは、事業承継を端的に表す表現といえる。
現代の表現であれば、創業は新築、承継はリフォームと言い換えてもいい。新築の場合、図面を引いて、建前をして、内装、外装と工事を進めていくが、リフォームの場合は、家に住みながら工事を行う必要がある。
前社長や古参の役員が残りながら新体制に引き継ぐ「事業承継」は、まさにリフォームといえるだろう。
ここでやってはいけないことは、切ってはいけない柱を切ること。大黒柱を切ってしまえば、その瞬間その家(企業)は成り立たなくなってしまう。
承継と同時に行うべき「ビジョン」の発表
なお、実際に事業承継を行った際には、同時に「長期ビジョン」を発表することを推奨する。
自分はこれからどんな会社にしていきたいのか、なにを目指しているのか......組織の新しいリーダーとして方向性を示すことで、価値観相違のリスクを小さくすることができる。このとき、中期ビジョンや中期経営計画として社内外に発表されるとなおいいだろう。
承継前・承継後、どちらもゴールを定めることが、事業承継をスムーズにするためにもっとも重要なことだ。承継とは未来を創ることだが、キャンバスにどのように描くかは自分しだい。事業承継のコツをおさえ、"守成"の第1歩を踏み出してほしい。
関連記事
-

物流業におけるROIC改善事例を解説!企業価値を高める方法とは?
- 資本政策・財務戦略
-

資本政策 事例|押さえるべき3つのポイントを事例を基に解説!
- 資本政策・財務戦略
-

組織における意思決定の種類とは?トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!
- コーポレートガバナンス
-

製造業における収益改善の2つの視点と5つのステップを徹底解説!
- 資本政策・財務戦略
-

-

収益改善の成功事例 | 効果的なポイントについて徹底解説!
- 資本政策・財務戦略
-

-

中堅企業が実装すべき財務戦略~ホールディング経営におけるトップのリーダーシップ~
- ホールディング経営
 コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト
コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト