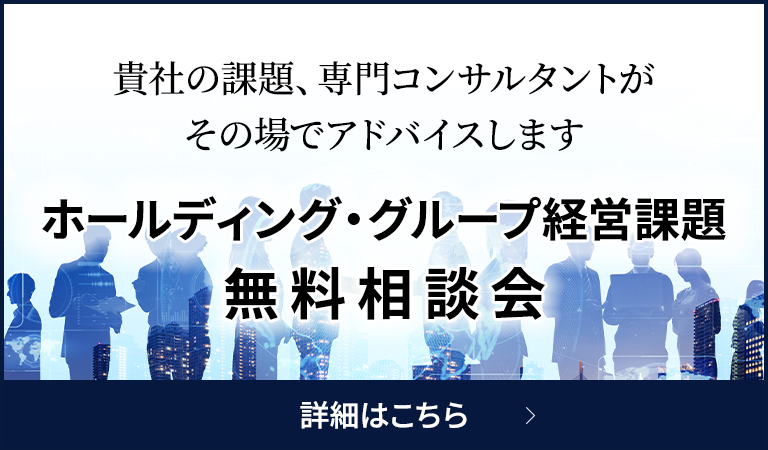組織再編の目的や手法、
実施する際のポイント
- グループ経営

閉じる
コロナを境にして外部環境の変化が激しくなった昨今では、組織再編を行う企業が増えています。実際、企業が持続的に成長していくためには、世の中の変化に合わせて事業戦略を変化させる必要があります。その事業戦略に合わせて、組織も変化させていかなければいけません。(組織は戦略に従う)
今回は、組織再編の背景と目的を整理したうえで、その手法や実施する際のポイントについて説明します。
組織再編の目的について
組織再編をする企業の背景や目的は様々ですが、大きく3点に分けることができます。まず、1点目は「競争力の強化」です。競争力とは他社に対していかに優位性を持つことができるかということであり、時にはM&Aなどで外部企業の力を使って競争力を強化します。当然ながら外部企業の力を使わずに、自社の力だけで競争力を強化できるような組織再編を行う場合もあります。具体的には新規事業の立ち上げ、DXやESG経営を推進するための専門部署の新設などが該当します。またグローバルに展開している企業では東南アジアやヨーロッパなど地域ごとの特性に応じた組織体制を整備することも該当します。
2点目は「経営効率の向上」です。経営効率を向上させるためには経営資源の適正配分が必要であり、時には不採算事業の整理や譲渡など採算性の低い事業から撤退することも経営効率の向上には必要です。また何社も企業を保有しているグループ企業ではグループ内の重複した事業や業務を整理し、重複を解消することで経営資源の有効活用を図ることがあります。グループ内の企業数が増えれば増えるほど、組織が複雑化し、意思決定のスピードが低下することになります。そのため、組織再編を通じて業務プロセスを簡素化し、権限や責任を明確にすることが重要になってきます。
最後に、3点目は「人材活用の最適化」です。組織再編は従業員の能力を最大限引き出すための手段としても使われるケースがあります。適正配置を行うことができれば、エンゲージメントが向上し、組織全体の生産性の改善、ひいては企業価値の向上にも繋がります。またジョブローテーションなどを通じて、組織や人材の活性化を図るケースもあります。まずはそれぞれの組織においてどのような人材がほしいのか、(人材ビジョン)を明確にした後に、現状とのギャップを把握することが必要です。
組織再編の手法について
実際に組織再編を行う際には、その目的に応じて適切な手法を選択することが必要です。ここでは「組織構造の変更」「部門の統廃合」「外部リソースの活用」という3つの観点に分けて説明します。
まず、組織構造の変更について説明します。弊社では企業規模の成長や事業戦略に伴って組織構造を変えるべきと提言しており、組織構造は機能別組織、事業部制組織、マトリクス型組織などに分けることができます。機能別組織とは、業務内容や機能ごとに部門が分かれている組織を指します。具体的には営業部、製造部、総務部のように分かれている形態です。事業部制組織とは、製品やサービスごとに部門が分かれている組織を指します。具体的には○○事業部という部門が複数存在する形態です。事業部制組織がさらに成長して、事業部から会社へと進化してホールディングス化するケースも多く見られます。最後にマトリクス組織というのは機能別組織と事業部制組織を組み合わせた組織のことを指し、複数の指揮命令系統が存在します。企業の成長に伴って、機能別組織から事業部制組織やマトリクス組織へと進化していくケースが昨今は多く見られます。
よく「どの組織構造が一番良いのですか?」という質問を受けますが、それぞれメリットとデメリットは存在します。また、企業規模や事業戦略によっても異なりますので、一概にどの組織構造が良いとは言えません。大事なのは自社が置かれている状況によって組織を適正に変化させていくということです。
続いて部門の統廃合について説明します。重複する部門や非効率な部門を統合することであり、経営資源の最適化を目的に実施します。M&A実施後に同じ機能を持つ部門の統合や廃止を行ったり、収益性の低い事業を切り離したりすることも多くあります。グループ全体でいかに経営資源を最適化することができるかが重要な観点になります。
最後に外部リソースの活用について説明します。アウトソーシングやアライアンスの活用により組織の柔軟性を高める手法で、単純業務や非中核業務を外部委託することで中核業務に集中できる体制を整えるために行います。最近では経理業務などの間接業務を外部委託し、自社の限られた人員を営業などの直接部門に多く配置する企業も増えています。また、他社との連携により経営資源を共有しながら新たな市場を開拓するケースも出てきており、外部リソースの活用は新規事業創出のための重要なファクターになっています。
実施する際のポイント
以上のような組織再編を実施するためには、計画的に行うことが重要であり、後述する3点についても留意する必要があります。まず、1点目は「戦略との整合性」です。繰り返しになりますが、組織は戦略に従うという言葉の通り、組織は事業戦略を推進する最適な形になることが必要です。事業戦略を推進するうえで重要なファクターである、どの部署の誰が推進するのかが明確でないと、戦略を推進することができないからです。
2点目は「従業員の理解と協力」です。組織再編は従業員の反発を招く可能性を含んでいるため、組織再編の意義や目的を従業員には丁寧に説明する必要があります。また、時には従業員の声に耳を傾けることも必要であり、納得感を持たせることで推進力を高めることが重要です。
3点目は「実行後のフォロー」です。組織再編を実行したら終わりではなく、その後が重要です。運用状況を適切にモニタリングし、ブラッシュアップしていくことも必要であり、具体的には従業員のモチベーションや業務プロセスなどを確認し、必要に応じて改善していきます。
まとめ
以上が組織再編の目的や手法、実施する際のポイントになります。繰り返しになりますが、あくまで組織再編は企業が持続的に成長するために行うものであるため、しっかりと計画を立てて実施していくことを推奨します。
関連記事
-

物流業におけるROIC改善事例を解説!企業価値を高める方法とは?
- 資本政策・財務戦略
-

資本政策 事例|押さえるべき3つのポイントを事例を基に解説!
- 資本政策・財務戦略
-

組織における意思決定の種類とは?トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!
- コーポレートガバナンス
-

製造業における収益改善の2つの視点と5つのステップを徹底解説!
- 資本政策・財務戦略
-

-

収益改善の成功事例 | 効果的なポイントについて徹底解説!
- 資本政策・財務戦略
-

-

中堅企業が実装すべき財務戦略~ホールディング経営におけるトップのリーダーシップ~
- ホールディング経営
 コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト
コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト