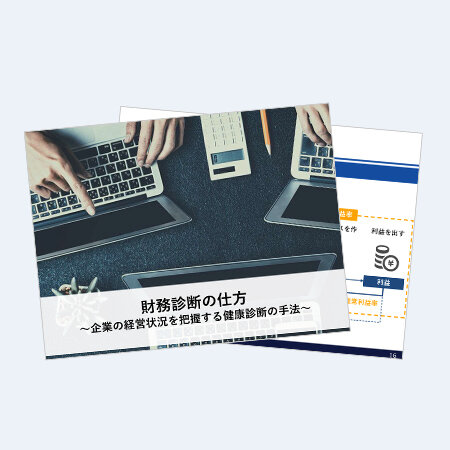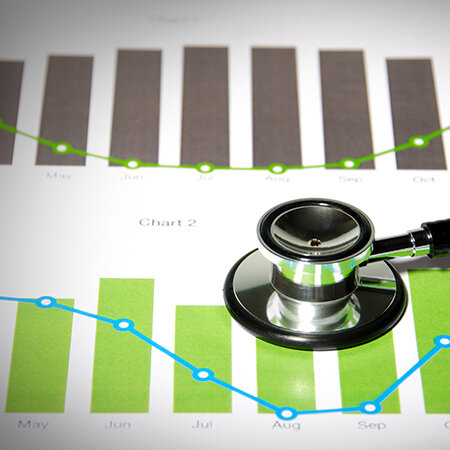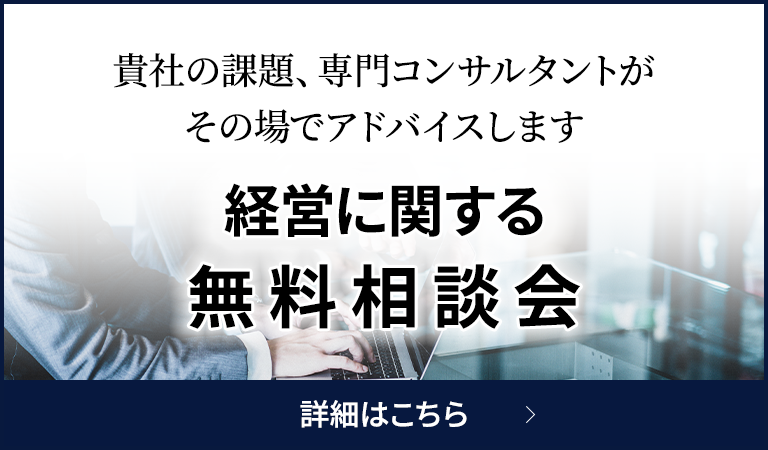業績管理の要諦と
成果を上げるための重要指標
- 企業価値向上

閉じる
米国大統領選でトランプ氏が再選したことで、海外輸入品の追加関税や減税恒久化に伴う財政収支の悪化、移民抑制による労働力不足で生じる賃上げ圧力など、米国経済のインフレ再燃と景気悪化への警戒感が強まっています。そのような不安定な経済環境下においても、自社業績の現在位置や目標値とのギャップを把握し、次の一手を早期に打つことが求められています。
業績管理の要諦とKPIの実務的運用
(1)先行業績マネジメント
不安定な経済環境下における業績マネジメント
現代はVUCAの時代と呼ばれ、経営における先行きが読みづらい時代となっております。VUCAとは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)という4つの単語の頭文字をとった言葉で、目まぐるしく変転する予測困難な状況を指しています。そのため、期首に掲げた予算に対して外部環境による影響が強く、ぶれが大きくなってしまい予算が形骸化してしまっている会社も散見されます。次年度の中期経営計画をローリングして都度軌道修正を図る方法も大切ではありますが、そもそも正しい業績マネジメントのサイクルを回せているか、自社の状況をチェックする必要があります。
策定した予算をもとに定期的な予実管理を行い、業績状況をモニタリングしている会社は多いと思います。しかし、業績モニタリングだけの実施では、➀過去の結果に対する確認、➁予算との差額の認識、といった情報共有にとどまってしまう懸念があります。業績モニタリングを攻めの経営に活用するためには、情報共有としての業績マネジメントから、予算達成に向けた業績マネジメントへとサイクルを変革していく必要があります。以下の2点が業績マネジメントサイクルを回す要諦となります。
期首に作成した予算と実績の差額確認を行うだけでは、期首の計画とこれまでの結果だけの対比となり、最終の業績着地が現在の延長線上となる恐れがあります。そのため、年間の業績における現時点での将来売上として確実な部分も織り込んで業績を先行管理し、期末の着地ないしは四半期ごとの着地と、どれだけ差額があるかを見極める必要があります。
将来の業績はわからないという会社が圧倒的多数であります。そのためまず初めにわが社の売上を「ベース売上」と「スポット売上」に分けて先行業績を作成していきます。安定収入や2か月以上の長期契約、季節的受注(セミナーやイベントの先行販売分など)をトップラインの売上で各月ごとにプロットしていき、あわせて経常的に発生する固定費や、スポットで発生することがわかっている費用も計上します。そして、これらを基に年間の変動損益計算書を管理会計ベースで作成します。そうすると現在決まっている売上高が先行して把握できますので、あとどれだけの売上・利益を積上げなければ、四半期や通期の業績が達成できないかを直接会計上の数字として把握することができます。これがいわゆる「先行業績マネジメント」です。
多くの会社が当月における予実管理のみの対応となり、現時点で予算に対し達成ペースかどうかの判断軸となっています。そのため、着地が読み切れていないケースが多く見受けられます。一方で、都度の売上計上いわゆるスポット売上が大半という会社も多いことは事実であります。この場合、会社の業績安定に向けたベース売上を計上できる事業開発の模索や、既存事業において「月別の過去*年平均売上」を基に売上予測を算出していくことが有効です。前年単体だとサンプルとしての偏りが生じるので、複数年の平均が良いでしょう。
(2)差額対策
差額対策でPDCAを回す
上記で記載した先行業績マネジメントの体制づくりを整えた後は、「差額対策」による業績マネジメントの実施が重要となります。先行業績マネジメントにより予実の差額が過去・現在・未来と把握できるようになります。業績未達となった月については、まず現状把握から行います。どういった要因により未達となったのかを冷静に分析する必要があり、未達となった部署や人を責める場では決してありません。的確な現状把握が出来ないと、対策として打つべき手も打てなくなります。
次に要因に対する差額対策を講じていきますが、ここも次月だけではなく先行業績マネジメントを活用して、通期・四半期での達成に向けて、どこでの売上が見込めるのかを見極めます。またベース売上が中心の会社は、どういったスポット売上で盛り返しを図れるのかという戦術を練る場となります。短期的な差額対策は現場の情報が重要になるため、現場メンバーを巻き込んだレイヤーでの会議体の設計も必要となります。会社全体での予算達成に向け、それぞれのレイヤーにいる人達が何をできるのかを考え、全社単位で取り組む組織作りも業績マネジメントサイクルを回すための大事な要素になります。
(3)戦略的KPIマネジメント
戦略と紐づくKPIマネジメント
正しい業績マネジメントサイクルを回すにあたり、そもそもの追っていく指標(マネジメントする対象)が会社の戦略や方向性と合致しているかどうかを確認する必要があります。例えば、会社が賃上げを持続的に行っていく方針であれば、人件費の成長率より粗利の成長率を伸ばしていく必要があります。一方、依然として各事業部の売上だけをKPIとして追わせている企業はまだまだ散見されます。会社の戦略として目指す方向(定性・定量含め)からブレイクダウンしたKPIツリーを作成することで、各事業部が追っている数字の達成が、全社として目標としている数値の達成に繋がっていきます。
KPI策定においては、BSC(バランススコアカード)を応用して、業績だけでなく会社として進みたい方向へ進めていくための総合的なKPIを策定することもできます。BSC(バランススコアカード)とは、「業績の視点」を起点に「顧客の視点」で何を追いかければ良いか、「業務プロセスの視点」で何を改善していくか、そしてそのために「人材と組織の視点」において何を整備する必要があるかといった「戦略マップ」をKPIと結びつけます。これにより、戦略的なKPIを策定することができます。例えば、M社では業績悪化した際に、再建計画内に、営業部だけでなく生産部(工場)における生産性改善につながるKPIを策定し、利益体質の強化に遂げることができました。このように何を目的にするか(戦略)とKPIは強く紐づくので、大方針にあったKPIの策定が不可欠です。
最後に
「先行業績マネジメント」「差額対策」「戦略的KPI」について、業績マネジメントにおける要諦をお話しさせていただきましたが、どれか一つでも欠けてしまうと適切な業績マネジメントのサイクルを回せず、全社の行動がバラバラとなり、業績達成が出来なくなってしまいます。いわゆる、経営層と現場がうまく繋がらないといった事象が発生します。
業績マネジメントにおける設計自体は経営層で行いますが、運用はマネジメント層を中心とした現場の方々に委ねられます。全社の方向性を統一し、不安定な経営環境下でも突破できる組織体制を作るためには、業績マネジメントが重要な役割を果たします。ぜひ自社の状況を今一度見直し、改善に向けた取り組みを進めてください。
関連記事
-

物流業におけるROIC改善事例を解説!企業価値を高める方法とは?
- 資本政策・財務戦略
-

資本政策 事例|押さえるべき3つのポイントを事例を基に解説!
- 資本政策・財務戦略
-

組織における意思決定の種類とは?トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!
- コーポレートガバナンス
-

製造業における収益改善の2つの視点と5つのステップを徹底解説!
- 資本政策・財務戦略
-

-

収益改善の成功事例 | 効果的なポイントについて徹底解説!
- 資本政策・財務戦略
-

-

中堅企業が実装すべき財務戦略~ホールディング経営におけるトップのリーダーシップ~
- ホールディング経営
 コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト
コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト