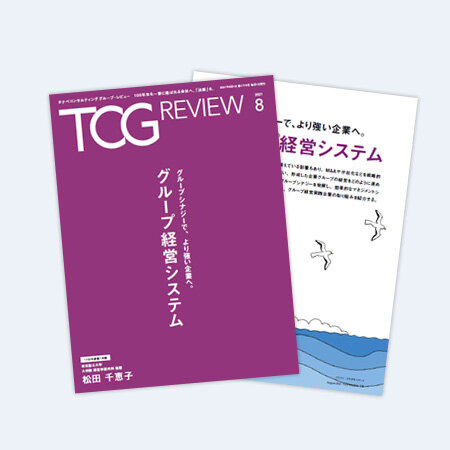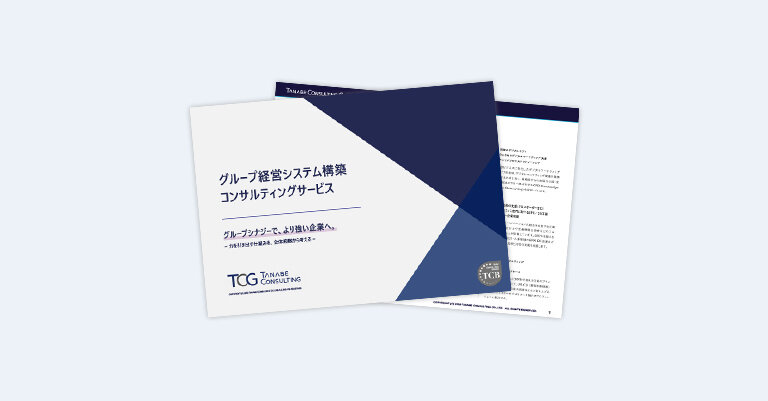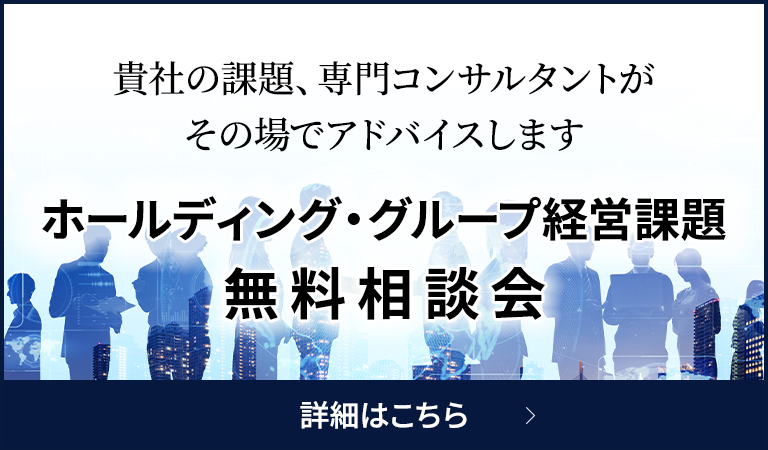シェアードサービス機能のデザイン
ホールディングス化を取っているが、本社及びグループ会社間で重複する業務が存在することでオペレーションコストが増加しているケースが多数見られ、いかにグループでの競争力を高めながらコストを最小化していくかがグループ経営では求められています。
- グループ経営

閉じる
シェアードサービスとは
シェアードサービスとは複数の企業・組織で実施している共通業務を集約させ、サービスを提供する企業変革のことです。シェアードサービスの起源は1980年代にアメリカのゼネラル・エレクトロニック(GE)と言われており、比較的新しい企業変革手法です。日本でも2000年代以降大企業を中心に取り入れており、近年では複数の事業・会社を保有する中堅企業でも導入され始めています。
シェアードサービスを行う組織体制と業務範囲
日本でシェアードサービスを導入している企業の組織手法は主に以下の2種類に分類されています。
1つ目は本社部門方式であり、業務を集約するシェアードサービスセンターを本社の一部門として設置し、社内やグループ会社内の間接業務をその部門に集約します。統括会社としての本社機能の維持や業務の効率化を目的とすることから、ホールディング会社を中心としたグループ組織再編を行う際にはシェアードサービス機能を設計することが多いです。
2つ目は子会社分社方式であり、シェアードサービスセンターを本社内に作らず子会社化することで企業として個別に財務諸表を作成するので、業績を数字で直ぐに把握することが出来ます。
尚、一般的にシェアードサービスの対象となる主な業務は
- 財務・経理業務
- 総務・人事業務
- 経営企画業務
- 情報システム業務
- 法務業務
であり、上記5業務以外でも間接業務で集約した方がグループ全体にとって適した判断であると考えられる業務があれば集約することも可能ですが、要はシェアードサービス導入に際しては具体的にどの範囲まで対象とするかが重要です。
シェアードサービスの目的
そもそも企業がシェアードサービスを行う目的は大きく分類すると以下の3点です。
1.コスト削減
グループ内の間接部門を1つに集約することで各社にあった間接部門を統合することが可能になり、人件費や設備コストが大幅に抑制されて、グループ全体の利益最大化に寄与します。
2.グループ業務の標準化
各社に紐づいていた業務をグループ本社に集約することでグループ共通業務(マニュアル)に昇華させます。
3.業務品質の改善
シェアードサービスセンターに間接部門の機能を集約することで、その部門に特化した人材による高品質な業務を行うことが出来ます。また業務が集中し業務量が増加することで、部門内で専門性が高まり更なる業務の品質向上も期待できます。
関連記事
-

事例から学ぶROIC経営の落とし穴とは?
- 企業価値向上
-

-

-

-

企業価値とは?意味と評価方法をわかりやすく解説
- 企業価値向上
-

-

なぜ企業価値向上が今必要なのか?背景と対策を解説
- 企業価値向上
-

ROIC経営の重要性とは?評価方法についても解説
- 資本政策・財務戦略
 コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト
コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト