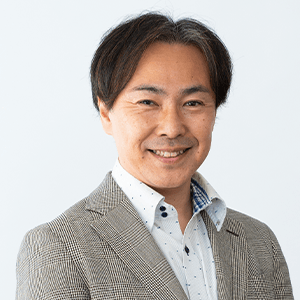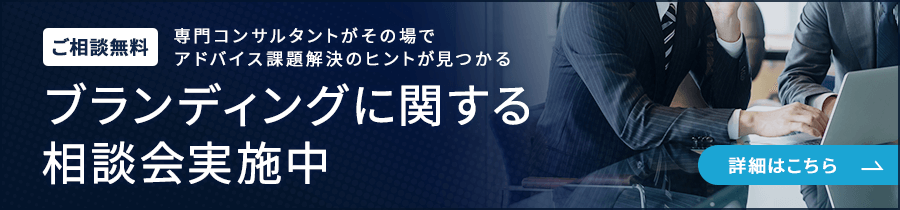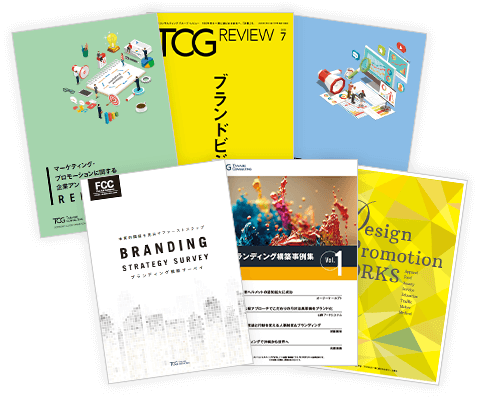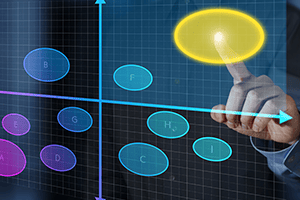閉じる
近年、経営課題として「人材の採用」や「定着率の向上」を挙げる企業が増えています。背景には労働市場の変化、具体的には少子高齢化にともなう生産年齢人口の減少、インターネット・ソーシャルメディアの普及、働き方・テクノロジーの変化などがあげられます。本コラムでは、人材の採用や定着率の向上に関係する現在の時代背景と、企業がとるべき対策を考えていきたいと思います。
急速に変化し続ける社会環境と求職者の価値観
冒頭述べたように、近年、経営課題の優先事項として、人材の採用や定着率の向上をあげる企業が増えています。
その理由としては下記のようなことが考えられます。
総務省の「日本の将来推計人口」によれば、日本の総人口は2020年の国勢調査による 1億2,615万人が2070年には8,700万人に減少すると推計されています。これは今後50年間で人口が約3分の2に減少することを意味します。また、総人口に占める65歳以上の人口割合(高齢化率)は、2020年の28.6%から、2070年には38.7%へと上昇するとされています。
2.インターネットとソーシャルメディアの普及(1)インターネットとソーシャルメディアの普及
求職者は企業の評判や文化をオンラインで簡単に調査できるようになりました。求人サイトなどのプラットフォームを通じて、企業の内部情報や社員の声が広く共有されています。
(2)口コミの影響力
ソーシャルメディア上での口コミやレビューが、企業のイメージに大きな影響を与えるようになりました。これにより、企業はポジティブなブランドイメージを維持するための戦略が求められています。
ミレニアル世代・Z世代は、企業の社会的価値や働きがい、自己成長の機会を重視する傾向があります。企業はこれらの価値観に応えるためのブランディングが必要になってきました。また、リモートワークやフレックスタイムなど、柔軟な働き方が求められるようになり、これらに対応した働き方の設計とその発信が求められるようになりました。
このような時代背景から、従来の採用活動(代理店まかせ、現場まかせ)では通用しなくなってきています。組織が競争優位を獲得し、自社戦略にもとづいた人材を確保するには、その募集・選抜プロセスのマネジメントが重要となっています。施策レベルの改善ではなく事業戦略レベルからの落とし込みをして、川上から川下まで一貫した採用戦略を行わなくてはなりません。
採用戦略設計の全体機能を支える5つの役割
川上から川下までぶれない自社の世界観を届け続ける仕組みづくりとは
採用戦略は、川上から川下まで一貫したメッセージ(世界観)を伝える仕組みづくりと申し上げました。
では、そのような仕組みはどのように、また、何から検討すれば良いのでしょうか?下記5つのカテゴリーを参考にしてみてください。
1.募集・選抜プロセスのマネジメント
人物要件の定義、母集団形成、応募者対応などのプロセス全般をマネジメントする仕組みを構築します。このフェーズが採用戦略の中心となり、以下の4つのカテゴリーをハンドリングする役割を果たします。
2.事業戦略と採用の整合性を整理する
事業戦略と採用活動との一貫性を調査・設計します。経営理念やビジョン、パーパスからなる自社の世界観を、ペルソナへ刺さるメッセージやビジュアルに変換して一貫性を醸成します。
3.伝え続ける仕組みを作る
上記2.で考えた、メッセージやビジュアルを、誰が・何を・どのように・いつなどレギュレーションも含めて決定し、伝え続ける仕組みづくりを行い実行します。
4.採用戦略の振返りとアップデート
目標(KPI)を設定し、上記の取り組みの成果を確認し、状況に応じて内容の見直し・リトライを行い、PDCAを回していきます。
5.採用組織の構築
前述したように、近年の人材採用は、施策レベルではなく事業戦略の一貫でないといけません。そのため、社長・リクルーター・面接官など縦組織と横串の組織の設計で、採用活動を行う組織や運営方法を決めておきます。
上記の5つのカテゴリーを1つの海図として考え、全員で共有し推進していくことが重要です。
魅力ある世界観の創造
「つまらない」「刺さらない」「ピンボケ」な世界観では意味がない。「わくわく」を感じさせるメッセージとは‼
前述したように、採用ブランディングは5つのカテゴリーから検討することが、効率的に成功に導く方法だとお伝えいたしました。また、一貫したビジョンを事業戦略として全員が共有し、内外に発信し、自らも実践している状態がより採用戦略を力強く推進できることもお話させていただきました。
しかし、理念・ビジョン・パーパスなどから世界観(コンセプト)をつくり、ターゲットに向けてメッセージ・ビジュアルを発信するクリエイティブな部分に関しては、いくらカテゴリー通りに検討したとしても、この部分が「つまらない(刺さらない)」「ピンボケ」など、ターゲットに対して世界観の「影響力」「衝撃」「力強さ」がなければ、いくら効率的なプロセスを踏んで検討しても、本末転倒となってしまいます。
ですので、この部分に関しては、検討する人の中にクリエイティブ(デザインやワードなどについて)な方、外部の広告代理店やコンサルティング会社といった経験と事例が豊富なプロフェッショナルと一緒に作り上げる事をお勧めします。また、最近の企業コンセプトやメッセージをみますと、ふんわりした・わかりにくいものも多く見受けられます。
よりわかりやすく、かつ「影響力」「衝撃」「力強さ」を感じられるデザインやメッセージがより、ターゲットに刺さるものではないかと考えます。
下記に私が、良いなと感じている事例を挙げます。
1.「お値段以上ニトリ」
皆様ご存じの、ホームセンターの「ニトリ」です。このフレーズに込められた、お値段以上の「価値」「満足」「品質」「体験」「信頼」といったものが、リーズナブルに提供されているのだという意思に、ユーザーの誰もが共感できるのではないでしょうか。
2.「最高のコストパフォーマンスを提供します」
「おいしい料理は良い素材から。トリュフ、フォワグラ、キャビア、などなど高級食材をふんだんに使用し、至極の料理をご提供いたします。どこでも体感できない最高のコストパフォーマンスを是非感じてください。」というメッセージとともに、今まで中間層では敷居が高かった、食材をリーズナブルなお値段で提供している「俺のイタリアン」のコンセプトになります。ここでの体験は「非日常」を感じさせてくれそうなフレーズで非常に共感できます。
3.サードプレイス
ブランディング事例ではおなじみとなっている、スターバックスのコンセプトです。ファーストは家、セカンドは会社、第3の場所としての空間の提供といった意味合いでおなじみのフレーズですが、非常に共感をもてるので改めてご紹介させていただきました。
最後にタナベコンサルティングの事例を紹介をさせていただきます。
タナベコンサルティングのメッセージには「We are Business Doctors」「その決断を、愛でささえる、世界を変える。」といったものが有ります。前者に関しては、私も事あるごとに、先輩方から「タナベは病院で例えれば、外科もあれば内科・循環器科・小児科などのスペシャリスト人材が、診察・治療をすることができる企業の総合病院だ」と教えられてきました。それを今の時代に変換したワードで表現しており、後輩達に伝承され、外部にも洗練されたメッセージとして打ち出した良い例かと思います。
また「その決断を、愛でささえる、世界を変える。」は、弊社のパーパスであり、経営理念に「企業を愛し」「世界への道を開く」というのがありますが、そこから変換されている事例になります。
これらに共通するのは、どれも「わくわく感」「衝撃」「影響力」を感じさせてくれ、かつわかりやすいと言うことです。ビジュアルに関しても、弊社のWEBサイトを見ていただければと思いますが、やはりそのメッセージを表現した洗練された内容になっており、イメージをうまく表現しています。どの媒体を使う際も、一貫したレギュレーションを設計し発信しているので、発信をするたびにイメージが変わったり、全くお門違いなメッセージになることはありません。
繰り返しになりますが、いくらプロセス通りに検討し、コンセプトやストーリー・レギュレーションを設計したとしても「わくわく感」や「衝撃的」なものにできなければ、ターゲットに響かず、失敗に終わる確率も高くなります。成功させるためには、外部パートナーの活用をお勧めします。よく「トップダウンで決めて発信」という手法をとり、若手世代に響かず失敗に終わる事象をよく見ます。それを回避するためにも、一緒に考えまた経験豊富な外部パートナーと一緒に進めることをお勧めいたします。
少子化高齢化、価値観の多様化、テクノロジーの進化が企業に小さくない課題となっている時代です。良い人材は施策レベルでは確保できない。まして、ミスマッチで定着率が悪いとなると、企業体力がますます疲弊してしまいます。場合によっては、カルチャ―の創造、リライトの検討も必要になってくるでしょう。
人材採用は、企業戦略として中長期の経営計画に落とし込み、川上から川下まで一貫したメッセージ(世界観)を伝えつづける仕組づくり。あわせて、刺さる(わくわく感のある)メッセージ・ビジュアルといったクリエイティブを検討していただくことをお勧めします。長くなりましたが、このコラムが少しでも課題の解決につながれば幸いです。
 ブランディング・戦略PR情報サイト
ブランディング・戦略PR情報サイト