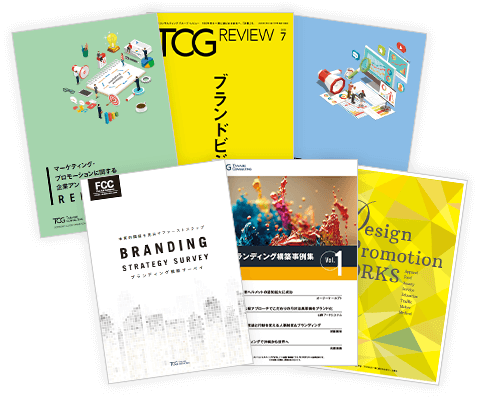閉じる
ナラティブは、「物語」「語り」といった意味を持つ言葉で、語り手自身を主役とした物語を表します。ビジネスシーンでは、「ナラティブマーケティング」「ナラティブアプローチ」といった言葉で使われ、様々なシーンで問題解決に活用されています。「ナレーター」や「ナレーション」は、ナラティブから派生した言葉とされています。
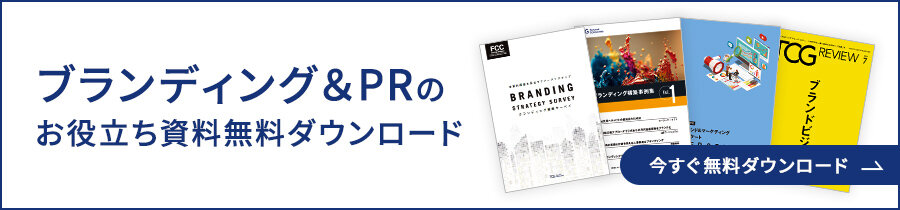
「ナラティブ」とは何か?
ナラティブアプローチ。本当の物語の主人公はだれ
ナラティブはもともと、1960年代にフランス文化(フランス構造主義)における「物語の役割」について関心が高まるなか、「ストーリー」とは異なる文芸理論上の用語として、定着したと言われています。
そして、現代では文学の領域を超え、医療や教育の分野で使われるようになりました。
医療分野では、医師と患者の対話方法として「ナラティブアプローチ」として提唱されて今にいたっています。患者を物語の主人公としてとらえ、自分の病気とどう向きあっていくかを話し合う方法です。
教育現場では、教師ではなく、生徒を主人公とした物語にシフトをして、枠組みに子供が適応するのではなく、教師は生徒をサポートして、主体的に考える力を伸ばす教育へと変化しています。
物語の主人公を医師から患者へ、教師から生徒へと物語の主役変更が重要なポイントです。
ストーリーとの違い
「ストーリー」は、物語の内容や筋書きです。そしてあなたはオーディエンス(聴衆)です。物語にあなたはいません。「ナラティブ」では、あなたが主人公で、一緒に物語を作る演者です。
そして、「ストーリー」は起承転結のある終わりある物語ですが、「ナラティブ」はあなたがつむぐ現在進行形の物語です。
マーケティングにおいて、なぜナラティブが注目されるのか?
ソーシャル時代がやってきた
2007年にiPhoneが発売されて以降、スマートフォンの普及と、SNSの浸透により、コミュニケーションの取り方が大きく変容しました。それにより、企業からの一方通行の情報発信(広告など)では、顧客を惹きつけることが難しくなってきています。その反面、企業が消費者と直接コミュニケーションをとることも容易になり、マーケティングにおいて、企業と消費者の関係性を見直す必要性がでてきました。そのような中で、顧客を主人公とする「ナラティブ」が注目されています。
さらに、コロナ禍期間に、従来のような対面でのコミュニケーションが容易にできなくなり、企業としてこれまでと異なる情報発信として、消費者の共感や信頼を獲得しやすい手法としてSNSの活用が促進され、ナラティブの活用が加速した側面もあります。
一緒に社会を作る共創関係
2015年の国連サミットで採択されたSDGsやESGsなどの社会課題への注目が広がっている中で、企業だけでなく、個人においても「社会貢献」や「社会的価値」に意識を向ける人が増加しています。「社会において自身ができることはなにか」を考える中、自身を物語の主役として考えるナラティブの重要性が高まっています。
企業と個人が共創して持続的社会を実現していく環境が生まれつつあります。
ナラティブマーケティング事例
味の素冷凍食品「冷凍餃子フライパンチャレンジ」
きっかけは、ひとつのSNS投稿
ナラティブマーケティングの事例として、「冷凍食品は手抜き? 手間抜き?」論争も巻き起こした、味の素冷凍食品が行った、「冷凍餃子フライパンチャレンジ」を紹介します。
これは、2023年5月に、味の素冷凍食品の「ギョーザ」がフライパンに張り付いてしまったという、ひとつの SNS 投稿から始まった「ギョーザ」の永久改良を目指すプロジェクトです。
失敗なく羽根つきギョーザが焼き上がる感動を皆さまにお届けすることを目指している味の素冷凍食品は、「検証のために張り付いたフライパンを送ってほしい」という呼びかけをしました。そうしたところ、全国から多くのフライパンが届き、そのフライパンの検証を通じて、商品改良に取り組まれました。
結果、2024年1月9日(火)に、取り組みの成果として、「ギョーザ」のリニューアルを発表されますが、その経緯もプロジェクトサイトやNote上で公開されています。
まとめ
企業とクライアントが共に体験して創り出す!
「ギョーザ」を調理して食べていただく、ユーザーを主人公として、企業とユーザーが共に、商品リニューアルに取り組む様子が印象的です。また、それを、現在進行形としてプロジェクトサイトやNote上で見られることが、同じ体験を一緒にすると言う、重要な要素ともなっています。
「主人公はだれか?」や「終わらない物語」を表現した良い事例ではないでしょうか。
皆さまもぜひ参考に、ナラティブマーケティングを理解いただくと共に、ぜひ自社でも取り組んでみてください。
AUTHOR著者
ブランド&PRコンサルティング事業部
ゼネラルマネジャー
椋野 啓司
CRMとして顧客データ管理や、関係構築強化に従事。プロモーション活動を推進し、リード獲得、ナーチャリングに寄与。現在は、プロモーション戦略の推進・運営に携わり、マーケティングサイトの運営含め、デジタル化に取り組む。顧客との新たなコミュニケーションモデルを構築し、価値創造を推進する。

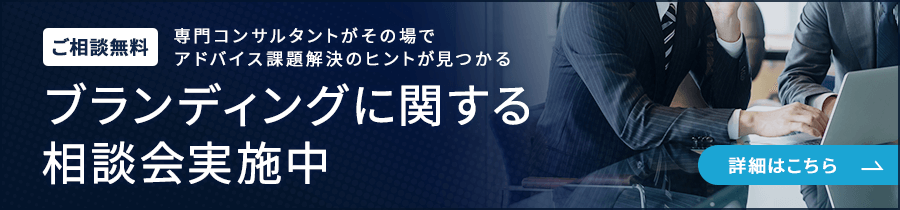
 ブランディング・戦略PR情報サイト
ブランディング・戦略PR情報サイト