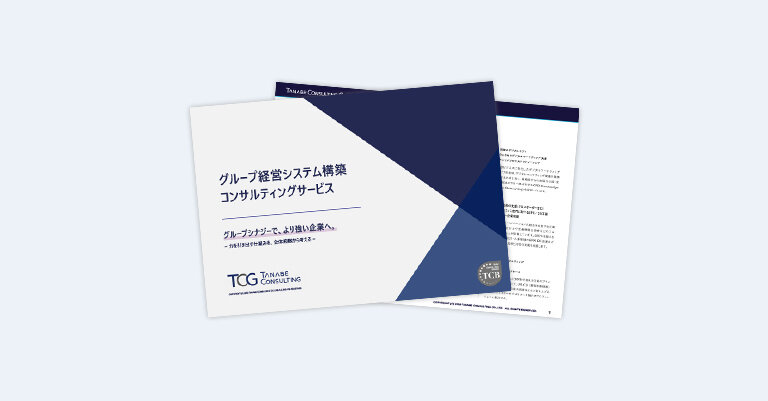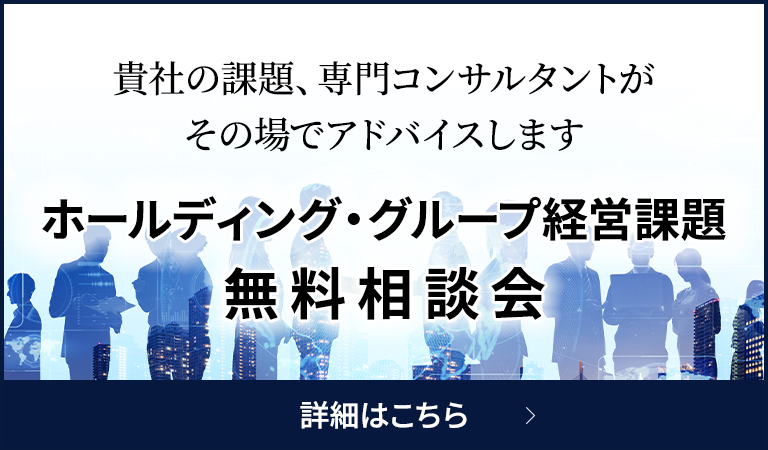今、なぜグループ経営が求められるか?
- グループ経営

閉じる
昨今の経済環境変化は目まぐるしいものです。100年に1度と言われる変化が当たり前のように発生します。
記憶に新しいところでは、為替相場です。4月29日に1ドル160円台への突入という未曾有の円安水準を記録しました。
また、2024年3月の日本銀行金融政策決定会合では、マイナス金利政策が解除され、17年ぶりに‟金利がある世界"が戻ってきました。
今後の金利上昇に加え、今や当たり前になった人手不足の中、さらには30年ぶりのインフレ経済への突入という環境変化が起きている中、中堅・中小企業においてはこれまでとは異なる考え方・価値観を持って、「ヒト」「カネ」という経営資源をいかに効率化できるかが今後の成長の重要なポイントです。
また、1つの事業だけで持続的な成長を描ききれる時代でもなくなりました。複数の事業でバランスを取りながら成長する"多足事業体"とも言える体制が必要となっています。その際多くの経営者が考えられるのが、‟グループ経営体制"です。本稿では、グループ経営体制とは、複数の事業を営みながらも、グループとしての方向性が一致しており、グループ本社機能を集約・強化・マネジメントしていくことで、‟単純な足し算的集合体"ではなく‟グループシナジーをもった掛け算的集合体"で利益の最大化を目指していくこと、と定義します。グループ経営体制の目的は、‟グループ利益の最大化"と捉えておいてください。
それでは、グループ利益の最大化に必要となるグループシナジーの掛け算的集合体について整理します。
本稿ではグループシナジーを大きく6つに分類します。
①規模の経済
グループ共同購買による単価引き下げ、ベンダーに対する発言力の強化
②ブランドの共有
知名度のあるブランドを共有することによるステークホルダーからの信頼獲得
③ノウハウの共有
製品・サービス技術の転用等、既に獲得しているノウハウの転用や共同利用
④経営基盤の共有
シェアードサービスやネットワーク基盤等の共有
⑤バリューチェーンの強化
グループでワンストップサービス等付加価値を高めることで販売機会を獲得していく
⑥最適資金配分
グループ間の資金移動による余剰資金や不足資金の解消
単一事業だけでコスト競争力を高める、付加価値を高めるためには限界があります。
現在の経営環境を踏まえると、複数事業で上記のようなシナジーを生み出す戦略こそが持続的な成長に不可欠であることは経営者の皆さまにはご理解頂けると思います。
グループシナジーを最大化するための手段としてのグループ経営システム
グループ経営体制構築に向けた課題・ハードルとは
グループ経営体制が有効であることは多くの経営者は漠と理解されることと思います。
しかしながら、なかなかその体制構築が進まないのが現状です。
その理由は大きく以下の3点です。
① グループとしての一体感の欠如
(グループ全体を方向付ける経営方針や戦略がなく、グループ各社の「部分最適」が優先されている)
② グループ会社は増えたが、全体で間接業務が重複しておりオペレーションコストのムダが多い
(グループ全体をマネジメントする仕組みがない)
③ グループ経営企画機能・人材の不足と事業会社の経営者人材の不足
(経営者と同じ考え・視点でグループ各社の個性を活かし、とりまとめる人材が確保できない)
特に①が不足している会社は、何をやっても‟行き当たりばったり"な施策に終始し、
ただ寄り集まっているだけの烏合の衆的な、ただの企業集団となってしまいます。
本来望む方向とは全く逆の結果を招くことになりかねないため、注意が必要です。
こういったことを避け、グループをあるべき姿を導くための基本を解説します。
ポイントは大きく5点です。
①グループ理念~グループ共通の価値判断基準を確立し、1つに方向付ける~
自社グループが、
・どのように顧客・社会へ価値を提供していくか(=Mission)
・どのような姿を目指していくか(=Vision)
・そのためにどのような行動指針(Value)を掲げるか
自社グループたる所以(一種のアイデンティティ)を策定し、グループ内外に発信・浸透し続けることが重要です。
②グループ経営企画機能~グループ全体の司令塔を明確にする~
グループ全体の戦略・方針策定と計画立案ならびに運用と管理部門を確立します。
具体的には、グループビジョンマネジメント、事業ポートフォリオ(資源配分)の決定、
グループ予算の策定、ブランディングをどのように実施・運用していくかのルールを設計・運用していくことです。
③グループガバナンス~グループ各社をグリップし、部分最適に走らないよう牽制する~
決めたことを確実に実行し続けることでグループ組織としての結束が強化され、シナジー発揮に繋がります。
そういった意味でグループガバナンス構築は非常に重要な要素です。
グループが拡大すればするほど、ガバナンスの構築・運用徹底は難易度を増していきます。
グループとしてのルール・意思決定プロセス・責任と権限の明確化等がガバナンスにあたります。
より具体的に言うと、例えばグループ本社とグループ各社の、‟どちらにどこまでの責任と権限を持たせるか"
‟その意思決定は、どの会社の誰がするのか"‟グループ全体の意思決定機関はどこか"等が挙げられます。
それ以外にもコンプライアンスの徹底、リスク管理や各社の監査等を含めたグループ全体の目付け機能を担います。
④グループマネジメント~グループ各社をモニタリングし、評価・コントロールする~
先ほど申し上げたグループ経営企画機能は、グループ全体の戦略や方針策定・運用管理をするのに対して、
グループマネジメントにおいては、グループ各社の業績向上の設計をしていきます。
具体的には、グループ管理会計システム、業績マネジメント、人材マネジメント、CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)などです。仕組み自体の構築も重要ですが、人に頼らないシステム化も見据えた設計が不可欠となっています。
⑤シェアードサービス~業務集約化により全体の生産性を向上させる~
グループを形成しながらも業務の共通化をしないのは、まさに「もったいない」状態です。
我が国において人手不足が解消する見込みは限りなく低く、限りある資源を有効活用する仕組みを構築するのは、
もはや当たり前の領域になっています。その手法がシェアードサービスです。
当然、グループ各社でビジネスモデルが異なることから全てを一元化できることはなく、グループ各社に
オペレーション業務を残すこともあります。一般的には、総務・経理・人事・システム関連部署はグループ本社に集約します。
そうすることで、グループ各社は本業に資源を集中投資でき、より自社グループの持つ価値を顧客に提供するチャンスを増やしていくことができます。
人の集まりが組織・企業グループである以上、意思統一は不可欠
大きく5点のポイントを解説しましたが、まず着手すべきは①のグループ理念の確立です。
グループ経営体制構築に苦労する会社の多くは、グループの理念がそもそもなかったり、中核企業の理念をそのまま引用しています。
グループ形成の過程が、M&Aにせよ分社化にせよ、ビジネスモデル・歴史・DNAが同じ会社は2つとありません。
そして、人の集まりが組織・企業・グループである以上、その方向性を統一しなければ霧散してしまいます。
人手不足、‟金利のある世界"、インフレ経済にある現在において、ヒト・カネに対する考え方は180度変える必要があります。
そしてグループ経営体制の構築は、今後の中堅・中小企業の持続的成長に向けた最善手です。
先ほど申し上げた5つのポイントを押さえながら、わが社グループ‟らしい"体制を構築していくことで他社との違いを打ち出し、ヒト・カネが集まる一歩を踏み出しましょう。
関連記事
-

中堅企業が実装すべき財務戦略~企業を取り巻く経営課題~
- 資本政策・財務戦略
-

中堅企業が実装すべき財務戦略~「財務価値分析」から見る経営実態~
- 資本政策・財務戦略
-

事例から学ぶROIC経営の落とし穴とは?
- 企業価値向上
-

-

-

-

企業価値とは?意味と評価方法をわかりやすく解説
- 企業価値向上
-

 コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト
コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト