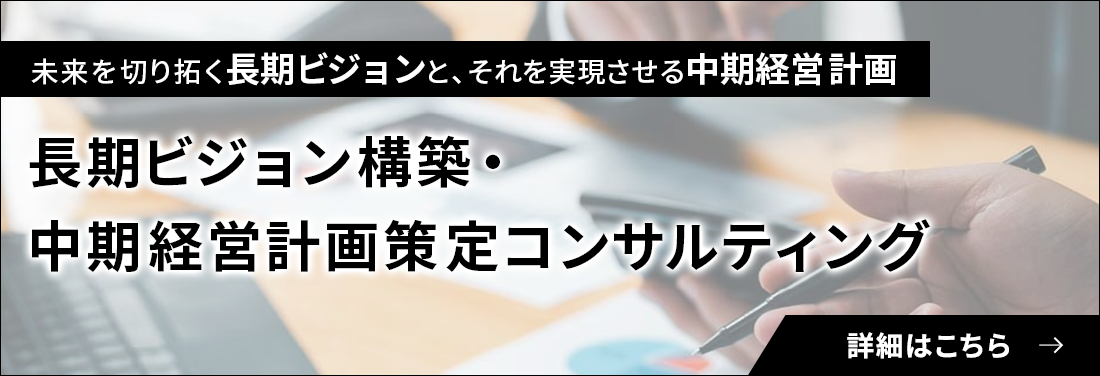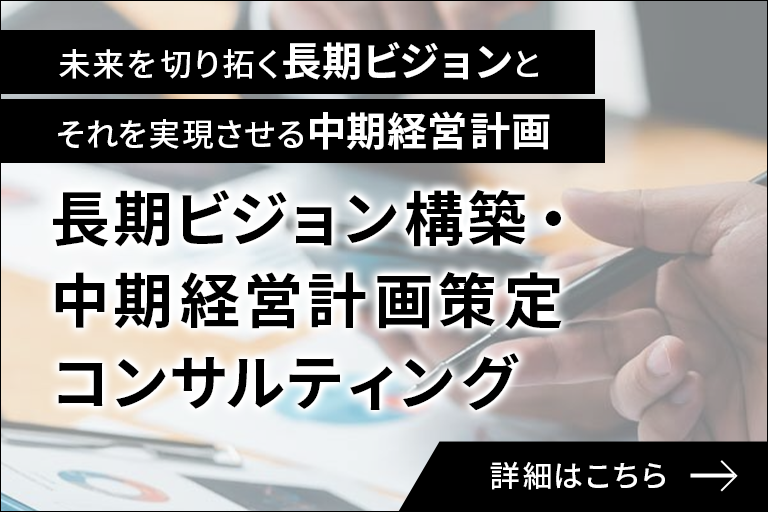COLUMN
コラム
閉じる

中期経営計画はなぜ必要なのか?
(1)経営における中期経営計画とは
企業経営の最大の目的を、存在価値を高め、投下した資金を上回る回収をするといった短期的なものではなく、持続的に成長・発展させるという長期的な目標を設定していることが多いです。言い変えると、企業経営にはゴールはなく、ゴールなきマラソンを走り続けるということになります。しかし、ゴールのないマラソンを走り続けることほどつらいものはありません。ゴールのないマラソンに社員が疲弊することなく走り続けるためには、経営者および経営幹部が一体となって、ゴールを設定することが必要となります。すなわち企業の成長プロセスにおける中期的なゴールを設定することになります。この中期的なゴールが「中期経営計画」です。また、中期経営計画においては、目指す姿であり、経営者および経営幹部の強い意志がこめられていなければなりません。これは、"こういった会社になりたい"、"これくらいのレベルには達したい"という企業の将来像です。自社の存在価値や外部環境・内部環境から見て、3~5年後に自社がどのような企業に成長するのかをスローガンとしてまとめ、中期経営計画とは、自社が3~5年後に達成すべき数値基準を経営レベルで設定することになります。
(2)中期経営計画の影響
中期経営計画は単なる計画に留まらず、ポジティブな影響があります。
1点目:あるべき姿の共有化
「こういった会社になりたい」「業績目標を達成したい」という経営者および経営幹部の"夢"に当たります。
その夢を全社員と共有することにより、社員の意欲を喚起します。また、現状のレベルと将来のあるべき姿とのギャップを正しい危機感として共有し、夢を実現するにはどうしたらよいかという「可能思考」にて社員一人ひとりが考え、自発的な行動へと結び付けていく効果が期待できます。
2点目:戦略的発想の根源
中期経営計画は現状の積み上げ算式に設定されるものではなく、あくまでも将来のあるべき姿として設定されます。したがって、中期経営計画を実現するための計画・方針(戦略)、それを達成するための方法論(戦術)、それに基づいた行動(戦闘)が必要となります。しかし、従来通りの方法論や行動の延長線では、中期経営計画は実現し得ないことが多いです。前述したように、"あるべき姿"であって、現状をベースに積み上げた将来予測ではないからです。したがって、現状のレベルとのズレ、「戦略ギャップ」を埋める必要があります。それを埋める活動が戦略となり、明確な経営計画が存在しない中では戦略的発想は生まれづらくなります。
3点目:リーダーの求心力向上
「環境変化が激しく、先行きも不透明な時代に経営計画なんて作成する意味がない」「業績が低迷しているのに計画など描けない」といった意見もあります。しかし、先が見えないことや業績が低迷していることは、社員にとって将来に対する大きな不安となっている可能性があります。したがって、リーダーの求心力やモラールの低下をもたらすことがあり、先行きが不透明なときこそ、経営計画を明確に示すことによって社内における求心力を高めることが必要です。

中期経営計画を策定しない会社とは?
中期経営計画を策定しない理由は主に下記3点が挙げられます。
1点目:「忙しいからビジョンをたてる暇がない」
中期経営計画とは、企業における中期的な価値判断基準です。その価値判断基準が明確になっていないから、様々なことに手を出してしまったり、あるいは何をやってよいか分からずに右往左往したりしています。経営計画が存在していないことにより、採用や人材育成などの要員計画もその場しのぎとなります。そうなると、業績が上がらないのにバタバタするという、バタバタ貧乏の状態に陥ります。実は、そういった忙しさの原因は計画がないことなのです。
2点目:「先行き不透明な時代だから計画をたてても意味がない」
中期経営計画というのは、中期的な未来を予測することが目的ではありません。人は誰しも先が見えない暗闇の中では不安が募ります。経営者や経営幹部と同様に社員も会社の将来が見えないことで不安感を抱き、モラールの低下を招く可能性があります。したがって、先行き不透明な時代であるからこそ、自社の目指す姿や数値指標が必要なのです。
3点目:「計画では食っていけない」
「計画では食っていけない」ではなく、「計画がないから食っていけない」が正しいです。「戦略なくして数値基準(数値計画)なし」「数値基準(数値計画)なくしてアクションプランなし」「アクションプランなくして成果なし」です。全ては成果を上げることにつながっており、場当たり的な目先だけを重視した経営は、社員を右往左往させて、中期的に見れば成果につながらないことが現実です。

中期経営計画作成の流れ
まず10年後などの長期的なあるべき姿の目標設定が必要です。長期目標からバックキャスティングで中期経営計画を策定する必要があります。そのうえで下記3点が中期経営計画において重要な要素となります。
1点目:未来を全天候で考える
中期経営計画は予算とは異なります。あくまでも事業戦略の進捗を測るものさしであり、数値による基準づくりですので年度予算を策定するように、精緻な数値を組み合わせてつくり上げることが目的ではありません。あくまでも未来に向けての数値基準です。中期経営計画を策定する上で必要なことは「全天候思考」です。全天候思考とは、数値基準を天候に例え、「晴れ」「曇り」「雨」の3 つの数値計画を描くことです。例えば、「晴れコース」は戦略が順調に進み、社内的に掲げた経営計画に向かって進むコースであり、「曇りコース」は経営的に見て必ず達成すべき数値計画であり、対外的にコミットする数値計画といえます。「雨コース」は、晴れコースや曇りコースとは少し趣旨が異なり、計画値を決めることが目的ではなく、実績値が一定の基準に満たない場合や基準値を下回る水準に陥った場合、ズルズルと時間だけが経過することを避けるために、あらかじめ判断と対策を講じておくことが目的です。外部環境の変化により、常に戦略の実行が予定通りに進むとは限りません。したがって、中期経営計画には、雨が降っても赤字にならない、「悲観的に準備して楽観的に行動する」全天候思考が求められます。
2点目:バランスシートに基準を持つ
バランスシート(貸借対照表)に数値基準を設定している会社は数多くはありません。バランスシートに基準を持たない会社に起こりうる事象は、過大投資を行う、過剰在庫、あるいは不良債権を抱えるなどが考えられます。バランスシートに基準を設定することにより、売上高を伸長するために在庫を多く抱えたり、リスクのある取引先へ販売したりもしないはずです。損益計算書については予算や目標という基準を持つ企業は多いですが、経営活動の結果としてのバランスシートではなく、基準という強い意志をしっかり入れる必要があります。このことが、未来へ向けた数値基準である中期経営計画に求められます。また、バランスシートの基準において、重要視しなければならないのは「現預金残高」です。なぜなら、戦略を実行・推進するための手許資金を確保しておくことが重要だからです。一般的に、手許流動性資金は月商の2 カ月分以上が基準です。その上で最も望ましいのは、「実質無借金経営」になることです。実質無借金というのは、借入金をゼロにするということではなく、借入金の残高が現預金残高の範囲内にあるということである。これらを踏まえ、中期経営計画の策定に当たっては、強い意志を持ってバランスシートの基準を明確化し、成長へ向けての財務体質の健全化も実現していただきたいです。
3点目:撤退基準なき財務戦略は機能しない
企業が成長していく上で必要なのは投資です。特に、事業投資や開発投資、設備投資などがなければ、企業の成長戦略を描くことが難しいことがあります。したがって、財務戦略における投資計画は、中期経営計画における重要な意思決定であり、判断です。しかし、投資をするという意思決定や判断以上に大切なのは、「やめることの判断基準」、すなわち撤退基準を明確にしておくことです。固定資産投資や新規事業投資において、投資回収が予定通りに行われなかったり、不採算状態になったりしたとき、埋没コストを表面化させることを回避するために、撤退を先送りするケースが多く見受けられます。しかしこういった場合、撤退の判断を先送りして吉と出ることはほとんどありません。新規の投資を行う際には、投資計画とともに撤退基準も明確にしておくことが必要です。
著者
最新コラム

- 物流事業者が2030年に向けて打つべき手

- ビジネスモデルを構成する収益モデルとバリューチェーン

- バリューチェーンとサプライチェーンの違いとは?それぞれの役割と事業戦略の進め方

- パーパスと経営理念の違いとは?パーパス戦略の基本とその重要性を徹底解説
ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと
進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド
~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド
~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド
~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~
資料ダウンロード

- 製造業企業事例集_vol1

- 長期ビジョン・中期経営計画に関する企業アンケート調査レポート2025年

- ストラテジー&ドメインコンサルティングメニュー紹介資料

- 統合報告書 ストーリー設計のコツ~企業価値は「説明」では動かない。「物語」が動かす。~

- 設備工事業界の未来を切り拓く:課題解決と成長戦略の最前線~人手不足からデジタル化まで、業界の変革を支える実践的アプローチ~

- TCG REVIEW 顧客創造モデル

- 収益構造を変える!ビジネスモデル・イノベーション~高収益を実現する事業ポートフォリオとPLのデザインはできていますか?~

- 食品業界の企業が中期経営計画策定で押さえるべきポイント~重要になるテーマと事例5選をご紹介~
 長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト
長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト