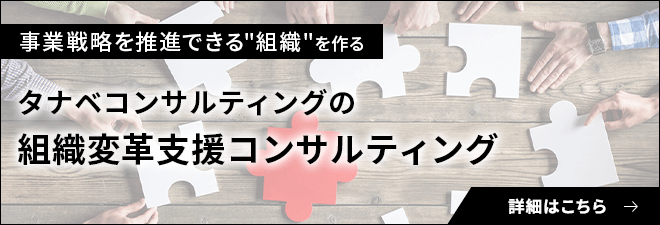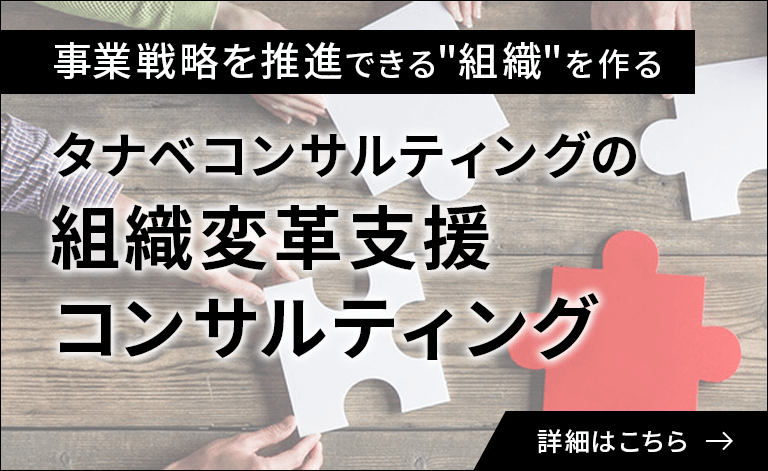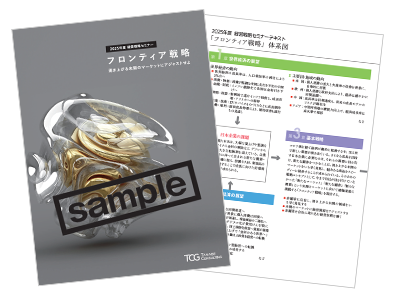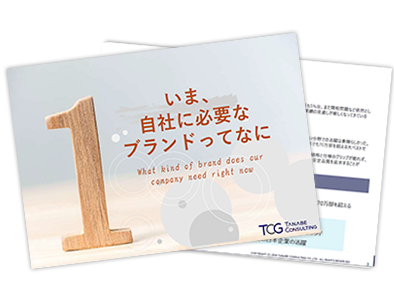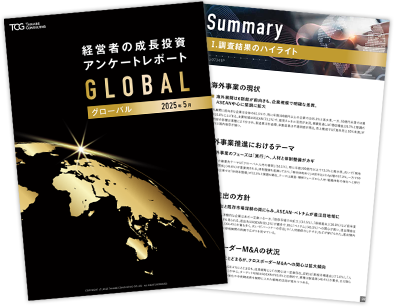COLUMN
コラム
閉じる
2024年問題によって大きく変革が迫られる物流業界。サプライチェーン構造の変化を機会として新たな荷主獲得を実現する営業組織組成が企業成長の鍵を握る。
物流業の営業組織体制の現状と課題について
特定荷主へ依存をしている受け身型体質からの脱却が必要になる
今こそ物流業は営業機能を強化すべし!
みなさんの会社は独立した営業組織を持っていますか?中小・中堅の物流会社の特徴として特定荷主への売上依存度の高さが挙げられます。特定荷主様の成長とともに、自社の拠点・人員数の拡大そして現場ノウハウが蓄積している半面、営業組織を独立で組成している企業は少ないと筆者は感じています。
そんな状況の中で特定荷主への売上構成比を低減すべく、新たな取扱い荷種の獲得を目指す営業組織体制構築を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
直近の外部環境のトレンドとして「2024年問題」が挙げられます。2024年問題の影響により、従来から物流網は再構築を迫られ、サプライチェーン全体が大きく変わる転換期になると予測されます。そのような24年問題を機会として、新たな荷主獲得に向けた営業組織体制構築を目指していくべきです。
物流業における営業組織を組成するにあたって、最初にネックになるポイントとして挙げられるのは「営業パーソンが備えるべきスキルを保有する人財」の不在です。
営業パーソンには大きく3つのスキルが必要になります。一つ目は顧客の顕在・潜在的な課題を抽出する課題認識力、二つ目に顧客との人間関係を良好に保つコミュニケーション能力、最後は自社のサービスを顧客の課題とマッチさせて提案するソリューション能力です。
物流の業務特性を一言で表わすと「調整」が一番しっくり来ます。荷主の要望を限られた条件の中で的確にこなしていくためには何が必要かを常に考え続けることが求められます。非常に大切なスキルではありますが受け身型の社員が生まれやすい環境にあると感じています。
営業で結果を出すためには課題認識能力、コミュニケーション能力そしてソリューション能力が必要と前述しましたが現場の人財が営業人財へシフトする際には能力の強化、人財配置のアンマッチを防ぐことが必要です。

物流業の目指すべき営業組織体制とは
仕組化×デジタルを組み合わせた営業組織体制をデザイン
脱アナログ・感覚営業!!そしてデジタルを融合させる!
前段では物流の業務特性から踏まえた現場社員の特徴について述べましたが、ここでは物流業の目指すべき営業組織体制について検討を進めてまいります。組織体制構築をするにあたり、最初にポイントを言いますと、徹底した仕組み・ルール化とデジタルを組み合わせたモデルをあるべき姿として設計していくことが必要です。
みなさんの会社の営業活動は、普段の綿密な計画の元設計された物流現場作業と比較して、少し感覚的なところはないですか?個人で受け取った名刺は全社のデータベースにて一元で管理されていますか?他にも顧客のフォロータイミングが曖昧になっていませんか?
普段の現場ではロジカルに業務設計がされているにもかかわらず、営業活動は感覚的...。私は営業こそロジカルに!(仕組み・ルール化の徹底)が必要になります。
営業をロジカルにするためには、営業を大きく3つのタイミングに分けて施策を体系的に棚卸することが必要です。一つ目は潜在顧客からの引き合いを得るタイミング、二つ目は引き合いを得た潜在顧客を育成(ナーチャリング)するタイミング、最後に商談・受注するタイミングです。
まず潜在顧客からの引き合いを得るタイミングですが、施策と考えられるのはホームページ、広告運用や無料説明会の実施などが挙げられます。引き合いを得た潜在顧客を育成するタイミングでは、潜在顧客リストへの定期的なメルマガ配信等が挙げられます。最後に商談・受注するタイミングでは提案書作成から訪問による提案活動があります。
あくまで一例として記載しましたが、まず3つのタイミングに自社の営業活動を分解してどこが不足しているかを検討していくことが必要になります。

御用聞き営業から提案型営業へシフト
身の丈を超えた環境により新たな発想を生み出す営業組織開発
前向き×自由な発想が会社の成長を支える!
筆者は営業組織改革のご支援をしているとPJメンバーから会議中こんな意見が出ることがあります。「私、営業やったことないし...」「うち(自社)の強み、選ばれるポイントなんてないし...大手企業の方が圧倒的に(サービス価格が)安いし...」特にPJ開始の最初の段階では後ろ向きな発言が目立つケースが多いです。
ところが当社で実施している顧客の生の声をアンケート形式でご回答いただく「ブランディングサーベイ」を実施してみると、自分たちが気づいていない強みを認識することができてPJメンバーが前向きにどう提案したらいいかを考え出すことがあります。
きっかけ次第で雰囲気が変わるので、時間をかけながら根気よく営業人財の育成に取り組む事が必要になります。
最後に、営業を担う人材が自由な発想を生み出すために行っている年商500億企業になることをビジョンに掲げている150億のA社様の事例を紹介します。その会社は「身の丈を超えたことを考えよう」をコンセプトの元、年に1回東京の高層ビルのレンタルオフィスを借りて営業戦略会議を開催しております。
普段の本社会議室ではなく、少し環境を変えて営業施策について検討することで固定概念にとらわれず、自由な発想での意見を引き出すことに成功しています。
ぜひ、営業パーソンに求められる人材像と自社社員のスキルギャップの可視化、ロジカルな営業体制の確立そして自由な発想を生み出す環境整備について取り組んでいただきたいです。
著者
最新コラム

- 海外進出の方法とは?実際の流れからその後の成長戦略までを網羅的に解説

- 中堅・中小企業における海外進出のメリットとは

- WEB対談:燈様×タナベコンサルティング

- 海外マーケティングの手法とは?海外進出におけるテストマーケティングの役割とポイントを紹介【入門編】
ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと
進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド
~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド
~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド
~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~
 長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト
長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト