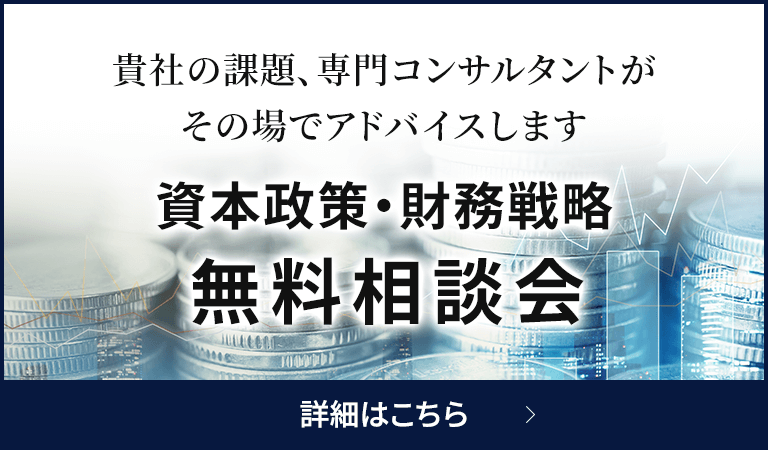企業再生とは 事業再生との違い、金融機関との付き合い方などをわかりやすく解説
- 資本政策・財務戦略

閉じる
企業再生とは?
企業再生とは、経営状態の悪化による債務超過や資金繰りの悪化などで経営の存続が困難であったり、実質的な経営破綻状態にある企業に対して、経営状態を悪化させている原因を取り除き、健全化させる取組みを指します。
企業再生において取られる選択肢としてはM&Aやリストラ、事業の縮小・撤退等様々ですが、まずは経営状態を悪化させている要因を正しく把握することが必要になります。
企業再生と事業再生の違い
企業再生と似た言葉で事業再生というものがあります。
この2つの言葉の違いは、立て直しを図る対象が企業の経営状態か、企業が営む事業の収益性かという点です。
事業再生は、不採算事業の廃止や事業活動の見直しによる収益力改善など業務活動の改善により事業を再生させることを指しますが、企業再生においては役員のリストラや事業の売却など、取組みの対象が経営全般にわたります。
ただし、2つの言葉に法律上の明確な定義はなく、経営状態を立て直すためには事業の再生が必要であるため、企業再生と事業再生は密接に関係していると言えます。
企業再生の種類
企業再生は法的再生と私的再生の2つに大別されます。
それぞれにはメリット・デメリットがあるので自社においてどちらの選択肢がベストなのかを比較検討して選択する必要があります。
■法的再生
法的再生とは法律の定めに基づき、裁判所の監督の下で、債務者の資産・負債の整理を行う手続きであり、目的に応じて「再生型」と「清算型」に分けられます。
ここでは企業再生を目的としているため、清算型に該当する破産や清算については説明を割愛します。
法的再生のメリット・デメリット
(1)民事再生や会社更生の場合は、債権者による決議が必要とはなりますが、一部の債権者が反対していても再生計画・更生計画を実行に移せる場合があります。
そのため、メリットとしては法律に基づき強制的に債務負担を軽減できる点が挙げられます。
(2)一方でデメリットとしては、法律に基づいた手続きを行う必要があるため、期間が長期化しやすく準備や対応に多くの労力を要する点が挙げられます。
また、法的再生では全ての債権者を対象として実施されるため、企業価値の毀損(ブランドイメージの低下等)も大きなデメリットになります。
■私的再生
私的再生とは民事再生法や会社更生法の法的手続きを用いず、債権者と債務者の当事者間の合意に基づき自主的に債権整理を目指す手法を指します。
私的再生のメリット・デメリット
(1)私的再生のメリットとしては、先述の法的整理のデメリットとは反対で、債権整理の対象が原則金融機関のみとなるため、事業価値の毀損を回避できる可能性があることが挙げられます。
また、法的再生が債権カットを規定すること多いことに対して、私的再生では返済額の軽減や返済計画の見直し等を求めることが多く、金融機関との関係を正常化しやすいこともメリットの1つに数えられます。
(2)一方でデメリットとしては債権者の同意を得られなければ成立しない点が挙げられます。
そのためにも策定計画の合理性や金融機関に対して説明する際の説得力が必要となります。
企業再生支援のステップ
企業再生支援を行うにあたってのステップを以下に整理しました。
1.現状を把握する
2.再建の可能性と再建を進める経営者を見極める
3.再建計画を策定する
4.再建計画を実行する
1つ目のステップとして、まずはじめに「なぜ自社の経営状態が悪化したのか」を把握する必要があります。
原因が不明瞭なまま、企業再生に着手してしまうと自社に不適切な手段を選択してしまったり、場合によっては経営状態をさらに悪化させかねない選択をしてしまう可能性があります。
2つ目のステップは、そもそも再建が可能か否かを見極めることです。
再建には多大な費用や労力がかかるケースがあります。企業の状態として、経営再建が不可能に近い状態であれば、清算という選択肢を採ることで余計な費用や労力をかけずに済む場合があります。
また、経営者の能力や決断力も重要です。
経営者の能力や決断力が不足していると企業再生を進める上で支障が出る可能性があり、そのためにも経営者の再建に対する意識や意欲、実行力を改めて確認する必要があります。
3つ目のステップは、再建計画の策定です。
特に私的再生においては債権者との合意が必要になりますので、再建計画の合理性や実行可能性が高いものでないと、実行に移ることができません。
再建計画の目的として以下の2点を抑えることが債権者との合意形成において重要な事項になります。
(1)赤字の早期解消
(2)金融取引の正常化
特に(2)の金融取引の正常化を実現するためには金融機関との連係が欠かせないため、計画策定段階から金融機関と協調して取り組むことが求められます。
4つ目のステップは計画の実行です。
策定した計画に基づいて実行するのはもちろんのこと、進捗状況と成果を債権者と共有することが重要になります。
そのため定期的なモニタリングが求められます。
企業再生支援における金融機関との付き合い方
先にも述べたように企業再生において必要不可欠になるのが取引金融機関との密な連携になります。
短期的な支援としては、返済条件の見直しによる返済金額の軽減があり、再建計画実行における事業資金の確保のためには非常に重要な支援になります。
また、長期的な支援としても、事業立て直しのための追加融資など、企業再生における金融機関の役割は非常に重要なものになります。
以下では企業再生際しての金融機関と良好な関係を築くために意識すべきポイントを整理しました。
1.再建計画検討前から自社の置かれている状況と今後の方向性を共有する。
2.再建においてコンサルティング会社等の外部機関を利用する場合は、外部機関と金融機関が連携できる体制を整える。
3.再建計画において返済条件の見直しを織り込む際には、返済条件の早期正常化を図るための具体的施策と合実性を明確にする。
企業再生においてキャッシュフローの改善は必ず取り組まないといけない最優先課題です。
赤字企業のほとんどが借金を抱えており、その返済金額の軽減がキャッシュフロー改善における効果的な施策の1つです。
しかし、それを企業単独で行うことはできず、また一方的な主張によりそれがなされたとしても、金融機関との関係が悪化しては倒産を免れたあとの成長・発展のための支援は期待できません。
そのためにも金融機関との関係性構築は企業再生の成否を分けるポイントと言えるでしょう。
さいごに
企業再生においては、従業員のリストラや事業の撤退、子会社の売却など非常に難しい決断を迫られるケースがあります。さらに言えば、企業を存続させるために経営陣の退任といった選択肢も検討しなければなりません。
また、再建計画策定においては合理的かつ実現可能性が高いこと、改善に向けた抜本的な計画であることが求められます。
企業再生支援の目的は債権者との合意形成がゴールではなく、計画を確実に実行して経営状態を改善させることにあります。
そのためにも社内だけでなく外部機関や専門家など外部知見を積極的に目を向けて活用し、企業を存続させる強い意志を示していくことが重要です。
関連記事
-

中堅企業が実装すべき財務戦略~企業を取り巻く経営課題~
- 資本政策・財務戦略
-

中堅企業が実装すべき財務戦略~「財務価値分析」から見る経営実態~
- 資本政策・財務戦略
-

事例から学ぶROIC経営の落とし穴とは?
- 企業価値向上
-

-

-

-

企業価値とは?意味と評価方法をわかりやすく解説
- 企業価値向上
-

 コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト
コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト