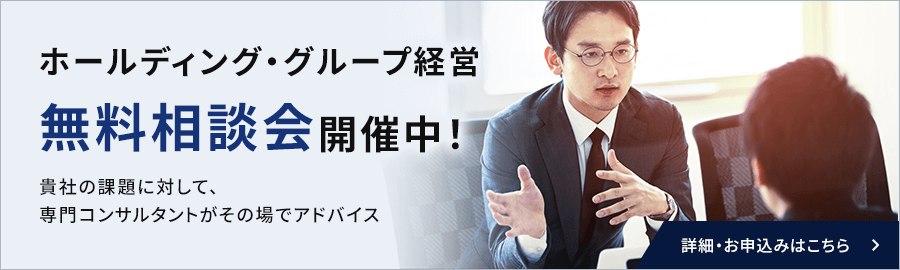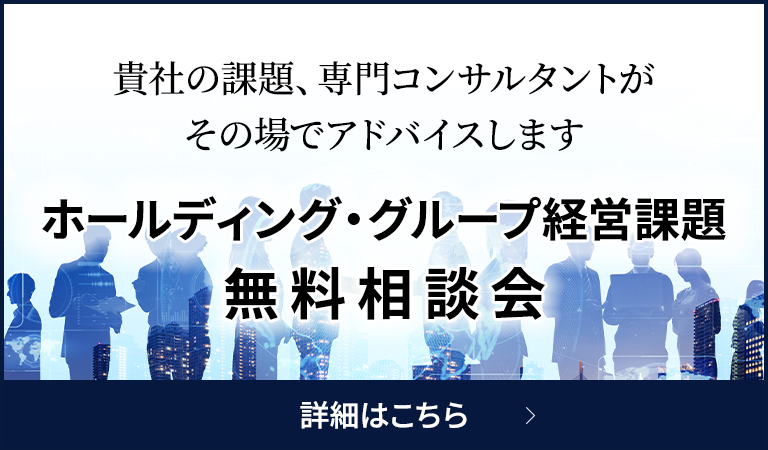業務効率化・平準化を加速!
シェアードサービス活用のメリット
- ホールディング経営

閉じる
生産性を上げていくにあたり、まず検討するのが「業務効率化」です。ただ、実態は業務効率化が上手くいって、〇%生産性が向上した、という事例は少ないのが現状です。業務の集約を図り、効率化の結果、生産性が高まるというサイクルを描くには、どのようにシェアードサービスを導入していくのが良いかお伝えします。
シェアードサービスで実現する業務効率化と平準化
昨今、どの業界においても人手不足が深刻化していると言われています。グローバルな競争に世界中が巻き込まれ、成長が大前提の経済社会下において、島国である日本は人口減少・高齢化社会・移民受け入れ体制の不整備といった背景から、労働力の減少が火を見るよりも明らかとなっております。
そんな環境背景を元に、人手不足への対応策として「生産性向上」、つまりはAIの活用やDX化の推進など新たな技術を用いて、従来人手をかけて実施していた業務の負担を軽くする、ないしは業務そのものを新たな技術に任せていくという風潮にあります。
その風潮自体は間違っておらず自然の流れではありますが、同時に要件定義や削減に向けた目的を見失った「秩序なき業務効率化」を推進してしまうと、局所最適となり全体として「効率化や平準化」が遅々として進まないケースが多数存在しております。
改めてわが社は何のために、何に向けてシェアードサービスを推進・実行していく必要があるか、経営陣と現場担当者が密に連携し、確認を取りながら進めていく必要があります。シェアードサービスの推進を単に事務コスト削減の手段と捉えるのではなく、バックオフィス業務に費やしていた時間を収益を生む活動に振り向けることで、収益力を向上させることが可能です。また、シェアードサービスの導入により、これまで見えなかった業務の傾向を把握し、それを基に戦略を立案するなど、ナレッジの共有と活用を通じて多方面での効果が期待できます。
業務の細分化・平準化に向けた3つのポイント
自社の業務効率化・平準化に向けてシェアードサービスの見直しを図る際に、最初に実施することは「業務の細分化」となります。今、一連の流れで行っている各業務について、一つずつの行動レベルにまで細分化を行い、業務フロー図の作成を行います。
ポイントは3つあります。一つ目は、業務効率化を目的とするのであれば、一つの部署・部門だけで業務フローを作成するのではなく、全社を通じて業務フローの見直しを行う必要があります。仮に、部門単位だけで見直しを行いたいというねらいがあったとしても、最低でも業務上の関わりのある部門はなるべく全て実施するべきです。理由としては、業務が他部署にまたがる場合、前後の業務の流れを把握する必要があり、他部署がその後どのような業務を行っているのか、またはどのような業務を経て自部署に引き継がれているのかを確認することが求められます。この前後作業の業務フローが場合によっては大きな改善となるケースがよくあります。そもそも前工程に非効率がある、もしくは後工程に業務が偏ってしまっているため、慢性的な人手不足となっている(平準化ができていない)というケースこそ改善の余地がありますので、改めて「自部門だけではなく、関連部門、全ての業務フロー見直し」が必要となります。
二つ目のポイントは、できる限り業務単位を詳細に記載することです。業務フロー図の完成を目的に、おおざっぱに業務を括って作成してしまうケースが多々あります。例えば「見積書作成→受注→仕入先支払い」など、この粒度で業務フローを作成してもどこに改善点があるか見出しづらくなります。「顧客依頼→見積書作成を営業事務に依頼→営業事務がExcelで作成→...→受注→受注データ登録(ランク替えなど)→仕入先連絡→経理へ報告→経理が支払いシステムへ入力→紙ではきだし実態と突合」など、これでもまだ粒度は粗いですが、細かな作業や動きベースで業務の流れを洗い出すことが重要です。その際に、受注データの登録はバックオフィスで対応できないか、紙での作成・出力を廃止できないかなど、業務における非効率を見つけて課題業務フローに目星をつけていきます。着眼点は後述しますが、「業務の細分化」を意識した業務フローを作成してください。
三つ目のポイントは、必ず第三者にチェックをしてもらうことです。業務フローの作成自体は当事者にヒアリング、ないしは観察しながらでないと作成できませんが、どこに非効率があり、どこに業務が偏っているかなどの課題を挙げていく作業は必ず第三者の目を入れる必要があります。理由は、現業務を過去から続けてきた当事者だけでは、現業務における異常を発見しづらい、ないしは表面的なできない理由をあげるなど、抜本的な改革につながりづらいためです。第三者から見て、なぜこの業務を行っているのか、なぜこのステップを踏んでいるのか、紙の意味があるのかと、フラットな目線でチェックをしてもらいましょう。社外の方だと社風・文化も知らない中での提言となるのでなおよいです。
業務改善・平準化の着眼点「ECRSの法則」
業務改善の着眼点としてよく知られているのが「ECRSの原則」です。
「ECRSの原則」とは、
排除(Eliminate):業務をなくすことができないか?
結合(Combine):業務を1つにまとめられないか?
交換(Rearrange):業務の順序や場所などを入れ替えることで、効率が向上しないか?
簡素化(Simplify):業務をより単純にできないか?
の視点をまとめたものです。
この視点を元に再度業務フローを見て、そもそもこの作業いらないのではないか(E)、部門間・担当者間で無駄な行き来がないか、データをまとめられないか(C)、先に対応すべき業務を優先した方が効率的ではないか、または事務所や工場内のレイアウト変更が必要ではないか(R)、申請フローをもっと簡略化できないか(S)など、ECRSの原則に立ち返ることで、「業務改善・平準化」へとつながります。シェアードサービス導入の結果が、コスト削減だけでなく、業務の簡素化に通じ、ガバナンスの強化や、社内人材リソースの活用、プロフィットセンターのフル稼働へとつながり、より一層の収益体質の強化が実現します。
最後に
これまで、業務効率化・平準化に向けたシェアードサービス導入には以下3つのポイントと「ECRSの原則」による観点が必要とご説明しました。
①全社単位での業務フローを作成する(少なくとも前後部署含めたフロー)。
②業務を行動レベルまで細分化する。
③第3者に違和感をチェックしてもらう。
以上は、あくまでも現況の課題を洗い出していくフェーズとなります。現場レベルで改善が図れるものや、社内規定を変更して改善・平準化できるものは随時実行に移していくと良いと思いますが、抜本的な改革にはどうしてもシステム投資が絡んできます。とはいえ、ここまでで作成した業務フロー(システムも記載したもの)があれば、システムの非効率性・重複などの問題も見えているので、設計がすでにでき上がっている状況です。あとはより効率化に向けた行動・施策を新たなシステムに追加していく作業となります。以上を踏まえて、改めて業務改善の原点は「行動レベルの業務フロー作成」となります。まずは一度、ご自身や自部門の周りを「業務フロー」に落し込む作業から始めることで、業務上ネックとなっている工程・作業を洗い出すことから始めてみてください。
関連記事
-

物流業におけるROIC改善事例を解説!企業価値を高める方法とは?
- 資本政策・財務戦略
-

資本政策 事例|押さえるべき3つのポイントを事例を基に解説!
- 資本政策・財務戦略
-

組織における意思決定の種類とは?トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!
- コーポレートガバナンス
-

製造業における収益改善の2つの視点と5つのステップを徹底解説!
- 資本政策・財務戦略
-

-

収益改善の成功事例 | 効果的なポイントについて徹底解説!
- 資本政策・財務戦略
-

-

中堅企業が実装すべき財務戦略~ホールディング経営におけるトップのリーダーシップ~
- ホールディング経営
 コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト
コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト