
1.DX時代の人材育成
(1)変革期に必要な人材要件は「あらゆるものに好奇心を持てるかどうか」
時代の潮目には、変革を推進する人材の登場が求められるものですが、とりわけ過去の歴史や習慣的作法を重んじる日本企業においては、「今あるものを過度に破壊せずに、全体の調和を意識しながら緩やかに変えてくれる人材」が求められるように感じます。その要求は、激変する社会に適合するにはいささか不安を感じさせるものではありますが、事実、外部からスカウトしてきたDX推進役の比較的若いリーダーが、本人よりも年齢が上のベテラン社員との連携がうまくいかないため機能せず、組織全体を巻き込みながらのDX推進にとん挫する例が頻発していることからも、日本企業には日本企業らしい変革者が求められることは間違いありません。
結論として、日本企業に適した変革者に必要な資質は「全体を巻き込み変化を促進する能力」ではなく、「多方面に好奇心を持ち、未来のビジョンを描き、それを皆に示していける能力」であると考えます。日本人は真面目で誠実な気質であり、正解を提示されればそれに向かって努力できる優れた人材が多いです。しかし、変革には正解がありません。そのため、過去の前例を研究しても、それを自社に適用できるかどうかの判断に迷うケースが多くなります。このような状況では、変革の旗振り役に対する抵抗感が強まりがちです。変革者は、組織全体が共感できるビジョンを描き、それが実現したときのメリットとデメリット(必ずメリットが大きく見えるようにすることがポイントです)を提示することが求められます。また、経営層だけでなく、現場の一人ひとりがそのビジョンに納得できることが重要です。たとえば、あなたが事業部の営業実績を前年比120%にしたいと考え、それを達成したとしましょう。その目標達成は、単にあなたに課せられたミッションを果たした結果ですが、一方で、その達成により、他の誰かが見た夢の実現が一歩近づくことになるのです。目標の達成は、大きな夢の一部に過ぎず、どのようなビジョンを描き、どのように実現するかの一要素です。
夢を描くことができる人材は、あらゆる事象に好奇心を持ち、「なぜ?」と問い続ける姿勢を持つ人物です。日本企業の変革期において重要なのは、「全社員が緩やかな変革マインドを持つ」ことです。そのためには、既存の慣習的な思考にとらわれず、「純粋に多方面に興味を持てる」人材育成方法を確立することが必要です。
(2)変革期における人材育成方針
現代は人間の生き方やビジネス、企業の在り方が多様化し、自社最適化人材を育成する方針が敬遠されがちな風潮があります。社員自身が永久雇用制度に縛られていないため、一社限定的に最適化された人材として育っていくことに抵抗感を持っています。そのため、以前は1:Nで対応していた人材育成方針が、1:1でないと対応しきれず、その分現場の負荷が増大しているのが現状でしょう。
まず、新卒社員だろうと中途採用社員だろうと、現時点での能力パラメータを正確に把握することが重要です。自己申告や書類の経歴だけでは測れない実践知レベルの情報や、その人の働く基本姿勢、さらには人生で希求しているものを把握するレベルまで、初期の段階で情報精度を高めていかなければ、本当にその人材が組織にマッチングするかどうかは測れません。現在考えられる対策は二つです。人事部門が採用段階でそこまで手広く精緻に人材の本質を見抜く仕組みを導入するか、現場での試用期間を最低1年間以上確保するかです。
昭和の時代に「理想的な社員像」をある程度確立してきた企業ほど、その理想像を誠実に追及する傾向が強く、教育方針が先行しがちです。ただし厳しい意見として、その理想像を令和に合わせてアップデートすることは急務です。さもなければ社員は一定数以上定着しません。そのうえで、1:1で社員一人ひとりと向き合う仕組みを整えることが必要です。その際は、背中を見て学ばせるのではなく、確実に教えたいことを言語化し、相手に届く表現で伝えてください。世代間ギャップがかつてないほど深刻化しており、言葉のニュアンスが正しく伝わらない場面が多く見受けられるためです。
2.「DX人材」とは
(1)「DX人材」として求められる職能
さて、DX時代における人材育成について意見を整理してきましたが、そのなかでも時代を象徴する「DX人材」について言及したいと思います。
DX人材とは、デジタル技術を手段として事業や組織そのものを変革し、新たな価値を生み出せる人材を指します。単に最新ツールを扱えるエンジニアではなく、課題を発見し、ビジネスゴールから逆算してテクノロジーを組み合わせ、変革を社内に定着させるまでをリードできる存在です。そのため担う職能はきわめて幅広く、たとえばAIやクラウド、データ分析の知見を武器に経営層へ変革案を提示する「DX提案」、業務をどう変えるかを言語化する「DX定義化」、プロジェクト体制やKPIを設計する「DXロードマップ策定」、開発やPoCを推進する「DX構築・導入」、稼働後の効果測定と改善を担う「DX運用」など、フェーズごとに異なる専門性が求められます。
しかし現実には、こうした多岐にわたるタスクを情報システム部門や「ITに詳しい人」へ丸投げしている企業が少なくありません。デジタル変革はIT部門だけの課題ではなく、マーケティング、営業、製造、人事など各部門がデータを読み解き、顧客体験や業務プロセスを再設計する主体性を持ってこそ前進します。DX人材とは、部門横断でビジネスとテクノロジーを橋渡しし、変革をやり遂げる推進者であり、企業の競争力を左右する鍵なのです。
(2)「誰でもできる」がDXの基本
そもそもDXとは、特定部署の誰かに担ってもらう性質のものではありません。DXとは単なる技術革新であり、「一定条件を満たしたすべての社員が使いこなせるように変化する」ことが基本です。
誰もが「これやってみたら面白いのではないか?」「これを導入すれば●●部署はもっと楽になりそう」と、もっと気軽に「DXした場合の夢」を描ける状態が普通であり、それがDX提案です。「そのDXを進めた場合、いつまでにできれば今後の業績に良い影響が出そう」、「それに間に合わせるためには、全員が参加しないと難しそう」、「どのような協力体制をとれば良いか」と考えるのがDXロードマップ策定と実行計画策定の基本です。
このように、「余白と余裕を持ったDX検討」ができていない日本企業に対して、大きな違和感を抱いています。これは冒頭で述べた「日本人は夢を描くのが苦手」という特性に起因しているのではないかと筆者は推察しています。
3.DX人材に必要なスキル
(1)変革をデザインするビジネス・コミュニケーションスキル
DXは「どの技術を導入するか」ではなく「顧客体験と事業をどう変えるか」を出発点に設計されます。
そのためDX人材にまず必要なのは、ビジネス課題を発見し、経営目標から逆算してロードマップを描く戦略思考です。市場調査からバリュープロポジション設計、KPI/OKR設定まで一貫して行う構想力に加え、部門横断のステークホルダーと合意形成を図るファシリテーション力が欠かせません。
さらに、アジャイル開発におけるプロダクトオーナーシップ、失敗を学びに変えるリーン思考、組織を動かすチェンジマネジメントも求められます。DXプロジェクトは技術導入より文化浸透の方が難易度が高いからこそ、論理と情理を行き来しながら人と仕組みを動かせるコミュニケーションスキルがDX人材のコアコンピテンシーとなります。
(2)価値を具現化するデータ・テクノロジースキル
構想を机上の空論で終わらせないためには、データとテクノロジーを自在に操る実装力が不可欠です。
基盤となるのはデータリテラシー──SQLやPythonによる抽出・可視化、統計解析を通じて示唆を導く力。そこにクラウド(AWS/Azure/GCP)やSaaSを組み合わせたアーキテクチャ設計、APIによるサービス連携、生成AIや機械学習モデルの選定・チューニングなどの技術知識が加わります。また、DX推進にはセキュリティとガバナンスも欠かせません。
個人情報保護法やSOC2などの基準を押さえ、安心してスケールできる仕組みを整備する視点が求められます。最後に、稼働後の効果をダッシュボードで可視化し、データドリブンに改善を繰り返すPDCA運用ができて初めて、DXは企業の競争優位へと転換します。
4.DX人材不足における課題解決策
(1)全社員リスキリングとジョブローテーション
DX人材不足は「適任者が社内にいない」以前に、「潜在スキルが可視化されていない」ことが根本課題です。まずはデジタルリテラシー診断で現状を数値化し、スキルギャップに応じたオンライン講座・PBL型研修を設計。マーケ・営業・開発など部門横断のジョブローテーションを組み込むことで、データ×ビジネスのハイブリッド人材を計画的に輩出します。
(2)外部タレントと共創するアジャイル体制
短期のリソース逼迫は、フリーランスや業務委託のDXタレントを活用し、社内メンバーと混成チームを構築するのが効果的です。外部人材にはPoCやMVP開発などスピードが要求されるフェーズを任せ、社内メンバーは要件定義や運用設計を担当することで、ノウハウ移転と人件費最適化を両立。契約形態は成果連動に設定し、KPIを共通言語にして進捗を可視化します。
(3)学習コミュニティと評価制度で文化を定着
単発研修だけではスキルは定着しません。SlackやNotionで社内DXコミュニティを運営し、成功事例やコードスニペットをシェアする仕組みを整備。さらに「データ活用件数」「自動化率」などDX貢献度を人事評価に組み込み、アウトプットを正当に報いることで学習行動を継続的に促進します。こうした仕組み化が、慢性的なDX人材不足の解消を加速させる鍵となります。
5.効果的なDX人材の育成方法
(1)スキルギャップの可視化と個別ロードマップ
DX人材育成の第一歩は「自社に何が足りないか」を数値で捉えることです。全社員を対象にデジタルリテラシー診断を行い、データ分析・クラウド・業務設計など十数項目をレーダーチャート化して現状を見える化。結果を基に「即戦力」「伸びしろ大」「基礎強化」の3層に分類し、目指すロール(プロダクトオーナー/データサイエンティスト/DXアーキテクトなど)ごとに1〜2年単位の学習ロードマップを提示します。ゴールと道筋を明確にすることで学習動機と投資効率が飛躍的に高まります。
(2)実務直結のアジャイル学習エコシステム
知識を定着させる鍵は「学んだ瞬間に使う」仕組みです。部署横断で編成したスクワッドが、自社データを用いたCX改善や業務自動化を2週間スプリントで回すPBL(Project Based Learning)方式を採用。SlackやTeamsには外部メンターを常駐させ、疑問を即時解決できる環境を整備します。週次レトロスペクティブで失敗も含めて学びを言語化し、ライトニングトークやTechブログ執筆を義務化。「アウトプット前提」の文化を根付かせることで、スキルとナレッジが組織内部に循環します。
(3)評価・キャリア・外部資源を結ぶ仕組み化
学習成果を人事評価へ直結させなければ、DXは"夜間活動"で終わります。データ活用件数や自動化率などDXKPIを設定し、達成度を昇格・報酬へ反映。専門職グレードを整備し、中長期のキャリアパスを描けるようにして離職リスクを抑えます。また、MOOCやベンダーブートキャンプ、国・自治体のリスキリング補助金を組み合わせれば費用と時間を圧縮可能。さらにPoCフェーズに外部タレントを参画させ、ノウハウを社内へ高速移転することで育成サイクルが加速し、慢性的なDX人材不足を抜本的に解消できます。
6.DXが当たり前の世界で求められるマーケティング機能とは
(1)マーケティングの目的と基本機能
DXが当たり前の世界においても、マーケティングの目的は変わりません。しかし、アプローチ方法は従来の固定概念を捨てることなく、軌道修正し、より人間主義を追求する路線に変更せざるを得ないだろうというのが筆者の結論です。まずマーケティングの目的ですが、こちらは大きく三点に整理されます。
①モノやサービスを新しく売ることができる市場を生み出す
②経済やヒトの動きが活発な市場への参入方法を探り、その市場を多角的に分析する
③モノやサービスを購買してくれそうな顧客リストの抽出
です。現状、マーケティングはどうしても販促戦略などの出口アプローチの技術や戦術が発達しがちですが、本来は商品開発や商流デザイン、ビジネスモデルのアップデートなどにも貢献する機能です。この機能が企業内で正しく認識されていないケースも見受けられるため、まずはマーケティングの目的および基本機能を正しく認識し、経営計画に役立てる意識が必要です。
(2)DXが当たり前の世界で求められるマーケティング人材とは
DXが当たり前の社会で求められるマーケティング人材は、従来のマーケティング理論を使いこなし「従来型の正解」を提示する人材ではなく、変革的な目を持ちながら顧客が描く夢を自分事として捉え、顧客と真摯に向き合うことで夢の実現に向けた糸口を見出し、伴走支援を行いながらよりよい解決策を提案する人材だと筆者は捉えています。その解決策には当然、DXに関連するものが多く含まれるでしょう。この変化は、社会が大なり小なり日々変革を起こし、受け入れ、アップデートしていくあり方を選んだためだと筆者は考えています。
社会は会社と裏表の関係と言われるように、社会を構成する重要ユニットが会社と捉えれば、この選択は会社ひいては会社を構成する人間が選択した結果と言えます。前述したように、あくまでもマーケティングの目的は従来と同様です。しかし、顧客の夢を理解し、ともに実現させていく目線と伴走支援できるだけの「夢の補完者」たる能力は、従来のマーケティング理論に則った方法では補いきれない場面も出てくる可能性が高いのです。少なくとも弊社のマーケティング人材育成においては、変革期に適応した視野が広く、好奇心にあふれた人材の育成を基本原則として推進しています。
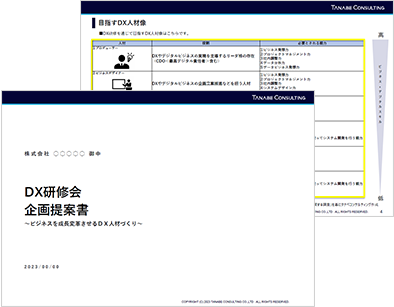

 デジタル・DXの戦略・実装情報サイト
デジタル・DXの戦略・実装情報サイト











